
拝金主義を擁護した真意 大日本帝国と史論家山路愛山の時代21
勝海舟論で意気投合したのか

福沢諭吉死後に著わされた信濃毎日新聞主筆時代、明治三四年(一九〇一)二月九日に『国民新聞』へ寄せた「田舎より首府へ(四十三信) 嗚呼彼れ惜しむべきなり」の追悼文を見てみよう。
「福沢諭吉先生は独り慶応義塾一派の先生なるのみならず、大日本の人民がつねにその同情の中に敬愛したる碩学なり。(中略)今や先生逝きぬ。余は一個の日本人民として無限の哀詩を彼の記念に献ぜんと欲す。余は実に赤心より然かなさん事を欲す」[i]
愛山は福沢は独り慶應の所有品ではなく、また独立自尊という宗派の所有品ではなく、大日本人民の公共的所有品だと讃える。この言の背景は何があったのだろうか。 時期は不明ではあるが、愛山は福沢の自宅を訪れたことがあったという。
「私がある時福沢諭吉先生の御生存の時分に、たった一度御訪ねいたしたことがありましたが、その時先生はおまへの家は何だと尋ねられたので、私の家は幕府の小さい家人でありまして、アアその時分は御目見え以上といつた役柄を勤めた家の子息であります、と御答えいたしましたら、先生はいささか冷笑の語気を現されまして
「さうであつたか、私はその時分幕府の旗本などと云ふものは御公卿様みたやうなもので、ごく詰らぬもののやうように思つていた」
と話されましたが、実際その通りであつたに違ひないと思います」[ii]
愛山と福沢は勝海舟を好まず福沢は「痩せ我慢の説」(二四(一八九一)年に脱稿、三四(一九〇一)年発表)で勝を批判した。愛山は『勝海舟』(四五(一九一一))を書く際に、徳富蘇峰が説得してようやく腰を上げたという経緯もある。会話の内容が幕臣の批判であることから推察してみても、似たような、海舟観を共有していたことは考えられる。福沢は二君に仕えないのが武士であるとし、海舟は旧幕臣であるにもかかわらず明治新政府の大臣まで勤めたために、その節操の無さを「武士道」の見地から批判した。その福沢の勝論について愛山は
「ことに翁が勝伯を非難したる議論には甚だ甘腹せざるものなれども幕士、もし薩長氏の為す所に畏服して一人だも起てこれに抗するものなく、唯々、諾々、そのまま天下泰平に帰したるならば恭順謹慎、誠にこの上なき結構のことのやうなれどもかくの如き無気力の人間のみを集めてはたして日本国は世界の競争に堪へ得べきやいなや。日本国のどこにも容易に他人に屈せざる気概あり、その信ずる所に従て死に得べき節義あり、男気あり、瘠我慢あり、国の細胞総て健全なるがゆえに国運も繁昌す」(前掲)
と述べ福沢の勝への批判に一定の理解を示している。日本人が無気力であるというのは、既存の権力に対する抵抗精神のなさとして、しばしば論じられている。例えば、津田左右吉もその一人であり、終戦後、日本人は無気力だからあの戦争が起きたと批判している(拙著『津田左右吉大日本帝国との対決』勉誠出版を参照)。懐疑精神のなさと、それからくる現象への盲目的追従を無気力という言葉で表しているのである。
福沢も、愛山も、勝海舟論を通じて人々の抵抗の精神がなければ未来を創造していくような活力は無いことを述べている。福沢と愛山は会話の内容を見ても分るように、武士道を拠り所にして相互の理解を図った。この頃には、愛山自身が福沢に対して尊敬の念を持ちはじめたのであろう。従ってこの哀悼の意の言は、実際に福沢を知る者の認識が反映されていたのである。
拝金主義の擁護
さらに注目したいのは、愛山は
「彼は日本の人民に、天地の間に頼むべきものは、自己の手腕と此手腕と此手腕を客観的に表はしたる黄金のみなる事を教えたり」[iii]
と、福沢の「拝金宗」は、その時代における便宜的な主義であり、当時の日本が必ず学ばなくてはならなかった教訓として評価している点である。福沢門下の高橋義雄などが〈拝金宗〉を鼓吹した時代でもある。

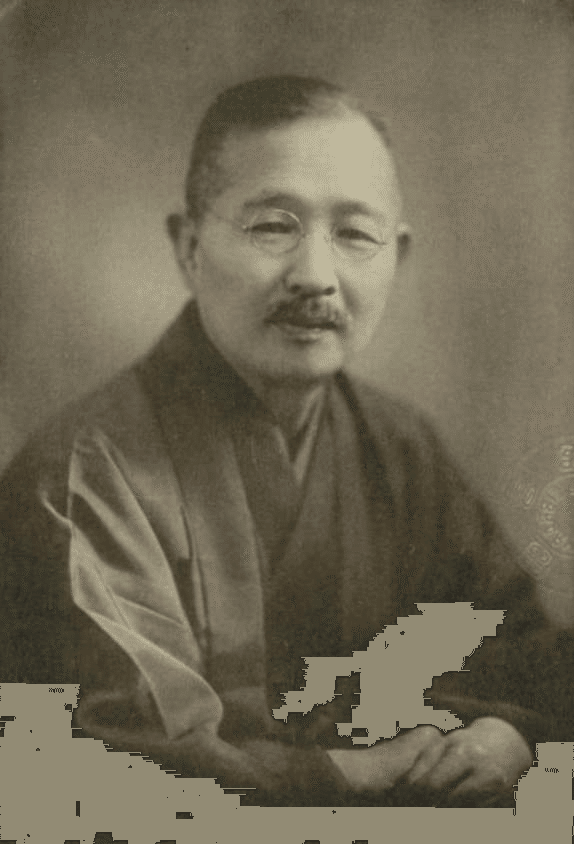
結城大佑氏(慶應義塾ニューヨーク学院(高等部)教諭)によれば、高橋義雄は文久元(1861)年に水戸藩下級武士の家に生まれ、昭和12(1937)年に77歳で亡くなった。実業家として三井銀行、三井呉服店、三井鉱山、王子製紙といった三井関連企業を渡り歩き、特に三井呉服店で主導した経営改革は日本の小売業の近代化にも大きな影響を与えた。
愛山は明治四一年(一九〇八)に『現代金権史』で資本家を批判的に描いた。従って、拝金主義をそのまま肯定しているのではなくあくまでも、「その時代においては仕方がなかった」としている所に留意すべきなのである。「拝金宗」は愛山にとっては自由主義・個人主義的傾向として認識されていたのであった。
「そもそも個人主義、自由主義を経済学の原則と立てて、それを金科玉条と守るに至りたるその議論を歴史上より見ればこれ即ちこれによつて国家の力を増さんがためなるに外ならず」[iv]
と述べ、明治初期は国家の力を増進させるという優先順位に従うのが道理であると見なした。それは政府ということではなく、国民の存在も含まれているのは言うまでもない。しかしそれは同時に、その時代によって富を増した資本家と労働者の対立となって現れていく。資本家が育っていない時代、労使対立が起きた時代、それを順番通りに見ているのが愛山なのである。福沢はその時代に必要なことを訴えたのであり、愛山は彼のおかれた立場を理解したのである。
ここにも徳川時代の陽明学者中江藤樹の〈時〉〈処〉〈位〉に依拠して判断を下すという思想に近いものを感じる。必ず時代状況を見なければならず、それには局所的な見地からでは判断がつかない。専門を超えねばならない。そして、分際をわきまえながら、全体性への志向を失わない。

あくまでも自由主義、個人主義が供する目的は、国家の経済的側面の増強で、それらは究極的には平民級への富の分配にも結実する。そして、その後に想定される必ず大資本家からの平民に加えられる圧力からの擁護をしなければならないとも言う。国家自体が「巨大な会社組織」のようになり、経済界を支配下に置く展開を想定した。
明治三八年(一九〇五)の『国家社会主義梗概』を見ても分るように、愛山は平民級への「物質的満足」ということを重視しつづけた。
「(七)物質的満足 共同生活の大義は家人父子の情誼をもつて人心を固結するに在り。これを為さんがためには賢者をして位に在らしめ、能者をして職に在らしむるに在り。是に次ぎて起るべき問題は如何にして人民に物質的満足を与ふべき乎是なり。(中略)貧富の運命は人民自から取る所にして国家の知る所に非ずと云ふは我先皇先民の道に非ず。ベンタム・ミルの徒又曰く 国家の目的は国民の最大多数の幸福を与ふるに在り。 国を治るはまづこれを富饒にするにあり。管仲が衣食足りて栄辱を知ると云ひ、孔子が人民はまづこれを富ましめて、しかる後にこれを教ふべしと云ふもまた物質的満足をもつて急務とするものなり。これに於てか社会政策なるものを生ず」
愛山の理想とする仁政は物質的満足なくして、精神的安定もまたありえないということであった。また、ミルとベンサム(注:文中はベンタム)の名前が挙がっているように、愛山の国家社会主義はベンサム、ミル的な「功利主義」に帰着するところがあった。
功利主義は現代では適用が難しい思想である。人々に多大な被害を与えながら生活をしている人間が大勢いたとして(ニートなど)、「最大多数の最大幸福」に基づくならば、ニートに支配され、その社会自体を殺してしまいかねない。また、社会主義革命では、この論理が貫徹され、人民大衆という大多数の幸福のためならば、少数の特権者は犠牲にされてしかるべきだとされたということにもなる[v]。
大多数の貧民に生きた愛山の頃と、大多数が中産階級になってしまった現代(今では多少違うが)では、時代背景が違いすぎるが、彼の時代に功利主義を強調するのはやむをえない面があった。
愛山の後年の福沢論は肯定と否定が入り混じった評価となっている。例えば、三九年(一九〇六)の『現代基督教会史』は最終的な福沢論といえるのだが、それをみると物質主義は時代の要請であり、福沢の鼓吹者たる役割は認めると述べた後に、
「彼れは到底処世接物の現世主義より外に眼を転ずる能はざりき。されば彼の宗教を見るやまたただ浮世の一方便を以てするのみ。「手を合はせて拝みさへすれば神なり仏なり」とは彼のかつて説きたる所にして彼の宗教に対する思想はついにこの範疇を出づること能はざりき」[vi]
とその宗教的無関心に問題性を見るようになった。 愛山については北村透谷がなしたように、「唯物主義者」といった批判が多いが、それはありえない。愛山は「人間は唯物主義でも唯心主義でも生きていけない」ということをよく理解していた。そのことは、彼の福沢論から証明されており、 彼の複眼的思考は単一的な価値を肥大化させることはない。

[i] 『国民新聞』明治三四(一九〇一)二月九日
[ii] 『勝海舟』 改造社出版 昭和一四(一九三九) 一二頁
[iii] 『国民新聞』明治三四(一九〇一)二月九日
[iv] 「渋沢翁の位置」『山路愛山選集第一巻』 萬里閣書房 昭和三(一九二八) 四五三頁
[v] 佐伯啓思『自由とは何か』 講談社現代新書 平成一六(二〇〇四)七〇頁
[vi] 『基督教評論・日本人民史』所収「現代日本教会史論」 山路平四郎校注 昭和四一(一九六六) 五七頁
