
眠れない夜なので普段話す機会のないこと書いてみる
起業して当初、裏方に徹すると決めて表には出ないスタイルでやりたいと思っていたが、抑えきれない自己顕示欲をnoteでだけでも発散したいとはじめたものの、結局表に立つことも増えて6月以来書いていなかったが、今夜は寝れないのでテーマを決めずに書いてみる。
書きたい内容はあったがいろんなことを気にして言葉にできずにモヤモヤしていた。
なんか、こう見え方を気にする自分の良くないところが出てしまう。
この"見え方"というなんとも曖昧模糊なものに振り回されてきた人生である。人からどう見られるか、人からどう見られたいか。
他者の価値基準に合わせて服装も表情も話し方も均して、本当の自分ではない社会人としての別人格を演じてしまう。社会人のコスプレである。

そんな自分ではない自分を演じながら、大きな保険業界の歯車の一つとして回り続けていくことに、己の中の何かが爆発して研究の事業化のタイミングであまり迷わずスパッと辞めた。
ゆえに、猫シャツを着ているのは自分が自分であるための意思表示のようなものなのである。
もちろんそんな深いことは考えず好きな服を着る幸せを謳歌しているだけという説もある。

好きな感覚で好きな服を着たいと思い出したのはいつからかと思えば、南米での彼らとの出会いが大きかったのではないかとふりかえって思う。

南米パタゴニアにかつていたセルクナム族。
南米大陸の先っちょ、極寒の地に住んでいながら裸族であった彼ら。基本裸、寒い時は火にあたりラッコの脂を身体に塗り、毛皮を羽織る程度だったと言われる。
(ちなみに普段からこんな格好ではなく祭りの時に木の仮面を被り精霊に扮したものの写真であると伝わる。)
そして、ヨーロッパの宣教師が訪れ、服を着ることを教えたが、洗うということを教えず、不潔から疫病が蔓延して滅んだと一説には言われており、セルクナム族はもういない。
なんとも儚い彼らである。
私は彼らに出会って10年。心を奪われっぱなしである。
このセンセーショナルな見た目もさることながら、彼らは人類の歴史で前に進み続けた者の血を引くことも魅力に思う。
それは、人類がアフリカに誕生し、世界の各地に散って行ったわけであるが、ある者はヨーロッパに。ある者はアジアに落ち着き、それでも進む者は、ベーリング海峡を渡り、北米・中米を南下し、南米に到達。さらに進み続けた人類が最後に辿り着いたのが最南端パタゴニアである。

その末裔が表現するものが先述のアレである。
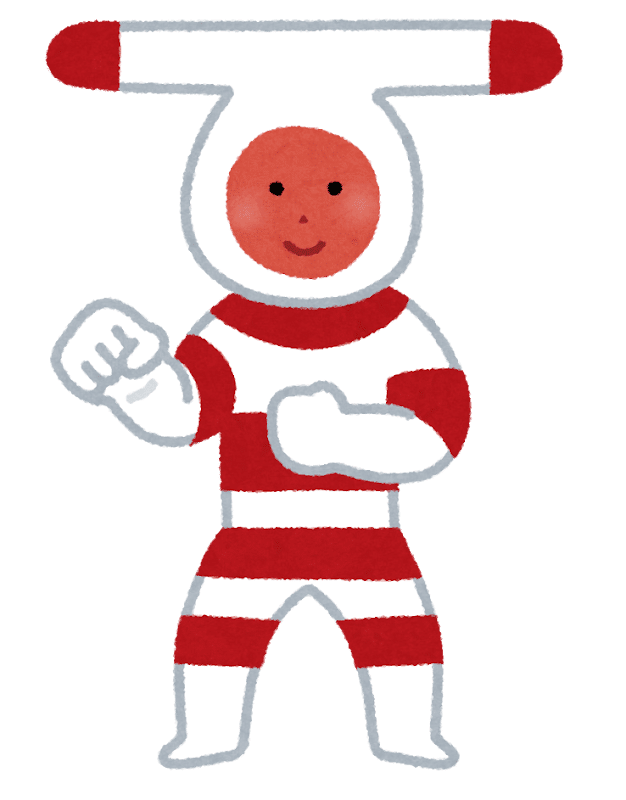
たまらんよい。
自然と共に暮らした彼らを傲慢な価値観で滅亡に追いやった当時のスペイン人たちを批判したところでもうなんともならないのだが、悲しい。
かといって、現代にそのままのスタイルで彼らが残ったかといえば絶対にそうではないだろう。
きっとノースのダウンジャケットとか普通に着てると思う。
それでも彼らの精神と独特のセンスには敬意を表したいし、いつまでも語り継いでいきたい。
さて,もう一つ私の心を掴んで離さないのが、人類の最後の到達点のひとつイースター島。

ハワイ・NZ・イースター島へ分かれる。
正式にスペイン語でパスクア島であるが、ここは周囲2000km 人の住む島が無い。
タヒチから辿り着いた彼らの船旅は想像を絶する。島の無い方向に船を出し命を落としたものもいただろう。
イースター島は言わずもがな、モアイ像で有名である。
モアイは集落の守り神であり、そのほとんどが海を背にし立っている。"立っていた"が正しい。
今立っているモアイは全て現代に立て直されたものである。

ここは日本企業の協力で立て直されたことで有名。
モアイは全てうつ伏せで倒されていた。
今でもうつ伏せに倒れたままのモアイも島内で見ることはできる。
なぜ、モアイは倒されたのか。ここでは起こりうる人類の未来の一つが既に起きていた。
火山島で絶海の孤島イースター島はかつて木々に覆われた緑の島だったとされるが、現在はほとんど大きな森は存在しない。ほぼ草原である。
ポリネシアを経由し人類が移住し、定住。各地に集落が栄えたとされる。
その集落の守り神として彼らはモアイを建立したといわれる。その大きさが集落の力を表すとされ、次第に巨大化していったとされる。
人口が増えれば増えるほどに、食料生産のため畑を開墾し、木を燃やし、森を切り開き続けた。
小さな島ではいつの日か森が消えた。
木を切れば土壌が流出し土地が痩せる。
多くの人口を支えるための食料生産ができなくなり、争いに発展する。
敗れた集落のモアイは倒される。
モアイは目に霊力が宿るとされ、それゆえ全てうつ伏せに倒されている。
争いと飢餓は絶えず、スペイン人に"発見"されるころには絶滅寸前であったという。

全てのモアイはここで作られたとされる。
よく見られる土に埋まったモアイは作る途中にうち捨てられたものである。
逃げ出すことのできない絶海の孤島。日に日に島の環境が悪化し、土地が痩せ飢餓が進み、漁に出るカヌーすら作れず、争いも絶えない中、彼らは神にすがったことであろう。
彼らの信じた神は何を今見つめているのだろう。
この話は太平洋の小さな島で起きた悲劇で片付けることはできない。
世界の人口は日々増加し、人類の食糧を確保するため森は開墾され、経済発展の名の下に山は太陽光パネルで覆われる。
今や人類は自らの未来を削りながら生存していくしかできない。地球から逃げ出すことなんてできない。周囲何千光年、住める星などないのだ。
若干思想くさくなるが、資本主義の世の中において経済発展は環境を犠牲にしながら行われていく。利潤と発展を求めれば、更なる土地を求め、資源を求め、森を開き山を削るしかない。
資本主義のいう【環境保護】は自らの経済活動を正当化するための言い訳でしかなく、再生可能エネルギーなんかも発電単体のCO2排出は小さいかもしれないが、それを製造するための資源掘削コストや設置するために犠牲になる自然と天秤にかけたら再生可能エネルギーの効率は悪い。
ましてや、カーボンクレジット制度など資本主義社会の中で形のないものに金銭的価値を勝手につけて、金を払い、勝手に許された気になるもので、正直反吐が出そうになる。(これ以上他者批判につながるので自重)
資本主義そのものは人類の歴史で生み出されたもので、否定するつもりはないし、社会主義者でも共産主義者でもないのだが、現代の「いきすぎた資本主義」には違和感を感じる。
大量生産・大量消費。先進国による途上国の搾取。持続可能の名の下に削られる自然という矛盾。
(その批判をその象徴であるようなスマホで書き込む私も矛盾した存在である)
持続可能とは、誰のための持続可能性なのか。
だからあまりSDGsそのものは好きではない。
弱小スタートアップとして世の中のトレンドに合わせてPRしないといけないジレンマは感じるが、目的を遂行するために飲み込みながらやっているのは悔しい。
持続可能性とは、誰も泣かない形でなければならない。
ただ誰かが搾取されたり、環境が削られてしまっては、それは欺瞞であろう。
私たちのテーマは、海の生態系バランスを取り戻すという壮大なチャレンジである。
人間如きが偉大なる自然の流れを変えようとすることは傲慢なのかもしれないが、壊せたのだから、戻すこともきっとできるだろう。
ただここでチャレンジしなければいずれイースター島と同じ未来が地球にも起きる。
「森がない」と多くの島民が気がつき、影響が顕在化した時にはもう手遅れであったことだろう。
今の地球はどうか、それはわからない。
しかしできることはすぐにでもやらなければならない。それだけは確かだ。
誰がやる、私がやる。
それは苦しい、苦しい。だが、それがいい。
前職では大きな業界の末端の小さな歯車で自分が業界ましてや世界を変えるなんてことはあり得なかった。
しかし、世界を変えることができる可能性がある。自分は歯車どころかモーターとして人々を巻き込んで小さくも世界を回す役割になれる。
苦しみ悩むことはあれど、それがこの上なく幸せである。
そのために大切なのは何か…。
解決への熱とやり切るという意気、そして突き進む力ではないか。
奇しくも商業高校から始まり100年を越える我が母校の校訓にたどり着いてしまったわけだが、おそらく真理であるのだろう。
己がやるのだと固く決め、10年以内に磯焼け解決に答えを出すと目標を掲げ、本格的にスタートアップとして方針転換することを決意。
(株式という資本主義の仕組みのど真ん中に組み込まれにいくのは皮肉なものだ)
その道を踏み出しての最近の悩みは、なぜ今磯焼けを解決したいのか。その熱が思ってるよりも伝わっていないということ。
この背景と考えを短い時間で伝えるのは非常に困難であるし、根の話し過ぎて伝えるべきものでもないかもしれない。
きっとここまで読んでくれたあなたはその一端を受け取っていただけたものかと思う。
これをもっと簡便にわかりやすく、短い時間でズドンと心を動かしたい。
書けば書くほど悩みの尽きない夜。
もう日が昇る。
