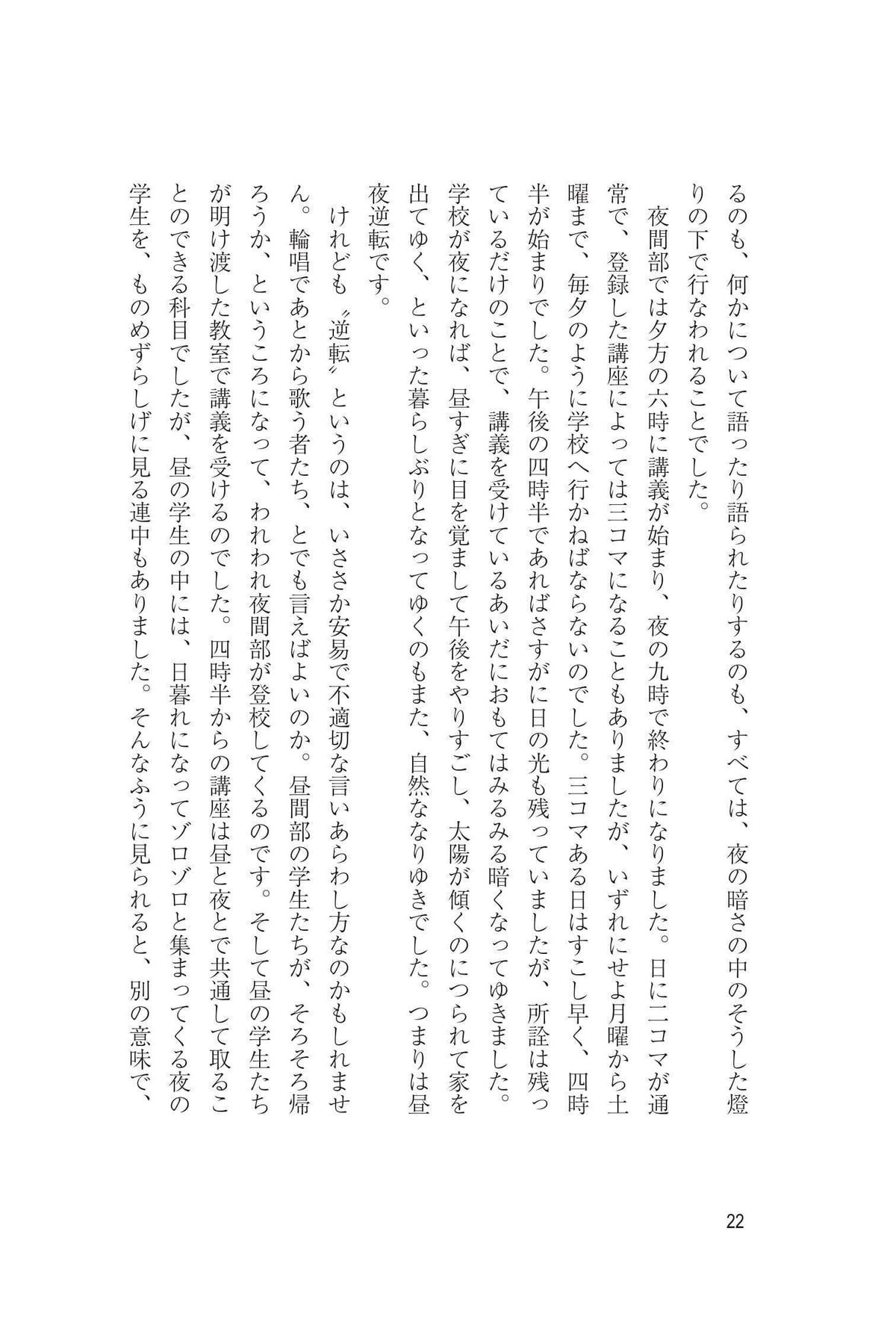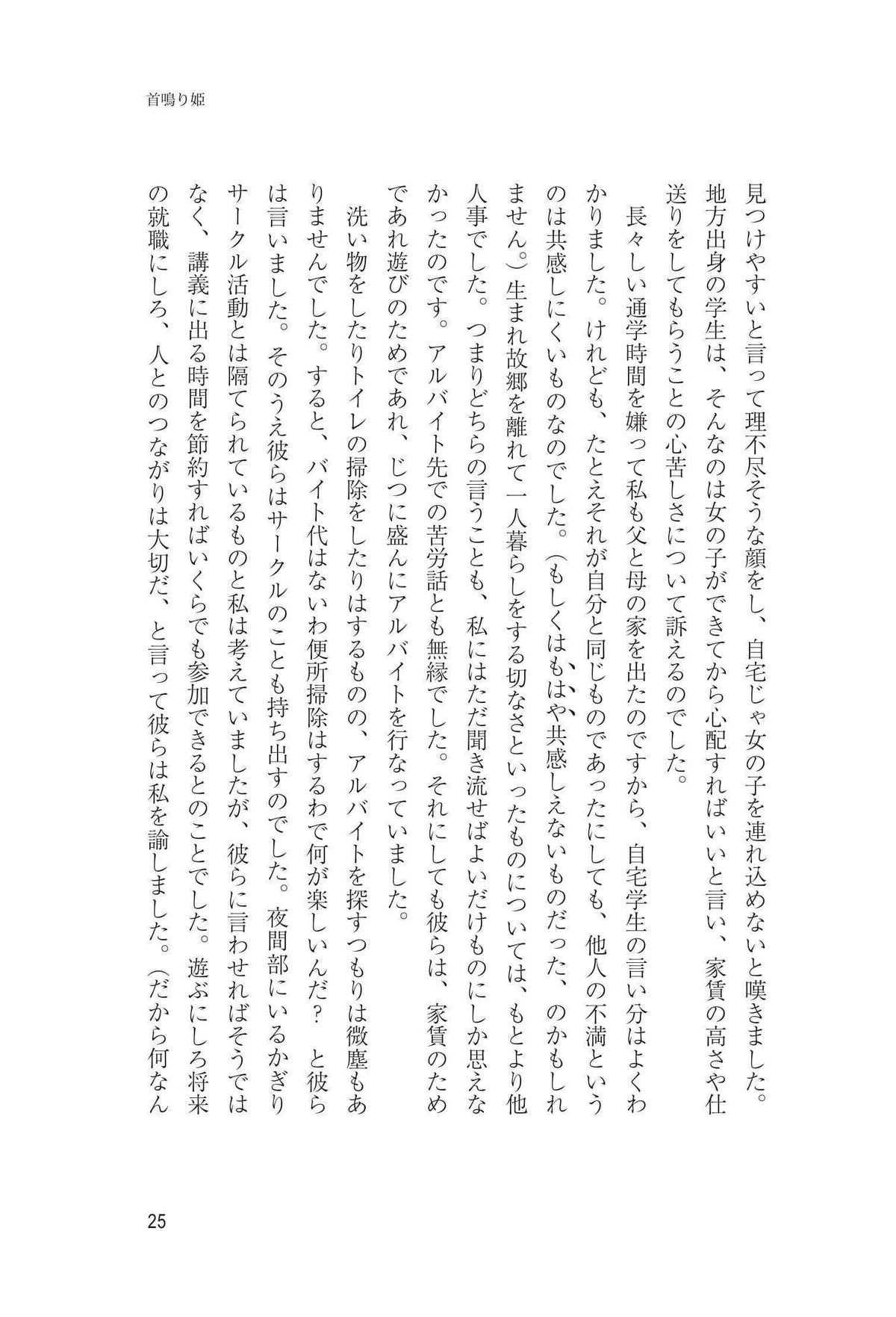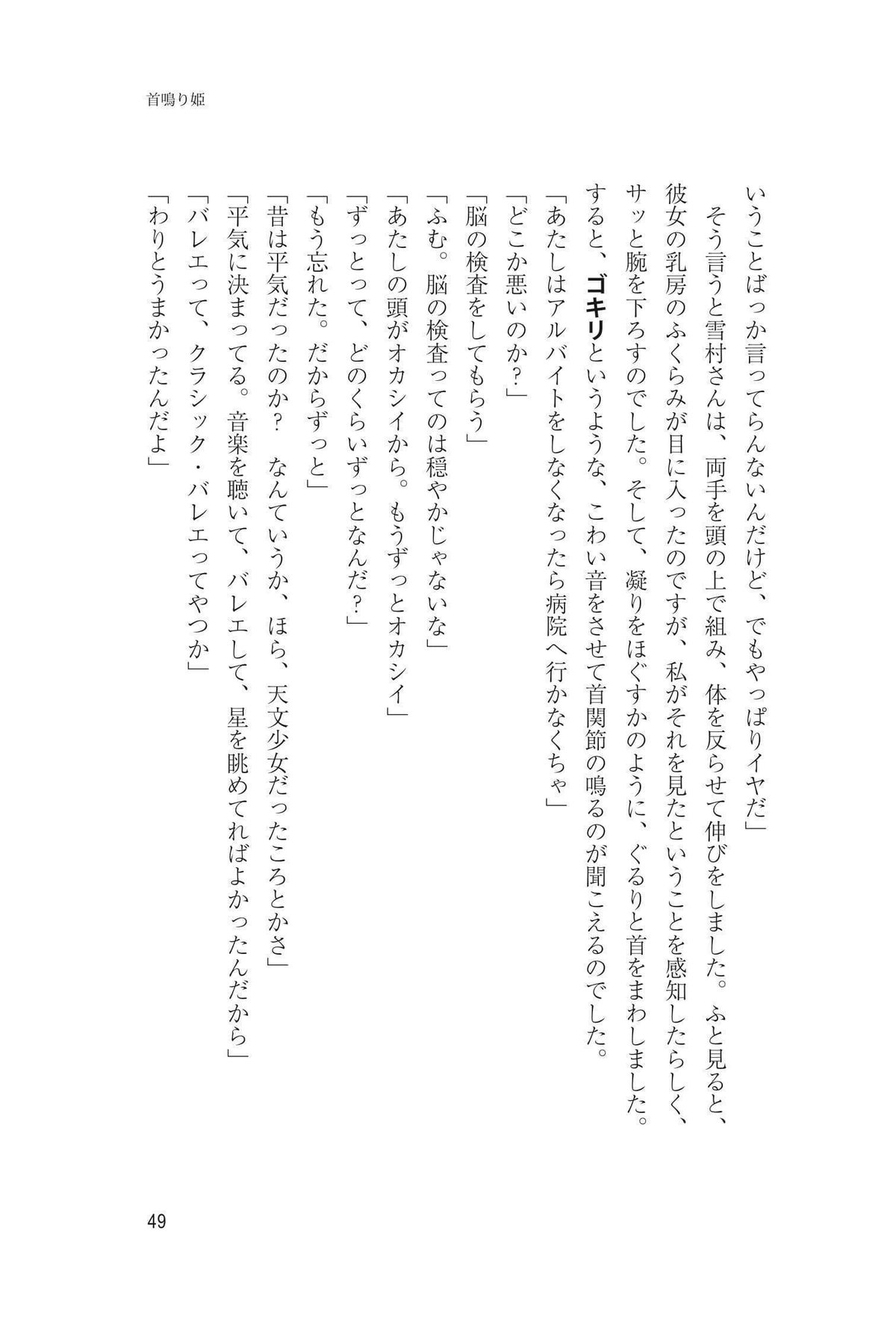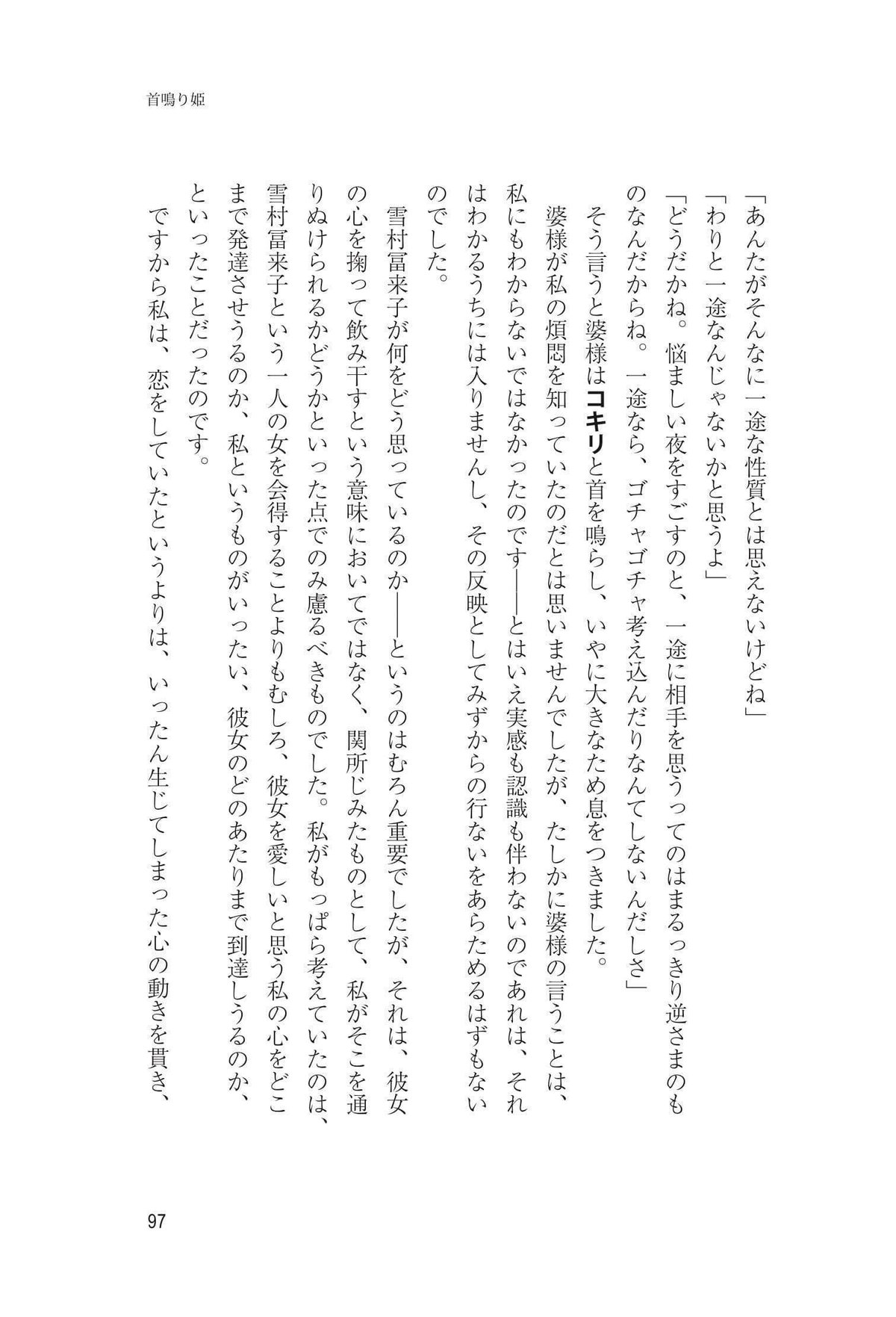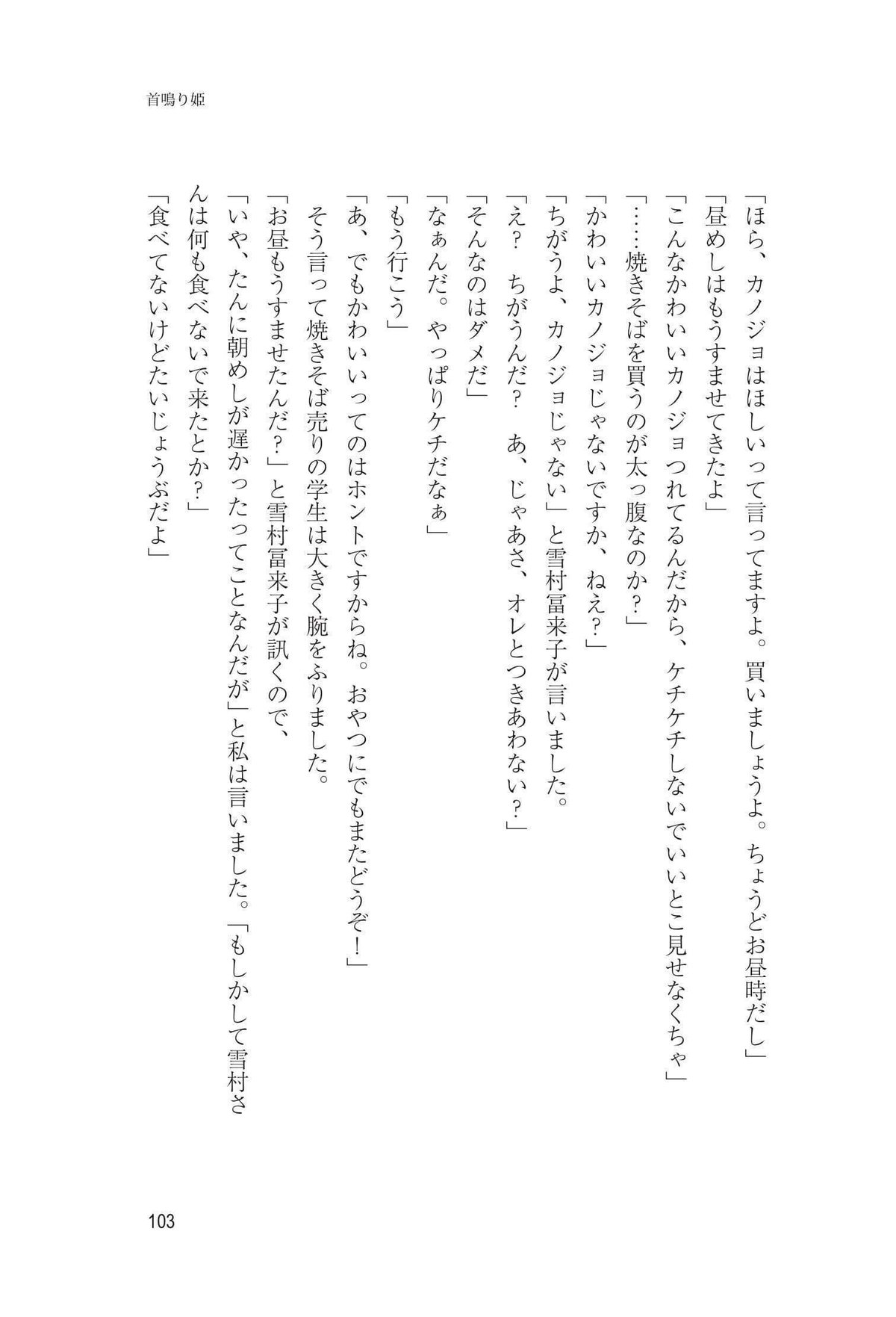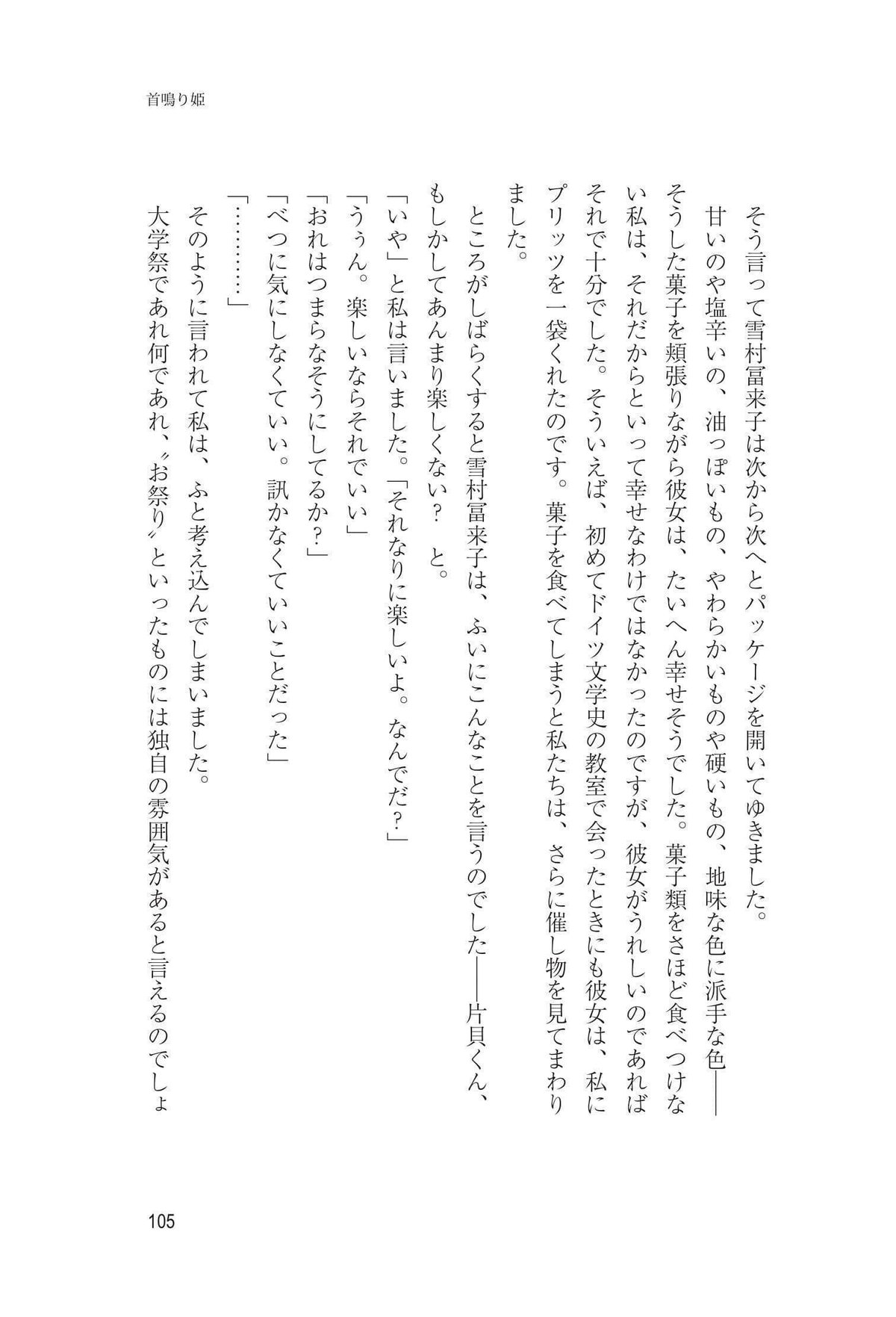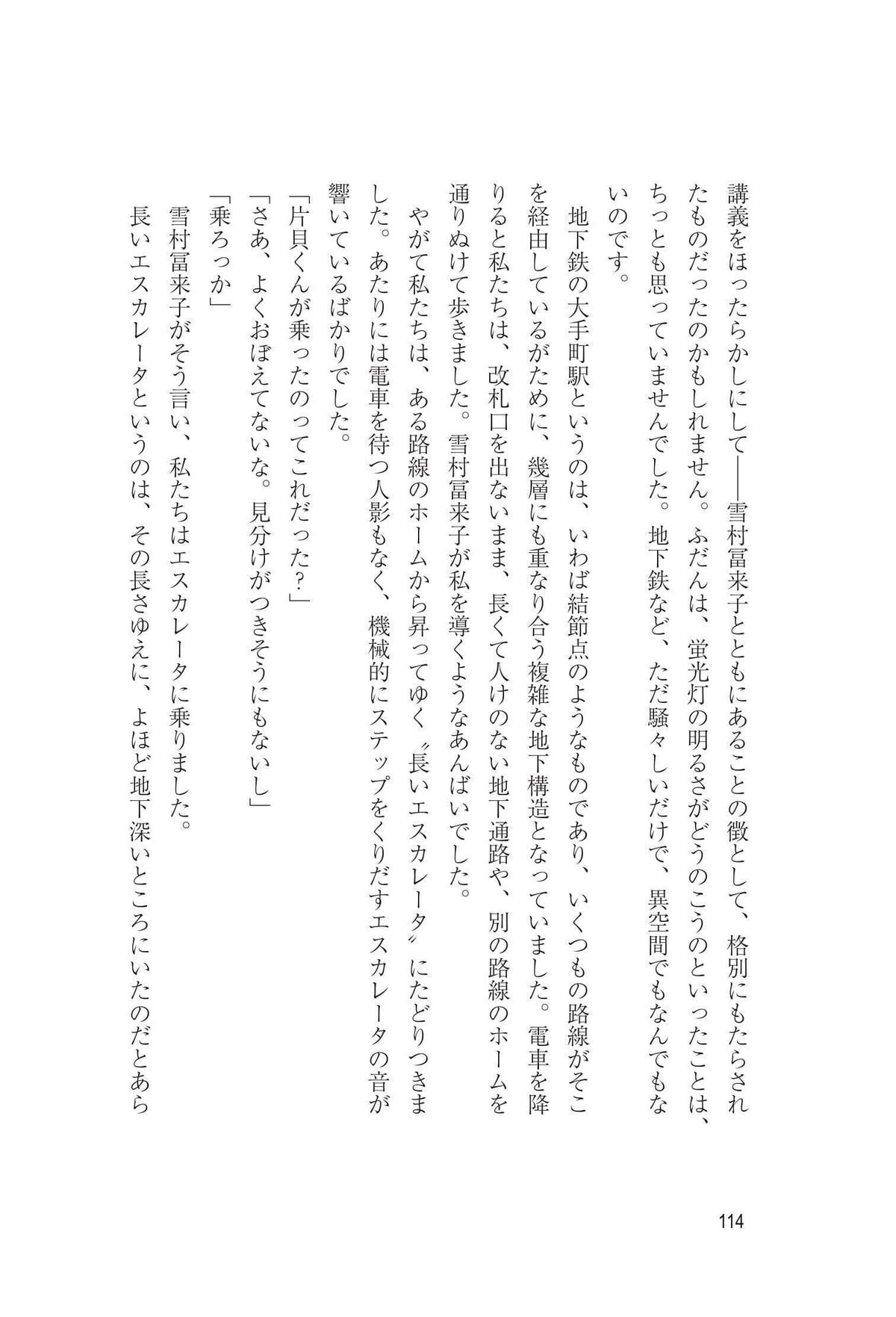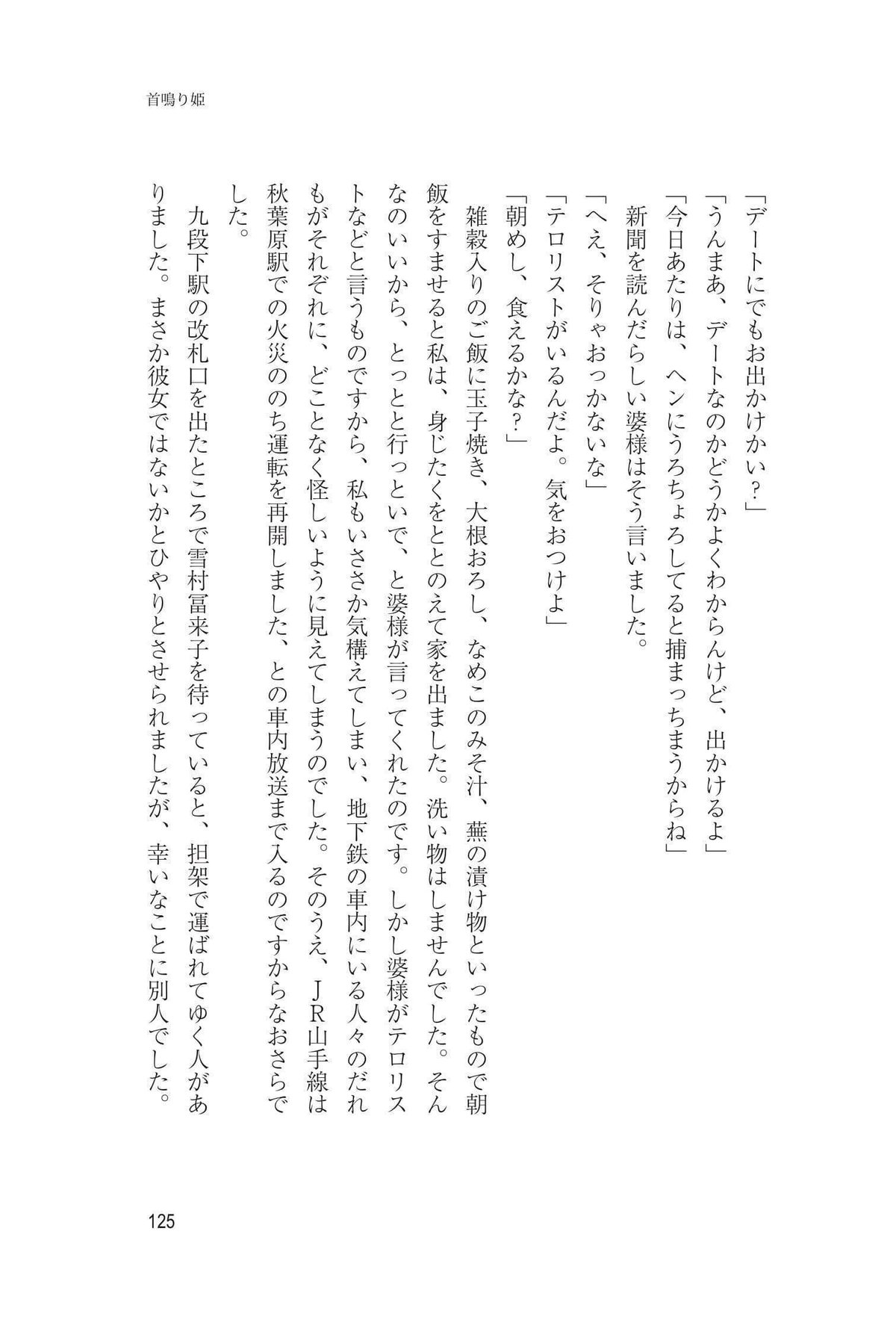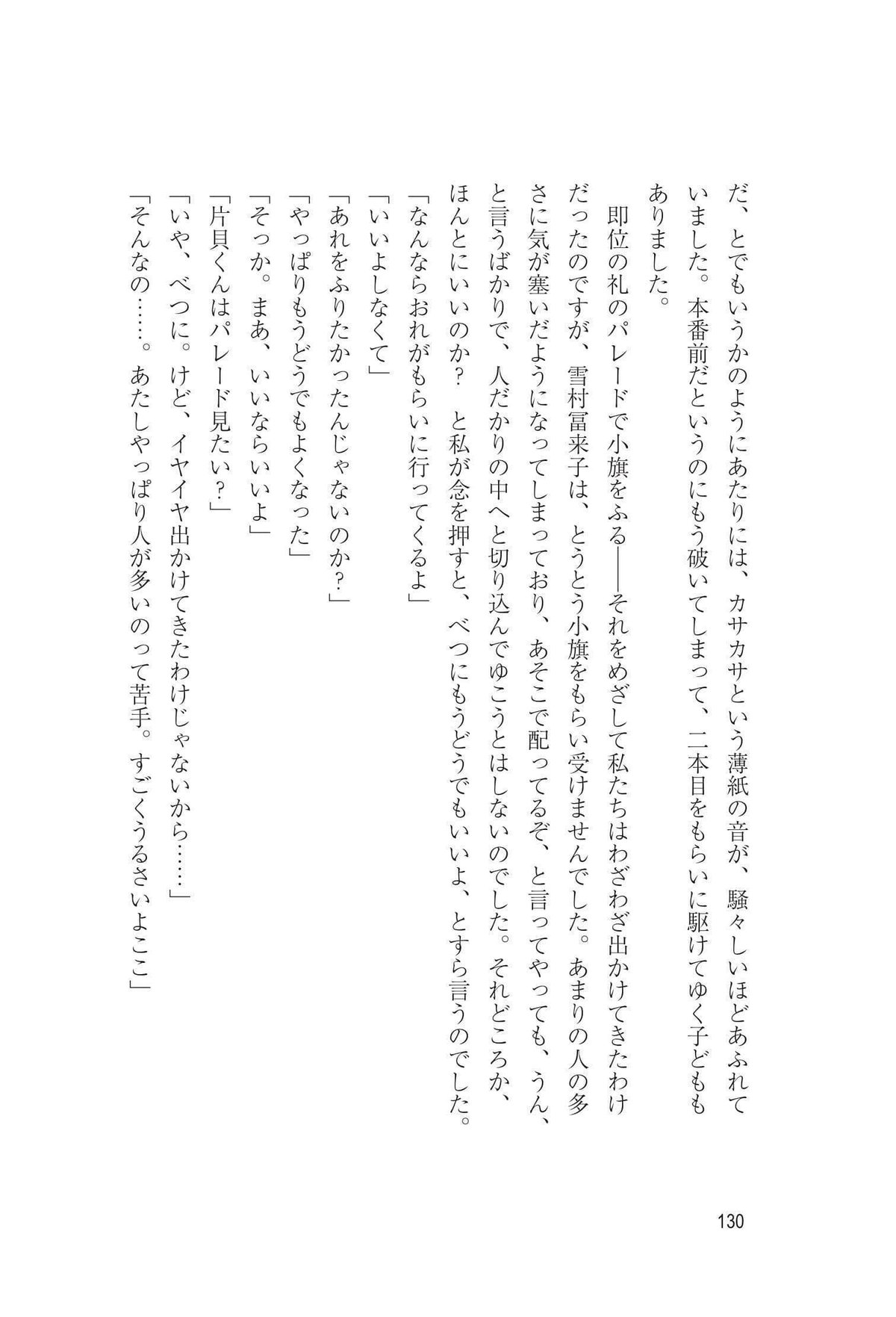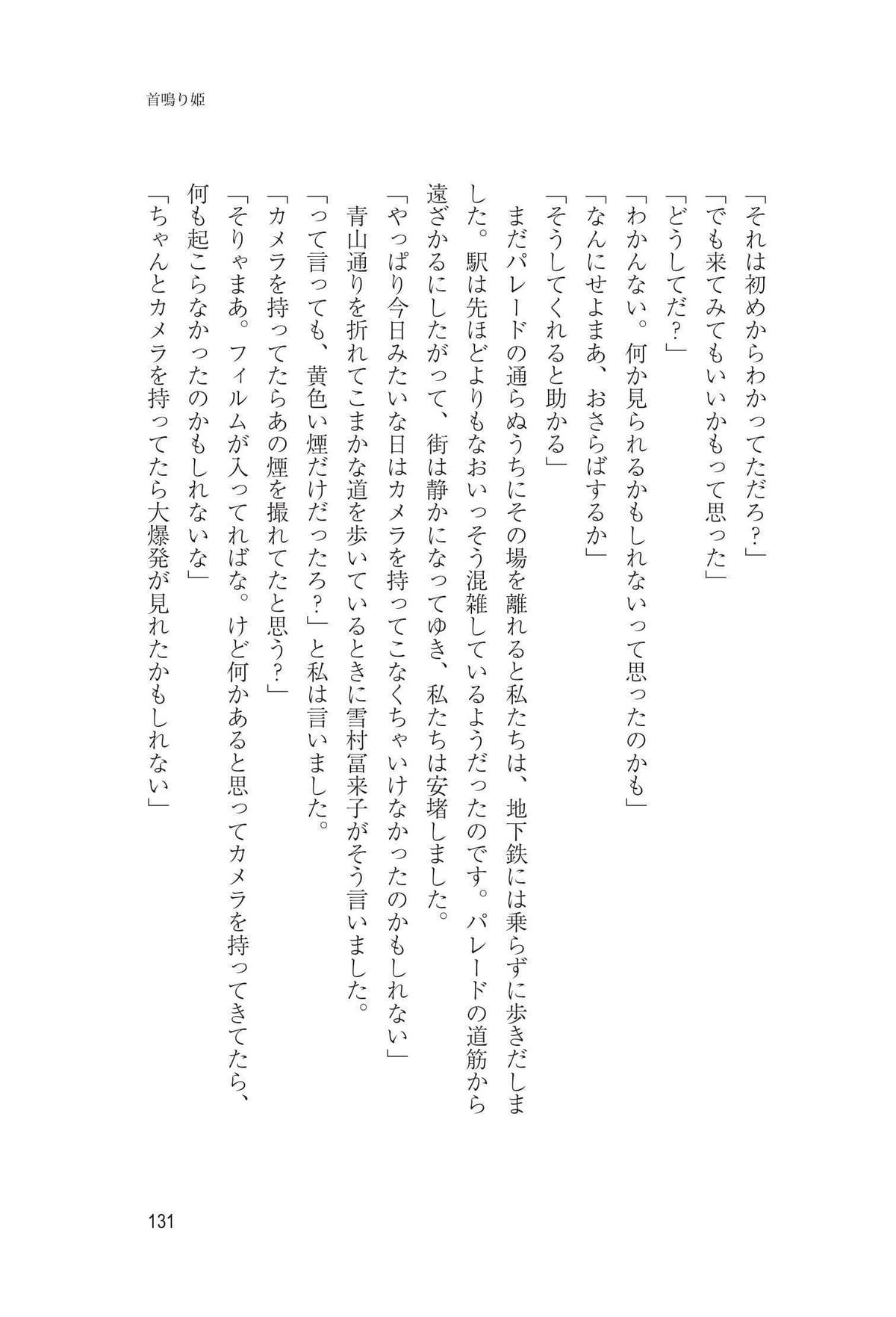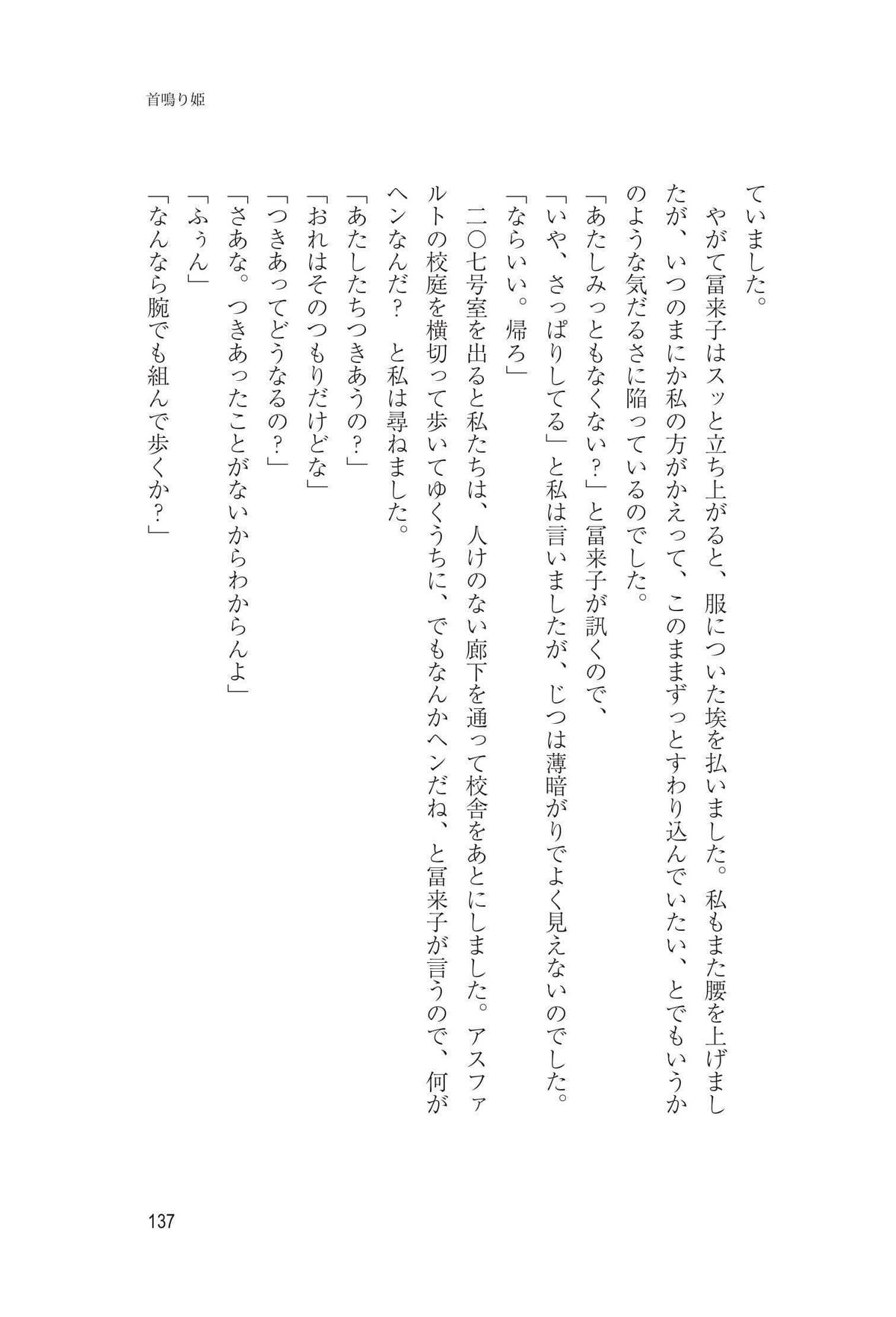首鳴り姫
書き下ろし作品
『首鳴り姫』2002年9月(講談社)
約400枚/400字詰め換算
遠く離れたところから見ると、そのときはわからなかったことがわかるようになる──というのは、特にだれが言ったということもない、ありふれた通念だと思いますけど、でもたしかに、作品を書いて出版した当時よりは、客観的な手ざわりがあるように感じられます。
──あんなに美しい夜はなかった
という帯の文言は、著者自身が書いたものですが、自らの作物のことをできるかぎり遠ざけたうえで、できるかぎりの愛凛を込めたつもりでした。にもかかわらず今の自分であれば、さらにもうひと息、巧みに遠ざけることだってできるかもしれない、などと、おこがましくも思ったりします。
カタガイくんとフキコちゃんには、ネカフェもなければスマホもなく、震災もなければコロナ禍もありませんでした。何かがなかったことによる制約もあれば、何かがなかったことによる自由もあった二人を、古き良き時代の恋人たちと呼べるのかどうか、わかりません。
文学において恋がどうあるべきなのか、これといった強固な見解は持ちあわせていないので、そのような書き手が恋愛小説を書いたらどうなるのか、という試みの姿勢はありましたけど、結局は〝恋愛小説みたいなもの〟でしかなかったのかもしれない、と思ったりもします。ところどころグッとこさせるものは、もちろんありますけどね!
ところで、データによるアーカイブのようなこの場で、紙書籍について言及するのは、ちょっとばかり気が引けるのですが(などと言いつつ、のっけから帯文のことを書いているので何を今さら、という感じですが)表紙にカンディンスキーの「Riding Couple(馬上の二人)」の絵を使うことと、ダストカバーのない角背の本にするというのは、著者のわがままでした。当時はそんなわがままも聞き入れてもらえたのです。美術館で実物を見たときには、思っていたよりも小さなサイズの絵で、ちょっとびっくりしたのをおぼえています。