
沼津高専を救いたい
こんにちは。NIT2.0の萩原です。
NIT2.0は学校を盛り上げるために活動している組織です。活動を始めた当初は5年生数人のちっぽけな組織でしたが、今となっては学年の壁を超え、50名以上の学生が一緒に活動したいと声をあげてくれました。
そして今、高専祭まで1ヶ月を切りました。
これから更に勢いを上げていき、もっと多くの人たちに僕たちの活動について知ってもらうつもりです。
このタイミングで、自分たちの活動を振り返り、もう一度気を引き締める気持ちでnoteを書きました。
目次
・はじめに
・NIT2.0が目指している世界
・NIT2.0の意味
・具体的な策とこれから
はじめに
5年生になったとき、日々の生活の中で高専を「卒業」することを意識するようになりました。
そのときに思ったのが、
「自分は4年間の学校生活の中で高専らしいことや高専じゃなきゃできないことをやってきただろうか」
ということでした。
高専に入学してから3年間を寮で過ごし、みんなで騒いで遊ぶのは楽しいんだけど勉強は中途半端。4年生になって寮を出てからもバイトと遊びに明け暮れる日々。これじゃ普通の高校生や大学生とたいして変わりません。
実際、4年の途中まで、高専生としての僕の技術力は本当に絶望的なものでした。
こうして高専生活を振り返ると、
「そもそも自分が高専に入ったキッカケは?」
ということを考えるようになりました。
僕の場合、高専に興味を持ったのはなんとなくプログラミングができたら将来カッコいいし楽しそうだったからです。
みなさんの場合はどうでしょうか。
元からめちゃくちゃ技術に興味があって高専に来た人はもちろん凄いと思いますが、そういう人って案外少ないと思います。大体の人は明確な目的は無いけど僕のように、「楽しそう」や「ワクワクする」といった漠然とした期待感を信じてこの学校にやってきたのではないでしょうか。
僕は、それでいいと思います。
その期待を、自分を信じてこの学校を選んでくれたあなたを失敗だなんて言って欲しくない。あなたはきっと間違ってない。
だけど、もしかしたら時間が経ってしまったり環境が変わってしまったりして「楽しむ気持ち」を忘れてしまっているかもしれない。
あの頃みたいにキラキラ輝いて楽しいことをしたい。
もっと良い雰囲気の学校にしていきたい。
だって僕たちはそれだけの力を持っているんだから。
こんな想いがNIT2.0を立ち上げた初期衝動です。
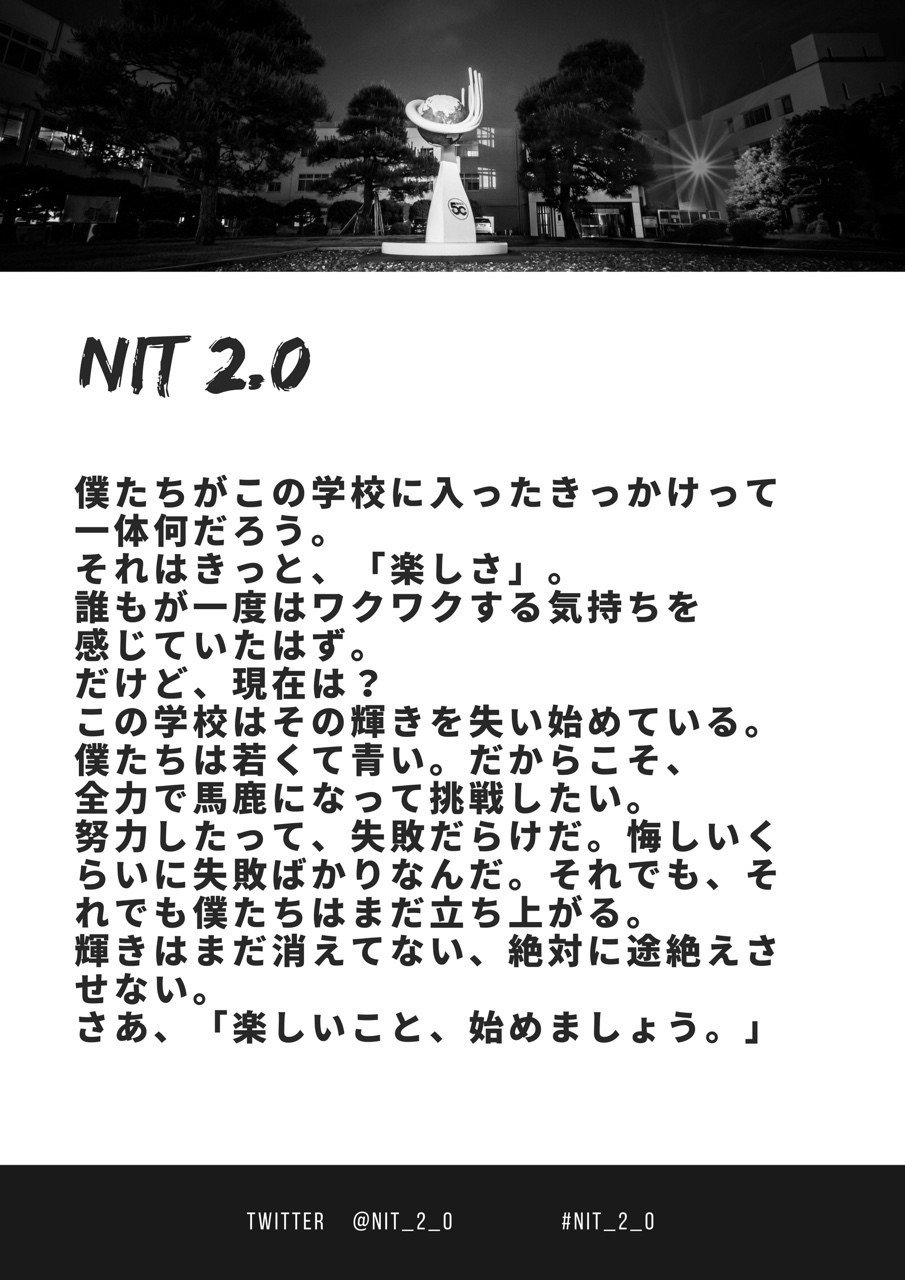
(ちなみに上の写真で写っている謎のオブジェは「成長の芽」といって、沼津高専の設立50周年に、高専生の成長を願って建てられたものです)
NIT2.0が目指している世界
次にNIT2.0が目指している世界のお話をしたいと思います。
僕たちが目指すのは、何かをやってみたい・挑戦してみたいと思った学生が最後までやりきれる世界です。
出る杭はこれでもかという程にボコボコに叩かれる世の中ですが、そんな波に負けることなく言いたいことややりたいことを言える・やれるような世界の方が素敵だと思います。
高専という学校には若くてエネルギーのある人たちがたくさん隠れています。だけど今の出る杭を打つ風潮のせいで新しくなにかをやってみるハードルが高くなっていると感じる人もいるのではないでしょうか。
でも、学生である今だからこそ挑戦する。失敗してもいいんです。そもそも技術開発なんて失敗の方が多いんですから。そうやって、失敗してまた失敗してまたまた失敗して、挫けそうになりながらも這いつくばって挑み続ける。そんな姿から輝きは生まれるんじゃないかと思います。そんな姿を馬鹿にする人もいるでしょう。笑いたきゃ笑えばいい。僕たちは駆け抜けていく。
そして高専にはそれができるだけの人材がいる。僕たちNIT2.0はそんな人たちが挑戦できる環境を提供して学校を良くしていく力になっていきたいです。
NIT2.0の意味
2018年の5月にNIT2.0は立ち上がりました。立ち上がったといっても、当時は何をやる組織なのか、自分たちの定義付けすら曖昧な状態でした。
そこで、NIT2.0というネーミングについて少しお話をしたいと思います。
みなさんはweb2.0をご存知でしょうか?
従来は情報の送り手と受け手は固定化され、送り手から受け手への一方的な流れしか存在しなかった状態から、webの登場により双方向なコミュニケーションが実現しました。ちなみにWeb2.0の主な例でよく挙げられるのがWikipediaです。
NIT2.0でもweb2.0のように。これまでのただ授業を受けるだけ、あるいはただスタッフに参加するだけの行動を見直し、自分から意見を積極的に言えるようにする。そんなことが起きたらいいなあと考えています。
興味をもった人は是非全文を原文のまま読んでみてください。
具体的な策とこれから
今までは、学内LT会を開催して好きなことをプレゼンしあったり、プログラミング講座を行って低学年がプログラミングに触れられる機会を設けたりしました。
そして現在は、高専祭での技術展示を実現するために組織は動いています。
高専祭での技術展示については近いうちに別の記事で少しずつ紹介していきたいと思います。
長くなってしまいましたが、これにて終了です。とにかく伝えたいのは、僕たち高専生はやればできるってことです。僕たちと一緒に楽しいこと、始めましょう!
これを読んでくれているあなたと共に活動できる日が来るのを心から楽しみにしています。
