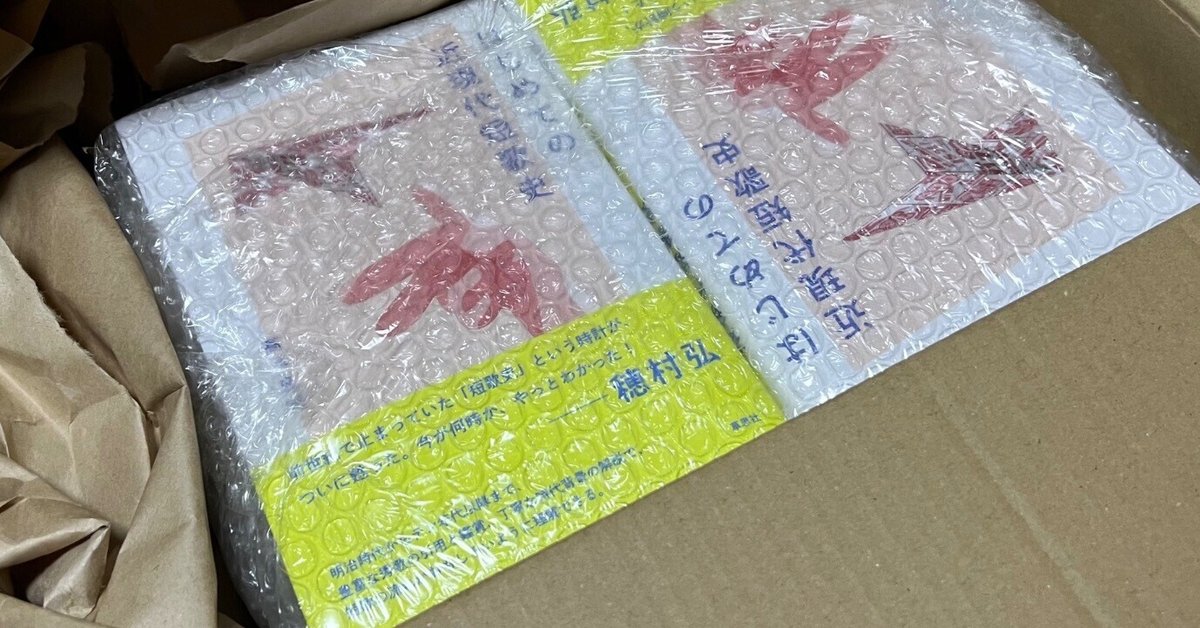
現代短歌史を取り戻せ(月のコラムにしなかった文章)
近頃は短歌シーンと言われます。ある場面(シーン)は前後から切り離されていて、茫漠たる時間の靄を浮游しています。それを過去と繋げて、物語として紹介するのが私のような短歌史記者の仕事です。
今年の8月に、明治年間後半から昨年2023年までの短歌を扱った『はじめての近現代短歌史』を書き終えました。書きはじめたのは去年の7月末だったので、ちょうど1年かかった形です。いろいろ苦労もありました。なぜそこまでして短歌史を書いたりするのかにはもちろん幾つか理由があります。
“現代”短歌の名の下に、例えば塚本邦雄を語るとしましょう。塚本邦雄は2005年に逝去しており、来年6月で没後20周年となります。20年前の過去が現在だとしたら、一体、いま生きている歌人はどこにいるのでしょうか。過去が“現代”になり、現在の現代は未だ来たらざる時間に放り出されてしまいます。故に次のように宣言することもできるでしょう。
“現代”を取り戻せ。私たちはここにいる。
短歌シーンと言われるようになったのは新しく、少なくともここ10年以内のことです。「シーン」は音楽、特にヒップホップ界隈で使われる言葉で、そこからの借用でしょう。短歌シーンと短歌史はどのように関係を結ぶことができるのか。篠弘の『現代短歌史』3巻本が刊行されて以降、現代短歌史は長らく止まったままでした。吉川宏志が『短歌研究』で70年代短歌史を書き始めたのは2021年のこと。とはいえ70年代も半世紀前のことがらです。人が短歌を続けていれば、その歩みはおのずと歴史になるはずなのに、歴史を書く営為は途絶えたままでした。どうしてこうなってしまったのでしょう。おそらく何かしらの時代的な背景が関係しているだろうとは思いつつ、答えを出すには手がかりが不足しています。少し視点を変えてみましょう。
2024年9月末、思潮社から『カッコよくなきゃ、ポエムじゃない! 萌える現代詩入門』が出版されました。タイトルが長いので以下『萌え詩』と書くことにします。著者は詩人の広瀬大志と書評家の豊崎由美。『現代詩手帖』で2019年から連載されていた対談の総集編です。現代詩史は短歌史と同様に、長らく60年代末で止まった状態となっていました。現代詩シーンも短歌シーンと同様にどこを漂っているのかよくわかりません。『萌え詩』はその状況に一石を投じる画期的な本です。
内容を少し覗いてみます。第1章「現代詩のフォッサマグナはどこだ?」では、その前後で詩のイメージが大きく切り替わる時代はどこかを探っています。フォッサマグナはご存じ地質学的な溝のこと。例えば「現代詩の断層」とかでも意味は同じでしょうが、まあ、フォッサマグナで喩えた方がかっこいいんだろうと思います。「カッコよくなきゃ、ポエムじゃない!」ですからね。ともあれ、広瀬は戦後詩のはじまる1950年代に第一のフォッサマグナを設定しています。ここでは詩人が歌謡曲や校歌の歌詞を書くというビジネスモデルが失われ、同時に詩の大衆性も失われたようです。そして第二のフォッサマグナが1980年代後半のバブル景気。ここで現代詩は“ポエム”の蔑称を与えられ、地位を失っていったと広瀬は解説しています。
『萌え詩』ではこのような歴史の把握からはじまり、近代詩はもちろんのこと、2020年代前半に登場した新人詩人まで縦横無尽に紹介されています。特に第7章「賞 must go on ――詩の賞をめぐって」は、駄洒落のタイトルとは裏腹に、かなり真面目に2020年、2021年の新人賞を受賞した詩人たちの作品を読んでいます。私にとってはここが一番の読みどころでした。
さてこのフォッサマグナを軸とした歴史の把握に基づくと、詩の地位が凋落する1980年代を境として、詩史をまとめる営為が失われていることが見えてきます。短歌の方では、1987年に俵万智の『サラダ記念日』がミリオンセラーとなり、サラダブームと呼ばれる社会現象を巻き起こしました。けれども90年代に入っても、70年代の短歌史は書かれませんでした。なぜなのか。答えを出すには、まだ何かが不足しています。
ここで、なぜ短歌史は書かれないのか、という問いを少し変形してみます。短歌史はどのように書かれてきたのでしょうか。私は先に、短歌史は時代ごとの短歌の場面(シーン)を過去と繋げて物語にしたものだと書きました。一ヶ月や一年といった短い期間の短歌シーンは「時評」や「年末回顧」といった形で総合誌上に掲載されています。けれども、それを物語として記述し、編集する営為は途絶えてしまった。ポストモダン批評を読んだことがある人ならば、ここで「大きな物語」の終焉をキーワードとして何か言いたくなるかもしれません。実際、ニューウェーブ短歌はポストモダンの短歌という言葉で批評されたこともありますが、一旦その線は外しておきましょう。
念のため、近代短歌史の研究は80年代以降にも盛んに書かれていたことを注記しておきます。石川啄木、斎藤茂吉、北原白秋など、1880年代生まれの歌人たちには夥しい数の研究論文が書かれています。書かれなくなったのは、生きている人たちを含む歴史です。
そもそも、短歌史はいつから書かれ始めたのか。直近数十年の短歌史を扱った書籍が見えるようになるのは昭和初期です。例えば改造社から刊行された『短歌講座』シリーズでは、第3巻に「明治大正時代名歌鑑賞」と題して新派和歌の歌人が並べられているほか、第4巻では新興短歌のシーンを概説した評論が多数収録されています。この時期の書籍や雑誌をめくっていると、短歌シーンと短歌史は非常に近い距離にあったことが感じられます。書き手も若い人からベテランまで多様でした。若手による、書籍の形をとった短歌史記述の例としては、安部忠三の『歌壇史稿』や、渡邊順三の『史的唯物論より観たる近代短歌史』などを挙げることができます。
その昭和初期の短歌史は、戦後に再びまとめられることとなりました。木俣修『昭和短歌史』(1964)は、1957年から1962年に『短歌研究』上で連載されたものです。ただし、この本の記述は1953年で途切れています。木俣が前衛短歌嫌いだったことも影響しているでしょう。戦後には、短歌シーンと短歌史の距離が少し開いています。このあたりから、短歌史記述の担い手がベテラン歌人を中心とするようになっていきます。
戦後の短歌は、角川『短歌』1968年1月号から2年間「共同研究 戦後短歌史」として連載されました。時代としては学園闘争の時代とか、高度経済成長期とか言われている時期です。執筆は島田修二、上田三四二、岡野弘彦、篠弘、岡井隆の5人による交代制です。ここでは主に1965年までの内容が扱われました。この連載は書籍化されていません。その代わり、記述内容は篠弘『現代短歌史』3巻本(1983-1994)の資料となっています。
そして1965年以降、つまり昭和40年代以降の短歌史は、最近のことだからという理由で書かれないまま60年以上放置されてきました。短歌シーンの積層が短歌史になるまでの時間はさすがに開きすぎです。篠弘は1933年生まれで、それ以降の世代からは短歌史記者が生まれていません。なぜなのか。とはいえ、この観点からも何か言うことは難しそうです。
というか、そもそも、短歌が好きな人にとって短歌史は必須ではないのかもしれない……。お笑いが好きな人にお笑い史は必須ではないし、ヒップホップ・クルーにもヒップホップ史は必須ではありません。必須でないなら読まれませんし、読まれないなら書かれないことにも合点がいきます。私は学生短歌会でかなり早い段階に短歌史の勉強会を経験して、篠弘を短歌評論の親だと思って文章を書き続けてきましたが、短歌に短歌史があって当然だという前提自体が間違っている気がしてきました。そうなれば話が早い。こういう場合はだいたい市場の問題です。いまを生きる私たちにとっては、詩情(ポエジー)と同じくらい市場(マーケット)の話も大切です。
『萌え詩』には、なぜ詩が読まれないのかを市場の観点から分析した箇所がありました。
広瀬 何で詩が読まれなかったのかを市場分析の立場から単刀直入に言えば、マーケットに版元が投資しないからです。ではなぜ投資しないかと言うと、利益を回収できないから。その状態では流通へのプロモートは不可能なため、かろうじて自費出版によるリスクヘッジで詩集を出していくことが可能なくらいです
そのためにいまほとんどの詩集が自費出版の形をとっています。利益回収には時代ごとにいろいろな手法があったと思いますが、新しい詩の動きを敏感に察知し目を向けていかなければならない。
マーケットに版元が投資せず、自費出版で歌集が出版される構造は短歌の方でもだいたい同じようなものでした。9月の月のコラム「短歌ブームはだめなのか?」では、70年代以前の出版資本主義と短歌の関係として、そうした状況に言及しています。広瀬は引用文の前段で、詩人というビジネスモデルの崩壊に言及していますが、戦前の短歌の世界ではごく少数の例外を除き、歌人というビジネスモデルは成立していませんでした。
ところで、これは余談ですが、1950年代以前に詩人というビジネスモデルが盤石であった訳ではありません。明治時代末期に専業文学者を意味する「文士」は赤貧(とても貧乏な状態)の代名詞でした。山本芳明の『カネと文学』は、原稿料が上がり、作家が職業として成立するようになったのは大正8年(1919年)ごろであることを明らかにしています。詩人より稼げると言われる小説家でもこれですから、大正初期の詩人も赤貧です。すると、職業としての詩人が成立していた期間は、広く見積もって1920年代から50年代までの30年間となるでしょう。悲しいかな、詩情と市場の蜜月は近現代史のわずかな期間だけのようです。
ビジネスモデルの例として広瀬の挙げる詩人の名前には、与謝野晶子、北原白秋、石川啄木も混じっています。このうち啄木は明治45年(1912年)に没しており、原稿料で暮らすことのできる大正中期を経験することはありませんでした。
余談ついでに竹柏会の主宰である佐佐木信綱の家計事情も見ておきましょう。お金の話は楽しいですからね。もう少し続けます。『心の花』1949年1月号の「追憶」には、信綱が妻・雪子の追悼文として若いころを振り返った文章を掲載しています。
「歌を教へるのは道を教へるのである。師たる者は、親しみと共に厳然とした矜持がなくてはならぬ。たとへば金銭を借りるといふことは、そのことだけで相手に負ひ目を意識するやうになるから、道を伝ふる弟子からは決して金を借りるな」とは、亡父の遺訓であつたので、自分は五十年来その言葉を守りつづけて来た。同人の好意をうけたことはありはするが、金子を借りるといふことはなかつた。学者生活の苦しさは、今も昔も変りはない。〔中略〕同人からの謝儀と著書の収入とが全収入であつた。東大の講師は二十六年の長きにわたつたが、名誉講師とて、最初の数年は無給であり、やめても恩給もない。子女が多く、その養育、教育、ことに病気等、家計は実に苦しかつた。
信綱の文章からは、結社の主宰としての謝儀が大きな収入源となったことが示唆されています。竹柏会は大正年間を通して歌壇最大の結社でした。当時の主要短歌結社の雑誌上出詠者数を数えたことがあるのですが、竹柏会は当時権勢を誇った前田夕暮の白日社『詩歌』や歌壇を制覇したと言われるアララギよりも多くの出詠者を抱えています。アララギが竹柏会に追いつくのは大正末を待たねばなりませんでした。その主宰ですら赤貧の生活を送っていたとなれば、あまりに夢のない話です。特に東大の講師が無給だったという箇所は悲惨です。
けれども、近年の考察では信綱の記述に異議が申し立てられています。三枝昻之は次のように語ります。
しかし〔中略〕信綱には門前列をなす弟子への指導料やメディアへの稿料、講演の謝礼、そして歌人の安定的な収入の一つである新聞雑誌の選歌料を加えると、収入総計は堅く見積もっても国会議員と同額かそれ以上だったかと思われる。信綱は明治三十一年に「時事新報」の歌壇選者となってから新聞雑誌の選者を一生続けた。子だくさん家計、そして研究者としての高価な文献購入などを考えても、「追憶」が示す暮らしの苦しさをそのまま受けとるのま難しい。雪子の内助の力を強調するのが主意だろう。
三枝は信綱の家計について、支出から逆算すると収入もそれなりにあったであろうと推察しています。ここで「歌人の安定的な収入の一つ」として「新聞雑誌の選歌料」が挙げられていることを見落としてはなりません。具体的な金額は私も知らないのですが、大手新聞歌壇の選歌料は歌人一人を支えるのに十分な額であると言われています。
詩人は仕事にならないようですが、近年の歌人は「選歌」という形でビジネスモデルを確立しています。しかしこの仕事にはそれなりの権威が必要で、ポストも少ないため、必然的にベテラン歌人が就任することになります。全国の新聞を見ると年齢はだいたい50代以上です。それまで歌人は霞を食って生活している訳ではないので、他に食いつなぐための仕事をすることが一般的です。こう考えてみると、いま崩壊しているのは歌人のビジネスモデルではなく、“若手”歌人のビジネスモデルだということになります。
話を短歌史にもどします。戦後において典型的に短歌史記者の役割を担ってきたのは、大学教授のポストを得た歌人たちでした。代表的な名前を挙げてみましょう。小泉苳三も、木俣修も、篠弘も全員が大学教授の職に就任しています。また全員が文学博士の学位を取得しています。従って、これを短歌史記者の典型的なビジネスモデルとして考えることができそうです。ところがゼロ年代以降、歌人が大学教授の職を得ることは少なくなっていきました。詩と同様に短歌がハイカルチャーとしての性質を失ったことに加えて、博士号の制度も変化し、アカデミアが生粋の研究者を教授として雇用するようになったことも影響しています。文学研究の世界では、若手の作品を研究対象にすることが基本的にありません。大学教育の現場で、歌人は短歌創作の授業を非常勤講師として担当するばかり。非常勤講師で食べていくことはできません。
ここまで扱ってきた事象を勘案すると、次のような仮説を立てることができます。昭和初期、つまり短歌史記述の黎明期はベテランも若手も短歌史を書いていたが、次第にベテランによる短歌史の囲い込みが生じた。結果として、大学教授職にあるベテラン歌人が短歌史を書くようになり、短歌シーンと短歌史には距離が生まれていった。そしてアカデミアの変質により、大学教授職にあるベテラン歌人が新たに生まれなくなったため、短歌史記述の営為は停止したのではないか。ようやく時代的な背景が見えてきました。
私はずっと篠弘の仕事を引き継ぎたいと思っていました。けれども、『はじめての近現代短歌史』を執筆するにあたって荻原裕幸さんにインタビューをしたときのことです。篠さんの仕事を引き合いに出すと、荻原さんは「篠さんがああいう仕事をできたのは、時代背景もあってのことだからね」と言われました。ここまで考えてきたことは、荻原さんの言葉を発端としています。
時代背景を加味すると、これから従来のような短歌史記者はもう現れないでしょう。短歌の世界は昭和初期と比較にならないほど複雑になり、短歌史を書くには少なくとも短歌に専念できる環境が必要です。現に私はいろいろあって仕事をやめました。しかも結社によって歴史観が微妙に違っており、ベテラン以外が短歌史を書けば四方八方から批判を受けることは必至です。これでは誰も短歌史記者なんかやりたくありません。私はこれらのことに後から気づいて、なんという貧乏くじを引いたものかと大いに嘆きました。軽い気持ちで草思社から短歌史本執筆の依頼を受けてしまったのが運の尽きか。いや、不幸自慢をしても始まりません。しっかりしなければ。それに依頼は企画出版であったので、数ヶ月は生活できるくらいの印税を得る予定です。これには大変助かりました。
私がここまで短歌史記者という役割の背景を考えてきたのは、「“現代”を取り戻せ。私たちはここにいる。」と宣言するためのことです。まずは若手歌人のビジネスモデルを確立すること。そしてもっと気軽に短歌史を書いていくこと。この二つを実現しなければ、ちょうど今ゼロ年代短歌があまりよく見えないように、20年後に現在の短歌の状況がぼやけてしまうでしょう。
短歌史を書き、それを共有することは、未来に対する投資になります。『はじめての近現代短歌史』のおわりには、「本書は短歌史の入門書です。この入門は、既存の短歌史を読むことだけでなく、書くことにも開かれていると信じます」と書きました。これからは短歌史記者の新しいあり方を考えていかなければなりません。この営為に、誰か同伴者が産まれることを、私は願っています。
