
【レポート➀】~こども家庭庁が解説~「自治体こども計画」と「こどもの意見反映」自治体に求められることとは?
放課後NPOアフタースクールでは、5月30日(木)に「自治体のこども計画策定とこどもの意見反映~放課後の居場所づくりはどう変わる?~」と題し、行政の方々をお招きしてオンラインフォーラムを開催しました。
開催レポートとして、3部に分けて講演内容をお伝えしていきます。
本記事では、こども家庭庁担当者による解説のもと、自治体こども計画やこどもの意見反映に関連する国の施策・指針について紹介します。
▼登壇者のプロフィールなどはこちらから
「自治体こども計画」と「こどもの意見反映」自治体に求められることとは?
こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当)佐藤 勇輔 氏
(代理 参事官補佐 新田 義純 氏、高山 健太 氏)
こども基本法とこども大綱
・こども基本法
令和5年4月に施行されたこども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。同法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定、自治体こども計画の策定及びこども・若者の意見の反映などについて定めています。

・こども大綱
令和5年12月22日、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」が閣議決定されました。こども家庭庁のリーダーシップの下、「こども大綱」に基づき、政府全体のこども施策が推進されていきます。
こども大綱では、こども施策に関する6つの基本的な方針として、こども・若者の権利の保障、最善の利益を図ること、こども・若者の意見を聴き、対話しながらともに進めていくことなどを掲げています。また、こども施策に関する重要事項は、こども・若者の視点に立って、分かりやすく示すため、ライフステージ別に提示されています。

自治体こども計画とは?
自治体こども計画の策定は、こども基本法第10条において、地方自治体の努力義務とされています。
都道府県は国のこども大綱を勘案し、また、市町村は国のこども大綱と都道府県こども計画を勘案し、それぞれ、こども計画を定めるよう努めるものとする。(こども計画の策定・変更時は遅滞なく公表すること)
自治体こども計画は、以下のポイントをおさえて作成するものとされています。
◯ こども大綱を勘案し、地域の実情に応じて策定する
◯ こども・若者、子育て当事者等の意見を聴き、計画に反映する
◯ 各法令等に基づくこどもに関する計画等を一体的に作成することにより、
・こども施策に全体として横串を刺すこと
・住民にとってわかりやすいものとなること
(これをみれば我が自治体のこども政策の全体がわかる)
・自治体行政の事務負担軽減にもつながること
が期待される。
◯地域の実情に応じて個別に計画を作成し、それらを相互に関連計画として位置付け、内容に応じて適宜参照しあうなど整合を図ることで、それらの計画を自治体こども計画と位置付けることも可能。
自治体こども計画策定のためのガイドライン
こども家庭庁は、自治体こども計画策定の支援の一環として、ガイドラインを作成しました。ガイドラインには、自治体こども計画策定の工程「事前準備→調査→策定→推進」と工程ごとに取り組むべきことの概要、ポイント、自治体における事例が記載されています。
▼自治体こども計画策定のためのガイドライン(概要版/全体版)

こども・若者の意見反映とは?
こども基本法第11条では、こども施策の策定や実施等において、こども・若者等の意見反映に必要な措置をとることが国及び地方公共団体の義務として定められています。
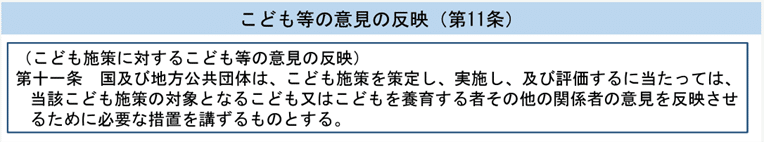
こども施策の基本方針は、こども・若者の意見を聴いて、その声をまんなかに置いて、対話しながらともに社会をつくることであり、こども・若者の意見を聴くことによって、状況やニーズをより的確に踏まえ、施策がより実効性あるものになることが期待されます。
また、こども・若者にとって自らの意見が反映され、社会に変化をもたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、社会の一員としての主体性を高めることにつながります。

国によるこども・若者の意見反映の取組「こども若者★いけんぷらす」
「こども若者★いけんぷらす」は、全国の小学1年生から20代のこども・若者を対象に希望した方が登録し、対面やオンライン、アンケートやチャットなど様々な方法で、省庁側が意見を聴きたいテーマやこども若者が意見を言いたいテーマについて、意見を伝えることができる仕組みです。集まった意見は、国の審議会や様々な会議などで参照しながら政策への反映を検討し、その結果として、反映されたかどうか、されなかった場合にはなぜか、という点について、フィードバックを行うこととしています。
▼こども若者★いけんぷらす(こども家庭庁HP)

こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン
こども家庭庁では、こども・若者の意見反映を推進していくため、ガイドラインを作成しました。ガイドラインには、こども・若者の意見反映を進める工程を「企画→事前準備→意見聴取→意見反映→フィードバック」の順に整理し、工程ごとに重要なポイントや留意点、自治体の取組事例等をまとめています。
▼こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン(概要版 / 全体版)

こども・若者の意見反映サポート事業
こども家庭庁は、自治体への支援として、実際に意見を聴く場づくりについての相談応対やファシリテーターを派遣するサポート事業を実施しています。概ね、3ヶ月ごとに希望する自治体を募集するサイクルで運営していく予定です(2024年5月30日時点の情報)

その他、こども・若者へ向けて、こども基本法やこども大綱などをわかりやすく説明する動画やパンフレットも作成し、こども家庭庁のHPに掲載しています。
オンラインフォーラム内で取り上げた質疑応答を一部ご紹介
Q.こどもの意見反映、こども計画策定によって、居場所づくりはどうなっていくべきですか?
令和5年12月に閣議決定された「こどもの居場所づくりに関する指針」において、こどもの居場所づくりを自治体こども計画に位置付けて計画的に推進することが求められています。また、こども大綱においても、こどもの居場所づくりに関する指針に基づき、こども・若者の声を聴きながら居場所づくりを推進することを規定しています。自治体においては、居場所づくり指針やこども大綱を踏まえて、自治体こども計画においてその方針や施策を位置付け、地域の実情に合わせて、こどもの声を聴き、こども・若者の視点に立った多様な居場所づくりを推進していくことが期待されています。
また、民間団体が主な居場所づくりの担い手となることも多いので、官民の連携・協働も重要となります。
▼こどもの居場所づくり(こども家庭庁HP)
こどもの居場所づくりに関する指針(概要版 / 本文)

今年度より各自治体におけるこどもの意見反映や計画作りが本格的に検討されている中、国のガイドラインやどのようなサポートが得られるのか、参加者の皆様にとっても関心の高いポイントでした。この度のご登壇、ありがとうございました。
文:コミュニケーションデザインチーム・岸田
▼開催レポート②「~滋賀県・川崎市の事例から学ぶ~自治体のこども計画策定とこどもの意見反映」はこちら
▼開催レポート➂「~南あわじ市・放課後NPOアフタースクールの事例から学ぶ~こどもの意見を反映した放課後の居場所づくり」はこちら
■行政関係者向けメールマガジンの登録受付中
放課後児童クラブや放課後子ども教室など、子どもの居場所づくり等に携わる行政関係者の方に向けて、子どもの声を聴く事例や、様々な自治体の取り組みなどの記事を、定期的にメールマガジンで配信しています。
ご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。
