
見落とされてきた小さな声に耳を傾けて【13歳だった私が知らない3.11③ 】
あまりに大きな災害のなかで見落とされがちだった小さな声。最終回となる第3回では、生きづらさを抱えた人、女性や性的マイノリティの人の声に耳を傾けてきた二人の記者さんに、わたしたちの日常と災害時のつながりを聞きました。
特別企画 13歳だった私が知らない3.11
大きな津波や原発事故。当時13歳だった私は東日本大震災を知っているけれど、直接の被害があったわけではなくて、語れるほどに濃い記憶や知識があるわけじゃない。今の私や日本社会が、どれほど震災に影響されているのかも、きっと分かっていない。
そこで、震災について取材してきた6人の記者さんにインタビュー。皆さんが被災地で見たこと、人に接して感じたことを通じて、私が知らない3.11に向き合ってみようと思います。
日々の小さな「生きづらさ」は、非常時と地続き。
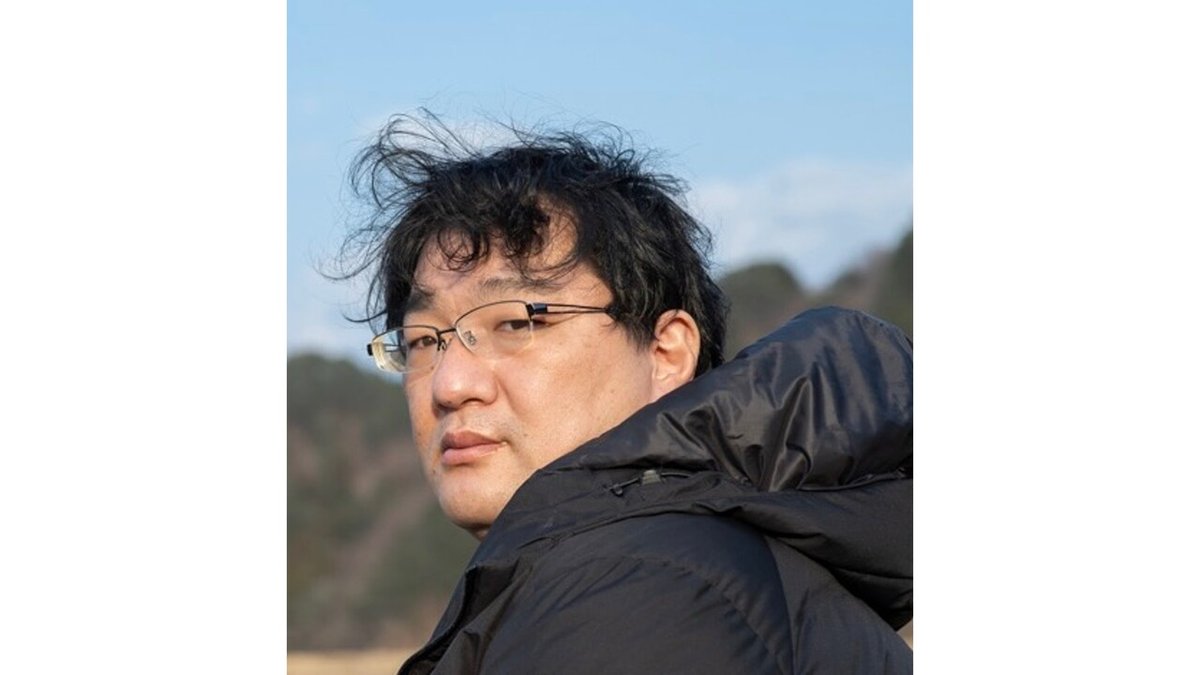
渋井哲也さんノンフィクションライター
東日本大震災直後より、災害トラウマや災害関連死に関するテーマを取材。震災を経験した個人の生活の変化や、現在の姿に焦点を当てた執筆活動を行う。
渋谷記者のTwitterはこちら
関連記事:
復興ムードの中で「自分だけは忘れないように…」身重の妻を亡くした美容店主の思い。営業は再開したものの…
震災直後、災害トラウマにより、東北沿岸部の自殺率が急激に上がるのではと危惧し、被災地の自殺率やメンタルヘルスに関心を持ち、取材することに決めました。
実は、東北の沿岸部は、心療内科など生きづらさを感じた人の相談先が少なく、震災以前から自殺率が高い地域なんです。もともとリスクが高い地域だからこそ、注視していました。
当時は、東京都の精神医療のチームも、深刻な被害を受けた陸前高田市で、メンタルヘルスのサポートを行っていました。結果として震災前と震災直後の自殺率は変わらなかったのですが、原発事故のあった福島県では、宮城県、岩手県よりも震災に関連した自殺が多く報告されています。「原発さえ無ければ」という言葉をメモに残して自殺された福島県相馬市の酪農家の方もいらっしゃいました。原発事故で原乳を出荷できなくなった苦しい経営状況下、悩み吐き出す場所がなく、自分の言葉をメモに残すしかなかったのではないかと思います。
生きづらさは、悩みを打ち明けることができないことや意見が届かないことから生まれるのだと思っています。

ただ、震災があるからメンタルヘルスや自殺が悪化するのではなくて、もともと自殺のリスクが高くなっていると、震災が起きたときに数として現れます。被災地は、震災以前からSOSを出せる(心療内科のような)場所が少なく、悩んだ時に受け止めてもらえる環境がなかったことが、災害という非常事態時に課題としてあらわになったと思うんです。
「生きづらさ」という切り口で取材を続けていく中で、その芽のようなものを見つけることもありました。
例えば、東北沿岸部のある小学校の図書室には、専任の先生がいないうえに、基本的に鍵が閉まっていて、子どもたちが自由に出入りできないようになっていました。学校の先生のほとんどは子どもたちの成績をつけて「評価しなければならない」立場である一方で、保健室や図書室の先生は子どもたちにとって数少ない「評価しない」先生ですよね。そのような「評価しない」先生がいないことは、子どもたちから小さな悩みを吐き出せる場所を奪い、想像以上に大きな影響を与えているかもしれないと感じています。
日常と非常事態時は地続きだから、こうした小さな「生きづらさ」や脆弱さが、震災などの非常時に、深刻な課題になるのではないかと思うのです。

現在は自分で発信できるメディアがあるので、震災の体験談や個人の生きづらさは記録に残しやすくなりました。一方で、情報量が多すぎて、誰の体験をどう解釈したらいいかが分かりにくくなりました。また、事実の一面だけが切り取られて震災の体験談が美化されてしまうことも多いように感じています。
例えば、当時津波が迫ってきた際に中学生が小学生の手を引いて逃げたという報道が話題になり、多くの人が「十分な津波に対する避難教育のおかげで、自主的に逃げることができた」と絶賛していました。そうした面がないわけではないですが、実際は現場にいた大人の助言があったからこそ逃げることができたのです。
教訓を正しく伝えていくために、被災者の体験談の一面を切り取るのではなく、当時の状況やその背景も含めて伝え続けたいと思っています。
災害は日常に。「かわいそうな誰か」だけのものじゃない。

泉谷由梨子さん
ハフポスト日本版副編集長
東日本大震災時には、毎日新聞の宇都宮支局に勤務し、震災直後の宮城県や、福島県から避難した方々を取材。2012年1月からは、福島支局で被災地の取材を行った。
泉谷記者のTwitterはこちら
関連記事:
【3.11】東日本大震災を経験したセクシュアル・マイノリティの人々が、「わかりづらい話」を集める理由避難所で性行為を強要、DVが悪化… 被災地であった女性への暴力その後【東日本大震災】「絆」の危うい弊害。災害女性学を提言する研究者は「ネットワーク」を訴える。【東日本大震災】
震災の取材を通して、復興の過程の中で、女性やマイノリティの方の視点が見落とされやすい構造になっていると感じました。特に感じたのは、福島第一原発の事故によって放射能の影響を受けた地域から避難した方々への意向調査に関わる取材をしたときです。
事故前の居住地に戻るかの調査でしたが、その対象が世帯主だったんですね。つまり、実質的にはお父さんの意向調査になっている可能性が高かったんです。
自治体は街の復興のため原発から飛んできた放射性物質を取り除く除染作業を進めますが、その規模や街の復興計画を決めるために、どれくらいの人が戻ってくる意向があるのか知ることが目的でした。私が取材した女性の中には「私は帰りたくないんだよね、お父さんは帰りたいと言っているのだけど…」と答える方も沢山いました。
新型コロナウイルスによる特別定額給付金が個人ではなく、世帯主に支払われる方式だったこと(その後DV被害者らへの救済策が準備された)は記憶に新しいですが、日本って世帯主義なんですよね。この地域に住んでいる全員の問題であるはずなのに、この女性の意見は届いているのだろうか、女性の他にも子供たちの意見は届いているのだろうかと不安に思いました。子どもは案外都会の方がよかったりもするんです。一方で、自治体としては何とか帰ってきてほしいという想いもあり、取材している中で、一体町のために人があるのか、人のために町があるのか、わからなくなることもありました。

津波の被害を受けた宮城県・石巻市荻浜港付近 2021年2月撮影
平常時の視点が被災した時に如実に現れるので、日頃から女性やマイノリティの方などをはじめとした多様な人の視点で考えることは大切です。被災時に困ったことをセクシュアル・マイノリティの方に取材したとき、被災後プライバシーがなくなることを危惧して、自分の部屋にあったBL本を封筒に入れて隠したとお話してくれた方がいました。
家が倒壊して本棚が露わになったり、避難所での集合生活でプライバシーが守られなくなってしまうことは非常時にはあり得ること。ここでより本質的な問題は、仮にプライバシーを守れなくなり、意図せずカミングアウトせざるを得なくなった場合に、どれほど差別されることなく暮らせる社会なのかという点だと思います。震災が起きた時だけではなく、日頃からどれだけ多くの方が、自分とは状況が異なるかもしれない多様な人の視点で考えることができているかということが大切になります。

(宮城県・石巻市の日和山から街を見渡す 復興の工事が進む 2021年2月撮影)
日本には被災したらある程度環境が悪くてもしょうがないという雰囲気があると感じています。ですが、日本の避難所の環境は世界と比べても劣悪です。
2019年末発表の調査で、日本は気候変動の影響を受けている国ランキングで一位(「世界気候リスク・インデックス」2020年版)になり、もう災害は日常化する時代にきています。災害はすごくかわいそうな誰かだけではなく、今後日本に住む全員が経験しうることになります。
だから「備えは自助努力」というのは個人としては大切ですが、社会のインフラとしてそろそろ避難所に対する考え方をアップデートしていかないといけないと思います。
ここまで、女性やマイノリティの話をしてきましたが、その人々のニーズを満たすことは、他の様々な人の避難生活も改善します。例えば女性にとって必要と言われている避難所のプライバシーの問題も、現代の意識や若い世代の感覚では耐えられないもので、本当は皆が求めていることだったりします。女性やマイノリティのニーズは、みんなが生きる力を回復するためのニーズなのです。
今後、災害が日常化するという意味では、災害は若い世代の問題とも言えるかもしれません。不満なことも言わないと分からないので、日常から発言していくことが一つひとつを変えていくことになると思います。
================
3回にわたり「特別企画 13歳だった私が知らない3.11」を掲載してきました。
この10年の間で、震災を踏まえて自分の生き方や社会について考えてきた記者さんと、それをしていなかった自分との差は、知識量だけに留まらないと感じました。
震災を見る視点や深さが違えば、今の自分の考えや行動も違っていた気がします。
それでも、わたしたちは3.11の延長線にある社会を、そして次の震災に遭う可能性が十分ある社会を生きています。
今知れたのなら、遅くないと思いたいです。
この企画の締めに、震災を自分ごとに考えていきたいです、という安易な決意表明はそぐわない。ただ、みなさんが記者さんの言葉から気づいたことが、これから持つ意見や行動に届くことを願っています。
*本記事中の画像は渋井記者・泉谷記者に提供いただいています。
いいなと思ったら応援しよう!

