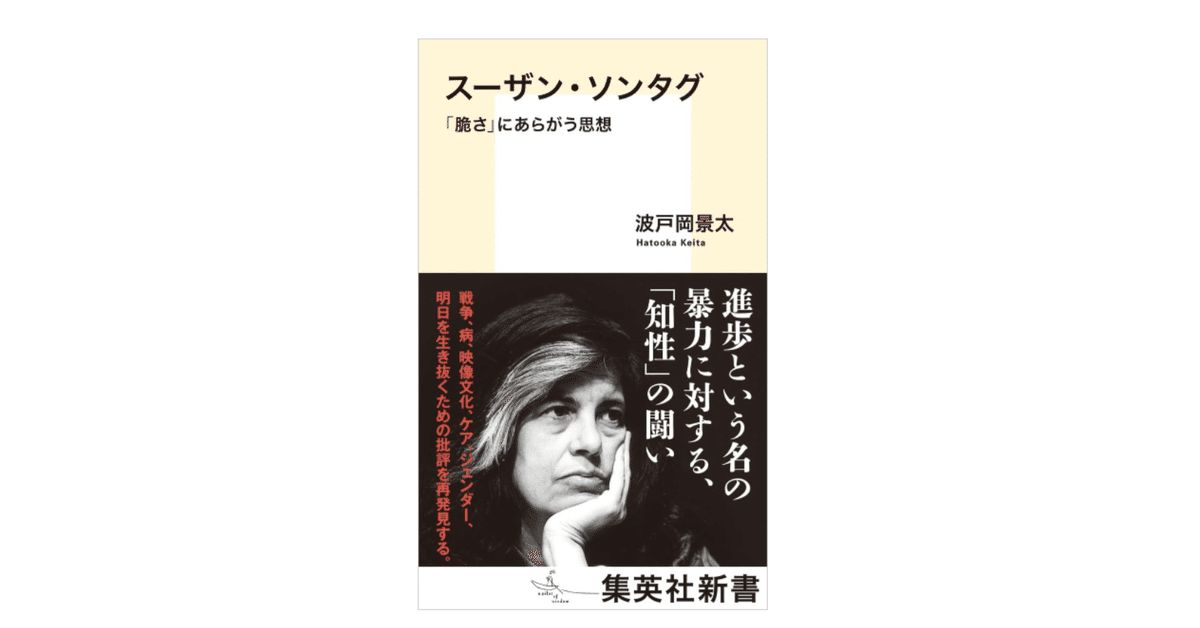
波戸岡景太『スーザン・ソンタグ 「脆さ」にあらがう思想』
☆mediopos3300 2023.11.30
スーザン・ソンタグは
『スーザン・ソンタグ 「脆さ」にあらがう思想』
の著者である波戸岡景太の表現しているように
「カッコいい」のだろうか
「カッコいい」のだとすれば
それはあらゆる脆さ(ヴァルネラビリティ)に
あらがうというそれだからだといえる
ソンタグの思想は
反解釈・反写真・反隠喩によって
戦争やジェンダーといった事象における
あらゆる「ヴァルネラビリティ」に「あらがう」ものだったが
ソンタグはその「ヴァルネラビリティ」に対し
その本質を追究したり克服しようとしたりするのではなく
「すべての存在が抱える脆さというものへの
アプローチの方法を考えてみること」であらがおうとした
おそらくそこに「カッコよさ」はある
わたしたちは誰もが「ヴァルネラブル」な存在であり
ソンタグはそれに対して「批評的言語」で応えようとした
たとえば「写真を撮ることは、他の誰かが抱える」
「死すべき運命、ヴァルネラビリティ、
移ろいやすさといったものに関与することである」と言う
「誰かの苦痛は、たとえ間接的にであれ
「私」によってもたらされたものであり、
同時に、「私」もまた、そうした苦痛をもたらす
誰かの意志や行為から無縁ではいられない」
私たちの「関与」は「(たとえその瞬間には見えなくとも)
力が加わればたちまちにあらわになる傷をうちに抱えたもの」
という意味で「ヴァルネラブル」なのである
その意味において
「私は強い(だからあなたは私を攻撃できない)
とすごんでみせたり、
私は弱い(だからやっぱり、あなたは私を攻撃できない)
と被害者になってみせたりする前に」
わたしたちのだれもが置かれているだろう
「この汚染された世界のヴァルネラビリティそのもの」に
参与することが示唆されている
わたしたちがなにかに「関与」するということは
それそのものがヴァルネラブルな行為であって
単に片方が加害者でもう片方が被害者だという
単純な図式が成立しているわけではない
ソンタグが亡くなったのは二〇〇四年
その名はとくに日本では忘れられかけているようだ
ソンタグはメディアや医療の現場に
特別な興味をもっていたそうだが
ソンタグがまだ生きていて
意図的に起こされている
現在のワクチン被害の現状に直面したとしたら
どんな批評言語で応えようとしただろうか
またソンタグは「物書きたるもの、
意見製造機(オピニオン・マシーン)になってはならない」
と言っているが
ChatGPTという意見製造機に対してどう応えただろうか
本書を読みながらそんな想像をしてみたりもした
個人的にいえば
若いとき出会ったソンタグはどこか近づきがたく
ある一定の距離をとってきてもいて
それについて語ることもないままきていたのだが
ようやくその存在の「ふるまい」といったものに
興味をもつ余裕がでてきているところがある
必ずしも共感するというのではないのだけれど
ソンタグだったら
あるいはソンタグ的な視点からすると
どんなふうに「書いた」だろうかと
著者の波戸岡景太は
「自己矛盾を前提としたアフォリズムを書き連ねることで
他者を救おうとするソンタグのあらがい。
そんな、ドン・キホーテ的ともいえるふるまいは、
けれども、自己肯定を前提としたシンプルなスローガンを
ふりかざして他者を排除することをよしとするような、
今どきの風潮にはそぐわないのかもしれない」
というが
「今どきの風潮にはそぐわない」からこそ
ソンタグのような「ふるまい」が
切に求められているともいえるのではないか
■波戸岡景太『スーザン・ソンタグ 「脆さ」にあらがう思想』
(集英社新書 2023/10)
(「はじめに」より)
「実のところ、ソンタグのような偉人は、(いそうでいて)そうはいない。
もちろん、ソンタグと同じくらい優秀な学歴をもち、ソンタグと同じくらい刺戟的な文章を書き、そして、ソンタグと同じくたいメディアに注目された知識人は、今も昔も存在する。けれど、ソンタグのように自身の輝かしい学歴に背を向け、刺戟的な内容を絶妙な文章に磨き上げ、そして、メディアを利用しても決してメディアに踊らされることのなかった人というのはとても珍しいのだ。
そんなソンタグが亡くなったのが二〇〇四年。
当時は、日本でもかなるの人たちが、ソンタグの名前を口にしていたはずだが、あれから二〇年近くが過ぎようとしている今、世界的な再評価の高まりとは裏腹に、日本ではその名を耳にすることが減ってきたように思われるのはなぜか。
思うに、ソンタグが背負ってきた一九六〇年代的なアメリカの「カッコよさ」(それはたとえば、大人たちが主導する文化をひっくり返すために、若者たちのバカ騒ぎの中に新しい価値観を見出すといったたぐいの「カッコよさ」だ)が、今の日本ではあまり魅力的ではなくなってしまったということも理由の一つかもしれない、
あるいはまた、かつての若者文化がすでに賞味期限を迎えていることを宣言したり、がんやエイズのような難病治療にとって文学的表現は邪魔以外の何ものでもないことを告発したり、さらには、善悪の決めつけができないような紛争や戦争やテロに対してあえて一般的な感情を逆撫でするような政治的立場を表明してみせたりといった、一九七〇年代以降のソンタグが体現してきたもう一つの「カッコよさ」も、今の日本では流行らないからかもしれない。
とはいうものの、そうした傾向はあくまでも、「今の日本では」ということに過ぎない。類い稀なる知性と文才をもって生まれたソンタグ自身の、若者から成熟した大人へと変わる精神的成長の記録とでもいうべき著作群は、その読み方さえ理解することができれば、混迷を深めていくばかりの世界と対峙しなければならない私たちにとって、明日を生き抜くための最高のツールとなるはずなのだ。」
(「第2章 「キャンプ」と利己的な批評家」より)
「物書きたるもの、意見製造機(オピニオン・マシーン)になってはならない————。
先の章で引用したこの言葉は、「詩人はジュークボックスではない」というダドリー・ランドールの有名な詩句を意識してのものであった。
ここに見られる機械と人間といった二項対立は、ソンタグの批評活動においても重要な意味を持っている。というのも、ソンタグが特別な興味を持ってきたメディアや医療の現場は、人間の文化的生活におけるテクノロジーの侵犯が顕著な領域であり、そこに表出する人間の意志や感情や苦痛や快楽といったものを論じることこそが、ソンタグの仕事の大半を占めていたからだ。
たとえば、私たちは銃の引き金を引くようにしてカメラのシャッターを押すこともあれば、苦痛にゆがんだ他人の身体のイメージに自分の快楽を投影してしまうこともある。あるいはまた、日進月歩の医療テクノロジーを信頼すべき深刻な状況にあっても、ときに病名から連想される負のイメージの方を優先し、罹患したことを隠そうとしたりもする。
そうした矛盾を目にしたとき、「物書き」たちはいったい何を、どのように語ればいいのか。
ソンタグがその生涯をかけて探求してきたテーマは、端的に言って、人間存在が抱える「脆さ」(ヴァルネラビリティ)と、それが表出する際に身体と精神を襲う「苦痛」(ペイン、サファリング)であった。そしてそれは、機械と人間という二項対立が揺らぎを見せる場所————たとえば写真や映画————においてはっきりと観察されるものであり、だからこそソンタグは、時代を何歩も先取りするかたちで、メディア空間を生きる私たちの「生」を論じてきたのである。」
(「第5章 『写真論』とヴァルネラビリティ」より)
「カメラというものは、それ自体が暴力と密接なつながりを持つものとされる。(・・・)以下に引用するソンタグの『写真論』からのアフォリズムは、それをあまりに見事に表現している。
カメラは銃を理想化したものであるから、誰かを撮影することは理想化された殺人————悲しく、怯えた時代にぴっかりの、ソフトな殺人を犯すことなのである。
いやいやそれも詭弁だろ・・・・・・と、多くの(素朴な)写真愛好家たちは顔をしかめるかもしれない。だが、ソンタグにしてみれば、他者のヴァルネラビリティへの関与をやめない暴力的なツールという意味において、カメラは銃と等価であった。
そしてまた、こうしたカメラの暴力性は、惨劇もなく、観光地化もされていない、手つかずの自然の風景を撮影する場合においても例外とはされない。というのも、失われていく自然や、滅びゆく動物たちに向けられたカメラというものもまた、それらの美しさが傷つけられ、踏みにじられ、そして失われていくことを知覚したいがために必要とされる道具であったからだ。
(・・・)
たとえ環境保護の名のもとに撮られた写真であっても、それを批評的に考察する際には、対象のヴァルター・ベンヤミンに対する撮影者の側の「関与」の姿勢————それは怯えなのかノスタルジーなのか————もまた徹底的に問わなければならないとソンタグは主張するのである。」
(「第7章 反隠喩は言葉狩りだったのか」より)
「ソンタグの言動は、生前よりさまざまな論争を巻き起こし、その都度、彼女に対する不当とも言える解釈が生み出されてきた。だが、ソンタグ自身、すでに第一批評集『反解釈』の段階から、こうした悪意ある「解釈」の垂れ流しが私たちの感受性を汚染するのであるとの警鐘を、あらかじめ読者に向かって鳴らし続けていたことは、ここで一度思い出しておくべきだろう。
解釈は、世界を貧しくし、消耗させる————そして「意味」に満ちた影の世界が立ち上がる、ただの世界だったものが、誰かに解釈されることで、この世界、になってしまうのだ(「この世界」だなんて! まるで世界が他にもあるみたいだ)。」
(「第11章 ソンタグの誕生」より)
「未来の苦痛にさいなまれないで————。
ソンタグの生涯とその仕事について語ろうとするとき、この言葉ほど示唆的なものは、あるいは他にないのかもしれない。
ソンタグの最後の批評集が『他者の苦痛へのまなざし』であったように、苦痛とは、ソンタグの言論活動の重要なテーマだった。しかも、それは生きとし生けるものがそれぞれに抱える、あのヴァルネラビリティなるものを想起させつつも、それとは異なる、きわめて個人的な体験である。」
(「終章 脆さへの思想」より)
「ソンタグの「あらがい」というのは、結局のところ、本質を見抜くふりをしながら相手を煙に巻く「解釈」や、ファインダー越しの今を愛でるふりをしながらも、シャッターを切ることでそれを過去のものとしてしまう「写真」や、はたまた、難病の原因を探るふりをしながら患者みずからの精神的堕落を責めてしまう「隠喩」といったものへの抵抗であった。
反解釈、反写真、反隠喩。
これらの「反」が対峙するものを、ソンタグ自身は「汚染」と呼んだ。ただし、私たちもよく知っているように、現実の環境汚染であっても、単純にテクノロジーを拒否して、そして自然回帰をすればよい、といったものではない。同じように、解釈や写真や隠喩といったものに抵抗しようとする際にも、解釈することそのものを放棄してしまったり、写真というテクノロジーを頭から否定してしまったり、さらには、隠喩といったものをある種のウソとして拒絶してしまったりすれば、それは単なる「思考停止」であって、知的生活はいよいよ「汚染」されてしまうことになるだろう。
そう、ソンタグの「あらがい」を考える上で問題となるのは、いわゆる「知性」そのものへの抵抗が、そこに含まれるのか否かということだ。」
「一九六〇年代から二一世紀の初頭まで、ソンタグの知性は、反知性主義との高度な緊張関係のなかで育まれ、そして成熟していった。
ただし、生身の人間としてのソンタグは、きっと、この世の清濁をあわせ呑むといった境地には、あえて辿り着こうとはしなかったのだろう。そうではなく生きとし生けるものが抱える内面の脆さと、肉体的な痛みの、その両方に共感をし続けようとしたソンタグにとって、この世の「濁」なるものを呑み下さんとする折の嘔吐(えず)きこそが、「物書き」としての最大のモチベーションとなっていたのである。
自己矛盾を前提としたアフォリズムを書き連ねることで他者を救おうとするソンタグのあらがい。そんな、ドン・キホーテ的ともいえるふるまいは、けれども、自己肯定を前提としたシンプルなスローガンをふりかざして他者を排除することをよしとするような、今どきの風潮にはそぐわないのかもしれない。」
「ソンタグにとっては、文学も映画も演劇も写真も、およそあらゆる表現行為は、その対象行為は、その対象物が隠し持つヴァルネラビリティを顕在化させてしまうものとして説明される。もちろん、その顕在化のプロセスには技巧的なものもあれば、ハプニングのように無自覚なものもあり、同時にまた、その顕在化を隠蔽するプロパガンダのような表現形態もある。
だが、いずれにせよ、誰かのヴァルネラビリティが人目にさらされようとしている現場には、文字どおりの「暴力」が介在しているとソンタグは考える。そしてその暴力は、たとえば衰弱したソンタグを写真に収めようとするパートナーの、悪意なき意志によっても発揮されてしまうものであった。だからこそ、いくら「あらがい」を実践しようとも、ソンタグは、表現行為に伴う暴力を、その根本から否定したり、検閲したりということはしなかった。
「人間の脆さとは何か」であるとか、「それを暴きたてる暴力の本質とは何か」といった問題設定も、ソンタグにとっては魅力的なものではあったかもしれない。だが、そうした真理の探究めいた議論よりも、ソンタグはむしろ、「死すべき運慶にあるもの同士は、芸術のような表現活動を通じて、いかにした互いの存在にアプローチしているのか」といった、不可逆な時の流れ身をさらしている者たちの関係性を明らかにする議論を好んだ。
つまり、たとえば写真を撮る者と撮られる者がいたとして、そこには確かに非対称な関係があるのだろう。しかし、その関係性をただ問題視すればよいかといえば、そうではないはずだ、というのがソンタグの立場なのである。もちろん、一度ならず、二度三度とその関係性を転倒させてみることは大事だろう。だが、そうやって「関係性」というものそれ自体をためつすがめつ眺めてみたならば、私たちはきっと、そのどちらが本当に強いのか、わからなくなるはずなのだ。
本文中で何度となく引用した、「写真を撮ることは、他の誰かが抱える(あるいは他の事物が抱える)死すべき運命、ヴァルネラビリティ、移ろいやすさといったものに関与することである」というソンタグの言葉は、まさしくこのことを語っている。結局のところ、苦痛にもだえる他者にレンズを向け、シャッターを切る私たちは、そのファインダー越しに、みずからの死すべき運命を目撃している。誰かの苦痛は、たとえ間接的にであれ「私」によってもたらされたものであり、同時に、「私」もまた、そうした苦痛をもたらす誰かの意志や行為から無縁ではいられない。そうした現実を、ソンタグは、(たとえその瞬間には見えなくとも)力が加わればたちまちにあらわになる傷をうちに抱えたものといった意味で、「ヴァルネラブル」であると表現したのである。
スーザン・ソンタグの「脆さ」にあらがう思想。
間違ってもそれは、脆さの本質を追究し、あわよくばそれを克服しようとする思想ではない。そうではなく、すべての存在が抱える脆さというものへのアプローチの方法を考えてみることを、ソンタグは言葉を尽くした実践してきたのである。」
「かくして、ついにソンタグを「発見」したあなたは知るだろう。私は強い(だからあなたは私を攻撃できない)とすごんでみせたり、私は弱い(だからやっぱり、あなたは私を攻撃できない)と被害者になってみせたりする前に、まずはこの汚染された世界のヴァルネラビリティそのものに、批評的言語という盾を携えて参加してみることから、新世代のあらがいは始められるべきなのだということを。」
【目次】
はじめに
第1章 誰がソンタグを叩くのか
第2章 「キャンプ」と利己的な批評家
第3章 ソンタグの生涯はどのように語られるべきか
第4章 暴かれるソンタグの過去
第5章 『写真論』とヴァルネラビリティ
第6章 意志の強さとファシストの美学
第7章 反隠喩は言葉狩りだったのか
第8章 ソンタグの肖像と履歴
第9章 「ソンタグの苦痛」へのまなざし
第10章 故人のセクシュアリティとは何か
第11章 ソンタグの誕生
終章 脆さへの思想
おわりに
□波戸岡景太(はとおか・けいた)
1977年、神奈川県生まれ。
専門はアメリカ文学・文化。博士(文学)〈慶應義塾大学〉。
現在、明治大学教授。
著書にThomas Pynchon’s Animal Tales: Fables for Ecocriticism(Lexington Books)、『映画ノベライゼーションの世界』(小鳥遊書房)、『ラノベのなかの現代日本』(講談社現代新書)など。
訳書にスーザン・ソンタグ『ラディカルな意志のスタイルズ[完全版]』(管啓次郎との共訳、河出書房新社)など。
