
農経しんぽう20241028号 秋田アグリフロンティア育成研修 特別掲載記事
農経しんぽう2024年10月28日号で掲載している秋田アグリフロンティア育成研修について、紙面に掲載しきれなかった内容を含めてお届けいたします。
アグリフロンティア育成研修について
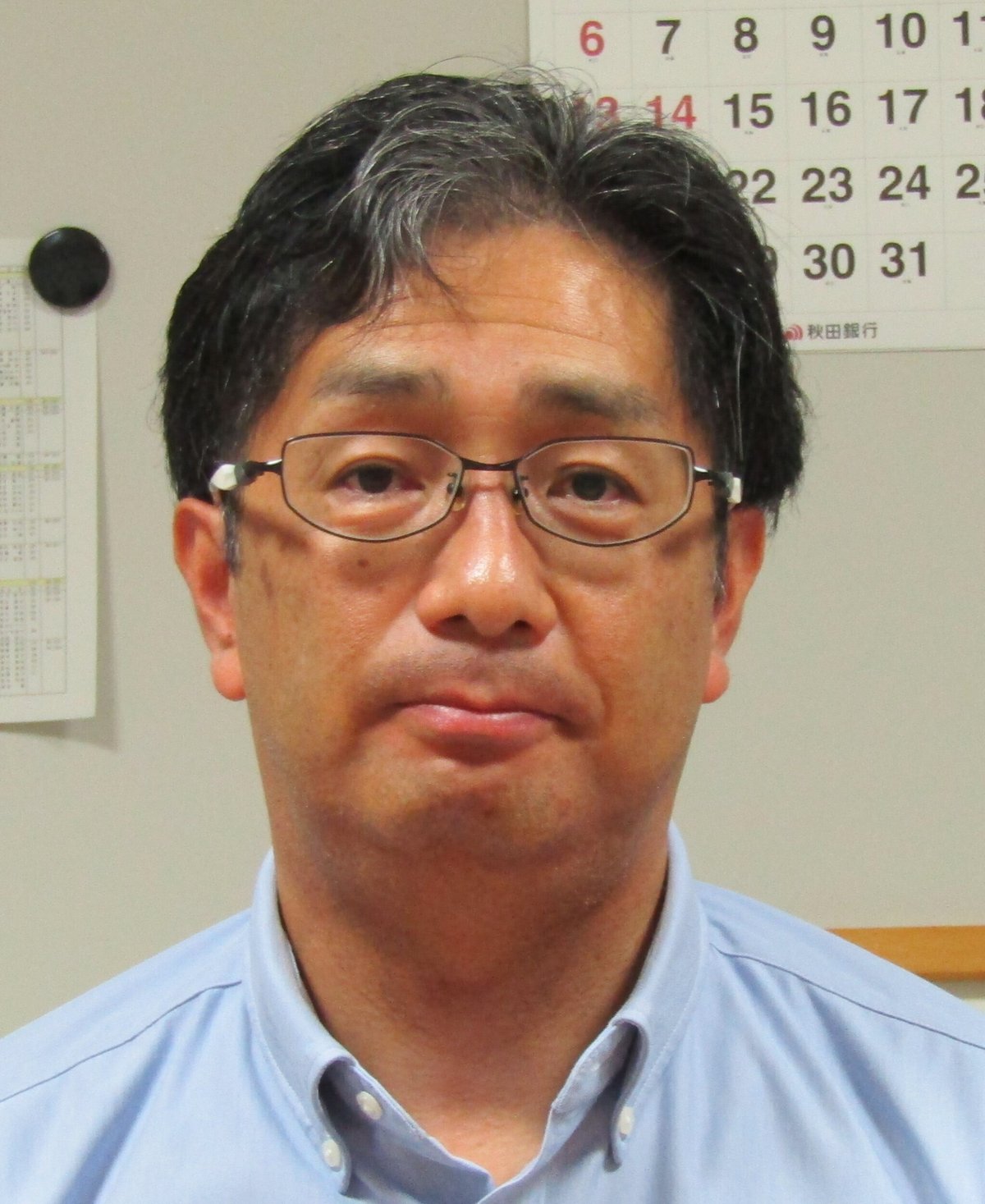
アグリフロンティア育成研修とは
今年度より発足した「秋田アグリフロンティア育成研修」は、平成3年度に「農業後継者技術習得研修」としてスタートし、平成13年度からは、「未来農業のフロンティア育成研修」となり、令和5年度までに615名の研修生を輩出してきた。近年、非農家出身者の新規参入者の割合も高くなり、求められる農業者としての資質も変化していることから、時代にあった研修体系を昨年度から1年間かけて構築した。この育成研修内容を組み上げた秋田県農業研修センター企画・研修チームの工藤英明チームリーダーに同研修の概要や役割、特徴等を聞いた。
秋田県には農業大学校がなく、後継者をどう育てていくかが課題で、体系的に教わる機会や新規作物の栽培ノウハウを教わることが難しかった。それを解決するため、秋田県では農業試験場などの研究機関での研修後、就農できる体制を用意すべく、前身となる研修はスタートした。しかし、時代の流れとともに、非農家の新規参入者が増加。研修内容においても、新しい農業者を育てるために抜本的な改革が必要となり、研修内容を見直す形で「秋田アグリフロンティア育成研修」としてリニューアルすることとなった。
研修内容は主に5つ
研修内容は主に①事業計画②農業技術③経営・財務④流通・販売⑤ネットワーク構築の5つ。これまでと大きく違うのは、農業技術以外を大きく充実させた点だ。工藤氏は「今の時代、農家は経営者。事業計画を立案し、年ごとに計画修正していく力が必要になる。そのため、農業技術に加えて、数字の分析判断能力、農協販売を含めた販売力、人的ネットワーク構築方法などを身につけていけるような内容に組み替えた」と説明する。この研修の魅力は、就農後のビジョンを作成するための充実した講義内容や県内各地にいる研修生がオンラインでも座学を受けられる体制、希望者は就農予定地域の農業者のもとでの研修選択ができる点など。事業計画立案の研修にも多くの時間を割いている。
研修コースは「試験場コース」と「先進農家コース」
研修コースは2つ。各地の試験場等に専攻が設けられた「試験場コース」は、学ぶことのできる作物がある程度限定されているものの、水稲・大豆から、野菜、花き、果樹、畜産と幅広い。一年間の研修後には、農家の元で実地研修できる選択肢も用意する。もう一つは「先進農家コース」。これは新規参入者の最大の難題ともいえる地域に馴染むための工夫がなされているコースでもある。「このコースの研修生には就農予定地にいる先進農家のもとで2年間実習を受けてもらい、師匠となる農家に指導してもらう」と工藤氏。その2年間で地域の担い手として適切かどうかを師匠が見極め、地域で育てていく雰囲気の醸成にもつなげていく。研修生にとっては篤農家から教わりながら、地域に根を下ろす糸口になり、地域の農家にとっては、その土地をともに守っていく仲間の育成になる。
充実の講義内容と講師陣

各講義の講師には県内の様々な方面から協力を仰ぎ、JA全農あきたや県内金融機関、機械化協会など、就農した際に必ず付き合っていく面々が力を貸す。その内容は、就農した時に力強い味方となることは間違いない。販路の面については、首都圏のバイヤーを招聘した。「秋田は首都圏向けの農産物が多いため、首都圏の消費者に目を向ける必要がある。しかし、首都圏の情報を秋田にいながら掴むのは難しい。そのため、首都圏の市場を良く知るバイヤーの方々から直接学ぶ機会を用意することにした」と工藤氏。自動車学校協会とも連携し、農業者用だけはない大特免許の取得も可能。これは冬場の農閑期に除雪作業で収入を得ることを見越してのことだ。どこまでも生産者のリアルな生活に沿って組まれた研修であることがよくわかる。
新時代の農業経営者を育てる
「最初の講義で研修生にはまず、『収入としていくら欲しい?』と聞く。年代も10代から40代まで幅広く、独身や子持ちもいて、おかれている立場も様々。いくらあれば生活できるか具体的に考えてもらう。市町村が認定する認定就農者制度は所得目標を市町村で定めているが、5年後の目標収入を立てて、そこに妥当性があれば認定するもの。市町村が定めている基準は一律でなければいけないが、個別には人それぞれ違うはず。そこで個々の必要な収入から逆算して、どんな農業をしなければならないか、農業だけで足りなければどうやって補填するかまでを考えてもらう」と工藤氏は話す。育成研修側ができる限りのサポートをすることで、研修生に本気になってもらい、秋田の農業の未来を担う農業者を育て、新しい人材を呼び込む。そして秋田県農業を活性化させていく。農家を育てるのではなく農業経営者を育てる。そんなメッセージをより具現化したのが、秋田アグリフロンティア育成研修である。
秋田県の新規就農者は令和5年までの7年間、右肩上がりの状況にあるが、この育成研修がその成長の一翼を担っていく存在であるといっても過言ではない。
今後は、選任相談員の設置や県内の講師陣のさらなる強化を図り、地域に根ざした育成体制を充実させていく。
同研修の詳細は、秋田就農ナビ:https://akita-agri-navi.com/ からも確認できる。
