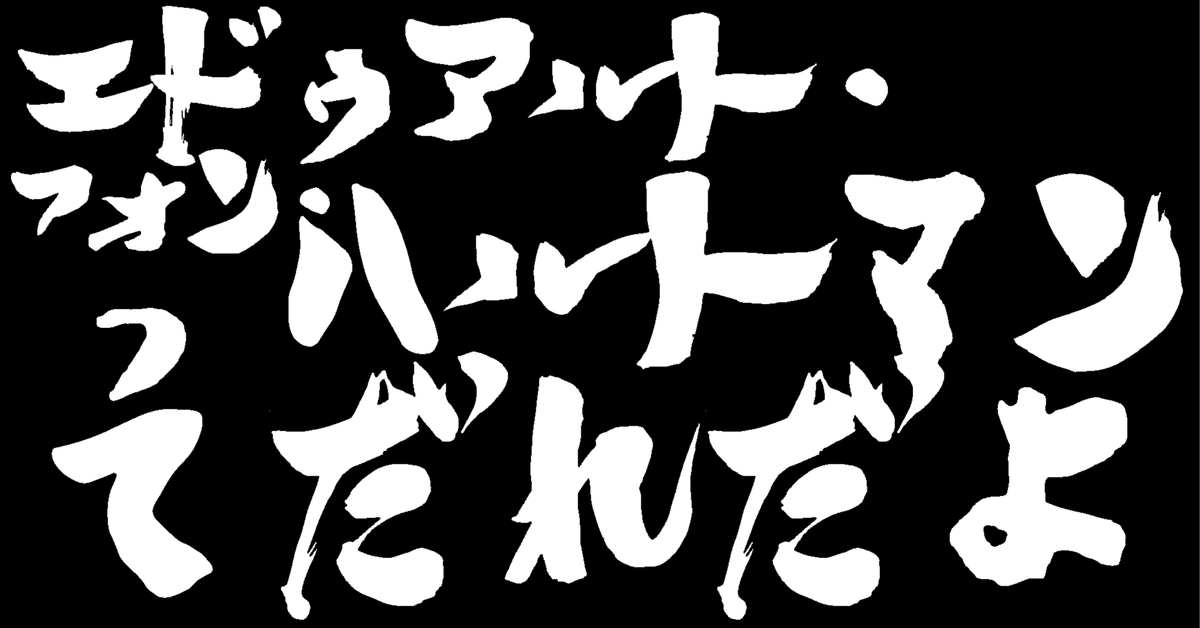
ハルトマン『無意識の哲学』についてのルポルタージュ
追伸
幻想郷学講談所に「ハルトマン『無意識の哲学』に挑む」を掲載させていただいた。元が東方発表会の原稿なので、スライドと併用して読んでいただくこともできる。今回ほとんど深堀りすることができなかったハルトマンの思想内容についても、初歩的な段階ではあるが、具体的に論じているので、参照されたい。(2024年1月19日)

「ハルトマンの妖怪少女」
古明地こいしのテーマ曲であるこのタイトルが意図していることとは何であるのか。やはり気になってしまう。ハルトマン、私が最初に思い浮かべたのは撃墜王のエーリヒ・ハルトマンだが、これではむしろ共通点を見出す方が厳しいだろう。それでもやはり人名には違いない。それもドイツらしい。そう思って調べてみると、幾人かの候補を目の当たりにすることになった。エドゥアルト・フォン・ハルトマン、ハインツ・ハルトマン、ヴィクトル・ハルトマン、ニコライ・ハルトマン……。
その中でもドイツの哲学者、エドゥアルト・フォン・ハルトマンは特に有望視されているらしい。
ヘーゲルとシェリングの体系と、さらにはショーペンハウアーを総合するという破天荒な企てをこなした『無意識の哲学』の著者。自らの立場を「無意識者」として掲げたというハルトマン。「無意識を操る程度の能力」の持ち主である古明地こいしにぴったりのモチーフだろう。
しかし、ヘーゲルも、シェリングも読んだことはない私にとって、ハルトマンの意図を汲み取ることなどできそうにない(ショーペンハウアーはエッセイだけ)。ただでさえ敷居が高い哲学史に踏み入るのは、骨が折れる作業だ。この記事の読者にしても、哲学に身寄りのない者が大多数だろう。
しかし、くねくねしていても話は進まないので、このハルトマンについて、少しだけ調べてみることにする。
ハルトマンのほうへ
「ハルマントのほうへ」……なんつって(プルースト)。さて、ハルトマンの思想を知るためには、それについての本を読むのが一番手っ取り早い。邦訳や解説書の類も探せば見つかるだろう、そう思っていた。

著作の邦訳は一切なし、解説書の類いも皆無、論文もまばら、ほとんど荒野の有り様だった。ただ、唯一の救いとして、『無意識の哲学』の英訳版は見つかった。
(「Get Access」から985ページ全文を閲読可能)
解説書の類いで唯一見つかったのは上田光雄『ハルトマンの無意識の哲學』だが、初版一九四八年の古書。流通も絶望的。
また、ハルトマンに関する論文もまばらにしか見つからなかった。その中で引用されるハルトマン研究者は、ハルトマンについて、未だ然るべき研究はなされていないと述べている。
この様子だと、ハルトマンを主題的に論じている本はまずないだろう。では、どのようにしてハルトマンを知ればよいのか。得られる情報も限られた見えないこの哲学者に対して、どのようなアプローチが有効であるのか。
ハルトマン個人を主題とする本がないのであれば、思想史の中で言及されるハルトマンをすくい上げる、そんな方法を取ってみよう。フロイトに先駆した無意識の提唱者としてのハルトマンを取り上げてみる。
この案を思いつくと、いてもたってもいられず、秒で書籍を購入してきた。種本は互盛央『エスの系譜』(講談社学術文庫)。無意識といえばフロイト、フロイトといえばエス。目次を確認すると、第二章でハルトマンについて言及されていた。
そこに一つの系譜を見て取るとき、まさに「無意識」という概念を携えて十九世紀後半に出現した人物が、同じ系譜の中に姿を現す。 それが、エドゥアルト・フォン・ハルトマン(一八四二─一九〇六年)である。
ハルトマンは、フロイトに先立って「無意識」を提唱したらしい。ハルトマンやフロイトにとって、人間心理の表層でしかない個人の意識や理性は、何ほどでもない。人間を支配するのは非理性的な「無意識」の領域であり、人間の自我なるものは、自らの家の主人ですらないのだ。
ハルトマンの見取り図
ここで一時停止。ここでは「無意識」の先駆者としてハルトマンに言及しているが、そのためにはフロイトを理解している必要がある。フロイトのいう無意識およびエスの意味を知らないと、これからの議論でお話にならない。また、ハルトマンが「無意識」を構想するまでの哲学の流れを理解しておく必要もある。このルポルタージュでは、ハルトマン以前とハルトマン以後に分かれてそれぞれ掘り崩すが、以前にしても以後にしても、それぞれ思想史的にかなり複雑な関係になっていることは間違いない。
だから、ここではハルトマンの参考程度に見取り図を作成した。詳しくは以下の通りである。

まずハルトマン以前に、哲学の流れであるカント、シェリング、ヘーゲル、ショーペンハウアーがいる。ここで特に話題にするのはショーペンハウアーだが、ショーペンハウアーの哲学の意図を理解するにはカントを理解しておく必要があるという、入り組んだ構図になっている。ハルトマン以後には「無意識の発見者」であるフロイトがいる。まずはハルトマンの「無意識」を理解するために、フロイトにそって理解を試みたい。ハルトマンのほうへ赴きたいところであるが、ここはまずフロイトに寄り道しよう。
フロイトのほうへ
ジークムント・フロイトはモラビアのフライベルク(現チェコ)生まれの心理学者、精神分析家である。彼の創始した体系は「精神分析」と呼ばれ、旧来の心理学(ヴントなど)と一線を期している。彼は、人間の心の大部分が無意識の領域にあることを発見し、その功績から後には「無意識の発見者」と呼ばれる。
古明地こいしのスペルカードに「無意識」「イド(=エス)」「自我」「スーパーエゴ」といった精神分析のタームが含まれていることは、古明地こいしがフロイトをモチーフにしていることを如実に示している。「フロウディアン」はそのままフロイト主義を意味し、フロイトの提唱した「精神分析」との強い結びつきを伺うことができる。
では、彼の提唱した「無意識」とは何であるのか。実感を伴って理解するために、彼自身の挙げる例に即して、具体的に論じてみる。
「錯誤行為」と呼ばれるものがある。いわゆる聞き違い、言い違い、読み違い、書き違いといったものに代表される間違いだ。多くの人が共有している事実として、こうした間違いは意識的になされるものではない。知らないうちにしてしまっていたり、不意にそうなってしまったり、少なくとも、意識の制御下にあるものではない。ようするに、「わざとではない」のだ。
それは例えば、意図された言葉とは逆の言葉が口をついて出る例。開会の挨拶に「議会の閉会を宣言します」と言ってしまった議長を例に、フロイトは無意識にある意図を汲み出そうとする。議長は本心では議会の閉会を望んでいたというのだ。フロイトは、この議長の言葉を額面通りに受け取る。議会を早く閉じてしまいたいと思っていたのが、その話そこないの意図であり、彼(=議長)の無意識の所作なのだ。
また、ある講師は物理の授業中に「物体B」と言うところを「びったいブー」と呼んでしまったが、講師も聴講生もこれに気付かずにそのまま続けて「びったいブー」と呼び続けていたので、その様子を見て、「私」は吹き出しそうになりながらも堪えて、そのまま授業を聞いていたという話がある。これもフロイトにおいては同様である。言い違いは、無意識の作用によるものであり、講師は「びったいブー」と言い違えることを無意識下では望んでいたというのだ。フロイトはこれこそ無意識の所作だと主張してはばからない。こうした話には枚挙にいとまがないが、これらのほとんどが、こうした無意識的な欲望を示唆するものであったと、フロイトは指摘する。
それに対して、その提案を受け入れがたい人はこう反対するはずだ。「そんなことはありえない。議長が望んでいたのは閉会ではなく、開会だったということは全く疑う余地がない。余人ならぬ議長その人が、本心では開会しようと思っていたのだということを認めているではないか。本人が間違いだったと認めている以上、この話のこれ以上の進展もない」
しかし、フロイトはこう反論する。実際に発言がそうなされている以上、その発言に対する肯定的な所作が心のなかでなされているのは確かであり、それ(=無意識)を蔑ろにするべきではない。反対者による批判はあくまでも意識的なものに留まっており、明らかに無意識的な領域に原因を持つ錯誤行為を、意識的な領域でのみ解決できると考えるのは不整合なことだ。
つまり、錯誤行為とは、錯誤行為そのものを望む無意識的な所作が結果としてあらわれたものである。無意識は錯誤行為の原因であるとともに、こうした錯誤行為を(われわれの意識的には理解し難いまでも)望んで為している。言い間違い、聞き違い、書き違い、読み違いといった錯誤行為は、それ自体かれにとって誤りであるのに関わらず、無意識によって望んで引き起こされた、心的作用の一つなのだ。フロイトによれば、錯誤行為を含めて学習、忘却、判断、認知、夢、精神疾患に至るまで、心の営みのほとんどは、この無意識的な作用によって行われている。
錯誤行為が無意識によって望まれた所要であるのか否か、議論が分かれるところではある。肯定的な意見としては、フロイトが主張するところ、すなわち「無意識領域」を措定することの有効性である。彼によると、当時の精神医学で精神病に対して有効な治療法を持ち得たものはなかった。従来の精神医学も、精神病に対しては種別の命名と分類に終始していたとフロイト自身が語っている。フロイトやその仲間たちが持ち出すまで、心理学の研究対象として無意識が検討されることはなかったというのだ。
それに対する反対意見としては、やはり無意識が錯誤行為という形で、なぜ本人の意図を損ずる方向に作用するのか、という点だろう。本人の心の奥底に無意識なる領域があったとして、なぜ錯誤行為を引き起こすことによって本人を困らせるのか。これでは、本人自ら本人を困らせることになってしまう。しかも自覚的でないという点で、なおさら悪質ですらあるではないか。また、無意識なるものがあったとして、すべてが無意識による所要とは限らないのではないか。そもそも、無意識なるものが確かに存在しているかも疑わしい。それは容易に観測されるものではなく、示されるにすぎない。フロイトが行っているのは「無意識」の過大評価ではないか。
それでも、フロイトはこう主張する。「無意識」を過大評価するよりも、その類いの危惧によって「無意識」を過小評価するほうがなおさら危険である、と。次の引用は、旧来の伝統的精神医学に対して、無意識を想定した精神療法(=精神分析)の有効性を強調するフロイトの矜持が見て取れる。
この点についてわれわれは、精神科医の言うところをそっと聞いてみたいと思うのですが、精神科医はわれわれを見捨てて知らぬ顔をしています。もともと精神科医は、われわれの設定する問題のうち、たった一つのものにしか立ち入らないのです。精神科医はこの夫人[精神病患者]の家族歴を調べて、われわれに、たぶん次のような答えをしてくれるでしょう。妄想は、これと類似の精神障害やその他の精神障害がくりかえてして現われている家系の人によくみられる、と。言いかえれば、この夫人がある妄想を示したのは、遺伝の結果だ、彼女がその素質を持っていたからだ、と言うでしょう。
(中略)精神科医は、このような症例の解明がさらにどういう道へと進んで行くか、その道を全く知らないのです。精神科医は、診断すること、そして豊富な経験にもかかわらず不確実な見通しとに甘んぜざるを得ないのです。
ところでこの場合、精神分析ならば、これより[精神病の命名と分類]以上のことができるのでしょうか。できるのです。先に挙げたような厄介な症例の場合でも、精神分析は、もっと正確な理解を可能にするような何ものかを発見できる、ということを私はみなさんに示したいと思っています。
精神病や精神疾患を解決する糸口は「無意識」の領域にこそある、と主張するフロイトは、精神分析という画期的手法によって症状の隠された意味を探ることで精神病の治療を試みる。これこそ、フロイトにとっての「無意識」である。フロイトの無意識は、意識と大別される。理性的なものである意識に対して、無意識は非理性的な領域にあり、欲望の渦巻くカオスであり、自我によって捉えられることのない広大な領域なのだ。
今日、自分がはっきり意識できない、よくわからない理由で何かやってしまったというようなことは、「無意識でやった」と言われるが、そもそもそうした使い方で無意識と言うこと自体がフロイトの発明であるから、二十世紀以後のわれわれはフロイトの思考の影響下から逃れられなくなっていると言える。人間は自らをすべてコントロールできてはおらず、何か「やってしまう」という、いわば自分のなかに別の自分がいるというべきか、意識を裏切る「盲目的な意志」に動かされている面がある。
フロイトとハルトマン
さて、ハルトマンを「無意識」の先駆者として紹介する際の文脈の意図は、多少なりとも把握できただろうか。フロイトに先行して「無意識」を提示したハルトマン。そしてハルトマンとフロイトの間には、間接的でいささか奇妙な関係が出来上がっている。
若かりし日のフロイトにとっても、ハルトマンは決して無縁の存在ではなかった。あの「ウィーン・ドイツ学生読書会」で出会った先輩で、のちに哲学者としてイエーナ大学やバーゼル大学で教鞭を執るヨハネス・フォルケルト(一八四八─一九三〇年)が自由主義の腐敗を糾弾する演説を行った際、フロイトは熱狂的な支持を示したが、のちに『夢解釈』で多くの夢の事例が引用されるフォルケルトの著書『夢空想』(一八七五年)は、ヘーゲル、ショーペンハウアー、そしてほかでもないハルトマンに依拠した著作だったのだ。
この引用の中では、ヘーゲルとショーペンハウアー、そしてハルトマンの影響がフロイトに流れ出ていることが指摘されている。フロイトはフォルケントという哲学者の見解を支持したが、このフォルケントは他ならぬヘーゲル、ショーペンハウアー、ハルトマンの流れを汲んだものだった。
ハルトマンの見取り図を振り返ってみよう。まず、哲学の流れとしてのカントがいて、カントを発展させたシェリングとヘーゲルがいて、そしてヘーゲルらとは別様にカントを継承したショーペンハウアーがいた、これがハルトマン以前の図式だ。

この中でショーペンハウアーの哲学はハルトマンやフロイト的な「無意識」のモチーフの源泉になっていて、大雑把に言えば「ショーペンハウアー─ハルトマン─フロイト」という三者が、「無意識」のような「非理性的なもの」によって貫通されている。理性的なものではなく、非理性的なものを主題的に論じるこの三人は、非常に関わりが深いと言うことができる。三人を貫通する「非理性的なもの」という主題は、ショーペンハウアーにおいては「意志」と呼ばれ、フロイトにおいては「無意識」として体系付けられている。
フロイトのいう「無意識」についてはわかった。精神には、意識的に把握することのできない沈黙の領域があって、それを前提にすることが人間心理を考える上で必須なのだ、それがフロイトの主張するところだった。では、ショーペンハウアーのいう「意志」とは如何なるものであるのか。ショーペンハウアーによって提起された「意志」は、ハルトマンを経由してフロイトの「無意識」に引き継がれるが、ハルトマンによって継承されるに至ったショーペンハウアーの「非理性的なもの」とはなんであったのか。
カントのほうへ
ショーペンハウアーのいう「意志」が意図するところを知る。フロイトの「無意識」に次いで、これを目標にしてみたい。フロイトがハルトマン以後であれば、ショーペンハウアーはハルトマン以前に位置する思潮と見なすことができるだろう。
アルトゥル・ショーペンハウアーは、ドイツの哲学者である。彼の哲学は西洋哲学における厭世主義、反出生主義に大きな影響を与えたとされ、その実、その体系から展開される悲観的な世界観を特徴としている。彼は仏教と、後に述べるカントの立場を継承しており、そのためにショーペンハウアーを理解するためにはカントを理解しておかなければならないという入れ子構造になっている。
イマヌエル・カントは、ドイツの哲学者である。彼は哲学史に輝く成果『純粋理性批判』によって、哲学の史上最大の金字塔という評価を受けている。事実、彼は西洋の哲学の方向性を決定づけたので「カント以前の哲学はカントに流れ入り、カント以後の哲学はカントから流れ出る」とさえ言われる。彼は名実ともに哲学のビッグネームであり、西洋哲学の歴史において重要な位置を占めるのだ。
カントは、世界そのものを「現象」と「物自体」の二つに分ける。前者は人間が知覚する世界、後者は人間の知覚によって捉えられない世界だ。普段われわれの知る世界とは、目で見て、耳で聴き、鼻で嗅ぎ、舌で味わい、手足の肌で感じるものである。われわれは感覚器官=感性によって知覚したものしか知り得ない。われわれが見ているのは脳内映像であって、世界そのものではないのだ。一方で、われわれが感性によって見聞きする世界とは裏腹に、世界そのものを考慮することもできる。
感性によって捉えることのできない「世界そのもの」をカントは「物自体」と呼ぶ。人間の知覚に先行して存在する、世界の原型であり、客観そのものである。注意しておきたいのが、人間の知覚のみならず、言語活動や科学理論によっても、この「物自体」は把握することはできないということだ。物体の運動の再現を可能にする科学理論は、客観的ではあっても、客観そのものではない。科学理論に代表される「客観─的」な事柄は、客観の写像であり、客観を記述したものでしかない。言語による記述という行為は、確かに判明明快ではあっても、現実そのものを意味してはいないのだ。「物自体」はいかなる方法によっても記述することができない。なぜなら、記述不可能であることが「物自体」の条件であるからだ。
やかんを抱える少女と、それを見る少女とがいるとする。

やかんを抱える少女と、それを見る少女との関係で、われわれが考えてしまいがちなのは、見る少女の目の前にやかんを抱える少女がいると想定することだ。本来、そこにやかんを抱える少女はそのままの姿では存在しない。少女の脳内に、やかんを抱える少女のイメージが存在するだけだ。よって、カントが指摘する図式は以下のようになる。

これは、われわれの直感に反する。普段われわれが人と話したり、社会に参画したり、仕事に勤めたりするときに、このような発想はまずしないだろう。われわれの見る光景が大脳皮質の後頭葉によって生み出された脳内映像であることは、脳科学の知見から指摘されることではあるし、時々意識することではあるが、客観それ自体と脳内映像、すなわちカントのいう物自体と現象は、その性質や実態において一致するものとして考えてしまうのがつねだ。
それでも、カントによる区分が正しいとしてみる。しかしそう考えると、なんとも言いがたい奇妙な状況が浮かび上がる。物自体と現象、この二つの次元において同一のものが認められるという事態が発生するのだ。カントの図式は画期的ではありながらも、なんとも歯切れが悪いものとして受け止められる。やかんを抱える少女で例えるなら、やかんを抱える少女は二人いることになる。一人目は物自体に、やかんを抱える少女の「根源的な原因」が存在していて、これはやかんを抱える少女の実体と考えて差し支えないだろう。それに加えて、それを見る少女にとって脳内映像として二人目がいることになる。これは直感的に変な事態であると、すぐに気付くだろう。
これを「二重存在」と呼んで、カント図式が持つ課題として考えておきたい。物自体を想定すると、同じ対象が二つあるという状況にどうしてもぶつかってしまう。この「二重存在」という問題は、物自体を想定することによって発生する宿命のようなものでさえある、そう思えてくる。
ショーペンハウアーのほうへ
さて、カントを経てショーペンハウアーが、この問題をどう考えたのか。かといって、私はショーペンハウアーを読んだわけではないので、これがまったく的はずれな理解になっている可能性もあることを重々承知願いたい。
ショーペンハウアーは、カントを継承し、物自体と現象の区別をそのまま「意志」と「表象」と言い換え、同じようなニュアンスで使っている。「しかし意志とは、ずいぶん怪しげなワードセンスだな。現象が意志ならまだ理解できるが、物自体が意志なんてのはおかしな話だ」と思われた方もおられるだろう。確かに、「意志」という物言いはひどく宗教的な印象を与える。しかし、それは便宜上のものだということで、のちのち納得できる理由がある。
さて、カントに即して考える。まず物自体があって、それを感性もとい感覚器官が捉え、脳内映像として投影される。これが現象である。この図式が抱える問題として、物自体と現象とに同じ対象を想定してしまうことが挙げられる。これは「二重存在」と呼ばれる。
ショーペンハウアーは、カントの物自体を意志と置き換える。物自体では、われわれはそこに現象の原型があって、決して変わることのない世界そのものの姿を実体として考えてしまう。実体ではなく、出来事や欲望、力、運動、生成といった実体のないものとして、さらにいえば人間にとって徹底して不気味で、無秩序で、常に暴走する混沌として物自体を考えること、それがショーペンハウアーの主張するところだ。
それはちょうど、自転車とサイクリングの違いのようなものである。自転車は物質からできている。メーカーによって異なるけれども、タイヤはゴム製、ホイールはアルミ製、フレームはスチール、サドルは革……などなど。このように、自転車は物質的なもので説明することができる。何によって出来ているか、自転車を説明するにはそれで十分だ。
一方、サイクリングはどうだろう。自転車と同じように説明できるだろうか。自転車は二年前に近くのホームセンターで買った、場所は山の麓から海辺まで、何時頃に始めて、どんな服を着て行くか、そして乗るのはまぎれもない私だ……そういうわけではない。サイクリングは、ペダルを漕ぐということを不可分なものとして持っているが、漕ぐという行為は、はたして物質的に説明できるだろうか。それは物質ではなく、出来事ではないだろうか。サイクリングを物質の面から説明することは、あまりに不敵ではないだろうか。
サイクリングを組成しているのは、目的地に到達するという目的、それを達成したいという意欲、それに伴う努力、運動、それをひっくるめた出来事である。この視座はちょうど、ショーペンハウアーのいう「意志」を考える上で透き通った見方を与えてくれる。
ショーペンハウアーは、物自体をカオティック、無秩序で盲目的なものだと考える。世界を動かす原動力である「意志」は、物質よりもまさに出来事の次元にあるのだ。物自体を人間に想定することはできない。けれども、それを際限のない盲目的な運動として捉えることで、世界そのものの見方を変える。世界とは、一つの事件であるのだ。
そして物自体を出来事として考えれば、物自体を実体的に想定することで発生した「二重存在」も、解決とまではいかなくともいくらか見通しが良くなる。世界の奥底でゆらゆらとうごめく、大いなる自然のイメージ。ショーペンハウアーはこれに仏教的な悲観主義を加えて、「意志」を苦悩の根源としているが、むしろ仏教的な厭世観のほうが先であるのかもしれない。いずれにせよ、ショーペンハウアーの提唱した「意志」とは、まさにそうした展望で見えてくる光景ではないだろうか。
例えば、医者が風邪の患者を治すのに「ゲン」をかついで、注射の場所を手にしたり足にしたりするとすれば、誰でも笑うだろう。しかし相撲取りが「ゲン」をかついでひげをそらなかったり、特定の言葉を口にしなかったりするのを怪しむ人はいない。ふつうの人間にとって人生は競争であり、勝負であるのだが、そういう場面では「運」とか「ツキ」というものが人間の競争や勝負の結果を作用する大きな原因のように感じられる。これはつまり、人間は自分の運命を左右するあらゆる事象について、その「原因」を想定せずにはいられない本性を持っているということだ。それは哲学的に引き伸ばせば「根本原因」と呼ばれる。人間はこうした「根本原因」を想定せずにはいられない生き物だ。
そうであれば、ショーペンハウアーの「意志」とは、いま見たような「世界のあらわれ(=表象)」とその根本原因としての「意志」という区分だと考えていい。この「根本原因」としての「意志」は、ほとんど西洋的な「神」と考えても問題ない。ただし、その神は人格的なものでも、秩序正しいものでも、人間にとって都合のいいものでもない。それは徹底して不気味で、無秩序で、非理性的な代物なのだ。
根本的な「意志」の具体的あらわれとしての人間の「生へのあくなき意欲」は、当然はげしくせめぎあって矛盾に満ちた世界を作り出す。生物においては弱肉強食という言葉にその事態が凝縮されている。人間は恐ろしい混乱と戦い、矛盾と悲惨の繰り返しだが、その根本原因はやはり人間の「あくなき欲望」にある。これまでのカントを含めた近代哲学は、そこに理性と調和をもたらす原理を求めてきたが、それはいわばごまかしでしかない。世界の根本原因は「意志」なのであり、そうであるかぎり人間の生の本性は「苦悩」であるというほかない。
非理性的なものの家系図

ショーペンハウアー、フロイトによって板挟みにされたハルトマンについて考えてみよう。ハルトマン以前にはショーペンハウアーがいる。ショーペンハウアーは世界を「意志」と「表象」とに分け、物自体とは表象の裏でうごめく無秩序で、不気味な混沌であり、生への盲目的な「意志」だと考えた。重力は落下を意志していて、植物や動物は「子孫を残したい」という意志の現れであり、人間においては動物の本能に代わって「欲望」が意志として現れる。表象だけでは一切が静止したままの世界に、意志は動的な力をもたらす。そして、それぞれの意志は互いに闘争を繰り返す。
この「意志」は、非理性的な性質を持っているという点で、フロイトの「無意識」と共通している。そうなると、「ショーペンハウアー─ハルトマン」から「ハルトマン─フロイト」へとつながる「意志─無意識」という非理性的なものの系譜で、ハルトマンがどのような位置にあったのかは、おおよそ予想がつく。ショーペンハウアーよりも心理学らしく、フロイトよりも哲学らしいところがあったと見るべきだろう。
近代において、人間の思考は、見えないもの、決して届かないもの、闇のようなものに向かって、あるいはそれをめぐって展開されることになる。思考は不可能性を運命づけられる。それはちょうどカント的な図式によって、理性的な認識の限界、認識可能と認識不可能の境界を設定するように。物自体を認識できないこと、そうした思考の不可能性である。人間の思考は、常に非理性的なものという闇を抱え込むようになった。思考において、思考を逃れるものが生じたというべきか。
こうした非理性的なものの発見が、ショーペンハウアー、ハルトマン、フロイトを貫いている。ショーペンハウアーのいう盲目的な「意志」、フロイトのいう人間心理の「無意識」といった概念は、人間自身が内に含むようになった、その闇の別称なのだと言うことができる。
ハルトマンのほうへⅡ
軍人の息子としてベルリンに生まれ、自身も十六歳で近衛隊に入ったハルトマンは、膝に持病を抱えて除隊を余儀なくされた一八六五年以降、哲学に専心した。持病ゆえに職に就くことなく執筆活動に専念したハルトマンの名を轟かしめたのが『無意識の哲学』(一八六九年)である。森鷗外が一八八七年に留学先のベルリンで手に入れ、「これが哲学といふものを覗いて見た初で、なぜハルトマンにしたかといふと、その頃十九世紀は鉄道とハルトマンの哲学とを齎したと云つた位、最新の大系統として賛否の声が喧しかつたからである」と回想したこの著作は、ベストセラーとなって一世を風靡した。
古今の文献から採られた「無意識」に関わる膨大な事例を素材にしたこの著作の企図は、序文で宣言されている。「私の体系とは、シェリングの積極哲学から原理的学説の指示を、シェリングの初期体系から無意識の概念の指示を得て遂行された、ヘーゲルの明らかな優位の下におけるヘーゲルの体系とショーペンハウアーの体系の総合である」
この時点で、ハルトマンの思想的立場がうかがえる。「ヘーゲルの明らかな優位の下におけるヘーゲル体系とショーペンハウアーの体系の綜合」という点で、この著作がいかなる野心の秘められたものであったかがひしひしと感じられる。
シェリングとヘーゲルの哲学を、さらにはショーペンハウアーの哲学を総合すること。ハルトマンが抱いたのは、そんな破天荒な企てだった。ショーペンハウアーは、世界は「表象」にすぎず、その根底にあるのが盲目的な「意志」だと主張したが、一方でヘーゲルはショーペンハウアーの批判した「理性的なもの」に依拠していた。
ヘーゲルは、理性の自己展開が世界とその歴史を作ると考えたようだ。歴史とは理性的な判断の繰り返しであり、それゆえに世界とは理性によって得られた結果にほかならない。歴史、理性的判断によって絶えず前進し、最終的に主観(=現象)と客観(=物自体)は一致する、と考えたという。世界は意志と表象の二つで構成され、意志による世界の自己展開を「盲目的な意志」として否定的に考えたショーペンハウアーとは異なり、ヘーゲルは理性を重視し、理性による人間の勝利を確信している。その点で、ヘーゲルは楽観主義的である。
ハルトマンは、その理性と意志を属性とする絶対者として「無意識」を立てた上で、シェリングの「積極哲学」に則って、無意識がそれらの属性の対立を、相互否定を通して自己を止揚し、ついには両者の属性の一致に至るのが「世界過程」だと断じる。
無意識を非理性的なものと考えるハルトマンは、世界過程の途上にあるものは欠如の状態にあり、そうである以上、その中にある個人の現実は「表象」という名の幻想にすぎない、と説いて十九世紀末のペシミズム思想に影響を与えた。個人の意志など何ほどでもない。
ハルトマンは『無意識の哲学』「緒論」の第一章で「無意識」という概念の先駆者を列挙しているが、その末尾近くには次のような一節が現れる。
バスティアンが彼の『比較心理学への寄与』を次の言葉で始めるとき、私たちにとって未知の存在のように働くヴントの無意識的な魂を鮮明に想起させる。「私たちが考えるのではなく、それが私たちの中で考えることは、私たちの中で起こることに注意するのに慣れている者にとっては、明らかだ」。この「それ」は、しかし[…]無意識の中にある。
「私たちが考えるのではなく、それが私たちの中で考える」
「それ」がショーペンハウアー的な「意志」やフロイトの「無意識」であることは間違いない。意識とは異なる別の人格、沈黙の領域。錯誤行為においては「〈それ〉がやった」としか言いようのない非理性的なものの所作。すなわち人間自身が内に含むようになった「闇」である。
言及されているのは、民俗学者のアドルフ・バスティアンである。ここで引用しているバスティアンの著作の一節に現れる「それが私たちの中で考える」の「それ」をハルトマンが還元してみせたのが、ハルトマンにとっての非理性的なもの、すなわち「無意識」にほかならない。
バスティアンは、「伝播主義」と呼ばれる初期ドイツ民俗学の草分け的存在であったようだ。伝播主義は、人間が原始に普遍的な構造を持っていたと考え、今ある文化の同質性や差異は、接触による伝播がもたらしたとする。だからバスティアンが未開民族に残る原始医学を調査したとき、彼は現代人が捨ててきた、しかし原始にあったはずの普遍的なものを見出す方法を探求していたと言ってよい。
個人の表象の根底でなされる無意識の自己発展のうちに、ハルトマンは普遍的なものを見る。だからこそ、バスティアンの「それ」は、「無意識の中にある」のでなければならなかった。ハルトマンにとっての「無意識」とは、普遍的なものでもあった。
結び
ショーペンハウアーからフロイトまでの「非理性的なもの」の系譜をたどり、そこに位置するハルトマンの思潮を掘り下げる形で議論を進めてきたが、ここで一旦筆を置くことにしたい。
言ってしまえば、私はこのルポルタージュで、ハルトマンについてはまったく論じることができていない。終盤にはいくらかハルトマン自身の立場について主題的に論じたが、それでも説明不足で、煙に巻いたような構成になってしまった。あくまでもショーペンハウアーやフロイトの思想をなぞるばかりで、本殿に立ち入ることはほとんどできなかった。
ただ、それについては仕方がない、と一方では納得してもいる。ハルトマンなど、目に見えてわかるが、いかにも手に余るような代物だ。これ以上は古明地こいしの考察を飛び越えて、ただの哲学研究になってしまう。そうなると、本末転倒だ。
哲学については、YouTubeにある「哲学チャンネル」さんがわかりやすい解説動画を出してくださっているので、ぜひともご紹介したい。ショーペンハウアーやフロイトの思想のエッセンスを短時間で理解できる優れものだ。
とりあえず、ここで一旦結びとさせていただく。ここまで読んでいるということは、とても根気強い方なのだろう。そうした方にはひそかに感謝している。私の努めも報われるというものだ。
では、また会いましょう。
参考文献:
互盛央『エスの系譜』(講談社学術文庫)
フロイト『精神分析入門』(高橋義孝・下坂幸三訳、新潮文庫)
竹田青嗣『ニーチェ入門』(ちくま新書)
千葉雅也『現代思想入門』(講談社現代新書)
ハルトマンのためのブックガイド
エドゥアルト・フォン・ハルトマンについて言及されている本を列挙する。
互盛央『エスの系譜』(講談社学術文庫)
第二章では、ハルトマンのごく短い概略と、それぞれ「フロイトとハルトマン」「シュタイナーとハルトマン」という対比、またショーペンハウアーやニーチェとの関係において言及がなされている。内容が濃いので、他の手頃なフロイトの解説書などで希釈してから読むべし。
フィルー『精神分析』(文庫クセジュ)
前編では、フロイトの無意識説につながるショーペンハウアーやハルトマンの哲学を紹介しているらしい。筆者未読。
新井正人『鷗外文学の生成と変容 心理学的近代の脱構築』(七月社)
索引によると、鴎外がドイツを訪れた際のハルトマンとの出会いについて書かれているらしい。筆者未読。
他にありえるとすれば、ハルトマンは時代的にヘーゲル/ショーペンハウアー以後、ハイデガー以前のドイツ哲学者と言うことができるので、そのあたりに詳しいドイツ哲学史の本に書かれているかもしれない。
