
相対性精神学入門講義
レイテンシー博士、あの『燕石博物誌』でおなじみの正体不明のアクティヴィスト、幻想の語り手が、例によって巧みな想像力と幅広い知見を駆使して、相対性精神学概論と題して講演を行った。教授の説明によれば、相対性精神学とは「経験」という直接的所与を人間存在の真実として描き出す試みである。「何を相対性精神学として認めるか」という主張のもとに、「主観」を再定義する作業が始まる。
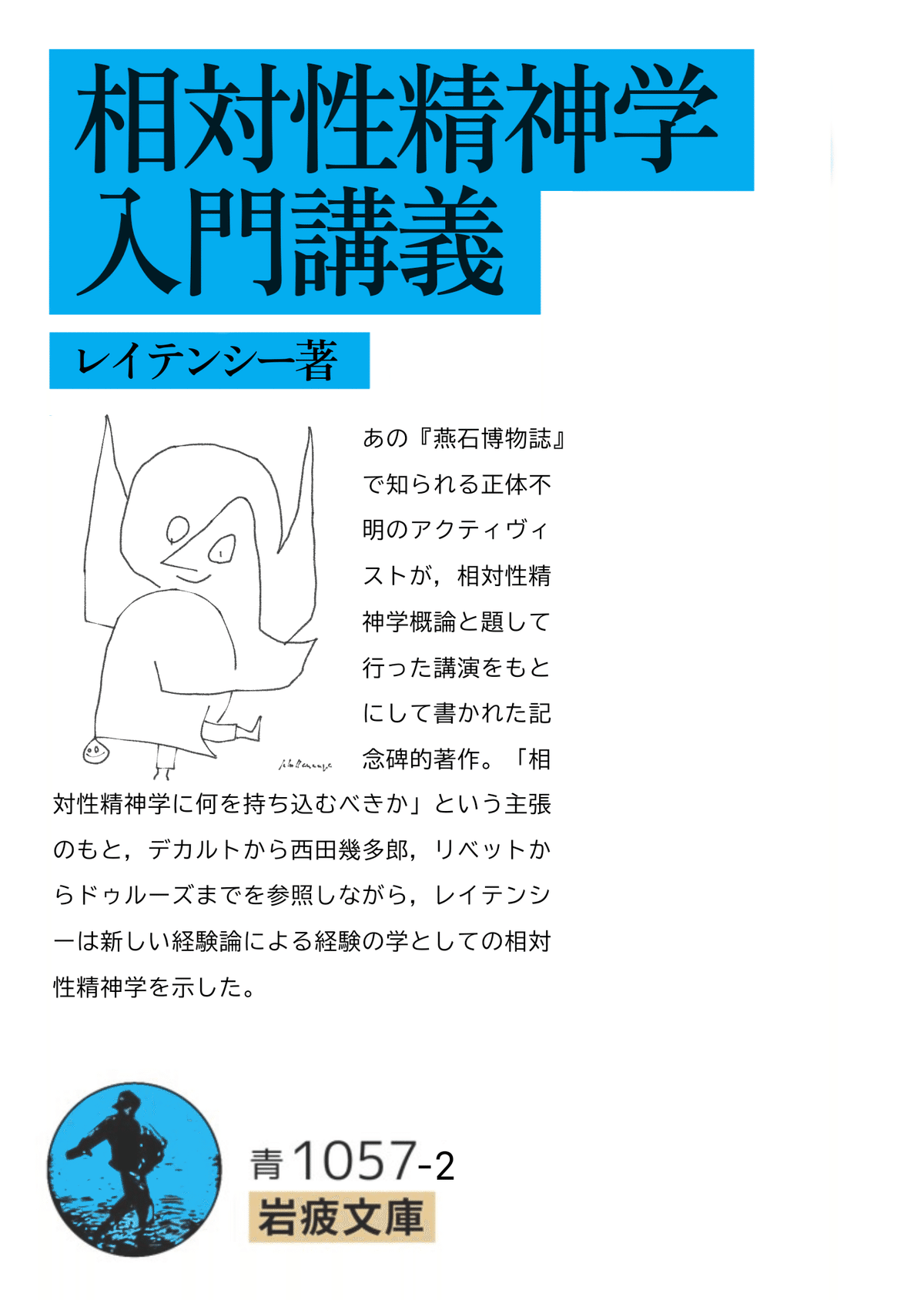
Latency
INTRODUCTORY LECTURE ON RELATIVITY SPIRITOLOGY
Complied by Ohsadahal
凡例
一、本書は、Latency, $${\textit{Introductory lecture on Relativity Spiritology}}$$の翻訳である。底本にはヒロシゲ校訂版『レイテンシー著作集』第二巻を用いた。
一、原文のイタリック体のうち、著書の標題は『 』で示した。
一、原文の強調箇所は太字で示した。
一、引用符” ”は「 」で示した。
一、原文の補足説明として使われている括弧( )は、そのまま( )で示した。原語を示す場合など訳者の判断で( )を加えた箇所もある。また、引用箇所の( )も訳者の判断で加えた場合がある。
一、注釈は[1]というように末尾にまとめて示した。挙げられた参考文献はできるかぎり頁数も指定したが、必ずしもそれに従うわけではない。
序論
脳神経科学研究に由緒あるこの場所[1]で、相対性精神学について語ることができるのにわれわれは、いや私は[2]たいへん身の引き締まる思いでいるが、それには特別な理由がある。相対性精神学は人間の主観の問題について革新的見解を携えて登場した。偉大な思想家ヴィルヘルム・シュテッカーリング[3]はその功績によって諸学に新たな刺激を与え、すでに生まれつつあった相対性精神学の発展に直接働きかけた。一方で意識に対して無意識の地位を強調する精神分析や、心を脳のニューロンの発火現象として説明する脳科学といった現代の諸思潮はこれに反発的であった。脳科学が前提する心脳同一説および随伴現象説に対する批判として挙げることができるのに、現代ではマルクス・ガブリエルの新実在論がある。主観を特権視するばかりの相対性精神学は、認識論における現象主義や科学哲学における反実在論がそうであるように、科学的認識を不当に貶めつつ人間や社会の物理主義的土台を隠し続けるだけの、科学世紀に特有の絶対主義にお似合いの反動思想だったのだ、云々。一足も二足も早い弔辞にしてはずいぶんやかましいが、一時の思想界においてはそれほど大きな思潮を成してきた。
主観の問題は、現代における諸思潮の中で無視される傾向にあった。ニュートンは「私は仮説を作らない(Hypotheses non fingo)」といったが、ここにはデカルトが念頭に置かれている。フーコーは「〈人間〉は発明された(l'homme n'est qu'une invention recente)」[4]といい、「〈人間〉は波打ち際に描かれた砂の顔のように消え去るだろう」と宣告した[5]。なかでもとりわけそれが神秘体験を付随する場合にあっては、より厳しい嘲笑が加えられた。ベンヤミンは、神秘思想家のシュタイナーに対して「前近代への願望でしかないと見て深く軽蔑していた」と語ったという。
しかしこの問い──パスカルによる「「私」とは何か」[6]という問いが放棄されるべき愚見であったことはただの一度もないと、私は強調したい。時代のなかで、むしろ時代に要請されるように、この誘いを前に、人間が沈黙を決め込むということが、未だかつてあり得ただろうか。汲めども尽きぬ情熱とともに、いつの時代も、われわれは問うてきたのだ。この「「私」とは何か」という根源的な問いに。
パスカルは「「私」とは何か」と問うた。デカルトは精神の本質を「思惟すること」と定義した。ラ・メトリは「魂は機械である」といった。スピノザは精神も「神」の顕現の一つの形態とした。カントは主観の中に認識の条件を見出した。ランボーは「私とは一個の他者である」と述べた。ウィトゲンシュタインは「私」を「形而上学的な主体」と呼んだ。キルケゴールは「主体性の真理」を主張した。ベルクソンは間断なき意識の流れに「持続」を見出す。荘子からプラトン、デカルトからヒュームまで。カントからランボー、ベルクソンから西田幾多郎まで。彼らが執拗に問うてきたであろう「「私」とは何か」という問いが、この時代にも反復される。むしろこの時代でこそ、「私とは何か」を問うことが重要なのだ。その中で何が正しいか否かを決める相対性精神学の純化こそが、私の狙いである。
最近まで、「新実在論とは何か」と問い尋ねられてきた。今では、相対性精神学とは何かと問い尋ねられている。前者の問いには、ひとまずの決着がついた。後者の問いは、刊行されつつある作品にかかわるので、高い関心が払われている。現在は二〇九六年である。作品が出揃っていないからといって、答えるのを避けることはできない。出揃っていないからこそ、問いに意味があるのだ。
そこで、「相対性精神学とは何か」という問いは、別の問いに置き換えられる必要がある。「何を相対性精神学として認めるか」という問い、「相対性精神学に何を持ち込むべきか」という問いである。人口に膾炙した「真実は主観の中にある」[7]という命題は、すでに哲学史や思想史の中でかなり手垢がついている。主観という概念は、あまりにも多くのもの──意識、自我、表象、精神、独断、観測、現象、主体、所与、経験、実存、クオリアと混同されている。これをそのまま思考の現場に持ち込むべきだとは私は思わない。
だからこそ、新たに原点に立ち返る企てが必要である。原点に立ち返る企てといえば、今年はちょうどデカルトの生誕から五百年である。デカルトにおいてそれは主観に向けられた哲学という形をとった。私は相対性精神学という学問を、新たに始めることにしよう。「すべてを根こそぎくつがえし、最初の土台から新たにはじめなくてはならない」[8]というデカルトの言葉とともに。
第一章 デカルトの方法論
デカルトと方法的懐疑
主観とは端に意識であり、主体であるのではない。それは思考するものとしての主観であり、哲学する自我に立ち返るものとしての主観である。「真実は主観の中にある」という命題のルーツは、デカルトに認めることができる。
ルネ・デカルト、このフランスの哲学者は、コギトという概念と、その過程を示すものとしての「我思う、ゆえに我あり」という表現で知られている。彼は彼自身を発端とする大陸合理論、それに対抗したイギリス経験論、両者を調停したカントの超越論哲学、さらにフッサールの現象学運動にまで影響を与えている。その多大な功績のために、彼は近代哲学の父と呼ばれる。一方で、彼は数学者としても知られる。デカルト座標系(直交座標系)は彼の功績である。
デカルトは形而上学を哲学の根底に置いている。古代ギリシャのアリストテレスは、存在するもののあり方を一般的な仕方で考察するとともに、最も優れて存在するということのできる神をも扱う、一群の著作を残したことで知られる。アリストテレスが残した書き物をのちに編集するとき、それらの著作は自然を扱う自然学、現代における自然科学に相当する書物のあとに置かれたために、自然学書のあとに置かれた書物という意味でメタピュシカと呼ばれる。「メタ」とは、「あとに」、「あとの」を意味する前置詞である。しかしその「メタ」が、「超える」、「超えた」という意味で理解されるようになる。つまり、自然学を「超えた」書物という意味で形而上学(メタフィジックス)が理解されるようになる。そのために形而上学は、自然学を超えてそれに基礎を与える学問というニュアンスを持つようになる。
デカルトの『哲学原理』がフランス語に訳される際にあたって序文の代わりとして書かれた訳者への手紙に、デカルトの学問観が表れているので、ここに引用しよう。「真理を見出す習慣を若干身につけたときに、真の哲学に取り組むことを真剣に始めるべきです。その第一の部門は形而上学で、認識の諸原理を含み、これには神の主なる属性、我々の心の非物質性、および我々のうちにある一切の明白にして単純な概念の解明が属します。第二の部門は自然学で、そこでは物質的事物の真の諸原理を見出したのち、全般的には全宇宙がいかに構成されているかを、次いで個々にわたっては、この地球および最もふつうにその廻りに見出されるあらゆる物体、空気、水、火、磁体その他の鉱物の本性が、いかなるものであるかを調べます。これに続いて同じく個々について、植物・動物の本性、とくに人間の本性を調べることも必要で、これによって人間にとって有用な他の学問を、後になって見出すことが可能になります。かようにして、哲学全体は一つの樹木のごときもので、その根は形而上学、幹は自然学、そしてこの幹から出ている枝は、他のあらゆる諸学なのですが、後者は結局(医学、機械学、道徳という)三つの主要な学に帰着します」[1]。
デカルトはここで学問全体を一つの樹木に例えている。根は形而上学、幹は自然学、そして枝は医学、機械学、道徳を中心とした諸学である。ここでは、形而上学は自然学を含む諸学に対して基礎を与えるものとされている。以下では、形而上学と自然学とのこの関係を念頭に置きながら話を続ける。
デカルトは『省察』という著作を、次のような書き出しで始めている。「まだ年少のころに私は、どれほど多くの偽なるものを、真であるとして受け入れてきたことか、また、その後、私がそれらのうえに築き上げてきたものは、どれもみな、なんと疑わしいものであるのか。したがって、もし私が学問においていつか堅固でゆるぎないものをうちたてようと欲するなら、一生に一度は、すべてを根こそぎくつがえし、最初の土台から新たにはじめなければならない」[2]。
「すべてを根こそぎくつがえす」とは、心の知的大掃除である。これはデカルトの際立った特徴の一つで、彼は少なくとも形而上学においては、多少とも疑わしいものは一切残すべきではないと考えた。そのために、始まりは絶対に確かなものでなければならないのだ。デカルトの哲学はすべてを疑うことから始まる。「疑うこと」を「懐疑」というが、彼の場合は真理に至る方法に沿った過程として行われる懐疑であるために、この懐疑はしばしば「方法的懐疑」と呼ばれる。
デカルトは次のようにいう。「さて、これまでに私がこのうえなく真であると認めてきたすべてのものを、私は、直接に感覚から受けとったか(たとえば視覚によって色や形などを知る)、あるいは間接的に、感覚を介して受け取ったのである(たとえば親や教師にきいて知る)。ところが、これら感覚がときとして誤るものであることを私は経験している。そして、ただの一度でもわれわれを欺いたこのあるものには、けっして全幅の信頼を寄せないのが、分別ある態度なのである」[3]。感覚的な与件や、伝聞による情報が時としてわれわれを欺くことは、われわれ自身がよく知っている。
デカルトは懐疑を継続する。「夜の眠りの中で、いかにしばしば私は、ふだんのとおり、自分がここにいるとか、上衣を着ているとか、炉ばたに座っているとか、信じることであろう。実際は、着物を脱いで床の中で横になっているのに」。「これらのことを、さらに注意深く考えてみると、覚醒と睡眠とを区別しうる確かなしるしがまったくないことがはっきり知られるので、私はすっかり驚いてしまい、もう少しで、自分は夢を見ているのだ、と信じかねないほどなのである」[4]という、夢と現実の見分けは本質的につけることができないという論理にデカルトは到達する。
さらにデカルトが想定する懐疑の終着点に、「欺く神」というのがある。この議論は次のようなものである。私は全能の神によって造られたのだと聞かされている。とすれば、実際には天も地も形も大きさもないにもかかわらず、そうしたものが存在すると私に思わせようとしているのかもしれない。そればかりでなく、私が二足す二を行うたびに、あるいは四角形の辺を数えるたびに、私が間違えるようにしむけているのではないか。つまり、二足す二が本当は五ではないのに、五になると思い込むよう、あるいは四角形は本当は五つの辺を持っているわけではないのに、五つの辺を持っていると私が間違って思い込むようにしむけているのではないか、というものである。
デカルト的主体と自由意志
しかし逆説的に、真なるものがそこに見出される。私が世界にいかに欺かれようとも、私がいまここにあるという事実は、否定することができない。欺かれるには、存在しなければならないのだから。「このようにして、私は、すべてのことをあますところなく存分に、あますところなく考えつくしたあげく、ついに結論せざるをえない。「私はある、私は存在する」というこの命題は、私がこれをいいあらわすたびごとに、あるいは、精神によってとらえるたびごとに、必然的に真である」[5]。「我思う、ゆえに我あり(Je pense, donc je suis)」である。「我思う」は「我疑う」を意味する。
ラテン語においてはcogito ergo sumである(「疑う私」、「考える私」はこれに従って「コギト」と呼ばれる)。これはデカルト的コギト、あるいはデカルト的主体、デカルト的自我とも称される。デカルト自身は『省察』の中でこれを「アルキメデスの支点」に例えてもいる。「私に支点を与えよ。さすれば、地球を動かしてみせよう」というアルキメデスの言葉が現代においても伝えられている[6]が、デカルトはこの話を念頭に置いている。
コギトの存在が明らかになった以上、これが物体的なものと区別されることもまた明らかである。「心と物体、即ち思惟するものと物体的なものとの区別が、ここから認識される。そしてこれが精神の本性、およびその物体からの区別を認識するための最善の道である。何となれば、いったいこの我々、即ち自分とは異なるすべてのものを、虚偽だと想定する我々とは、何であるかを調べてみると、延長・形・場所的運動その他、物体に帰せられるはずのこの種のものは、我々の本性には属しないで、ただ思惟だけが属する」。「従って、思惟はいかなる物体的なものにも先んじて、かつ確実に認識されるわけである。というのは、我々はこの思惟を認識したのであるが、他のものについては未だ疑っているからである」[7]。ここにおいては物体の本性が延長という空間的な位相のもとで捉えられているのに対して、精神の本性は思惟であるとされている。デカルト自身は脳の中央部にある松果体が、心と身体をつなぐものだと考えていたようだ。「我思うゆえに我あり」という命題が常に真であることは、デカルトが「我々(精神)が人体と呼ぶ或る延長的・可動的な他のものに、結合していることによる」[8]というように、思惟が空間的な物体と結合しており、実質的な因果関係ありながらも、物質的な説明に還元されることなく存在していることの証左である。
さらに、デカルトは次のように結論する。「だが我々の意志には自由があり、多くのことに任意に或いは同意し、或いは同意しなかったりできることは明白であって、このことは我々に本有的な、最初のそして最も共通的な概念(公理)に数えることができる」[9]。思惟それ自体が物体から独立して考えることのできるものであれば、思惟は自由意志を持つ。
(思惟は二つの様態に分けることができる。知性と意志である。この場合自由であるとされるのは意志であって知性ではない。意志は知性に比べて及ぶ範囲が広いが、判断するには知性のみならず意志が必要であるため、デカルトは思惟による誤りの原因もそこに認めている。)
デカルトの思惟を別の視点から理解するように努めよう。これはある知人の経験談であるが、学業という極度の緊張状態から解放されたその人は、閑暇のなか部屋で大の字になって寝そべっていたときに、こんなことを考えたという。人間がものを見る仕組みは、一般的に次のように説明することができる。瞳孔から目に入った光が虹彩で調節され、ピントを調節する水晶体で屈折、透明なゲル状の硝子体を通過して、網膜の黄斑に焦点を結ぶが、その光が視神経を通じて信号として脳に伝達されるというものだ。では夢の場合はどうであるのか? ここから得られる教訓は、われわれが直接見ているのは光そのものではないということである。それは古代の哲学者たちでさえ知っていた。われわれが外の世界にあるものと考えているものは、実際には心の中にあると考えねばならない。デカルトはこれに観念と名付けて、実体と区別した。観念は実体を原因としているが、両者は同一ではない。
一方で、心のなかに存する観念と実在する物体の二つが存在するとは、われわれに奇妙な印象を与えるだろう。実在する物体と、それから刺激を受けてわれわれが感じるなにかという二つの種類のものの存在を認める立場を、バークリーは二重存在(twofold existence)説として問題にした。
デカルトによる思惟の発想は、哲学における認識の典型を大きく転回させている。それは主客二元論の導入であり、自由意志の提示であり、物心分離と心身二元論の遂行であり、二重存在説の発見である。主客二元論は主観的な観察者と客観的な実体との相関そのものである。自由意志は物質・身体から独立した純粋な思惟としての精神の優位である。物心分離と心身二元論はその代償として人間存在の探求において、自然の不合理な謎として残ることになった。二重存在説も乗り越えられるべき不合理として認められた。
プラトンからデカルトへ
「観念」の歴史を、さらに深く掘り下げてみよう。観念(ideas)はプラトン哲学において、本来普遍的客観的に存在する真理という意味で考えられてきた。イデア(ideas)は古代ギリシャ語の見る(idein)に由来する。は現実界の人や物は多種多様であり、時間とともに変化し、複雑極まりない。けれどもイデアはそうではない。プラトンが『国家』第七巻の中で提示した、「洞窟の比喩」を思い出そう。「地下にある洞窟上の住いのなかにいる人間たちを思い描いてもらおう。光明のあるほうへ向かって、長い奥行きをもった入口が、洞窟の幅いっぱいに開いている。人間たちはこの住いのなかで、子供のときからずっと手足も首も縛られたままでいるので、そこから動くことはできないし、また前のほうばかり見ていることになって、縛めのために、頭をうしろへめぐらすことはできないのだ。彼らの上方はるかのところに、火が燃えていて、その光が彼らの後ろから照らしている。
この火と、この囚人たちのあいだに、ひとつの道が上のほうについていて、その道に沿って低い壁のようなものが、しつらえてあるとしよう。それはちょうど、人形遣いの前に衝立が置かれてあって、その上から操り人形を出して見せるのと、同じようなぐあいになっている」。「ではさらに、その壁に沿ってあらゆる種類の道具だとか、石や木やその他いろいろの材料で作った、人間およびそのほかの動物の像などが壁の上に差し上げられながら、人々がそれを運んで行くものと、そう思い描いてくれたまえ。運んで行く人々のなかには、当然、声を出す者もいるし、黙っている者もいる」[10]。劇中で相手は「奇妙な囚人たちのお話ですね」というが、それにソクラテスは「われわれ自身によく似た囚人たちのね」と返す。ソクラテス=プラトンは以下のように続ける。「つまり、まず第一に、そのような状態に置かれた囚人たちは、自分自身やお互いどうしについて、自分たちの正面にある洞窟の一部に火の光で投影される影のほかに、何か別のものを見たことがあると君は思うかね?」 この問いは、われわれが直接見ているのは光そのものではないということである。イデアとは光そのものである。プラトンはこのイデアを知ることを目指した。
しかし現代人のわれわれはこのイデアが何であるかを理解している。ガリレオ・ガリレイはいう。「自然が我々に語りかける言葉とその記号を学んだもののみが自然を理解できる。この言葉とはまさに数学であり、その記号とは数学的構造である」[11]。有名な「慣性の法則」は、止まっている物体に、力を加えなければ、そのまま止まり続け、動き続けている物体に、力を加えなければ、そのまま動き続けるというものである。ガリレオにこのような観点をとることを可能にしたのは、古代ギリシャから伝統として伝わっていた幾何学を中心とする数学的思考法だった。そもそも、力を受けない物体が無限に直線運動(円運動)を続けるということは、幾何学的空間のような抽象的な空間のなかでのみ可能なことであり、こうして幾何学化され、数学化された世界を想定することができたからこそ、ガリレオは慣性運動のような地上では存在しない運動を考えることができたのである[12]。
ボイルの法則、シャルルの法則も同様である。この二つを体系的に説明する試みにアヴォガドロの仮説がある。この仮説のもとで「気体分子運動論」がクラウジウス以降、マクスウェル、ボルツマンらによって展開されていく。その仮説の背後にあるのが「理想気体」という理論モデルである。この「理想気体」という理論モデルにおいて、分子の大きさは無視され、ミクロ現象においては非常に重要な位置を占める分子間力も無視される。二つはいずれも人間の普段の生活から導き出されたものではない。ガリレオに始まる近代科学とは数学に照らし合わせてイデアを素描する試みである。
このようにイデアとは普遍的客観的な実在そのものであり決して生成消滅しない。摩耗もせず消え去りもしない。イデアが主観的な意味を帯びるようになったのはデカルトからである。デカルトは、この言葉を心に現れ意識されるすべてを表すのに使用する。客観から主観への観念の変遷である。その意味では観念(ideas)は、一般的に考えや思いつきという意味を持つものである。
アリストテレスからデカルトへ
この議論にもう一つ加えよう。主体(subject)はラテン語のsubjectumに由来するが、これはアリストテレスによるヒュポケイメノン(hypokeimenon, ὑποκείμενον)の訳語である[13]。これは「下に置かれたもの、横たわっているもの」を意味する。おそらく心について論じられたものでも最初期の書物『ペリ・プシュケース』の中で、アリストテレスは次のようにいう。「心というのは、第一の意味で、「それによってわれわれが生き、感覚し、思惟するもの」であり、したがって、一種の定義内容であり、形相であって、質料すなわち基体(ヒュポケイメノン)ではないことになる」[14]。ヒュポケイメノンは、感覚し、思惟する心ではないものである。「物体は基体(ヒュポケイメノン)に述べられるものに属するのではなく、むしろ、基体、つまり質料ということになるだろう」[15]。物体は基体に対して二次的な位置を占めるのではなく、基体そのものである。このことから、ヒュポケイメノンはむしろ客観的なものの位置を占めていたのである。存在論的には、さまざまな性質の「下に横たわって」いてそれらを担い支えているものとして、つまり「基体」として存在した。それは文法的にはさまざまな述語がつけられる基体としての「主語」である。
この用法はその後も続いた。たとえば古代末期のストア派の懐疑派では、人の心の外にそれ自体で存在するもの、ほんとうに存在するもの、さらにはわれわれの感覚的印象の原因になるものという意味で用いられているし、スコラ哲学や近代初期でも同様である。これを転回させたのは先に述べたように、デカルトであり、その次に登場したカントである。デカルトは「我思うゆえに我あり」をあらゆる懐疑に耐える不動の基礎とみなした。「考える私」によって明晰判明に認知されるものだけが真理であるのだから、このとき初めて基体(ヒュポケイメノン)は主観的原理となる。
それに対して、アリストテレスはアンティケイメノン(antikeimenon、αντικείμενον)という語を用いてもいた。これは、アリストテレスにおいてはたんに心の対象くらいの漠然とした意味で使われていたが、中世になるとその用法が変化する。もともと「~に対して投げられたもの」を意味するラテン語のobjectumが、「心に対して投げられたもの」、心へのものの投影、心の志向的対象、表象の意味を持つようになるが、これはまだ主観的意味合いを保っていた。これがロックによって「外的対象」(external object)という表現を用いることになり、客観的な意味を帯びるようになる。こうした原義を逆転させて、これら対概念を「主観/客観」という今日の意味に定着させたのがカントである。
基体としての主観は、デカルト以後はカントにおいてとりわけ目を見張るものがある。カントは(デカルト的な)観念の領域を現象界と呼び、現象の原因である物自体を思考することはできないと考え、さらに、客観的認識は客観そのものではなく、主観的にしか成り立たないということを主張した。カントはデカルトの批判者として登場するけれども、デカルトによるコギトの概念を、超越論的統覚として引き継いでいる。基体としての主観は、ヘーゲルにおいても同様である。デカルトからの主観偏重の流れがそこにあらわれている、『法の哲学』の序文で提示した言葉を、ヘーゲルは『エンチクロペディー』においても繰り返す。「理性的なものは現実的であり、現実的なものは理性的である」[16]。そして自然という非調和的な外面的存在に対して、精神(geist)にこそ真実を見出そうとするヘーゲルの「……精神こそが一切をそのうちにふくむ真の存在である」[17]、「いっさいは、真なるものを実体としてではなく、むしろ同様に主体として把握し、表現することにかかっている」[18]という姿勢に、デカルトによって転回された「基体」を見出すのは誤りであろうか。
こうした流れの相貌のうちでデカルトを見つめてみると、事態は大きく入り組んでいることがわかる。「相対性精神学に持ち込むべきはデカルト的主体である」あるいは「相対性精神学に持ち込むべきは自由意志である」と結論することは一つの道であろう。また、プラトンからデカルトへの「観念」概念の変遷、アリストテレスからデカルトへの「主体」概念の変容についても留保をつけておこう。相対性精神学における主観、「真実は主観の中にある」がこの壮大な転回にあるとしても、冒頭に述べたとおり、主観という語はあまりに広い意味を持つからである。
これからはデカルトの論点を中心としながらも、デカルトに対する批判を紹介するとともに、「何を相対性精神学として認めるか」を検討する。
第二章 デカルトへの批判
ラ・メトリの唯物論
一八世紀に開花したフランス唯物論のもっとも先鋭な代表者といわれる医師ジュリアン・オフレ・ド・ラ・メトリは、『人間機械論』の中でデカルト批判を敢行する。ラ・メトリは主に生理学を論拠とし、デカルトによる自由意志説に破綻を見出す。その中心的主張はデカルト的コギトを含め霊魂の存在を否定し、ただ物質だけが存在すると考える唯物論である。
ラ・メトリは生理学、医学、解剖学などの当時最新の知見を総動員しながら、人間がいかに物質的な制約に縛られているかを粘り強く論証する。彼の引き出す知見は現代の観点からは誤っているものばかりであるが、それは彼の理念そのものを軽んじる理由にはならない。
本書の論調は物腰柔らかなデカルトとは違い、論旨も相まって全体的にやや挑発的である。例えば、降りかかる苦難に対して精神の平静を説いたローマ時代の賢人たちについての言及。「死に近づくのを知って、子供のように、泣く者がいるかと思うと、戯談をいっている奴がいる。カヌス・ユリウスに、セネカに、ペトロニウスに、かれらの大胆不敵な態度を、卑怯未練な態度に変ぜしめるためには、何があればよかったのだろうか? 脾臓閉塞、肝臓閉塞、門脈の故障で十分だったのである。その理由はなにかといえば、想像力は内臓とともにふさがるものであり、ここからヒステリー、ヒポコンデリー等の疾患のすべての奇妙な現象がうまれるからである」[1]この個所だけでも、ラ・メトリの姿勢は十分にうかがえる。賢人でも誰でも、人間が平静な精神を保つことのできるのは、病魔にさらされていないというだけに過ぎない。精神疾患について生理学的な故障として説明できるという点についても、注目に値する。ある意味素朴でありながら、ごく一般な現代人にもおよびそうな考えだということができる。彼の立場を、魂や精神が物質的な制約によって成立するものとして、唯物論(materialism)と呼ぶことができる。唯物論は、魂や精神を物質的な観点から説明する物質一元論の試みである。
彼の唯物論は次のような言葉の端々にもあらわれている。「従って魂は運動の原動力、ないし脳髄の中の感じる力を持った物質的な一部分にすぎないのであり、これは、まごうかたなく、機械全体の主要なゼンマイとみなすことができる」[2]。ラ・メトリは彼の唯物論を「機械」という言葉で表現している。それは非現実的で曖昧模糊とした世界の像を捨て、物質的根拠を持たない妄想の入る余地を徹底的に排除しようという印象をわれわれに与える。彼の唯物論は、哲学というよりも科学者の一般見解というほうが適切だろう。科学偏重の傾向にあるこの後期科学世紀という時代においても、この見解を支持するものが多いように思われる。
ラ・メトリは人間の魂(ラ・メトリはこれ自体が非常に空虚な言葉であると指摘する)が脳の組織に依存すること、主観的意識、精神、思惟が脳の働きと身体を逸脱することはあり得ないことを主張する。「しかしながら魂のすべての能力はかくのごとく脳の組織そのものならびに体全体に依拠しており、否あきらかにこの組織そのものにほかならない以上、これは誠に経験を積んだ機械と言うべきである! けだし人間だけが人道を頒け与えられていたとしても、そのために機械でなくなると言えるだろうか?」[3]人間には善と悪を判別する力があり、善と正義と倫理を追求し社会に参画するという生き方ができる。しかし、それと動物であることは少しも矛盾しない、というのがラ・メトリの論旨である。「機械であること、感じ、考え、善と悪の識別を知り、また青と黄の区別を知ること、一言にしていえば理性と、道徳に対する確かな本能を持って生れていることと、それから動物にすぎないということは、すこしも矛盾するものではなく、それは猿であり、また鸚鵡であって、しかも快楽を味わう方法を知っているというのが矛盾しないのとすこしも変りはない」[4]。
確かに、デカルトは人間を猿から区別するために、「考える私」としての「思惟」を持ち出したかのようだ。しかしラ・メトリは「動物に対する人間の以上ののごとき優越にもかかわらず、人間を動物と同じ階級に並べることは、むしろ人間の名誉を尊重したやり方である」(同)といいきる。
したがってラ・メトリは次のように結論する。「人間は機械である。また、全世界には種々雑多な様相化の与えられたただ一つの物質が存在するのみである」[5]。全世界も人間も機械から構成されており、魂や想像力もその範疇にある。デカルトが「多くのことに任意に或いは同意し、或いは同意しなかったりできる」というように、無から有に転化するような人間の自由意志の存在もありえない。
スピノザの心身並行論
一七世紀オランダで合理主義哲学者として頭角をあらわしたバールーフ・デ・スピノザは、同じく鮮烈なデカルト批判を敢行する。あのアインシュタインが「私はスピノザの神を信仰している」[6]といったあの有名な逸話が示す、常人理解から著しく離れた(スピノザによる)「神」の発想についても言及することは避けられまい。幾何学的証明の形式で定義と公理から諸定理の証明を展開する、哲学書の中でも特異なスタイルで書かれた『エチカ』の第一部冒頭、スピノザは神を次のように定義する。「神とは、絶対無限の存在者、いいかえれば、そのおのおのが永遠・無限の本質を表現する無限に多くの属性から成りたつ実体のことである」[7]。
神は完全なる存在者である、よってそれは無限でもあるとは、デカルトも認めていた。デカルトは『省察』のなかで神の存在を次のように証明する。われわれ人間は不完全なるものである。一方で完全の観念を知っている。無限、全知全能などがそれである。これは完全なるものがわれわれに完全の観念を教えたからにほかならない。完全には必然的に存在が含まれる。完全なるものとは神である。よって神は存在する。次に、完全である以上神は他者を欺く必要がない。したがって神は私たちを欺かない。私たちは世界を明晰判明に認識することができる[8]。
デカルトは神を、世界の背後にあり、私の認識を明晰判明にしてくれる根拠として持ち出しているが、神が無限であるのならば、ここからここまでが神であり、ここからは神ではない、という線引きはできないということになる。線引きができてしまうことは、有限であることの証明になってしまうからだ。であるならば、神には外部あるいは例外がないことになる。つまり、すべての存在事物は神の内部にあり、一切を神が内包しているということになる。よってスピノザは神を自然と同一視する。神とは世界そのものであり、世界とは神そのものである。だから、神を理解することは自然法則を理解することである。
であれば、精神と身体という二つの原因は、神という実体の二側面として説明することができる。スピノザはこの側面を「属性」という言葉で表現する。人間にとって属性は思惟と延長の二つである。
スピノザによるデカルトの自由意志批判は第二部定理四八に登場する。「精神の中には、絶対的な意志あるいは自由な意志は存在しない。むしろ精神は、このこと、あのことを意欲するように原因によって決定され、この原因も他の原因によって決定され、さらにその原因も他の原因によって決定される。このように無限に進む」[9]。デカルトの自由意志は根拠がない。というよりも、人が「多くのことに任意に或いは同意し、或いは同意しなかったりできる」と考えているような自由意志の観念は、それを成り立たせる原因を知らないことによって成り立つようだ。
同じ部にある定理三五の注解を顧みてみよう。「自分が自由であると思う〈すなわち、彼らが自由意志によってあることをなしたり、またしなかったりすることができると思う〉人は誤っている。このような意見を述べることは、ただ、彼らが自分の行動を意識し、自分がそれへと決定される諸原因を知らないからである。それゆえ彼らの自由の観念は、彼らが自分たちの行動の原因を何も知らないことにある」[10]。このスピノザの言葉を覚えておこう。
スピノザもデカルトも、心と身体の関係を二元論として考えるのは同じことであるが、デカルトが心と身体を因果関係として捉えており、つながりを念頭に置いていたのに対し、スピノザにとって、心と身体は直接の関係がなく、互いに並行して働くものである。彼の心身問題についての立場は心身並行論(parallelism)と呼ばれる。
リベットの実験
自由意志の成立が「自分がそれへと決定される諸原因を知らない」ことに由来するのであれば、知るように心がけよう。「我々は知らねばならない、我々は知るであろう(Wir müssen wissen, wir werden wissen)」[11]というヒルベルトの言葉とともに。今日の神経科学は、私の心のすべてが、私の脳のニューロンの発火に伴って起きる「脳内現象」に過ぎないことを指摘してやまない。現在知られている大脳生理学の実験的データに基づいて論理的に考えれば、次のようになる。外界にどのような事物があっても、脳の中のニューロンがそれに対して発火しなければ、心にはその事物の認識は生じない。たとえ外界に事物が存在しなかったとしても、脳の中のニューロンがあるパターンで発火すれば、そのような事物が見えてしまう。
人間の脳は、約一四〇億の二ューロンと、ニューロンを取り囲む十倍ほどの数のグリアという「機械」からなっている。一個のニューロンは、数千から一万個の他のニューロンとシナプスを通して結合する。シナプスでは、一秒間に数十回、神経伝達物質の入った包みが放出されている。何の変哲もない化学物質だ[12]。
ベンジャミン・リベットは、「リベットの実験」と呼ばれる一連の研究の中で、人間の自由意志が迷妄に他ならないことをこの上なく明らかにした功績で知られている。一九六〇年代には、すでに神経生理学者のあいだで客観的な刺激と主観的な認識を比較する研究が始まっていた。この刺激と認識のあいだにある時差の研究──実際には、脳に埋め込んだ電極によって刺激に対する反応速度を計測するというものである──によって、意識が平均五〇〇ミリ秒遅れて生じることが明らかになった。
今、あなたが自動車を運転しているとしよう。いきなり前に人が飛び出してきたとして、当然あなたは「危ない!」と意識すると同時に慌ててブレーキを踏むはずだ。あなたはこの一連の動作を自分の意志が行ったと考えるだろう。しかし実際にはそうではない。意識がそう知覚する五〇〇ミリ秒前に無意識が判断し、無意識がブレーキを踏んでいる。しかしあなたは、それを自分の意志でやったと確信しているだろう。正確には、脳によって確信させられている。実験によって、脳にはタイムラグを修正する機能まで備わっていることが明らかになっている。この状況には、「私は喋るためにそこから出る、喋りながらもそこにいる、そう喋っているのは私だ、そして私ではない、あたかもそれが私であるかのようにふるまっている、しばしばそれが私であるかのようにふるまっている」[13]というベケットの言葉が似つかわしい。
ではわれわれ人間が無意識の操り人形であり、すべてが自動的に進行しているのかといえば、そうではない。五〇〇ミリ秒の後半一〇〇ミリ秒だけ自由意志が介在する余地がある。この瞬間的な時間において、われわれは無意識によって準備された行動を拒否する自由が与えられている。これをリベットは「自由不意志(free won't)」と呼んでいるが、しかしあまりにも脆弱であるといわざるを得ない。
トール・ノーレットランダーシュは、星の数ほどある脳の膨大な細胞群が、無意識下でどれほど機能しているかを、情報理論に用いられる単位でわかりやすく説明している。「はい」か「いいえ」という最も基本的な判断に費やされる情報量を一ビットとしておこう。無意識下で処理される情報量はおよそ一一〇〇万ビット、このうち意識にのぼる情報量は毎秒数十ビットである。ピアニストがピアノを弾くのにどの指でどの鍵盤を弾くかを意識しないように、われわれの行動はほとんどが無意識下に決定されている。
第三章 認識の可能性の条件
ソシュールの記号学
ラ・メトリにしてもリベットにしても、彼らの唯物論的見解に修正を求めるような打撃を加えることはなにも難しいことではない。われわれがまずここで言及するのは、ソシュールである。
近代言語学の父フェルディナン・ド・ソシュールは、彼が行った一般言語学についての研究と、彼の提唱した記号学(sémiologie)、そして後になって発展した構造主義との関連において知られる。ここでは「恣意性(arbitraire)」という言語一般の原理について述べよう。
まず第一に、ある語(記号)Aは次のように定義される。AとはAではないではないものである、というように。ソシュールは、差異だけが価値を持つと考えた。Aが持つ価値は、Aではない「ではない」ことによって生まれる。AではないものからAを区別するという否定的な契機においてしか、語は価値を持たないのである。語は記号と呼ばれる。
饅頭と風船の比喩を例に挙げよう[1]。ソシュールは、記号を何か実体的なものとして存在するとは考えない。記号の価値は「ではない」という否定的な契機によって生まれるのだから、言語それ自体が関係的である。

A, B, C, Dという四つの記号がある言語の総体、差異の体系があったとしよう。Ⅱ、実体の言語観は、「である」ことによって定義されるため、言語の総体からAが抜け落ちた場合、Aが占めていた箇所は空白になる。対して、Ⅰ、関係の言語観は「ではない」ことによって定義されるため、言語の総体から記号(狼)が抜け落ちても空白は生じない。狼という語が意味していた内容は、ほかの記号(犬、山犬、野犬)が位置を占めることになる。Ⅱが饅頭であるのに対して、Ⅰは風船で例えられている。
フランス語のmouton(羊、羊肉)は、(英語の)sheep(羊)と同じ意義を持つことはあっても、同じ価値を持つことはない。つまり、「moutonの毛を刈る」という文脈においては、たまたま(英語の)sheepと同じ意義を持つが、「moutonを食べる」という文脈においては、(英語の)muttonという意義を持っている。この例にだけ限っていえば、フランス語のmoutonの価値のほうが、(英語の)のsheepより大きく、(英語の)muttonをも包摂している[2]。
もともと、自然の中にはmoutonという単位も存在しなければ、sheepという単位も存在しない。moutonの価値は、フランス語という体系内で、たとえばbœuf(牛、牛肉)という辞項と対立することから生じ、sheepは英語という体系内でmuttonという辞項と対立することから生じたという、分節の線の引き方の相違に過ぎない。ソシュールは次のようにいう。「ところがじつをいえば、価値はまったく相対的なもので、さればこそ観念と音との連結は徹底的に恣意的なのである」[3]。
言語の「恣意性」は、ソシュール言語学における核心的位置を占めている。恣意性は必然性と対置される。必然性と結びつくのは、名辞と意味内容が固定的に結びつく「名称目録的言語観」である。記号学的視点に立たない限り、言語の本質を見損なうおそれがある、というのが彼の主張なのだ。記号学の主題が見えてこないのは、言語を言語ならざる別の視点から研究しているためである。言語を研究するとき、心理学者や哲学者が、さらには一般大衆がするやり方で行うと、記号学的主題は現れてこない。
言語を名称目録のように見なし、言語内の価値が互いの共存自体によって相互的に決定される事実を覆い隠してしまうと、言語の本質を見失うことになる。ヨーロッパの近代的知に依拠する多くの学問はこの名称目録的言語観を前提としている。その意味ではラ・メトリもリベットも、ソシュールが提起する認識の条件としての言語の問題をまったく無視しているといっていい。
カントの超越論哲学
「カント以前の哲学はすべてカントに流れ入り、カント以後の哲学はすべてカントから流れ出る」といわれた一八世紀の哲学者イマヌエル・カントは、西洋哲学におけるもっとも重要な仕事『純粋理性批判』の中で、認識の発生の条件を問う超越論哲学を構想した。
この「超越論的(Transzendental)」という用語は、一癖も二癖もある。カントの哲学は、諸物や宇宙の存在を前提としたうえで、それをどうやって認識するか探るのではなく、およそ諸物や宇宙などの存在者が存在者として成立するための条件を探る哲学である。カントが示したのは、実験科学が必要とする経験、そのための方法論としての経験論が頼りにする「経験」そのものが知性の関与なしに成立しえないことだった。
われわれなら直ちに「サイフォン」とわかるものがあったとする。ところが、それとまったく同じものをみても、ピダハンや英国人、一〇〇年後の人々はそう思わない。目に映る像は同じでも、その人が持つ知識や概念によって、何を知覚するかは変わってしまうのだ。現代の科学哲学者であるハンソンはこれを「知覚の理論負荷性」と呼ぶ。[4]
さてわれわれはサイフォンを「ひとつの」サイフォンとして認識するはずだ。しかしサイフォンはコーヒー粉を入れるロート、お湯を入れたフラスコ、それを支えるスタンド、そしてフラスコを加熱するヒーターから成りたっている。このすべては感覚によって与えられた感覚的所与である。ところで、感覚的所与としてはいずれも異なったものが与えられているにもかかわらず、われわれは「ひとつの」サイフォンを知覚している。「ひとつの」サイフォンを知覚するということが、まさにサイフォンを見るということ、あるいはそれを経験することに他ならない。直接的な感覚的所与しか認めない経験は、どこにも区切りが認められないために、ちょうどポロックの描く絵画のような様相を呈するだろう。「ひとつの」は感覚的所与からはえられない。ではどこからえられるか、というと、感覚とは異なるわれわれの能力、すなわち知性からだ、とカントはいうのである。
コーヒーにかんする知識や理論は地域や時代によって今後も変化するだろう。だが、われわれの経験には、より普遍的で基礎的な働きがある。それが「同一性」「因果」などのカテゴリーだ、というのがカントの考えである。カントは、感覚的所与からは得られない「ひとつの」を悟性から導かれるものとし、それを悟性概念もしくは「カテゴリー」と呼ぶ。カテゴリーは、その性質にかかわらず、およそある物が存在者として成立するうえでのあり方を分類する枠組みである。カントは「ひとつの(同一性)」のほかに、「複数」「非存在」などを量のカテゴリーとして挙げている。
同一性(「ひとつの」)などのカテゴリーがなければ、サイフォンがある、などの経験は成立しないのだから、カテゴリーは経験に先だって、それを可能にする原理である。これをカントは「~に先立つ」という意味のア・プリオリ(a priori)なカテゴリーと呼ぶ。何に先立つのかといえば、当然経験に先立つものである。逆に経験それ自体は「~の後で」知られるために、ア・ポステリオリ(a pos-teriori)であるといえる。
その意味で「同一性」などのカテゴリーは、およそ諸物や宇宙などの存在者が存在者として成立するための条件である。カントが主張した有名な言葉に、「認識が対象に従うのではなく、対象が認識に従う」というものがあるが、はじめに事物があって、それを見た時の意識内容は事物に依存していると考えるのではなく、意識内容=対象それ自体が、カテゴリーという認識の条件に従っているのである。カントはこのような認識の可能性の条件を「超越論的なもの」と呼んでいる。
では、われわれの経験は、いつの間にか埋め込まれた概念によって歪曲された主観的なもの、錯覚でしかないということになるのだろうか。水につけた棒が曲がって見えたり、目を寄せたときにものが二重に見える場合には、光学的、生理学的に歪みの発生メカニズムが説明できるし、そもそも、それが歪みといえるのは、それ以外に「正常な知覚」があるからだ。ところがカテゴリーの場合、「それ以外」というものがない。カントの話は、われわれの知覚構造に関わる「心理学的」な説明ではなく、およそ人間一般にとって経験が可能であるための「超越論的」説明なのである。それゆえ、経験と無関係にはじめから存在するものはなく、経験構造と存在は不可分となる。そこで自我も、カントによれば「超越論的仮象」とされる。
カントの考える経験は、物理学者などの実験や裁判官の審問に似ている。物体が落下する際の速度の変化を調べようとしたガリレオは、はじめ「物体の落下速度は、落下開始後から通過した距離に比例する」という仮説を立て、実際にものを落としてみた。が、速度の変化は通過距離には比例していないことがわかる。そこで、「落下距離は、落下開始後からの経過時間に比例する」という第二の仮説を立てたが、物体ははるかに早く落下した。そこでこんどは「経過時間の二乗に比例する」という第三の仮説を立て、実験したところ、たしかにそれに一致した。こうして生まれたのが物体の自由落下に関するガリレオの法則である。
問題は、ガリレオが自然を観察したり、実験したりする際に、あらかじめ一定の「仮説」をたてていたことである。このときかれは、落下物のさまざまな性質のうち、その仮説にひっかかるところだけに注目している。物体の色や味、落下時に発する風切り音などには注意を払わず、質料や落下速度だけに着目したのだ。彼は仮説にとって有意味な観点からのみ自然の諸性質を抽出し、自然に関する理論を作ったことになる。ここで、仮説や理論に当たるのがカテゴリーである。裁判官の審理においても、事件の真相(当日のアリバイ)に関わる真実や違法性(それを裁く法はあるか)は問われるが、被告人の食べ物の嗜好など、事件に関係のない事柄は問われない。
カントは、性質の背後にあってそれを支えるといわれる不可視の「実体」を前提とすることなく、同一物に関するわれわれの経験を解明し、その根拠を与えたのである。とはいえ一方でカントは物自体を認める。カテゴリーによって組織化された感覚与件をカントは「現象(Phänomen)」と呼び、それと「物自体(ding an sich)」を区別したのだ。現象として経験しうるものは、われわれにとって見えるものでしかないが、それとは区別された、そのもの自体のあり方が物自体である。われわれは物自体について思考はできるけれども、直観はできない。それを直観しうるのは神だけだ、とカントはいう。たとえば立方体は十二本ある辺すべての長さが等しい立体だが、われわれはその辺のすべてを一度に知覚することも、想像することもできない(思考することはできる)。神ならばそれを直観できる。しかしカントは、客観的認識は物自体という客観そのものではなく、カテゴリーという主観を成り立たせる条件のもとで成立する、現象のなかにのみ存すると考えた。
独我論の論理
これまで述べてきたのは、唯物論者に対する反論として想定されるものである。ソシュールもカントも、認識の可能性の条件を問うこととしては似ている。認識の可能性の条件を「超越論的なもの」と呼ぶことができるが、唯物論者はこれに対して無計画である。超越論的なものとは、主観的な認識をそもそもとして成り立たせている条件である。だから「真実は主観の中にある」をカントの立場から解釈することも可能であるし、これを私は超越論的相対性精神学と呼んでいる。詳しくは盟友が書いた『相対性精神学序論』を見よ[5]。
では、唯物論を相対性精神学からもっとも遠いものとして考えて、その対極にあるものを探ってみよう。主観と自我へもっとも大きな信頼を置く独我論(solipsism)の話をしよう。
ここに独我論者がいる。彼は自分の心だけが確実に存在するとし、自分の心以外から去来するあらゆる(心の)外部の考えも不確実であるとみなす。ここに黒板があって、私の書いたソシュールを解説した図がある。すくなくとも私の見た限りではそうだ。しかし私の目が悪さをしてないとは限らない。私は確かに書いたはずだ、ほんの十分前に。しかし欺く神がいて、五分前にこれを書いた痕跡と、記憶を私の脳に植え付けたのかも。私がいま存在しているということを除いて、何も確実ではない。
「世界五分前仮説」というのがあるらしい。世界は実は五分前に始まったかもしれないという、この仮説は否定することができない。それは過去が存在することを示すことができないということでもある。過去が存在すると主張する者は、過去を現在の記憶として保持しているにすぎない。この仮説は私の見方をしてくれるだろう。
「水槽の中の脳」というあまりに有名な思考実験がある。ある人は自分が公園を歩いていて、あたたかな日差しに照らされていることを確信している。本当はコンピューターが電極を通して脳波を操作しているにすぎないのに。たとえ外界に事物が存在しなかったとしても、私の脳の中のニューロンがあるパターンで発火すれば、そのような事物が見えてしまうのだから、この仮説は反証することができない。
「胡蝶の夢」も同様である。夢の中で胡蝶としてひらひらと飛んでいた所、目が覚めたが、はたして自分は蝶になった夢をみていたのか、それとも実は夢でみた蝶こそが本来の自分であって今の自分は蝶が見ている夢なのか、という説話である。デカルトのいうように、世界には「覚醒と睡眠とを区別しうる確かなしるしがまったくない」のだから、私が蝶になる夢を見ているのか、蝶が私になる夢を見ているのかは、いずれが本当か私にはわからない。
「ボルツマン脳」という思考実験も、私の見解を裏付けてくれる。ボルツマン脳は完全に人間の脳の形をしており、熱力学的平衡状態からの非常にまれなランダムな揺らぎのために発生し、私たちの宇宙での人間としての生活の完全な記憶を備えている。問題は宇宙ができて、地球ができて、私の生きる環境と生活ができて、私がいまここにいるという可能性よりも、偶然私の脳が宇宙空間にぽつんとできる可能性のほうが高いということだ。
以上の理由から、私は私の精神の存在だけを確信している。
ドゥルーズの他者論
これに対する反論はたやすく挙げることができる。ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインは「つまり、ソリプシズム(独我論)が思っていることは、まったく正しい。ただしそれは、言うことができず、しめされるだけである」[6]といっている。彼は「世界が私の世界であることは、この言語(私だけが理解する言語)の限界が私の世界の限界を意味する、ということにしめされている」と続ける。そのように言語で表現したときにはすでに、いいたいことからずれている。というよりも、いいたいことをまさにその言葉が裏切っているといえる。それはちょうど、「卯酉東海道は東京から京都までを五三分で移動することができる」という命題とはわけが違い、一般化ができないものである。アルチュール・ランボーは教師イザンベールへの手紙にこのように書いている。「「我思う」のは嘘です、こう言わなければなりません。「人我を思う」と。──言葉遊びのようですが。「我」とは一個の他者なのです」[7]。「私が一個の他者である」とは、いい得て妙であろう。それは言葉が「私」を他者にするのだともいえる。ウィトゲンシュタインは「私」を「形而上学的な主体」と呼んで、経験的内容として対象化されることがありえない主体ないし自我として捉えている。だから「私」は世界のなかの対象なのではなく、世界の限界、境界として理解される[8]。独我論の批判についてはデカルト[9]やフッサール[10]なども言及している。
これとは別に、二〇世紀を代表する哲学者の一人ジル・ドゥルーズが「無人島の発生と原因」の中で展開する他者論を手掛かりにしてみよう。自我に先立つ世界、自我がない世界、ドゥルーズはそれを「無人島(ile déserte)」といういくぶん不思議な形象を通じて論じている。「無人島の発生と原因」は不思議なテクストである。その論述は「島が無人であるということは、哲学的には当然に思えるはずだ」[11]という極めて難解な、どうやら哲学的テーゼらしい何かを経て、無人島なる形象に、ドゥルーズ独自の視点で迫る。先に引用した文章は、「ひとつの島が無人島でなくなるためには、なるほど、単に人が住むだけでは足りない」[12]というさらに謎めいた逆説へと展開される。
無人とは、もちろん人がいないという意味である。逆に、人がいる状態とは、島という客体に人という主体が住まう状態を指す。ドゥルーズがいわんとしてるのは、無人状態の島に誰かが一人ぽつんと置かれたとしても、この非-無人状態(島という客体に人という主体が住まう状態)が直ちに発生するかどうかは疑わしい、ということである。無人状態を「哲学的」に考えれば、それは主体も客体もない世界のことであろう。では、この無人状態はいかにして崩壊するのか? そこに人が住まうだけでは、その状態は壊れない[13]。
ドゥルーズは別の論文(「ミシェル・トゥルニエと他者のいない世界」)で、あの『ロビンソン・クルーソー』を例として挙げながら、次のようにいう。「ロビンソンとは、他者のいない島にいる男である」[14]。われわれは他者のいる世界を生きている。では、他者のいない世界とは、どんなものか? 非-無人状態にいる限り、他者によってもたらされる何らかの効果の中に(われわれは)いるはずである。われわれの生きる非-無人状態から無人状態を考察することは本末を転倒させることである。では、他者がもたらす効果とは何か。
それは「私」が知覚する対象や「私」の考える観念にそって「周辺的な世界」を組織することである。「私」が一度に見ることができる範囲は限られている。通りに立って建物を見れば、建物の正面しか見ることはできない。しかし普段われわれは、正面の壁の奥には建物が続いていて、部屋や廊下などがあると思っている。なぜそのように思い、信じ、想定することができるのかといえば、「対象の中で私が見ていない部分を、私は同時に、他者には見えるものとして考えるからである」[15]。
他者というものを想定すればこそ、見えない「余白」の部分を他者には見える部分として処理し、それが恒常的に存在していると考えることができる。これは空間の成立要件であるが、それだけではない。「私」には死角があり、ある対象の表と裏を同時に見ることはできない。そして、裏側を見るためには、裏側に移動する時間が必要である。他者によってもたらされる「周辺的な世界」の組織化は、そのような推移の時間を必要とする。
以上により、他者とは何かを定義することができる。他者とは、それなしでは知覚が機能しえなくなる「知覚領域の構造(structure du champ perceptif)」[16]である。すでにわれわれは非-無人状態にあるのだから、独我論、ひいてはデカルト的主体を第一原理として固定化する企ては、これを免れることができない。
実存主義と主体性の真理
この「主観」をめぐる議論の中に、キルケゴールを差し込んでみよう。実存主義の先駆として評される、デンマークの哲学者セーレン・キルケゴールは当時大きな影響力とともに受容されていたヘーゲルの形式的な思弁に抗して事実存在としての人間を重視した。ヘーゲルは、体系を哲学の原理として置き、さらに諸学、世界史までもがすべて包括されるような壮大な哲学の体系を築いた。ヘーゲルは『エンチクロペディー』の序論でいう。「哲学はその本質からして体系をなすが、というのも、具体的な真理は内部で自己展開しつつ統一を保持し維持する全体的な世界であって、真理がさまざまに分岐し、部分部分が明確に位置づけられることによって、部分の必然性と全体の自由が保障されるからである。体系を欠いた哲学はおよそ学問的なものではありえない」[17]。ヘーゲルは弁証法によって、矛盾した命題を超克することで最終的にすべての存在や現象、歴史などが弁証法運動を繰り返した先にある最終的な存在を絶対精神と呼んだ。その過程で、あらゆる存在は克服されるものとヘーゲルは考えた。
一方でキルケゴールは、人間の生きる世界の全体を普遍的な理性によって完全に捉えきることができるという、ヘーゲルの円満的な合理主義とでもいうべきものに、激しく反発した。キルケゴールのいくつかの代表作の題名を見るだけでも、ヘーゲルへの反発ないしヘーゲルとの思想的資質の違いは歴然である。いわく、「あれかこれか」「反復」「不安の概念」「死に至る病」などなど。「あれかこれか」、ヘーゲルなら「あれもこれも」であろう。そうして対立するものが対立しつつ一つの和解へともたらされることに、キルケゴールは反対した。対立する一方を否定し、一方のみを選び取るという偏頗な選択こそ、神ならぬ人間の、おのれの分に誠実なふるまいだとキルケゴールは考えた。「不安の概念」、不安が人間の心にわだかまることをヘーゲルとて否定はしない。しかしこれらは人間の意識全体から見れば、感情という低次の次元に位置付けられるものであって、後になって克服されて精神的な成長を遂げていく。キルケゴールは意識のこうした位階性に異を唱え、感情のうちにこそ崇高な宗教性が宿ると考え、そこに人間心理の真実を伺おうとする。「反復」、ヘーゲル哲学で精神の本質が「発展」であるとされていることを横目でにらむような命名だ[18]。
ヘーゲルの哲学は普遍的形式的抽象的な思考であった。それに対してキルケゴールは個人的現実的具体的な思考を対象としている。キルケゴールは一八三五年の手記に次のように書く。「……私に欠けているのは、私は何をなすべきか、というについて私自身に決心がつかないでいることなのだ。それは私が何を認識すべきかということではない。……私の使命を理解することが問題なのだ。神はほんとに私が何をなすべきことを欲したもうたかを知ることが重要なのだ。私にとって真理であるような真理を発見し、私がこれのために生き、そして死にたいと思うようなイデー(理念)を発見することが必要なのだ。いわゆる客観的真理などをさがし出てみたところで、それが私に何の役に立つだろう。〔…〕……真理というものが、私がそれを認めようが認めまいがおかまいなく、信頼して身をゆだねさせるよりもむしろ恐怖の戦慄を呼び起こしながら、冷たくそして裸で私の前に立っているとしたら、そのような真理が私に何の役に立つだろう。もちろん私は、認識の命令を承認すべきことを、この命令のゆえに人々のうえに働きかけることができるのだということを、否定しようとは思わない。しかしそれにはその命令がいきいきと私のなかに取り入れられなくてはならぬ。私がいま最も重要なことだと考えるのは、それなのだ」[19]。このような意味で主観的情熱の対象となるものが主観的あるいは主体的な真理と呼ばれるものであり、これをキルケゴールは「主体性が真理である」という逆説的なことばで簡潔にあらわした。人生の究極の真理は、客観的に、外部からひややかに、傍観しているだけでは到達できるものではない。実存とは、人間を理性や科学でとらえられない独自な存在として認めるものである。
キルケゴールにしたがえば、実存はこれを思考の対象とすることができない。もしわれわれが実存を思考の対象にするならば、実存は対象化されることで抽象的・普遍的な概念になる。思考するということは、現実から存在を奪い、現実性をたんなる抽象的可能性の領域に押しやることである。実存とは、思考されることのないあるものである。実存は、事物を客観化し対象化してとらえる個別科学の対象とはもちろんならないし、またそのような科学的認識を模範とする科学的な哲学によって自覚されることもない。私はたとえば、自分の存在を動物ももつような有機的生命として、あるいは科学的な一般的真理を学んだり探求したりする意識一般として、あるいは全体的な真理に至ろうとする精神として、対象化することができる。だがしかし、自己の存在はそのように対照的に把握されたどの存在とも同じではないし、それらをすべて寄せ集めたものでもない。自らをそのような存在として把握する私の存在は、生命でも意識一般でもない。いいかえれば、対象化によってとらえられた諸存在はいずれも私の存在の究極の根拠ではありえない[20]。
キルケゴールは『死にいたる病』の冒頭で、人間存在を端的に次のように規定している。「人間は精神である。精神とは何であるか? 精神とは自己である。自己とは何であるか? 自己とは、ひとつの関係、その関係それ自身に関係する関係である。あるいは、その関係において、その関係がそれ自身に関係するということ、そのことである。自己とは関係そのものではなくして、関係がそれ自身に関係するということなのである」[60]。自己がたえず自己自身に関係すること、いいかえれば自己が無限に自己自身にかかわること、それが、キルケゴールによれば実存の本来的なありかたである。この自己へのかかわりを忘れた自己は、失われた自己であり、精神の喪失である。
ところで、かかる自己は、自分で自分を置いたのであるか、それとも他者によっておかれたのであるか、そのいずれかでなければならない。だが、自分で自分を置いたという人がひとりでもあるだろうか? この私の存在は、私が自分の力でそこに置いたものではない。私がこの時この所にこのようにして生まれあわせたのは、私の意志ではない。「自然がこの私を生んだ、自然が私をこうあらせた」とは唯物論者や決定論者の口癖である。しかし、現代の実存主義は、何ものをもってしても私の実存を理由づけたり根拠づけたりすることができないという意味で、それを偶然だと考える。人間存在が、そのひとりひとりが、ここにこうして投げ出されているわけであるが、それをしいて理由づけようとすると、神とか自然とかいう他者をもちださなければならなくなる。いうまでもないが、キルケゴールにとっては、この自己を、かかる自己に対する関係として、ここに置いたのが神である。したがって自己は自己自身に関係することによって、同時に、この自己を置いた他者すなわち神に関係する。神が人間を、精神として、自己として、ここに置いたということ、いいかえれば人間を自己自身に対する関係たらしめたということは、神が人間をいわば神の手から解放したことである。人間が自己自身になるかならないか、自己を得るか失うかは、人間の責任にゆだねられており、そこに人間にとって無限の可能性と自由がある[21]。
第四章 観念論的相対性精神学
何を相対性精神学として認めるか
「何を相対性精神学として認めるか」という問いに戻ろう。ラ・メトリ、スピノザ、リベットなどの論拠から、自由意志を肯定することははなはだ困難である。相対性精神学も、あえて流れに逆らうような真似はしない。では何が主観であるのか。デカルト的主体はたんに自我としてではなく、観念や基体の意味の変遷の流れも含めて、大きく主観として認めることはできるだろう。ソシュールやカントのような超越論的領野による主観性の研究は特筆に値する。一方で独我論は、一見真実らしいように見えて、ウィトゲンシュタインやドゥルーズに鑑みれば、(意見の相違はあれど)ナンセンスである。しかしドゥルーズが『アベセデール』の中でウィトゲンシュタインを「哲学の大惨事」「哲学全体の後退」「大いなる貧しさの導入」と頭ごなしにけなしているのは興味深い[1]。
相対性精神学の今日的状況について言及しておく。相対性精神学における主観性の議論は紛糾を極めているが、これらをいくつかの学術的派閥として指摘することができる。ベーコンにゆかりのあるサロモン学院にはカント派がある。ベーコンによる『相対性精神学序論』は斯界でもとりわけ野心的試みとして注目されており、またユクスキュルやネーゲルの影響も見られる。また他ではチャレンジャーが層序学的内在平面[2]を、モリアーティは位相幾何学に着想を得た相対性精神学を構想しており、ラカン派精神分析の位相構造を引き継いでいる。ドイツにおいてはシュテッカーリング派が現存在分析との接続を図っている。ノーレッジにはシュテッカーリング文庫がある。またニーチェ批判を主眼にすえた見解もあり、これについてはカール・レーフラーによる「今日の神学にとってのニーチェ」が詳しい。ディア学派は神秘主義であり、歴史徴候学や超心理学、心理歴史学についての研究は目を見張るものがある。これについてのドミニク・ホールによる一連の著作は相対性精神学の理解の助けになるだろう。ミスカトニック大学においてはピーズリー[3]によってポスト資本主義における新しい欲望のモデルが提唱されており、とりわけ速度学、ミクロ政治学、批判地理学についての研究がさかんである。また、マクドナルド大学ではソーカルの見解(「境界を侵犯すること:量子重力の変換解釈学に向けて」[4])を支持して相対性精神学を変換解釈学の観点から研究する試みも見られる。また、他にはガダマーやリクールの解釈学をヘルメスと結びつけた解釈学的相対性精神学の動きも認められる。京都では冬月氏の形而上生物学、および岡崎氏の比較物理学によって主観性に迫る新たな試みがある。ここヴィクトル・コンドリアでもレスキネン教授が精神生理学と量子力学の架け橋として相対性精神学を研究しており、研究所内でもとりわけアトラクタフィールド理論における観測問題を議論する上で、相対性精神学による新たな主観の定義が注目されているようだ。
しかし私が始める相対性精神学は、これらのどれとも異なるものである。また「相対性精神学とは何か」という論文で提示された考察も、向かうべきところからして別である。さらにいえば、これら心身二元論、唯物論、心身並行論のいずれもある一つの重大な問題を抱えている。それは二重存在である。ベルクソンによる燐光の比喩を紹介しよう。「唯物論者も二元論者も、根本のところでは、これに関して同じ意見である。彼らは脳物質の一定の分子運動を、それだけ別個のものとして考察する。その上で、ある者はわれわれの意識的知覚を、それらの運動を追いかけて痕跡を照らす燐光だとみなす」[5]。ある講義[6]でのベルクソンの説明からすると、イメージされているのはマッチの点火である。昔のマッチだと、それ自体の尖端に発火用の燐がついている。暗がりで点火しようとこのマッチを壁にあててさっと動かすと、燐光がその運動の軌跡を示す。燐が光って、マッチの運動と同じような線が壁に描かれる。人間の意識とはちょうどその燐光のごときものである、そう唯物論はいうだろう。しかしこれは比喩である。ある一つのものが、片方では脳髄の原子の運動に翻訳されて表現され、同じものが片方では意識の言葉となって表現される。元が物質のほうにあるとして、では物質を調べれば人間の精神もわかる、精神のほうは随伴している現象に過ぎないと唯物論はいっている。しかしどうして、自然界に違う二つのものが場所を占めているのか。自然がそのような無駄な贅沢を許すだろうか。二つが違う役割を持つのなら、自然はそれを許すだろう[7]。
モリニュー問題
ここまで話したのは、彼らの学問である。私たちの相対性精神学を、ここから始めよう。私が提唱するのは、「経験」の学である。経験を事実としてありのままに受け取ることを目指す学である。これを経験論的相対性精神学と呼ぶことができよう。
経験論的相対性精神学の始まりとして認めることができる思想家に、アイルランドの哲学者ジョージ・バークリーの名を挙げることができる。カリフォルニア大学バークレー校は彼の名に由来する。バークリーが提唱したのは、「存在するとは知覚されることである」という観念論である。私が持っているリンゴは存在する。私はそう思っている。だが、そのリンゴは、私が見たり触れたりするのとはかかわりなく、存在しているといえるだろうか。バークリーは、物の、それ自体としての存在を否定し、私たちに知覚される限りにおいてのみ存在すると説く。
バークリーは『アルシフロン』[8]の中で次のように主張する。丘の上に城が見えるとしよう。それは相当離れたところにあることがわかる。向こうの丘の上の城は、はるか遠くの距離にある。しかしその距離というのは、その城からそれを見ている目にまで至る直線であって、見ている人にとっては一つの点でしかない。これは横から第三者として見れば、城と目のあいだは、かなり長い直線として捉えられるだろう。しかし見ている本人にとっては、その直線は、点でしかありえない。であるから、距離は目によって直接知覚されるものではない。
けれども、われわれは見ただけで遠い近いがわかる。その遠い近いは、何か別のものを介して知覚されなければならない。それは、小さく見えたり、かすんで見えたりするということであり、われわれは、これを幼少期からの経験によって、遠くにあるものが小さく見えたりかすんで見えたりすることを知っている。遠くにあることと、小さく見えたりかすんで見えたりすることの間には、類似性も必然的結合も存在しないが、経験によって両者が結びつくことによって、見かけが記号となり、それを介して距離を知覚するのである。
議論はまだ続くが、ここで言及しておくべきことがある。政治哲学者としても有名なイギリス経験論の父ジョン・ロックの主著『人間知性論』に登場する「モリニュー問題」である。ウィリアム・モリニューは優れた科学者で、ロックの友人であった。モリニューは『人間知性論』、中でも「知覚」に関わる章に注目している。ロックは、視覚は網膜の在り方からしても二次元的情報を与えるものであるという暗黙の了解をもとに、見ただけで三次元的な奥行きのある物体が知覚されるのはどうしてかを説明しようとする。まずは該当箇所のロックの叙述をここに引用する。「感覚によって受け取る観念は、成人ではしばしば判断によって変更されるが、われわれはこれに気づかない。ある一様な色の、例えば金とか雪花石膏とか黒玉とかの丸い球がわれわれの目の前に置かれるとき、それによってわれわれの心に刻印される観念が、われわれの目の前に置かれるとき、それによってわれわれの心に刻印される観念が、われわれの目の前にやってくるさまざまな度合いの明るさと輝きで多様に陰影づけられた平らな円の観念であることは確かである。しかし、われわれは、凸面体がどのような種類の見かけをわれわれに示しがちであるか、物体の可感的な形が異なれば光の反射がどのように違ってくるかをつねづね知覚し慣れているので、判断はすぐ習慣によってその見かけをそれらの原因へと変更し、本当は多様な陰影や色であるものから形を推測して、その多様な陰影や色を形の印として通用させ、凸面形と一様な色の知覚を形成する。ところが、それからわれわれが受け取る観念は、絵の場合に明らかなように、多様に彩られた平面にすぎないのである」[9]。
また、次の節では次のように述べる。「しかし、私の考えでは、これはわれわれの観念のどれにおいてもよくあることではなく、視覚によって受け取られる観念に限られている。なぜなら、視覚はわれわれのすべての感覚のうち最も包括的で、その感覚にのみ特有な光と色の観念をわれわれの心にもたらすが、また空間、形、運動という非常に異なる観念をもたらす。そして、空間、形、運動のさまざまな在り方は、その固有の対象である光と色の見かけを変化させるので、われわれは習性により、後者によって前者を判断するようになる。このことは、多くの場合、われわれが頻繁に経験するものにおいては、固定した習慣によって恒常的かつ迅速に行われるので、われわれは自分たちの判断によって形成される観念を自分たちの感覚の知覚とみなし、一方すなわち感覚のそれはただ他方を喚起するのに役立つだけで、それ自身はほとんど気付かれないのである」[10]。
これにモリニューは次のような見解を加える。「ある人が生まれつき目が見えず、今大人になって、同じ金属でできた、ほとんど同じ大きさの立方体と球を区別することを触ることによって学び、立方体と球に触ってどちらが立方体でどちらが球かわかるとせよ。そこで、テーブルの上に立方体と球が置かれているとするとし、その目の見えない人が、目が見えるようになったとせよ。その人は、それらに触る前に、見ただけでどちらが球でどちらが立方体かを言えるか」。これに対してロックは次のように答えるだろう。「それは言えない。というのも、その人は、球と立方体がその人の触角をどのように刺激するかについての経験は持っているが、自分の触角にかくかくの刺激を与えるものが自分の視覚にしかじかの刺激を与えなければならないという経験、つまり自分の手を不均等に圧迫した立方体のとがった角が、自分の目にはこのように見えるという経験を、まだ持っていないからである」[11]。
なるほど触覚で立方体と球が区別できても、触覚的にこう感じられるものが視覚にどう現れるかは実際に経験しなければわからないということ、視覚はそれだけでは、触覚的にわかる立方体と球の違いを私たちに知らせるものではないということが、問題に対処する際の前提となっている。ロックもまた、モリニューのこの否定的回答に同意する。先ほどの引用箇所にあるように、ロックはもともと、球は目には二次元的に、「平らな円」に見えているはずだが、そうした視覚的情報とそれらに触って得られる触覚的情報とが経験によって結びつき、「多様な陰影や色」を見ただけで奥行きのある球とみるようになると考えていた。であるから、目の見えなかった人が目が見えるようになったとき、見ただけでその立体感や触覚的区別がわかるはずがないと考えるのは、当然のことであった。
この見解が単なる憶測ではないことは、人類学の事例からも明らかである。人類学者コリン・ターンブルは、イトゥリの森でムブティ・ピグミーを調査していた際、次のように報告している。あるとき若手のピグミーを熱帯雨林からエドワード湖に連れ出したのだが、開けた空間を目の当たりにしたピグミーは遠くに見える水牛の群れを指さして「あの虫はなんていうんだ?」と尋ねたという。ターンブルはその後いくつかの質問を行ったが、熱帯雨林では遠くを見渡すことができないために、ピグミーは水牛が遠くにいるために小さく見えている、ということを理解していないことがわかった。
バークリーは『アルシフロン』のなかでこの問題を次のように取り上げる。経験以前には、人は自分が見ているものが自分から離れたところにあるとはまったく思わない。距離と必然的に結合しているのでもそれと似ているのでない見かけの小ささやかすみなどの観念ないし感覚が、さまざまな度合いの距離ないし距離そのものを、表示するものと表示されるものの結合を経験したことのない心に示唆することはできない。それは、言語を習得する前に言葉が考えを示唆することができないのと同じである。そこから、生まれつき目が見えず、のちに目が見えるようになった人は、はじめて見えるようになったとき、見えるものが自分から離れたところにあるとは思わず、自分の目の中に、あるいはむしろ自分の心の中にあると思うことが帰結する。バークリーはモリニュー問題に言及することによって、視覚はそもそも見えるものを自分から離れたところにあるようには見ず、自分の目の中に、あるいはむしろ自分の心の中にあるように見えるものである、と結論づける。
さらに、デカルトが屈折光学についての試論の中で言及した、対象の両眼視による距離の知覚についても話しておこう。両眼が対象に向かう角度の違いから、数学的に対象との距離が計算されるとするものである。

『アルシフロン』の中での、バークリーに対する物質肯定論者の見解を示す。「光学の研究者たちは、二つの光軸が作る角度のことを僕たちに語っている。そこでは、それらの光軸が、目に見える点ないし対象のところで交差する。その角度は、広ければ広いほど対象が近いことを示し、狭ければ狭いほど遠いことを示す」[12]。バークリーはこの考えに懐疑的である。心は物の距離を幾何学によって見て取ることを意味するが、だからといって、幾何学を学び、直線や角度について多少とも心得のある人だけがわかるというわけではない。これには当然、学ばなくとも身についている自然の幾何学が存在すると人はいうだろう。しかし、人が言葉でもっていおうとしていることを理解するには、まず言葉そのものを知覚しなければならない。であれば、角度が広いことから距離が近いことを、角度が小さいことから距離が遠いことを推論する者は、まず角度そのものを知覚しなければならないことになる。これらの角度を知覚せずに距離を推論する者はいないのであるから、人は角度によって距離を判断するのではないということになる。以上のことから、観念は物質的な根拠を持つものではなく、心から始まるのだというバークリー哲学の相貌が明らかになった。
バークリーの観念論
先に私は、バークリーがデカルトの「二重存在」を指摘した、といった。これは心の外に物が存在するが、それだけでなく、物の在り方に対応する心の中の観念も認めるというものであった。バークリーはこれを認めず、観念だけが存在していると考えた。観念だけが存在しているという立場を「観念論(idealism)」と呼ぶ。一方でこれは心の外にあるとされる物の存在を否定するために、バークリーはこれを「物質否定論(immaterialism)」と自ら呼ぶ。一方で、二重存在の考え方は、自然科学ではごく当たり前のことである。例えばわれわれは、電気コードの中を電流が流れているのを知っている。見えている電気コード、その被覆のビニールを取ってみても、銅線が見えるだけで、電気の流れそのものを直接見ることはできない。しかし、中ではそうした電子の移動という現象が起こっており、それがテレスクリーンや電子端末を作動させているという事実を知っている。こうした思考は二重存在の典型例である。「物自体」は心の外にあり、私たちの知覚の直接的対象とはならない。知覚の直接的対象となるのは「観念」である。物自体と観念の二重存在は、バークリーにすれば、われわれを世界から隔てるものであり、物の本当の姿を見えなくするものである[13]。先に紹介したロックは、観念から独立して存在する物自体を認めていた。ではわれわれは物のどこまでを知り得るのか。
ロックによる一次性質(primary qualities)と二次性質(secondary qualities)の区別がある。それはわれわれが知覚するさまざまな性質のうち、形や大きさなどを一次性質と呼び、色や味、熱さ・冷たさなどを二次性質であると説明するものである。ロックは、知覚される性質を区別しようとしたわけではない。ロックによれば、一次性質は物自体が本来持っている性質であり、二次性質は物自体が一次性質に基づいて持っているある種の能力のことである。そのある種の能力は、われわれの感覚器官に作用して、われわれに物が本来持っていない色や味などを知覚させる能力である。であるから、ロックの区別では、物が持つ性質と、それによって心の中に引き起こされる感覚ないし観念の区別が前提されているのだ。バークリーはこの区別を疑問視する[14]。
彼が「相対性からの議論」と呼ぶものから話を始めよう。形が見る角度によって違って見えるのは当然であるし、大きさにしても、われわれにとって小さいのも、小さい動物には大きく見えるはずである。よって、バークリーは一次性質の場合も結局は二次性質の場合と同様に、知覚されている性質は物の性質ではなく、それらもまた心の中の観念でしかないと考える。この議論に加えて、バークリーは、視覚的に感覚される形には必ずなんらかの色がついており、想像力を働かせて形を想像する場合でも、その形にはやはりなんらかの色がついていることに注意を向ける。色のない形は感覚することも想像することもできず、形は必ず色を伴うとすると、色が先ほどのように心の中にしかないとすれば、それと不可分な形もまた心の中にのみ存するといわざるを得ない。二次性質が心の中にあるのならば、一次性質も心の中にあると考えざるを得ない。よって性質のすべては、心の中にあることが帰結される[15]。
ここからどのようにして物質否定論へと行きつくのか。その道筋をたどってみよう。バークリーが取り上げるのは、われわれが知覚する観念と似た物質が存在するというタイプの物質肯定論である。われわれが感覚的に知覚し、日常「物」とみなしているものを、バークリーは「可感的な物」と呼ぶ。周知のように、「可感的な物」はそれ自身も観念であることになる。われわれが知覚している日常的な「物」が「可感的な物」であり観念からなるということは、先に見た論理からも明らかである[16]。そうした可感的な物が心の中の観念であるとしても、それとは別にそれに似たものが心の外に物質として存在すると考える、そのような物質肯定論である。これは一般的な世間で受け止められる素朴な姿勢であるために、素朴実在論と呼ぶこともできよう。
これに対してバークリーが用いるのは、研究者たちが「似たもの原理」と呼ぶ考え方である。『人知原理論』第一部第八節から引用する。「観念に似ることができるのは観念でしかない。色や形に似ることができるのは別の色や形でしかない。自分の思考をほんのわずかでも調べれば、観念どうしを除いては似たものを考えることができないということがわかるであろう」[17]。観念に似た物質なるものを考えてみるとする。例えば、見ているリンゴは観念であるが、これに似たものがこの世界に物質として実在している。もしこの観念としてのリンゴに似た物質が考えられるとすると、それは、リンゴに似た、何か想像されたものでしかない。しかし「観念」という言葉の使い方からすれば、想像されたものは観念である。よって、観念に似た物質が存在するという考えは成り立たない。以上のように、物自体は知覚されずとも存在すると考える、ロックの見解を含めた物質肯定論に対して、バークリーは「存在するとは知覚されることである(Their esse is percipi)」、というテーゼを導き出す。
一方でバークリーの発想は量子力学の先駆けとも称される。量子力学においては、不確定性原理と波動関数の収縮がそうである。電子の位置を測定したとしよう。位置を測定すると位置の不確定性は小さくなる。例えば、電子の二重スリット実験でどちらのスリットを通ったかを確認すると干渉パターンは消えるが、測定の結果として電子の位置が片方のスリットに限定されたためである。すると、不確定性関係のために電子の運動量は測定前よりも不確定になる。「位置の測定」という行為そのものが運動量の情報を変えてしまうのである。これは逆も同様で、運動量の測定を行うと位置が不確定になる。そのため、電子の位置と運動量を両方測定したとき、位置を測定してから運動量を測定した結果と、運動量を測定してから位置を測定した結果はどうしても違ってしまう[18]。そのような量子は、古典物理学の粒子のように「確定した位置や速度を持つ状態」ではなく、「位置も速度も不確定な状態」にあると考えざるを得ない[19]。
一九二七年にこの不確定性原理を提唱したのは、ハイゼンベルクであった。彼は、いくつかの思考実験によって、粒子の位置と運動量のうちのどちらか一方を定めようとすれば、どうしても他方が不確定になることを示した。つまり、微視的粒子の軌道を完全に求めることは実験的にも不可能なのである。波動関数ならびに光の量子論は、このような測定精度の限界と矛盾しないように図られており、決して理論として不完全ではないことがわかる。このことは、同年に国際会議で、ボーアが波束を用いて具体的に説明し、粒子・波動の二重性を統合解消するものとして歓迎された。また、不確定性原理は、波動力学においてだけでなく、行列力学においても、行列で表される物理量の非可換性($${ab≠ba}$$)と関連させられることが示された[20]。
波動関数$${ψ}$$で表される量子状態に対して、物理量$${\hat{A}}$$の測定を行ったとする。ボルンの規則によれば、$${\hat{A}}$$の固有値のいずれかが測定値として得られる。測定値が$${a_i}$$だったとすると、測定後の(測定結果を条件とした)量子状態は固有値$${a_i}$$に対応する固有状態となり、 測定後の量子状態を表す波動関数は測定前の$${ψ}$$と大きく異なることがある。 これを「波動関数の収縮」ということがある。
ということは、量子の状態には確定した物理量の情報がそもそも含まれておらず、古典物理学のように一回の測定で得られる値を完璧に予言することは原理的に不可能ということになる。ラプラスの悪魔はシュレーディンガーの化猫に食い殺されたのだ。
ヒュームと主体の発生
デイヴィッド・ヒュームは、イギリス経験論の論客の一人であり、その後の経験論、懐疑論、自然主義哲学に大きな影響を及ぼした哲学者である。彼はアダム・スミスやジャン・ジャック・ルソーとの交友関係でも知られる。ヒュームは、経験論と呼ばれる哲学を説いた。経験論とは、その名のとおり、人間の知性や認識の基礎を経験に求める哲学である。
ヒュームの仕事で有名なのは因果性批判であろう。たとえば机の上に静止したボールAがあり、そこにもう一つのボールBがぶつかって、初めのボールAが動き始めたとしよう。そのときだれでも「ボールBがボールAにぶつかった。だからボールAは動き始めた」といいたくなる。けれども、「ボールBがボールAにぶつかった」こと、その後で「ボールAが動き始めた」ことは感覚的に知覚しうるけれども、「だから」を知覚することはできない。ヒュームによれば、因果性とは、ある事象の後に特定の事象がしばしば続き(「恒常的連結」の概念)、それがくりかえし知覚されることによって生じる思考の習慣にすぎない。ヒュームは因果法則の客観性を否定することによって、因果法則によって成りたつ物理学など自然科学を根こそぎ否定したことになる[21]。
これを説明するために、ヒュームが提唱した観念の連合説を紹介しよう。ヒュームはニュートン的な引力を念頭に置いている。物体と物体がいかにして、また、なぜ互いに引き合うかを、われわれはまったく知らない。にもかかわらず、われわれは、物体と物体が引き合うことを、それらが何らかの法則に即して引き合っていることを知っている。精神の秩序においても、物体の秩序と同様である。現にそうなっているように、観念と観念が互いに喚起しあい、集合を形成するその原因については、われわれは何も知らない。観念と観念は互いに喚起しあって集合を形成しており、そうなる際の根本的法則を、われわれは見抜いている。ここにいう法則が観念連合の法則なのである。
まずヒュームは、類似(resemblance)による観念の連合を指摘している。何等かの事物や何らかの状態をわれわれが知覚する場合、これらの事物や状態と、以前にわれわれが知覚した他の事物や状態とのあいだに類似があるなら、われわれの現在の知覚に際して、多くの場合、以前に知覚された事物や状態の観念がわれわれの意識に喚起される[22]。
経験論が標的にしたのは、大陸系の合理論哲学だった。合理論哲学では、たとえばコギトのような、経験から逸脱した原理が哲学の基礎に据えられている。ここにいう理性とは生得的である。どんな人間的個人も理性を有しており、真実と虚偽を区別するために必要な同じ良識を有している。人間を人間たらしめたのは神の贈り物なのだ。この点に関して個人と個人を区別する唯一の相違は、彼らがその省察のなかで援用する方法に由来する。こうした教説が、経験論によって反駁される。
「知性のうちには諸感覚器官のなかにまず存在しなかったものは何もない」とジョン・ロックはいった。デカルト的生得性は、容認しえない虚構である。理性は経験の産物以外のものではない。精神はまずもって「何も書かれない板(tabula rasa)」である。成熟したときに精神が己のうちに見出すもの、それを精神のうちで発達させるのは、精神に対する世界の働きかけである。
他方デカルトは、どんな事物をも説明しようとして、三種類の実体を認めていた。第一は、非物質的で無限な神的実体で、神的実体は完璧な知性と全面的に自由な意志を備え、どんな事物をも創造することができる。第二は物質的実体で、これは幾何学的諸特性を備えた唯一の延長へと還元される(説明される)。延長が、運動法則に従属した諸物体の本質なのである。最後は非物質的な実体。この種の実体は、互いに分離された人間たちの魂の謂いで、有限で限界づけられているが、その各々が一にして自己同一的な自我を形成している。死後も存続し、不死性を所有した自我を。ところで、デカルトが認めたこれら三種類の実体のうち、若干の哲学者にとっては、その実在がまったくもって疑わしいものと映った実体が一つある。バークリーにとっては、何らかの物質的実体が存在するというのは虚偽だった。諸物体の存在は、それについてわれわれが有する知覚以外のものではない。物体に関しては「存在するとは知覚されることである」が真実なのだ。したがって、物質から知覚を誕生させようとする唯物論ほど誤ったものはない。非物質主義が真理なのである。しかし、バークリーはそれ以上先に進むことはなかった。バークリーは、精神的実体である魂の実在は承認していたのである。精神的実体に関しては、それらの実在は、精神的実体が有する知覚のうちに存しているという点を承認しなければならない[23]。
「タブラ・ラサ」は、現代において生得論の観点から否定されている。ノーム・チョムスキーは、その代表である。人間は普遍的な言語機能を備えており、全ての言語が普遍的な文法で説明できるとし、チョムスキーはこれを普遍文法と呼んだ。近代ではカントが、カテゴリーを認識のア・プリオリな形式として、生得的な要素として提案している。しかし現代の生得論は、西洋近代における理性の復権を促すものではない、ということに注意しなければならない。人間の奥底に、認識における共通の形式を見出したところで、それがわれわれを真理へと至らしめる存在だとはいい難い。もはや西洋知が意味を失って久しい現代に、そのような真理はないからだ。
ヒュームにおいても、「諸感覚器官のなかにまず存在しなかったものは知性のなかに何もない」ということを確信しており、その点で、彼はロックの教説に従っている。バークリーについてもまた、物質的実体が哲学的亡霊であることをヒュームは確信していた。原子もしくは、延長や抵抗力や重量などを有した粒子のことが依然として語られる場合にも、それは依然としてわれわれの表象の集合であって、それをわれわれは、自分たちの精神とは独立した実在として思い描いているにすぎない[24]。
ヒュームは知覚に関する二つの事象を区別している。印象(impressions)と観念(ideas)である。ヒュームの定義する印象は、精神に単純な諸観念を供給するのだが、これら単純な観念のおかげで部分的に自動的に、部分的に意志の支配のもとで、複合的諸観念が精神のうちに構築される。
こうした印象に関して、ヒュームは二つの種類を区別している。そのうち第一の種類に属するのは、感覚的起源をもつ印象である。どんな教育にも先立って、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚など諸感覚器官の機能を契機として与えられる印象の意だが、そのような印象としては、われわれの感覚が刺激されるや否や、われわれが感得する色や音や臭いや温度の感覚がある。第二の種類に属するのは、ヒュームが「反省的」と名づけた印象である。快、不快といった情緒や感情や情念をわれわれに明かしてくれる印象がそれである。要するに、この種の印象は、自分がなさねばならないことがらに関して、われわれのうちに生まれる主観的反応なのである。魂のうちに感覚を生み出す原因も、そこに情緒を生み出す原因も、われわれは知らない。しかるに、われわれは感覚や情緒を感じる。それが、感覚や情緒についてわれわれがいいうるすべてのことである[25]。
観念についてだが、観念はそもそも、われわれが感じ取った感覚の差異性ないし複製にすぎない。複合的な観念は、単純な観念が相互に併置されたり連合されたりして構築される。しかし、これらの単純な観念は構築物ではない。それらは要素であって、そのおかげで、構築物が建設されるのである。
単純な観念を一次的な印象と比較するとき、ヒュームによれば、われわれはある肝要な確認へと導かれる。観念はその強度によってのみ印象と相違する、との確認へと。印象とは極めて顕著な何かである。加えて、記憶によってもたらされる観念と、想像力によってもたらされる観念とを区別しなければならない。前者は「受容された印象」のごとき再生物であるが、後者はまさに印象の変形である[26]。
印象と観念の関係は、次のように説明することができる、すなわち、印象とは純粋に与えられた経験であり、観念に対して一次的である。一方で観念は印象にあるものを材料にして構成される。しかるに、印象のうちにないものは観念のうちにない。それはちょうど印象がぐつぐつ煮えた「熱い」知覚であるのに対して、観念はそれを模写するが本来の活気を失った「冷えた」知覚である。「印象(強い知覚)はつねに観念(弱い知覚)に先行するということ、また想像に供給されているすべての観念はそれに対応した印象のなかにまず出現するということである」[27]。
カントからヒュームへ
ヒュームはロックやバークリーとともに経験論と呼ばれる哲学を説いた。経験論とは、その名のとおり、人間の知性や認識の基礎を経験に求める哲学である。経験論が標的にしたのは、デカルトに代表される大陸系の合理論であった。合理論哲学では、たとえばコギトのような、経験から乖離した原理が哲学の基礎に据えられている。経験論哲学は、そこを批判し、経験世界に立脚して哲学を構築することを主張する。一般に、経験論哲学は保守的な思想とみなされている。経験世界に立脚した哲学の構築が目指されているならば、現に存在しているこの経験世界を肯定する思想がその哲学の中に見出されても不思議ではない。これと対照するなら、合理論はラディカルな現実変革の思想になりうると考えられるかもしれない。経験に基づかない原理を基礎に据える哲学ならば、現に存在しているこの経験世界を否定しうると考えられるからである[28]。
私がここで問題にするのは、以上のような「保守的な方法論たる経験論」という硬直しきった偏見である。私はヒューム哲学の根幹にある問いを次のような言葉で説明したい。「ヒュームが取り組むことになる問いはこうなる──精神はどのようにして一つの人間的自然に生成するのか?」この問いは何を意味するのか。人間的自然とは生成の結果として現れるということ、したがって人間について考えるにあたり、それを前提にはできないということである。同じ問いを「精神はどのようにして一つの主体へと生成するのか」と表現しよう。「精神」とは単なる諸々の観念の集合を、「主体」はそれらの観念が観念連合によって体系化された状態を意味する。あらかじめ主体があって、それが様々な外界からの刺激を知覚するのではない。精神と呼ばれるものは単なるバラバラな諸観念の集合であって、諸観念を入れる容器ですらない。精神は精神の中の観念と同一であるといえるだろう。しかし、精神を構成するそれらバラバラな諸観念が一定の原理に従って連合されたとき、「恒常性と一様性」をもった体系が発生する。連合には「近接」、「類似」、「原因と結果」の三つの原理があると言われるが、これら三つの原理に基づいて行われる観念連合がある臨界点に達したとき、精神という所与の状態を超出した主体が発生する。
ここに見出されるのは、主体の存在を前提せず、それを構成されたものとして捉える視点、その発生を問う視点である。超出を変容といいかえることもできる。つまり諸変容の心理学は、一個の構成された主体の哲学となるだろう。このような哲学こそ、合理論が失った哲学に他ならない。合理論は主体を前提する。それに対し、経験論は主体そのものの発生を問う。主体を構成されたものとして捉える。この意味では、合理論こそが保守的である。それ以上には疑いを進めない地点を設定しているからである。人間的自然、すなわち人間本性についても同様である。精神は自然ではない。精神には自然は備わっていない。人間本性は観念連合の効果として発生する。いいかえれば、観念連合の仕方が変われば、人間本性は変化する。主体も自然も前提せず、ただその発生を問うこと。同じことを理性についても述べることができる。精神は理性ではない。理性は精神の一つの変容にすぎない。発生について問うことは、変化について問うことであり、変化の条件を問うことである。私がヒュームに見出しているのは、哲学がそれまで前提としていた諸観念の変化の可能性を問う哲学に他ならない。
ヒュームの経験論はしばしば、カントの超越論哲学を準備したものとして語られる。いかなる因果性をも疑いうるとし、主体も自然も理性も前提しないヒュームの哲学は、カントをして「私を独断論のまどろみから解放してくれた」といわしめた(カントは当初合理論者だった)。しかしカントはその上で、ヒュームの連合説を批判した。カントによれば、現象の中に主観によって看取しうる一定の法則性がそもそも存在していなければ、観念連合自体が生じえない。たとえばわれわれは「明日も太陽は昇るだろう」という。だが、明日はまだ訪れていない。われわれに与えられているのは、これまでずっと太陽が昇ってきた、という事実だけである。にもかかわらず、われわれはそうした所与の観念(「昨日も太陽は昇った」「一昨日も太陽は昇った」……)を超え出て、「明日」について肯定する。そこには、何らかの飛躍、ヒュームのいう「信念」がある。所与のものだけでは基礎づけっれないこの超出によってこそ、認識は基礎づけられている。つまり、我々は自分たちに与えられるより以上のことを語り、経験という所与を超え出てしまっている。
ここにカントは次のような批判を加える。その信念が発生するためには、経験がそれを裏付けてくれなければならない。太陽が日によって昇ったり昇らなかったりするなら、認識は発生しない。太陽が毎朝昇るという法則があればこそ、認識が発生するのである。カントは『純粋理性批判』第一版、「構想作用における再生の総合について」で、次のようにいう。「再生のこのような法則が前提としているのは、とはいえ現象自身が現実にこうした規則にしたがっていること、さらには現象の表象という多様なものにあって、なんらかの規則にに適合した随伴あるいは継起が生じていることなのである。そのようなことがないとすれば、私たちの経験的な構想力はじぶんの能力に応じたことがらをけっして成しとげることができず、したがって、死せる能力、私たち自身も知らない能力として、こころの内部に隠されたままでおわるであろうからである。辰砂が、赤いときもあれば黒いときもあり、軽いときもあれば重いときもあり、また人間がときによりこの動物、ときによってはあの動物の形態に変わったり、夏至でもときに土地が果物で敷きつめられ、ときにはまた氷と雪とに覆われることもある、としよう。そのようなばあい私の経験的な構想力には、赤い色の表象とともに重い辰砂を念頭に浮べる機会すら得られないことになるだろう」[29]。よってヒュームのように、主観による構成のみで認識を、ひいては因果性を基礎づけることはできない、そうカントは考えた。カントは主観と客観の一致という古い形而上学的な考えを退け、物自体の現れである現象が認識能力に従属する、という考え方を打ち出した。
しかし私は、経験論的批判が超越論的批判によって乗り越えられたとは考えない。カントは、ヒュームを批判し、それによって新たな問いを発見した。そして、それは確かに哲学史において決定的な一歩であった。だが、だとしても、カントには問いかけをやめてしまった問いがあった。それは何か? いうまでもなく、主体の生成へと向かう問いに他ならない。カントは生成あるいは発生の対象であるはずの主体を前提とする。カント的平面に取りつく「いかにして何らかのものが一個の主体に与えられるのか?」という問いは、この前提があって初めて成立する。
カントは「超越論的」と呼ばれる探求の領域を開いた(これは先験的とも訳される)。経験される対象についてではなく、経験そのものについて、その条件を問うことを意味する。経験の可能性の条件を問うことが超越論的探求である。しかし明らかにカントは、そのようにして、超越論的と呼ばれる諸構造を、心理学的な意識の経験的諸行為を引き写すことによって描いている[30]。超越論的領野は経験的領野を基礎づけるものである。だが、カントは超越論的領野をちょうどカーボン紙で複写するようにして引き写す。カントが描く超越論的領野は不純である。さらに、カントはデカルト的な自我を超越論的統覚として引き継いでいるが、これは「そうしたものがあるとしか考えられない」という仕方で想定あるいは前提されるものであり、カントはその発生を問わない。「真実は主観の中にある」とは、主観の起源への探求を無責任に放置するのではない。相対性精神学は主観の発生を問うものである。
第五章 純粋持続と純粋経験
ベルクソンの哲学
「生の哲学」を提唱しノーベル文学賞を受賞したフランスを代表する哲学者アンリ・ベルクソンは、一九一三年にロンドンの心霊学協会に呼ばれて行った講演の中で、以下のような体験を話している[1]。ある婦人が、フランスの名のある医者に向かって、次のように証言した。この前の戦争の時、夫が遠い戦場で戦死する。パリにいたその婦人は、ちょうどその時刻に夫が塹壕で倒れたところを夢に見る。それをとりまいている数人の兵士の顔まで見たのだという。後でよく調べてみると、まさにその時刻に、夫はその婦人が見た通りの格好で、側を数人の同僚の兵士がとりかこんで、死んだのだ。これは、婦人が頭の中に勝手に描き出したものと考えることは、不可能である。どんな多くの人の顔を描いた経験を持つ画家も、見たことのないたった一人の顔を想像理に描き出すことはできない。見知らぬ兵士の顔を夢で見た婦人は、この画家と同じである。夢に見たとは、たしかに念力という知られない力によって、直接に見たに違いない。そう仮定してみることには何の不合理もないのである。
ところが医者はその話を聞いて、こう答えたのだという。私はその話を信じる。婦人は立派な人格の持ち主で、嘘など決していわない人だと信じる。しかし、困ったことが一つある。昔から身内の者が死んだとき、死んだ知らせが来たということは数限りなく多い。けれども、その死の知らせが間違っていたという経験も非常に多い。無数の正しくない幻があるだろう。なぜ正しくない幻の方を放置して、たまたま偶然に当たった幻の方だけをどうして取り上げなければならないのか、と。ベルクソンは横でそれを聞いていた。そこにもう一人若い女性がいて、ベルクソンのもとへやってきてこういった。「お医者さまのいまの論理は間違っているように思われます。どこに間違いがあるのかはわかりません。でも、きっとどこかに間違いがあります」。ベルクソンもこの見解を支持した。
ベルクソンは講演の中で、次のように説明する。一流の学者ほど自分の方法を固く確信している。そして、知らずのうちにその方法の中に入って、その方法のとりこになっているものだ。だからこそ、具体的にさまざまな現象の具体性というものに目をつむってしまう。今の話でも、医者は夫人が見た夢の話を好きなように変えてしまう。その話は正しいか正しくないか、夫人が夢を見たとき、確かに夫は死んだのか、あるいは間違いで夫は生きていたかを問題にしてしまう。しかし婦人は問題を話したのではなく、自分の経験を話したのだ。「すなわち彼は(婦人の)具体的でありありとした(…)光景の記述を、「その婦人のまぼろしは真実であって偽りではなかった」という干からびた抽象的な言い方によって置き換えた」のだとベルクソンはいう。それは婦人にとってたった一つの経験的事実なのだ。医者はこれを退けようとする。しかし本当に切実な経験というものは、主観的でも客観的でもありえない。人間に原始的な経験は、科学的精神の経験科学とはいささかも似ていない。人間の経験が科学的経験に置き換わったのは、わずかここ三百年来のことである。自然科学は、人間の広大な経験をきわめて小さい狭い道の中に押し込めてしまう。科学とは、計量可能な経験のみを認める。さまざまな方法に伸ばすことのできる広大な経験の領域を、勘定することのできる、計量することのできる合理的経験のみに絞った[2]。いまや人間の精神の領域さえも、フェヒナーから現代にいたるまで、合理論的ファシズムの時代を迎えつつある。精神を計量的に把握する試みは、精神に特異な意義と位置を与えるようでいて、その実すべてを奪うことにほかならない。
ベルクソンの「実在」とそれを特徴づける「持続(durée)」の概念は、この議論に示唆を与えてくれる。ベルクソンの哲学とは、実在をありのままに記述する試みである。生成の場面に直接入り込むベルクソンの企ては、どこにも定点がないという事情を徹底する。例えばベルクソンは、立ち現れてくる対象に固定した輪郭を認めない。知覚される対象が特定の輪郭をもって現れるのは、知覚する生命体が世界を生きるための便宜のような事態である。ベルクソンの考える実在とは実体のことではない。流れである実在は、すべてが変化しつづけるものである。だからそこで、明確に固定されたかたちが認められることはない。実在はすべてが動きつつあるものである。だから実在はつねに変化しつづけ、その変化を包括する環境の変容を引き起こし続ける[3]。
先に紹介したカントの超越論哲学や現象学の祖、エトムント・フッサールは、「知覚世界を私にとって可能にするような私」という超越論的主観性を設定した。これは次のようなものである。主観の思念作用とその思念が向けられる志向性が超越していくような開かれた作用の場面。つまり主観の思念作用とその思念が向けられる対象との相関関係により規定される志向性の働きとは、自我への内在から世界を構成するような観念論的なものではない。思念がなければ思念の対象もありえないというのがフッサールによる現象学の見解である。しかし実在は流れとしてすべてが変化しつづけるものである。ならば、超越論的な地平は最初から設定されていない。むしろ、超越論性は「すべてが変化しつづける」流れをなし崩しにしてしまうような固着物として認められるだろう。超越論的領野のような定点に基づいた思索は、流れのなかに内在することはできない。現象学において純粋な現れとは、超越論的自我に現れるものである。これに対してベルクソンにおいて重要なことは、私もその一部であるような実在をそこに参入しながら見出すことである[4]。ヒューム読解による超越論批判の観点がベルクソンにおいても見出されている。
ベルクソンはまず、「二種類の量」を区別する。一方は外延的(extensif)、他方は強度的(intensif)である。前者は空間的な広がりの中で定位され、明確な測定が可能な量のことである。そこで測定とは、重ね合わせの論理を利用した、空間に占める大きさの対比のことを意味する。そして量とは、単位的な大きさがどれだけ空間に含まれるかによって示されることになる。しかし強度的なものとは、こうした量ではない。ベルクソンは強度的なものの例を、「意識の諸状態、感覚、感情、情念、努力」と列挙するが、これらは外延的な量のように、二倍、三倍という仕方で明確に測定されるものではないのである。たとえば痛みや快楽といった感覚を考えてみるとする。ある痛みと別の痛みを比較した際に、どちらがより強い痛みであるかを述べることはできるだろう。しかしその場合でも、ある痛みが別の痛みの二倍であるか三倍であるかを明確に規定することはできないだろう。ベルクソンはその理由を、強度的なものは空間化できないからであると考える。つまり強度的なものは、空間的な重ね合わせとそれに伴う大小の比較の論理を利用できない量なのである。意識に与えられる実在において、こうして二つの量の領域が区分されることになる[5]。
ここで注意すべきことが二つある。一つは、空間性を利用する外延的なものが客観的なものと描かれるのに対し、強度的なものが主観的なものとして示されることである。ベルクソンは外延的な量を客観的な計測において、強度亭なものを主観的な内的諸状態において指示する。二つの量の区分は客観性と主観性という区分の仕方に結びつくだろう。しかしこれは議論の転回の中で見いだされるものであり、前提ではないことに留意すべきである。発端はあくまでも、外延的なものと強度的なものとの実在としてのあり方の差異にある。そうした差異をさらに特定する過程において、客観と主観という区分が浮上しているのである。
もう一つは、二種類の量が本質的に対比的であるにもかかわらず、外延的なものに依存して強度的なものを理解してしまう考え方が一般的には根深く存在していることである。それは空間的な量のモデルを拡張し、強度的な量を覆いつくすような発想であるだろう。ベルクソンはこの考え方を誤ったものとして排除する。こうした混同を避けること、つまり強度的なものをそれ自身に即したあり方によって把握すること、これが持続を見出す場面でなされるべきだという。
強度的なものの量をあえて計測するには、どのような方法があるだろうか。基本的にこの試みは、強度的なものを空間的なものに転写する作業から成りたつだろう。たとえば怒りや喜びなどの感情は、ほとんどの場合何らかの身体の反応を伴っている。だから感情的な強度の量は、身体的な諸反応の測定において見てとればよいという着想が生じてくる。身体の反応とは空間的なものだから、感情に付随する刺激や緊張の具体的なあり方はそこで計測しうるものになる。それが感情の量を表しているのではないか。一九世紀にグスタフ・フェヒナーが図った精神物理学やそのデルブーフによる批判的改良は、この方向に進みながら感覚の量的測定を精緻化したものである。フェヒナーは、心身二元論を前提に物理量とその感覚(心理量)の関係を理解しようとし、その方法として精神物理学を創始した。彼は感覚をE、刺激をI、cを定数とするとき、$${E=klogI+c}$$で表されるとし、これをフェヒナーの法則という。感覚の大きさ(E)は刺激の強度(I)の対数に比例して増大するということになる[6]。しかしこうした記述をいくら展開して、それが強度的なものの空間化という原理に依存していることは変わりがない。それは本当に強度的なものの量を測定しうるのだろうか。
こうした考え方にはどのような反論がありうるだろうか。問題は、強度的なものを把握しようとするこれらの仕方が強度的なもの自身には基づかず、間接的に、影響や原因としてそれらが関与すると仮定される空間により事態を処理する点にあるだろう。だが強度的なものは、空間化されない直接的な知覚として見出されていたはずである。それを空間という別種の存立を通じて把握することは、強度的なものの本質を失わせることになるのではないか。ではそこで何が失われるのか。
ベルクソンはこの場面に質的なものを導入することになる。たとえばさまざまな苦痛とは、身体的反応に着目するならば客観的な量として表現しうるものかもしれない。しかし強度的であるそれぞれの苦痛とは、本来はは苦痛という記号にすらとりまとめえないような独自のヴァリアントをもつものである。光の感覚に関しても同様だろう。たとえば光が二倍強くなった場面で感じられる「白い表面」とは、以前に耐えられる白さとはまったく別のものである。それぞれの白さとはニュアンス的に異なった現実なのであり、それぞれが強度的なものの与えられ方を形成している。感情や感覚の空間化的な測量とは、それらを見出す一つの仕方であるにしても、質の存在様式そのものは逃してしまう。
ベルクソンと純粋持続
ここにおいて、外延的なものと強度的なものとの違いが、実は量と質の違いであることがわかる。ベルクソンは量と質の存在様式をそれぞれはっきりと定式化しようとする。この場面では、多数性という術語が重要になる。量と質の両者とは、私が「二種類の量」と呼んだことからもわかるように、ともに多数的である。外延的なものが多数的であることは自明だが、ベルクソンは強度的なものも、空間に還元されない形で複数的な位相を含むと考える。量的多数性と質的多数性である[7]。
量的多数性とは、空間的に客観化されて把握される量のことであった。すなわち量とは、等質的な環境において同一化される相互外在的な単位が繰り返されることによって形成される多数性である。例えば、羊を数える際、そこでは個々の羊に認められる独自性は原則的に写像されなければならない。数えられる羊の一頭一頭は、個性を失った等質的な仕方で、同一的な単位を構成するものと見なさなければならない。
これに対して質的多数性とは、つぎのように規定されるものである。すなわちそれは、相互浸透的な諸要素が切り離されることなく融合し、異質的状況を生み出していく流れなのである。ベルクソンはメロディーの例によってこの多数性を説明する。メロディーはどのように成立するかを考えてみよう。それは明らかに複数の要素、数々の音を備えている。しかしながらメロディーを個々の音に分解すればどうなるか。そこではメロディーを構成する音が、バラバラのかたちで散乱することになるのではないか。するとメロディーは、もはやメロディーであることをやめてしまう。メロディーとは複数の要素が分割不可能に連関する総体的な配置においてこそ、メロディーとして存立しうるのである。一つの音は、それに先立つ音と溶け合うように融合して有機的な連携をもつ流れをなしてこそ、メロディーを形成するものになる。
ベルクソンによる質の規定を、ここから取り出すことができる。ベルクソンにとって質とは、分割不可能的な諸要素から成り立つ連続性のことである。あるいは、分割すればその質が別のものになる連続性のことだと述べてもよい。そこでの諸要素は、量的多数性が等質的な状況に置かれていたのとは対照的に、異質的なものと形容される。ベルクソンにとっての流れとは、異質的な連続性である。流れから異質性を捨象して空間的並存を許すのならば、それはすでに流れではなくなることになる。
さらにベルクソンは、質を時間において表現する。ここでいう時間は、空間性に依拠する量の規定への対比として描かれている。ベルクソンは時間のあり方を、存在が一度に与えられないことに見出だしていく。一度にすべてが与えられないこと、これが時間的であることの一つの意味をなすのである。それは次のように説明される。メロディーを聴くためには、メロディーが通過するのを待たなければならない[8]。一方で現実的な空間はすっかり表象されるものなので、原理的には待つことを介さずにすべてが与えられている。しかし与えられていることを待つというこの事情は、時間的なリアリティーの一つの本質をなす。
持続的なものを空間にしたがって解釈することを、ベルクソンは断固として拒絶する。時間的な持続を空間性により表彰することは、実在のあるがままの流れを記述するベルクソンにとって転倒した操作に他ならないからだ。ベルクソンが援用するゼノンのパラドックスは、時間という持続を空間から構成することの不可能さを示すのに適した議論であるのでここに紹介しよう[9]。
ゼノンのパラドックスの一つである「アキレスと亀」の事例。それは次のように展開される。まずは運動が無限に下位に分割され、現実的な空間性によりすべてが表彰されうると考えてみよう。するとそこで速いアキレスは、遅い亀を追い抜けないという事態が生じることになる。俊足のアキレスが鈍足の亀を追いかけるとき、アキレスがはじめに亀のいたところに追いついたときには、亀はわずかに前進している。ふたたびアキレスが追いかけて亀がいたところに追いついたときには、さらに亀はわずかに前進している。これを繰り返すかぎり、アキレスは亀に追いつくことはできない[10]。
実際にはもちろん、こうしたことは起こりえない。アキレスは易々と亀を抜き去っていくだろう。するとゼノンのパラドックスにおいては何が誤っているのか。それをベルクソンは、時間的な流れを無限に分割可能な空間に依拠して考える点に見出している。このパラドックスでは、流れの通過した空間の方から時間が思考されているのである。つまり移行しつつある時間的な流れが、現実化された空間表象の位置によって語られるのである。だからこの議論では運動のリアリティが写像され、受け入れがたい帰結が生じることになる。
なるほどベルクソンは同時代の自然科学が持つ空間的な時間認識にとりわけ敏感であり続けた。たとえばアインシュタインが相対性理論を発表するとその論文を読み、それに反対する意図で『持続と同時性』という論文を発表したこともある。ベルクソンとアインシュタインの関係は、非常に興味深いものがある[11]。相対性精神学における「相対性」が、相対性理論といかなる関わりを持つかについては、二人の時間論に鑑みて、より進んだ考察を展開することもできよう。
このようにベルクソンの描く実在とは、持続を根拠とした、時間性に深くかかわる生成の過程そのものである。それは強度的なもの、異質性、連続性、分割不可能性、相互浸透性、主観性によって説明される。経験一般を合理的理性によって捨象してはならない理由も、これらと関連付けられて語られるだろう。ベルクソンにとって実在は持続にこそ見出されるのだから、等質性のもとに時間を分割し、時間の空間による還元をたくらむ合理的精神は、持続による実在を含めた経験一般を捨象して合理的経験に貶めてしまう。経験されたものはまず、認めなければならない。
ベルクソンの主張は次の四つに集約されると見てとるべきだろう。一、あらゆる運動は、停止から停止への移行であるかぎり、絶対的に分割不可能である。ニ、実在する運動が存在する。三、物質を、輪郭が絶対的に規定された独立した物体に分割することは、すべて人為的な分割である。四、実在する運動は、事物の移動ではなく状態の移動である。
第一の主張は、運動の分割不可能性のテーゼである。ベルクソンはやはりゼノンのパラドックスを援用しながら、分割されたものから運動を成立させることの不可能性を論じていく。運動とは、分割されればすでに運動ではなくなるものである。分割された部分に基づいて運動の姿を回復させることは一種の転倒にほかならない。だから運動とは、その全体にわたる分割不可能性において規定されるだろう。この議論は、ただちに第二の主張につながる。それは運動の実在性のテーゼである。こうした分割不可能な運動が、そのまま実在をなすのである。分割されたその部分は、実在というよりも、むしろ仮構的に作り出された断面であるだろう。不可分に移行する運動の姿こそが、積極的な実在性と考えられるべきである。
これを拡張すれば、第三の主張に至りつく。それは実在の全体性についてのテーゼである。実在が運動そのものであるならば、与えられる知覚世界とは、すべてが転変する舞台である。すべては移行の途上にある。するとそこで、事物に明確な輪郭が存在するという考えは、運動の停止を想定することにより生じるものであるからだ。だから知覚世界に明確な輪郭を持つ対象を見てとることは、実践上の操作に過ぎなくなる。こうして考察は、第四の質としての実在のテーゼにたどり着く。知覚世界が、全体が一体になった運動であるならば、それは事物の移動とすら語れない。分節される事物がすでに存在しないからだ。そのすべては状態の移動である。つまりそれは、総体としての質的な流れとして記述されなければならない。これこそ、ベルクソンが純粋持続と呼んだものの正体である。
ベルクソンが用いた理解の区別に「直観」と「分析」がある。直観とは、あいだに何者をも媒介しないような理解である。腕を動かすとき、意識して腕を動かす者はいないだろう。一方で分析とは、情報が媒介するような間接的な理解の仕方である。分析がものを「外から」理解するような手法であるならば、直観はものを「内から」理解する手法だといえる。ベルクソンは「直観」について次のようにいう。「したがって、私の語る直観は何よりもまず内的な持続へ向かう。直観がとらえるのは並置ではなく継起であり、内からの生長であり、絶え間なく伸びて現在から未来へ食い入る過去である。直観とは精神による精神の直接的な視覚である」[12]。さらにこう続ける。「とはいえ、直観の基本的な意味が一つある。すなわち、直観的に考えるとは持続のなかで考えることである」[13]。ベルクソンによれば、「直観」のもっとも典型的な事例は、自分自身の「持続」を捉えることにある。ベルクソンによれば、われわれの意識に直接与えられているのは、「純粋持続」という有機的な時間の流動である。これこそが真の時間であり、われわれの真相だといえる。「直観」は、この「持続」という有機的な流動を把握する方法なのだ。そして、直観から分析へ向かう道はあれど、分析から直観へ至ることはできない。直観がなければ分析も始まらないという意味で、分析は直観に対して二次的である。
であれば、空間よりも時間に、外延よりも強度に、量よりも質に、分析よりも直観に身を寄せるベルクソンの思考に「真実は主観の中にある」という理念を認めることは、やぶさかではない。しかし、強調しておきたい。主観の中にしか見出されることのない「持続」を擁護する観念論的な思索、それだけにとどまらない相対性精神学の可能性が、ベルクソンの場合には認められるのである。
唯物論的相対性精神学
これまでベルクソンの観念論的な側面を紹介してきた。しかし、彼こそ唯物論的な思想家であるといわなければならない[14]。一般性や普遍性を目指して、抽象的、理念的な体系を作り上げるのが哲学の課題だという観点とは、まったく反対の「唯物論的」傾向と方法を、私はベルクソンに認める[15]。ベルクソンが思考する差異とは「事物と概念」の一致にほかならない。「その対象についてその対象だけに適用される概念、それがただそのものにしかあてはまらないために、それがなおも一個の概念であると、かろうじていいうるかえないかのような概念」を作り上げるのだ[16]。類や種のように一般的な差異ではなく、事物そのものにほかならないニュアンスを思考すること。何よりもまず、ベルクソンのこのような姿勢こそが「唯物論的」なのだ。『物質と記憶』のあとに書かれる『創造的進化』や『道徳と宗教の二源泉』を、それ以前の精緻な「唯物論」施策の延長線上に厳密に位置付けて読むことをせずに、大筋の主張を要約するだけで済ますなら、それはいかにも楽天的に見える「生の哲学」として、観念的にも神秘的にも理解されるだけでおわりかねない。現に、ベルクソンの唯物論的な思索に注目するどころか、科学や理性を越えた生命の神秘的、統合的原理をそこに見るような読み方はいつも優勢であった。ベルクソンのこのような読み方は、しばしば没政治的、非歴史的な観念論と合体した。そのため社会的抗争や葛藤に対してまったく鈍感な自然主義的思考に迎えられてきた[17]。私がベルクソンに読み取った「唯物論」は、必然的に「弁証法」を退け、弁証法を支える「否定」と「対立」の論理にも批判を向けることになった。弁証法とはヘーゲルの思想の原理を指している。しかし否定とはどこまでも観念の働きにすぎず、対立とは事物の無限の差異を、互いに否定しあう二つの項に還元することである。しかし事物や生命が生成し変化する過程それ自体には、ただ微細な変化や無限の差異と、それらを横断する秩序や構築があるだけで、否定も対立もありえない。
ベルクソニスムは、自然と人間をあくまでも連続した地平で考え、同時代の自然科学、とりわけ物理学的認識の転換にも敏感に反応している。自然科学とは、どこまでも量的な差異に事象を還元しようとする認識である。ベルクソンのほうは、自然と人間を貫通する次元について、あくまで質的な差異をめぐって思考しようとするのだ。そして自然と人間を貫通するものとは、何よりもまず生命であり、生命とはそれ自体すでに記憶であり、持続であり、記憶・持続として実現される「差異化」の過程である。ベルクソンの自然主義は、事物の無限のニュアンス、変化、運動にあくまで忠実な「唯物論」とともにある。
ベルクソニスムにとって、「潜在的なもの」と「可能的なもの」の相違は、とても大きな意味をもっている。可能的なものは、それが現実化されるといっても、むしろ現実化されたもののほうから後ろ向きに投射されたものに過ぎない。可能的なものは事後的な投射であるがゆえに、逆に現実の全体を確定するものとして認識される。しかし可能的なものが現実化されるのではなく、潜在的なものが現実化されるとき、そこにはある予見不可能な不連続があり、潜在的なものは何も予見することなく、ただ新しい価値を生み出すのである。
なるほどここで述べられる唯物論とは、ラ・メトリ流の物理主義などではない。「物質」を刷新する試みがベルクソン哲学の渦中で起こっていると見なすべきだろう。私は『燕石博物誌』のなかで「夢は魂の構成物質の記憶である」[18]と結論付けた。これは相対性精神学の観点から私の経験を推論したものである。夜の竹林という幻想的な風景のなかで私は、夢が魂の構成物質の記憶であり、遺伝子の奥底に刻み込まれた、駆動する幻想機械の記憶であることを確信する。
さて、記憶とはベルクソンにおいて重要な用語の一つである。ベルクソンは、過去はそれ自体として、そのまますっかり残存すると考えている。こうした過去の即自的存在が、純粋記憶を意味している。しかし過去すべてが残存するというこの言明は、常識的に考えれば法外なものにおもえていくる。何よりも、すべての残存というベルクソンの言葉の含意が推し量りがたいからだ。しかしこの言明が、実在を分割不可能な流れとみなす思考の本質的な帰結であることを踏まえなければならない。実在が分割不可能であるならば、過去は流れを構成するものとして、どこが現在でどこからが過去かを論じること自体が、意味をなさない問いになるからだ。そしてさまざまな流れのスケールを考えれば、原則的にあらゆる過去は、何らかの側面で現在に繋がる流れの一部であるだろう。このように理解するかぎり、過去すべてが現在に連鎖的なものとして同時に居合わせることになる。過去すべての存立が、分割不可能な持続というリアリティーにとって不可欠な要因になるのである。
過去とは現在とともに居合わせているものであり、過去すべてが残存しているのであれば、われわれは古代人の記憶をさえ、自らの身体に持ち合わせていることになる。私はここにカール・グスタフ・ユングを差し込んでみたい。ユングは、無意識という深層心理に先天的な構造領域が存在すると考え、これが集団や民族、人類の心と深く関わると考えた。集合的無意識は、個人的に獲得されたものではなく、生得的なもので、民族や人類一般に共通した普遍的な領域と考えられている。しかしこの領域はあまりにも深層に存在するために、人間はこれを意識に登らせることがめったにないといってよい。なるほど人間が夢を共有するには、共通の普遍的な心的構造を持ち合わせることが前提になるだろう。この夢の共有に成功したという稀有な事例を私は知っている[19]。夢の共有はこの集合的無意識を介して成功した、というのが私の推測であるが、それは神話や伝説、宗教の領域にある集合的無意識なしに、その文化的地盤の一致を他に成立しえなかったろう。
さて、この「夢は魂の構成物質の記憶である」には次のような反論が予想される。「夢は魂の構成物質の記憶である」というテーゼからは、「魂は物質から構成されている」という命題が導けてしまう。「魂が物質から構成されている」のであれば、主観が成り立たなくなる。デカルト的主体からソシュールによる恣意性の原理、カントの超越論哲学、ドゥルーズによる知覚領域の構造、バークリー=ヒュームの観念論は当然のこととして、これらはいずれも物質に還元して説明すべきものではない。なるほどこの指摘はもっともなものである。
しかしベルクソンが再定義した「物質」の概念に顧みて、この議論に反駁を試みよう。「イマージュ(image)」という概念に言及しておきたい。それは「魂は物質から構成されている」における「物質」の意味を解読する手がかりになりえるからである。先に述べたように、物質をそのままラ・メトリ流の物理主義のもとに解釈してしまうことは誤りである。イマージュはベルクソンが『物質と記憶』のなかで用いる概念である。ベルクソンにとって、物質であれ現実化される記憶であれ、知覚される世界の実質はすべてがイマージュである。イマージュは心理的概念でも物質的概念でもない。それは観念論者が主張する「表象」と、物理主義的、素朴実在論的な「事物」との中間(mi-chemin)に位置するものである。しかもこのいい方は折衷的なものではない。われわれに与えられる知覚世界とは、いつもこうした中間性でしかないからだ。観念論者が考えるような実在が表象であるならば、知覚世界は私の思考に閉じ込められてしまう。しかし眼に見え手に触れる事物が私の心的存在でしかないという発想は奇妙だろう。また物理主義的、素朴実在論的な観点を取るならば、知覚とはまったく異なった事物が知覚の基盤に存在することになる。だが、目に映る色も手に触れる抵抗もない別種の世界が真の知覚世界の姿だという想定は、これも受け入れがたい。知覚世界とはわれわれに与えられるがままのものである。一方でベルクソンは「私が「物質」と呼ぶのは、イマージュの総体のこと」[20]であるという。観念も事物もイマージュから分化するものであるとすれば、観念と事物は元来一であるとさえいえるだろう。ベルクソンによるイマージュの概念は、「真実は主観の中にある」と「魂は物質から構成されている」という観念論と唯物論の矛盾を解消することができるかもしれない。相対性精神学における最大の課題を解決する手段がベルクソン哲学にはある、とだけ今はいっておこう。
西田幾多郎の哲学
バークリー、ヒューム、ベルクソンという経験論の系譜の中に、次に持ち込むべきなのは、西田幾多郎である。京都学派の創始者として知られるこの日本の哲学者は、最初の著作『善の研究』のなかで、「純粋経験」という概念を提出している。この概念を知るために、次の言葉から出発しよう。「今もし真の実在を理解し、天地人生の真面目(しんめんもく)を知ろうと思うたならば、疑いうるだけ疑って、すべての人工的仮定を去り、疑うにももはや疑いようのない、直接の知識を本(もと)として出立せねばならぬ」[21]。真の実在とは何かを明らかにすること、またそのためには、われわれがものを認識するために仮構したものをすべて除き去り、「直接の知識」から出発しなければならないことがいわれる。そしてこの直接の知識とは何かという問いに対して西田が出した答えが「直覚的経験の事実」すなわち「純粋経験」こそがそうであるというものであった。加えてここで、この「直観的経験の事実」は考察の出発点であるだけでなく、それ自体が「真の実在」であることがいわれている。
『善の研究』は四つの編からなる。それぞれ第一編「純粋経験」、第二編「実在」、第三編「善」、第四編「宗教」である。第三編と第四編ではそのとおり、道徳と宗教を論じている。西田は、道徳と宗教とも純粋経験が強く結びついているとする。「世界はこのようなもの、人生はこのようなものという哲学的世界観及び人生観と、人間はかくせねばならぬ、かかる処に安心せねばならぬという道徳宗教の実践的要求とは密接の関係を持っている」[22]というのが西田の考えであった。
なお、『善の研究』はもともと「純粋経験と実在」と題されていた。このことからも、この書物が本来は「善」ではなく、純粋経験と実在を中心の思索としていたことがわかる。注目すべきは、先に引用した第二編の冒頭部分である。「哲学的世界観および人生観」と「道徳宗教の実践的要求」とが対比されている。前者は「知識においての真理」ともいわれている。こちらが知識に関わるとすれば、後者は行為や実践に関わる。前者が人間を含め、存在する者すべてが何から成り立ち、何のために存在しているのかといった問いに答えようとするのに対し、後者は、私が(あるいは人が)どのように行動すべきか、どのようにすれば心の安定を得ることができるか、そうしたことを問題にしようとする。この二つは、普通は別のことと考えられている。しかし西田は、両者が密接に結びついており、世界に対する考え方と、自分の行動や宗教についての考え方が別々のものであってはならないという。そのような意味で、「元来、真理は一つである」[23]と西田は述べている。
第二編で取り扱われる問題を西田は「天地人生の真相はいかなるものであるか、真の実在とはいかなるものであるか」[24]として表現している。存在の真の姿にせよ、人生の真の意義にせよ、われわれは往々にして表面的な理解で満足し、その真相には触れないままでいる。その真相に迫り、それが何であるかを明らかにしたいというのが、西田が『善の研究』に込めた意図だということができる。それではこの「天地人生の真相」を明らかにするという課題とどのように取り組めばよいのか、その点について西田は次のように述べる。「今もし真の実在を理解し、天地人生の真面目を知ろうと思うたならば、疑いうるだけ疑って、凡ての人工的仮定を去り、疑うにももはや疑い様のない、直接の知識を本として出立せねばならぬ」。まずここで注意を引くのは、「凡ての人工的仮定を去り」という表現である。第一編第一章の冒頭でも、「経験するというのは事実そのままに知るの意である。まったく自己の細工を棄てて、事実に従うて知るのである」[25]といわれているが、この「自己の細工を棄てる」ということと同じことがそこでいわれていると考えられる。第二編第三章でも、「我々がまだ思惟の細工を加えない直接の実在」[26]といういい方がされており、第一編第一章の「自己の細工を棄てる」という表現は、この箇所などを受けたものということができる。
「天地人生の真面目を知る」ためには、何も仮定しないで、あるいは「思惟の細工」を加えないで、事実を「事実そのままに」知らなければならない、というのが西田の考えであり、『善の研究』を通じてめざしたことであったといえる。しかしこの「自己の細工を棄てる」とか、「人工的仮定を去る」という表現にひっかかりを覚える者も当然いるだろう。というのも、普段、われわれは物を見るとき、少なくとも自分の意識の中では、なにか「細工」をしてそれを見ているわけではないからである。自分では、対象をゆがめることなく、むしろそれをあるがままに見ていると思っている。
それにもかかわらず西田が「人工的仮定を去る」とか、「細工を棄てて」というのは、われわれがものを見るとき、いわば無意識のうちに、われわれのものの見方のなかに先入見が入り込んでいるという事態を指して、そのようにいっているのではないかと推測される。先入見の特徴は、それが先入見であるという意識を当の人間がもっていないという点にある。権威に盲従する人間には当の権威の一面性が視野に入っていない。そのためにどこまでもその権威に従おうとする。そのように意識にのぼることなく、われわれのものの見方のなかに深く食い込んでいる先入見を西田は問題にしようとしたと考えられる。西田が「人工的仮定」という言葉でいい表そうとしたのは、そのような先入見であったと解することができる。
それでは、この「人工的仮定」や、われわれが無意識のうちに持ち込む「思惟の細工」とは具体的に何を指すのであろうか。その点に関して西田は第一章で、「我々の常識では意識を離れて外界に物が存在し、意識の背後には心なる物があっていろいろの働きをなす様に考えている」[27]といい表している。われわれは普通、物を見て、それが何であるか考えたり、判断したりするとき、まず、物を見たり、それが何であるかを考えたりする「私」あるいは「意識」というものがあり、そしてその「私」=「意識」の外に物があり、この両者のあいだに、見るとか、聞くとかいった関係が成立すると考えている。
こうした考え方が一般に「主客二元論」という言葉で呼ばれるのは、先に説明した通りである。つまり「私」という主観と、その主観が働きかける「対象」、つまり客観とが、それぞれ独立に存在しており、この二つのあいだでさまざまな関係が成立するという考え方である。この「主客二元論」的な考え方は、事実をそのものとして捉えたものではなく、そのような見方をするとき、そこにはすでにわれわれはわれわれの「仮定」、あるいは先入見を持ち込んでしまっていると西田は考えた。
さて、もう一度、さきほど引用した「今もし真の実在を理解し、天地人生の真面目を知ろうと思うたならば、疑いうるだけ疑って、凡ての人工的仮定を去り、疑うにももはや疑い様のない、直接の知識を本として出立せねばならぬ」という文章に立ち返ってみたい。「天地人生の真相」、つまり自然や人間の真のあり方やあるべき姿を探求するためには、「疑いうるだけ疑う」、つまりすべての事柄について、それが本当に真であるかどうかを吟味しなければならない。要するにわれわれのものの見方、世界観や道徳観のなかには、われわれが十分に検討しないで、あるいは無意識のうちに持ち込んでしまった先入見が存在する可能性がある。したがってそれを吟味の俎上に載せ、もし先入見が入り込んでいれば、それらをすべて取り除かなければならない。そうしなければ、われわれは物を物として、実在を実在として把握することができないと西田はいう。
西田幾多郎と方法的懐疑
このようにすべてのことを徹底して疑うこと、西田はまさにデカルトが行った方法的懐疑を念頭に置いている。それを徹底して行うことによって、徹底的な懐疑を遂行することによって、「我思う、ゆえに我あり(cogito ergo sum)」という命題をデカルトは導出した。デカルトにとって、徹底的な懐疑こそが真理に至るための必須の道、必須の方法である。西田はこの方法を採用した。そういう意味で、西田の思索の歩みはデカルトともに始められたといってよい。
デカルトについては、これ以上繰り返し述べるつもりはない。しかし西田もデカルトと同様に、『善の研究』において、確実な真理を見出すために「疑いうるだけ疑う」ということをしていた。しかし、この徹底的な懐疑の結果得られた結論は、デカルトのそれと同じではなかった。デカルトが得た結論は、他のすべてのものが虚偽の可能性をはらむとしても、「私」の存在だけは確実であるというものであった。それに対して西田が出した結論は、「さらば、疑うにも疑いようのない直接の知識とは何であるか。そはただ我々の直覚的経験の事実すなわち意識現象についての知識あるのみである」[28]というものであった。何かを見たり、それについて疑ったり、考えたりしている私ではなく、その何かを見たり、それについて疑ったり、考えたりしていることそのもの、その直接的な経験、つまり意識現象の直接的な知識こそが、疑いを差しはさむことのできない、絶対に確実なものだというのが西田の考えであった。この直接的経験から二次的に導き出されたもの、たとえばそこに一つの物体、椅子や机があるとか、あるいは逆に、それを見ている「私」が存在しているということについては、それが本当かどうか、疑うことができる。しかし、そういう二次的な考察が加えられる以前の「直接的な経験」そのものについては、真か偽か疑うことはできない、というのである。
それに対して、物はやはり物としてある。われわれが見ようが見まいが、机は机としてある。そしてそれを見たとき、われわれはそれを机として判断するのだと、反論する人もいるにちがいない。そういう疑問を想定して、西田は、「しかし、物心の独立的存在などということは我々の思惟の要求によりて仮定したまでで、いくらも疑えば疑いうる余地があるのである」[29]と述べている。カントの「物自体」論が示すように、われわれは、われわれの意識を離れて物それ自体を、あるいは心そのものを知る手段をもたないからである。はたしてそれらが独立したものとして存在しているのかどうかを示す確実な手段をわれわれはもたないのである。
われわれにとって直接に確実な知識というのは、われわれがまじかに経験していること以外にはないというのが西田の考えであった。第二章の冒頭で西田は「少しの仮定も置かない直接の知識に基づいて見れば、実在とはただ我々の意識現象即ち直接経験の事実あるのみである」[30]と記している。このわれわれの意識現象、あるいは直接経験の事実こそが実在であるという主張に対しては、次のような疑問が出されるかもしれない。われわれの意識はつねに変化し、移ろっていくあやふやなものである。それを実在と呼ぶことはできない。むしろわれわれの意識とは関わりなく存在している物体こそが実在ではないかという反論である。それに対しては、西田は「我々は意識現象と物体現象と二種の経験的事実があるように考えて居るが、その実ただ一種あるのみである。即ち意識現象あるのみである」[31]と述べている。バークリー=ヒューム的な観念論をここに見てとることができるだろう。バークリーは物質否定論によって、心の中にある観念のみが存在すると考えた。
そもそも一方に物体現象、つまり、われわれの意識とはまったく関係なく、物が動いたり、形を変えたりするということがあり、他方に、われわれがその物体の運動や変化を自分の心の中で意識するという考え方は、われわれの直接的な意識現象から、いわば派生的に考えられたものにすぎない。われわれが具体的に経験しているのは、たとえば、一つのリンゴがつややかな赤色をし、かぐわしいリンゴ独特の香りがし、おいしそうに見えるという出来事そのものである。そこから赤色や匂い、そしておいしそうだというわれわれの思いをすべて取り去ったところに残るのが、物体としてのリンゴである。それはわれわれの経験から二次的に考えられたものにすぎない。西田の理解では、意識現象から切り離された「物其者(そのもの)」というのは「我々の思惟の要求に由って想像した」ものであり、それを真の実在ということはできない。そのように主観と客観に分けられる以前のもの、「意識現象とも物体現象とも名づけられない者」[32]こそが真の実在なのである。
確かに西田は第二編の第八章で「自然」について、第九章で「精神」について語っている。しかしそれらは、われわれの意識の働きから独立してわれわれの意識の働きの主体、すなわち精神が一つの実態として存在しているという前提に立って論じられているのではない。いまいった意味での自然、自然科学者が問題にするような自然は、具体的な意識現象から、それを当居続けている主観的側面をすべて取り除いたものであり、「最抽象的なる者即ち最も実在の真景を遠ざかったもの」[33]であるというのが西田の考えであった。「精神」も多くの場合、客観的な存在とは性質を異にする単なる主観的な働きと考えられているが、それもまた一面的な理解に基づく。「精神」とは統一されるものから区別された単なる統一作用ではない。統一するものと統一されるもの、両者は本来一体である。
そのことを西田は具体的な例を挙げて、次のようにいい表している。「我々が物を知るということは、自己が物と一致するというにすぎない。花を見た時は即ち自己が花となっているのである」[34]。そこで注意する必要があるのは、西田が科学的なものの見方をそれ自体否定しているわけではないということである。第八章で銅像の例が挙げられているが、銅像を銅像として見るという直接経験の事実と、それを無数の銅の原子からなるものと説明することとは、決して衝突しないというのが西田の考えであった。むしろ「かえって両者相俟って完全なる自然の説明ができるのである」[35]と述べている。しかし銅像が銅像である所以は、それが銅の原子からなる点にではなく、芸術家がそこに芸術的な「理想」を表現しているところに、そして鑑賞者がその理想に心動かされるところにある、「主客を具したる意識の具体的事実」こそが「真実在」であるというのが西田の考えであった。「自然の本体はやはり未だ主客の分れざる直接経験の事実である」とも述べている。
西田は第三章で牛を例に挙げて次のように語っている。「我々の見るもの聞くものの中皆我々の個性を含んでいる。同一の意識といっても決して真に同一でない。例えば、同一の牛を見るにしても、農夫、動物学者、美術家によりて各々その心象が異なっておらねばならぬ。同一の景色でも自分の心持ちによって鮮明に美しく見ゆることもあれば、陰鬱にして悲しく見ゆることもある。仏教などにて自分の心持次第にてこの世界が天堂(天国)ともなり地獄ともなるというが如く、つまり我々の世は我々の情意を本として組み立てられたものである。いかに純知識の対象なる客観的世界であるといっても、この関係を免れることはできぬ」[36]。なるほど見る者聞く者によって対象の相貌が異なるということ、それが情意によっても個性によっても異なることが、西田によって指摘されている。科学的知識とはここから派生したものであるというよりも、むしろ「生存競争上実地の要求によって起こったもの」であり、決して情意の要求を離れた見方ではない。その意味で、客観的普遍的な知識とは「実在の真景を遠ざかったもの」であるのだ。
「同一の牛を見るにしても、農夫、動物学者、美術家によってその心象は異な」る。科学的知識は牛それ自体の客観的な理解を装うものであるが、真実在とは冷静な知識の対象ではない。それはむしろ、われわれの情意ににより成り立ったものである。まさしく単に存在であるのでなくて、意味を持ったものである。なるほど牛の心象は、観察するものの個性と情意とによって、絶対的というよりもむしろ相対的に決定されるものである。絶対性の精神学は、実在の真景を捉え損なうばかりか、根本的な過ちを犯してしまう点で看過されるべきではない。私が西田に汲み取るべきは、相対性の精神学である。われわれは「純粋経験」を携えることによって、相対性精神学を可能ならしめる唯一の手段を獲得するのである。
われわれの意識現象、あるいは直接経験の事実こそが実在であるという主張に対しては、もう一つ、次のような疑問が出されるかもしれない。われわれの意識の働きは秩序や連関をもたない孤立したものではなく、そこにはつねに統一性がある。それはこの意識の働きの所有者、つまり「私」というものが存在しているからではないか、という疑問である。これも西田が予想していた疑問であった。それに対して西田は次のように答えている。「意識は必ず誰かの意識でなければならぬというのは、単に意識には必ず統一がなければならぬという意にすぎない。もしこれ以上に所有者がなければならぬとの考えならば、そは明らかに独断である」[37]。
デカルトの場合には、疑わしいものをすべて排除していくという徹底した懐疑を遂行したあと、そこから翻って、すべてのものを疑っている「私」に目が向けなおされた。デカルトの懐疑には、その意識の働きの「所有者」である「私」がつねに伴っていたのである。しかし西田の考えでは、このすべての意識の働きに伴っていると考えられた「私」は、われわれの意識の働きをあとから見直してはじめて見出されたものであった。それをはじめから存在していたと考えるのは、「独断」にすぎないと西田はいうのである。
デカルトの場合には、疑う「私」と疑われる「対象」とを前提にして、すべての懐疑が遂行されていったのであるが、西田はこの前提其の物に懐疑の目を向けたのである。そしてこの疑う「私」と疑われる「対象」という主客二元論的な思索の枠組み自体をも取り除いていこうとしたのである。そのときに残るのは、ただ純粋な、直接的な経験のみであるというのが、西田がここで導き出した結論である。そこでは「誰かの」という所有者のことは問題にならない。ただ直接的な経験の事実があるのみである。西田は序において「個人あって経験あるにあらず、経験あって個人あるのである」[38]と述べるが、このことを端的に示したものということができる。この直接的な経験の事実こそが、われわれがそこから出発すべき「直接の知識」であることを西田は主張したのである。それは実在を理解するための出発点であるだけでなく、むしろそれ自身がまさに「真の実在」である。それ以外に、いかなる意味においても疑うことのできない真にあるものを認めることはできないからである。
西田幾多郎と純粋経験
『善の研究』の序のなかで西田は「純粋経験」こそが「余の思想の根幹である」と語っている。では、この西田の思想をその根底において支えている「純粋経験」とは何か。西田は第一編第一章の冒頭で次のようにいう。「経験するというのは事実そのままに知るの意である。まったく自己の細工を棄てて、事実に従うて知るのである。純粋というのは、普通に経験といっている者もその実はなんらかの思想を交えて居るから、毫(ごう)も思慮分別を加えない、真に経験そのままの状態をいうのである。例えば、色を見、音を聞く刹那、未だこれが外物の作用であるとか、我がこれを感じているとかいうような考えのないのみならず、この色、この音は何であるかという判断すら加わらない前をいうのである。それで純粋経験は直接経験と同一である。自己の意識状態を直下(じか)に経験した時、未だ主もなく客もない、知識とその対象とが全く合一している。これが経験の最醇(さいじゅん)なる者である」[39]。
まず「色を見、音を聞く刹那」という言葉に注目しよう。純粋経験とは、何か特別な経験のことではない。ある特殊な人だけがする経験ではない。道ばたのスミレの花を見て美しいと思う経験、小鳥のさえずりを聞いて気持ちよく思う経験のことである。普通、われわれが日常の生活のなかで行っている経験がそのもとに考えられている。ただ「刹那」といわれている点が重要である。そしてこの「刹那」においては、「未だこれが外物の作用であるとか、我がこれを感じて居るとかいうような考のないのみならず……」といわれる。純粋経験とは何かを考える上で、とくにこの点には注目する必要がある。通常われわれは、私がこちら側にいて、その目の前にあるスミレの花を見、そしてその美しさが私の心に映って、その結果、私の心が感動を覚えるというように考える。その場合、西田のいい方では、主と客、主観と客観が離れてしまっている。主客が分離してしまっている。そのように主客が分離したとき、その経験はもう「刹那」ではなくなっている。
さきほどの文章のなかで、もう一点われわれの注意を惹くのは、「自己の細工を棄てて」といわれている点である。「細工」をせずに、事実を事実のままに知る必要性が語られている。われわれはものを、自分の立っている位置とか視点、そのときの体調とか、目の具合とか、そういうものにまったく邪魔されずにそのものとして見ているわけではない。われわれは、誰であれ、そういう特権的な場所に立って、「ものそのもの」、「物それ自体」を見ているわけではない。われわれはつねに、ある一定の視点からしかものを見ることがないのである。そのようにものを見るということはどのような視点に立つかということに左右されるが、それだけでなく、知というものは、それが知として成立する、あるいは知として機能するとき、それが機能するための枠組みをも同時に成立させながら働いている。知は、知が持ち込む知の枠組みと切り離しがたく結びついているのである。どういうことかといえば、そもそも「何かを知る」ということを、そこにはすでに、「私が=主観が」、目の前にある何か=客観を見、「それ」を「知る」という構造ができあがっている。たとえばリンゴを目の前にし、それをリンゴであると判断するとき、われわれはそのリンゴを、何の細工もせず、何の先入見も交えず、あるがままにそのものとして見ていると思っている。しかしそこにはすでに、認識の主体である私=主観と、認識される対象=客観という対立図式が生み出されており、その図式の枠のなかでわれわれはものを認識している。つまり、「私」が「対象」であるリンゴを見るという構図を前提にした上で、リンゴが見られ、それが赤い色をしているとか、おいしそうだとか、その情報を得ている。文字通り外にあるものから、私のなかに情報がもたらされ、それを私が私の中で処理することで認識が成立していると考える。われわれはこの枠組みのなかで捉えられるものを真理として、いいかえれば、事柄の実相として考えている。
しかし捉えられたものはほんとうに事柄の実相といえるだろうか。それが西田の問題とするところである。事柄の実相に迫るためには、ものを認識するにあたってわれわれがもちこんだ「人工的仮定」、つまり認識の主体である「私」と認識される「対象」という対立図式を取り除き、もののあるがままの状態、つまり「色を見、音を聞く刹那」の「未だ主もなく客もない」状態に立ち返る必要があるのではないかというのが、西田がそこで得た結論であった。われわれは日常の生活のなかでも、認識の主体である「私」と認識される「対象」という対立図式のなかでものを見ている。そしてそこに何か問題があるとは考えていない。それと同様に、デカルトを典型例として、主観と客観との対立を前提にして議論がなされている。これに対して西田の姿勢は「何処までも直接な、最も根本的な立場から物を見、物を考えようと云うにあった。すべてがそこからそこへという立場を把握する」[40]ことにあった。
では「未だこれが外物の作用であるとか、我がこれを感じて居るとかいうような考のない」、「経験そのままの状態」とはどういう状態なのであろうか。西田は京都大学に着任後、「哲学概論」の講義を行った際、次のようにノートに記している。「真のfact of pure experience〔純粋経験の事実〕は、know〔知るということ〕だけである。I〔私〕はない。〔正確には〕Knowもない、rot〔赤〕ならrotだけである」[41]。ここでは純粋経験が「赤なら赤だけである」という言葉でいい表されている。われわれは普通には、「私が」という意識を持ち、たとえば目の前のバラを「外物」として意識しながら、「その花は赤い」と判断したりする。しかし西田は、純粋経験の状態においては、ただ赤が赤として意識されているだけであり、そこには本来、「その花は赤い」という判断も、花を知覚しているという意識もない。これが「色を見、音を聞く刹那」の意味するところである。西田はこれを第四編第一章で「未だ主客の分離なく、物我一体、ただ、一事実あるのみである」[42]という言葉でいい表している。
さて西田は「経験するというのは事実そのままに知るの意である」と述べている。いまやわれわれはこの意味を理解するはずだ。医者は婦人の純粋経験を「真実であって偽りではなかった」という干からびた抽象的な論理によって置き換えてしまった。私は、いやわれわれは、実在の真景を遠ざかろうとする者たちに反駁する。われわれの使命は、神秘体験をまやかしとして処理したがる論理実証主義者の意図に反して、純粋経験を人間存在の根本原理として擁護すること、事実そのままを受け入れるような経験の姿勢から出発することに他ならない。そのことを信じるわれわれの前には、実在の真景が開かれている。
こうしてみると、西田が独我論者のように聞こえてくるかもしれないが、その見解は間違っている。西田もいうように「個人あって経験あるにあらず、経験あって個人あるのである。個人的区別よりも経験が根本的であるという考えから独我論を脱することが出来た」[43]。なるほど個人が経験にとって二次的であるならば、経験が自我の可能性の条件ということになる。デカルトの場合には、疑う「私」と疑われる「対象」とを前提することで、すべての懐疑が遂行されたのであるが、しかし西田はこの前提そのものにも懐疑の目を向けたのであった。よって主客二元論は枠組みを取り除かれ、そのときに残るのはただ純粋な、直接的な経験のみである。よって西田は独我論者であるという旨の反論には答えることができた。
夢と現の境界は、真に経験そのままの状態、すなわち純粋経験によって合一する。私が『燕石博物誌』のなかで語った、竹林での悪夢の経験こそ、実在の真景であると確信する。人間が鮮烈な体験を興奮と情熱を以て語ろうとすることを「科学的にありえない」と否定することは簡単である。しかし、「客観的に見て明確な真実が存在する」という考え方は今にでも過去のものとなるだろう。
結論
われわれの探索は「「私」とは何か」というパスカルの問いに始まった。それは時代とともに反復され、いまここでも提示され直した問いである。古くは「汝自身を知れ(γνῶθι σεαυτόν、グノーセイ・セアウトン)」[1]というデルポイの神殿の言葉に始まり、デカルトによる徹底的な懐疑を経て思惟と定義されたこのものは、数奇な運命をたどってきた。ついでプラトン=アリストテレスからデカルト=カントにいたるまでの哲学的概念の転回。ラ・メトリは「私」の根拠の一切を剥奪する唯物論者として登場したが、これはリベットに代表される脳神経科学の系譜にある。しかしラ・メトリ流の唯物論は、主観を置き去りにして客観だけを認める物理主義に執心するあまり、客観的認識がいかなる主観的条件のもとで維持されるかを問わずにいた。「言語の恣意性」を携えて近代西洋知批判を敢行したソシュールは、名称目録的言語観に対して、記号学の観点から言語の根本原理である「差異」に注目し、言語が持つ主観的性質を明らかにした。カントは超越論哲学によって認識の可能性の条件を問い、客観的認識が主観的条件を前提することを指摘する。ソシュールにおいては言語論的転回として、カントにおいては認識論的転回として、客観から主観へのパラダイムの移行が達成される。さらに「私の心だけが確実に存在する」という、いかにも人口に膾炙した独我論がウィトゲンシュタインやドゥルーズによって反駁される過程をわれわれは見てきた。キルケゴールに代表される実存主義は人間存在の哲学であり、個別的現実的具体的な思考であった。
しかし私は、これらのいずれも相対性精神学の本意ではないと信じる。相対性精神学における「主観」とは「経験」である。それはイギリス経験論から始まり、バークリー、ヒュームによって頂点に達した。経験論は「知性のうちには諸感覚器官のなかにまず存在しなかったものは何もない」とする立場であり、「経験のうちにないものは理性のうちにない」と考える態度を備えていた。理性とはデカルト的主体のように、定点的に思惟するような自我のことをいう。経験論は、「人間は生まれながらにして知性や理性を備える」とする生得論に対して真っ向から批判を与えるものだった。あらゆる客観的認識も、科学的知識も、経験から学び得たものでしかありえず、経験こそが第一の原理である。
ロックは、モリニューの指摘を受け、「触覚で立方体と球が区別できても、触覚的にこう感じられるものが視覚にどう現れるかは実際に経験しなければわからない」との結論に達した。具体的な経験をすることで初めて具体的な認識が可能になるのだから、経験は認識に先立ち、認識を可能にさせる唯一の原理である。ロックは知覚される性質を一次性質と二次性質に区別し、前者は物自体=客観に由来し、後者は感覚器官=主観に由来するとした。一方でバークリーは二次性質だけでなく一次性質も心の中にあるとし、両者の区別を解体する。それによって導かれた結論が、観念のすべては心の中にあるという「観念論」であり、それは「存在するとは知覚されることである」という極端なまでの「物質否定論」的な命題として花開いたのだった。また、バークリーが現代物理学における量子力学的見解の先駆けとしても紹介された。ヒュームはこの態度を、さらに推し進める方向へ向かう。
ヒュームは「印象」という、自らが強い知覚として定義した直接的所与の地平を持ち出した。また、観念は印象という一次的な知覚によって再構築されるとし、それが観念連合という引力の作用として現前するのだった。バークリーにおいては認められていた魂の実在=自我が、観念連合という超出によって成立するということが確認される。経験された観念を結びつけるような変容が、自我という個人の契機である。そして「精神はどのようにして一つの主体へと生成するのか」という問いこそ、ヒュームによるものであって、カントによる超越論的領野は、これを台無しにするものとして明らかにされた。
「真実は主観の中にある」という相対性精神学の命題に、何を認めるべきか、何を持ち込むべきかという問いに答えることができる。それはすべてを観念として認める「観念論」である。「知性のうちには諸感覚器官のなかにまず存在しなかったものは何もない」と述べ、生得論を否定したイギリス経験論の徒であっても、ロックがこれに与さないことは明白であろう。バークリーは観念の一元論によって、客観的事実が観念に由来することを主張した。次に、ヒュームは「印象」を引き合いに出し、観念がこの強い知覚にとって二次的な構築物であることを明らかにした。ヒュームは経験論の最も先鋭的な例である。両者に共通するのは、観念という心的構成要素のみを実在として認める観念論的な姿勢であり、経験という直接的所与を人間存在の第一原理として置く経験論的な態度である。私はこの二人の観念論的、経験論的立場を引き継ぎ、相対性精神学における基本原理として認めたい。
先に見たように、ベルクソンは合理的経験を一般的経験から区別した点で、観念論者として数えることができる。ベルクソンは、普段固定的な静物として見られるような実在を、時間的な「持続」という面と照らし合わせながら、あるがままの流れとして記述することを試みた哲学者である。外延的、等質的、空間的な偽りの実在に対して、持続は強度、分割不可能性、異質性の連続性、相互浸透的なメロディーの論理として理解されるものであった。さらに、持続は主観が持つ間断なき意識の流れと結びつき、それが「直観」という理解の仕方として提示される。さらにベルクソンの哲学は観念論だけでなく、唯物論的側面も持ち合わせていることが発見され、ここに「魂は物質から構成されている」という主張の根拠が指し示された。「主観」と「魂=物質」の総合という、傍から見て矛盾の産物としか思えないような相対性精神学の難問を超克し、唯物論的相対性精神学という新しい相貌の可能性が検討された。
最後に引き合いに出されたのは、日本の哲学者である西田幾多郎である。西田はあらゆる人工的仮定を捨て去るデカルトと同様の方法的懐疑を経て、デカルト的主体さえも疑って、われわれの「直覚的経験の事実」を実在として認める。西田の思想の核心にあるのは「純粋経験」であった。純粋経験とは、「事実そのままに知る」ことであり、「全く自己の細工を棄てて、事実に従うて知る」ことである。それは「赤が赤として意識されているだけ」の、「色を見、音を聞く刹那」であり、「未だ主もなく客も」ない主客未分の領域であり、「知識とその対象とが全く合一」しているような原始の経験である。そこにおいて、純粋経験と直接経験は合一する。そして純粋経験こそが「実在の真景」であり、物質現象も、意識現象も、この純粋経験からいわば派生的に生じたものにすぎない。「個人あって経験あるにあらず、経験あって個人あるのである」という西田の言葉は、このことを端的に表したものであるだろう。
われわれはバークリー=ヒューム流の観念論から教訓を引き出したが、これと同様に、ベルクソン=西田に掉さす経験論の流れから、われわれの望む答えを導出することが可能となる。「夢と現実は区別はするが同じもの」という相対性精神学の命題に、何を認めるべきか、何を持ち込むべきかという問いに答えることができる[2]。夢と現実を区別するとは、習慣から、端に習慣からだ。デカルトもいうように、「しかしこの疑いは、ただ真理の観想に限らねばならない」[3]。同じものとは、起源が同じであるということに他ならない。「純粋持続」は、本質的に分割されえない間断なき意識の流れに現れるものであった。直観から分析へ向かう道はあれど、分析から直観へ至ることはできない。「純粋経験」は、主観と客観の分離が遂行されるよりも前の真景であり、刹那のただなかに、自己の細工を棄て、目の前にあるそのままの姿を事実に従って経験することにほかならない。純粋経験は、純粋持続とも、印象ともいいかえることができよう。これは本質的に同じ事態を示すものであるからだ。私が『燕石博物誌』のなかで語ったことは、あとから反省的に判断を下すことはあっても、しかし「ただわれわれの直覚的経験の事実、すなわち意識現象についての知識」を疑うことはできない。
われわれの試みは、本質的な点においてはその目的を果たしたといえよう。その目的とは「何を相対性精神学として認めるか」であり、「相対性精神学に何を持ち込むべきか」ということであった。なるほどバークリーとヒュームによって「印象」が、ベルクソンによって「純粋持続」と「直観」が、西田によって「純粋経験」が提示され、これが相対性精神学における「主観」であるという結論が導かれた。四者に共通して現れるのは、経験を人間存在の根本原理として置く、経験論的態度である。相対性精神学は経験の学であり、経験という直接的所与を人間存在の原理に据えた方法論である。私はここに、相対性精神学の理念の具体的な可能性を示したと信じる。体系を築くのは、この講演を聞いた諸君が自らの可能性へ向けて出発してから、先のことである。
こうして、「真実は主観の中にある」という言葉は、新しい意味を得たことになる。実証的な学問は、世界を喪失した学問である。世界を「経験」という根本原理において取りもどすために、自己の細工を棄てて、事実に従って知ることが必要である。アウグスティヌスは次のようにいう。「外に行こうとしないで、汝自身のうちに帰れ。真理は人の内部に宿っている」[4]と。
注釈
序論
[1]ヴィクトル・コンドリア大学脳科学研究所のこと。精神生理学会の招きにより、二〇九六年七月一六日と七月二一日の二日間にわたり「相対性精神学概論」という題で行われた講演の全体に相当する。
[2]著者は一人称を意図的にいい違えている。これには、さまざまな説がある。アメリカの物理学者・数学者のジャック・H・ヘザリングトンは、一九七五年、科学論文誌『フィジカル・レビュー・レターズ』に、研究成果を発表しようとしていたが、単独著者の論文であるにもかかわらず文中で一人称複数が用いられている(尊厳の複数)ため、この論文はリジェクトされるであろうとの指摘を友人から受けた。そこでヘザリングトンは、一人称単数へと変更するため論文をタイプライターで打ち直すことに時間を費やしたり、あるいは共著者を招き入れるのではなく、架空の共著者を作り出すことを選択した。それが、チェスターと名付けられたシャム猫のF・D・C・ウィラードである。著者が『燕石博物誌』だけでなく本文中でも言及した「シュレーディンガーの化猫」との関係が示唆されているのではないか。あるいは、ザミャーチンの小説『われら』を想起させもする。ザミャーチンは、科学技術だけでなく、科学技術と結びついた近代合理主義・設計主義の危険性を指摘している。一人称が複数形であるということは、もはや個を必要としなくなったということであり、私たちが科学主義的全体主義の中に片足を乗せつつあることの指摘としてもとれる。またドゥルーズがガタリと著した『千のプラトー』の序文は、「二人それぞれが数人だったのだから、それだけでもう多数になっていた。〔…〕今度はわれわれ二人の見分けがつかなくなるように。われわれ自身ではなく、われわれを行動させ感じさせ、あるいは思考させているものを、知覚できなくするために」という「二人で書くこと」の意味を問うことから始まる。レイテンシー当人も共同執筆者である可能性がある。
[3]ヴィルヘルム・シュテッカーリングは、訳者の友人フロイト狂いがChatGPTで遊んでいた経緯から生まれた架空の思想家である。それによるとヴィルヘルム・シュテッカーリングは相対性精神学の開祖であり、これは人間の心理的な相対性について研究する学問分野の一つだという。著書に『相対性精神学』『セックス・エコノミー(性経済)』『性とキャラクター』がある。相対性精神学黎明期を代表する著作にはモース・ハルトマン『相対性理論と文化の危機』やオットー・ランクによる『現代人の心的状態』などが挙げられている。当然でたらめである。なお、訳者の勝手によって主著に『現代心理学と実存解明』($${\textit{Moderne Psychologie und Exstenzerhellung}}$$)があるという設定が付け加えられた。
[4]『生成と消滅の精神史』
[5]『ミシェル・フーコー』六〇頁。
[6]『パンセ』二三六頁。「「私」とはなにか。〔…〕身体のなかにも、魂のなかにもないとするなら、この「私」というものはいったいどこにあるのだろう」(ブランシュヴィック版、三二三)
[7]『夢違科学世紀』
[8]『省察』六一頁。
第一章
[1]『哲学原理』二三-二四頁。
[2]『省察』六一頁。
[3]前掲書、六二頁。
[4]前掲書、六三頁。
[5]前掲書、七一頁。
[6]古代ギリシャの数学者アルキメデスは、てこの原理を発見したことで知られる。この言葉はアレキサンドリアのパップスが引用したとされる。
[7]『哲学原理』三九頁。
[8]前掲書、九六頁。
[9]前掲書、六一頁。
[10]『国家』(下)第七巻。
[11]『試金石の天秤』、ヒルベルト『自然認識の論理』から。
[12]『技術の哲学』一三一頁。ガリレオは『新科学対話』の中で、「いや、大した実験をしなくても簡単にそして確実に、二つの物体が同じ材料から出来ていて、要するにアリストテレスの言っているようなものでありさえすれば、重い物体の運動は軽い物体より早くはないことが証明できます」と述べている。さらには、『天文対話』のなかで、地球が運動することと物体が地上で垂直な落下運動をすることとが矛盾するものではないことを示すために、動く船のマストの上から物体を落下させる実験を行えば、そのことを示せると主張しながら、実験も不要なほど自明であると述べている。このような事情のために、アレクサンドル・コイレは「よい自然学はアプリオリに作られる」と述べており、また、ポール・ファイヤアーベントは、実験なしでも説得力をもつガリレオの議論の仕方にレトリックの力を見いだしている。エトムント・フッサールは、ガリレオによって、数学的な理念の世界と日常的経験の世界とが「すり替えられた」と述べている。
[13]この議論は主に「主観と客観」を参考にした。
[14]『心とは何か』七一頁。
[15]『心とは何か』八一頁。
[16]『エンチクロペディー』、長谷川『新しいヘーゲル』七九頁から。
[17]『美学講義』、長谷川『新しいヘーゲル』九五頁から。
[18]『精神現象学』(上)二八頁。
第二章
[1]『人間機械論』四九頁。一方でパスカルはこれと反対のことをいっている。「魂の非物質性。自分の情念を制御した哲学者たち。どんな物質にそれができたのだろう」(『パンセ』ブランシュヴィック版、三四九)。ここにおいて「自分の情念を制御した哲学者たち」とはストア派のことを指す。
[2]前掲書、一〇一頁。
[3]前掲書、九二頁。
[4]前掲書、一一一頁。
[5]前掲書、一一九頁。
[6]アインシュタインにとっての神の言及に、次のようなものが見つかった。「牧師さん、それは人間が神様の姿に似せられて造られた──つまり擬人化だが──などと教える宗教じゃないんだ。人間には無限の次元(ディメンション)があり、その良心の中に神を見い出した。この宗教では、世界が合理的であり、人は世界を思い、その法則を使って共に創造することが究極の神である、という教え以外に教義はない。ただし、そこには条件が二つだけある。一つは、不可解に見えるものが日常のものと同じほど重要だということ。二つ目は、われわれの能力は鈍感で、表面的な知識や単純な美しさしか理解できないということだ。しかし、直観を通すことによって、人の心は、われわれ自身と世界について、より大きな理解をもたらしてくれるんだ」(ヘルマンス『アインシュタイン、神を語る』)
[7]『エチカ』(『世界の名著 スピノザ ライプニッツ』)七八頁。
[8]デカルトは「私が神を理解するところの観念、すなわち、永遠で、無限で、全知で、全能で、自己以外のいっさいのものの創造者である神を理解するところの観念は、有限な実体を表示するところの観念よりも、明らかにいっそう多くの表現的実在性をそれ自身のうちに含んでいるのである」(『省察』九二頁)と表現する。また「作用的かつ全体的な原因のうちには、少なくとも、この原因の結果のうちにあると同等のものがなくてはならぬ」ということから、「より完全なもの、いいかえると、より多くの実在性をそれ自身のうちに含むものは、より不完全なものからは生じえない、ということも帰結する」(九二頁)。それによって「神は必然的に存在する、と結論しなくてはならない」(九八頁)というのが、デカルトによる神の存在論的証明である。
[9]『エチカ』(『世界の名著 スピノザ ライプニッツ』)一七四頁。
[10]前掲書、一六一頁。
[11]『自然認識の論理』
[12]『クオリア入門』一五頁。
[13]『名づけられないもの』二二三頁。
第三章
[1]この比喩は『ソシュールの思想』に登場する。
[2]『ソシュールを読む』一三八頁。
[3]『一般言語学講義』から、同掲書、五三頁。
[4]『哲学マップ』七五-七六頁。
[5]『相対性精神学序論』
[6]『論理哲学論考』一一二頁。
[7]『ランボーはなぜ詩を棄てたのか』九六頁。
[8]『はじめてのウィトゲンシュタイン』六〇頁。
[9]「そういう機械〔は〕、われわれが他人に自分の考えを述べるときのように、ことばを用いたり、またはほかの記号を組み立てて用いたりすることは、けっしてなしえないだろう〔……〕。というのは、なるほど一つの機械がことばを発しうるように、さらにはその器官になんらかの変化を起こす物体的作用に応じて、なんらかのことばを発しうるようにさえ──たとえばどこかをさわると「なんのご用ですか」と問うとか、ほかの場所にさわると「痛い」と叫ぶとか──つくられている、と考えることができる。けれどもそういう機械が、自分の前でいわれるすべてのことの意味に応じたこたえをするために、ことばをさまざまに配列するとは考えられないのである」(『方法序説』、『観念論の教室』六五-六六頁)
[10]「超越論的主観性の外部というのは無意味」(『デカルト的省察』一五三頁)とフッサールは述べる。しかし、彼の主張するのは、そのような「外部」を想定して、いかにしてそこに至るか、という問いを立てることがそもそも間違いで、それは実は「無意味」な問いを立てていたのだ、ということである。論者のなかには、この「外部」にこそ「他者」を見ようとする者もいるが、フッサールは「他者」をそのように考えていない。彼にとって「他者」とは「他の超越論的主観性」であり、それは、ともに「超越論的間主観性」を形成するものであって、「超越論的主観性の外部」という時の「超越論的主観性」とは「超越論的間主観性」だということになると、その「外部」に「他者」がいるわけではない。(『デカルト的省察』訳注)
[11]『ドゥルーズ・コレクションⅠ』九頁。
[12]同掲書、十頁。
[13]『ドゥルーズの哲学原理』五三頁。
[14]『意味の論理学』、同掲書五四頁から。
[15]『意味の論理学』、同掲書五四-五五頁から。
[16]『意味の論理学』、同掲書五五頁から。
[17]『エンチクロペディー』、『新しいヘーゲル』七七頁から。
[18]『新しいヘーゲル』一七四-一七六頁。
[19]『世界の名著 キルケゴール』二〇-二一頁。
[20]『ヤスパース 人と思想』
[21]『死にいたる病』(『世界の名著 キルケゴール』)四三五頁。
[22]『実存主義』六六-六七頁。
第四章
[1]『ドゥルーズの「アベセデール」』
[2]『千のプラトー』にある「道徳の地質学」は、「チャレンジャー教授、あのコナン・ドイルでおなじみの、地球を機械で責めて唸り声をあげさせたチャレンジャー先生が、例によって猿顔負けの気まぐれさで地質学や生物学の概説をあれこれミックスして、講演を行なった」という体裁で書かれている。
[3]「時間からの影」(『狂気の山脈にて』)
[4]『「知」の欺瞞』
[5]『物質と記憶』二八頁。
[6]「心と体」(『精神のエネルギー』)
[7]「講義 信ずることと知ること」(『学生との対話』三九-四〇頁)
[8]『観念論の教室』七一-八五頁
[9]『人間知性論』、同掲書七七頁。
[10]同、同掲書七七-七八頁。
[11]同、同掲書七九頁。
[12]『観念論の教室』八四頁。
[13]同掲書、一〇四頁。
[14]同掲書、一四六-一四七頁。
[15]同掲書、一四七-一四八頁。
[16]同掲書、一四九頁。
[17]『人知原理論』、『観念論の教室』一五〇頁。
[18]『量子とはなんだろう』一三六頁。
[19]同掲書、一二一頁。
[20]『量子力学(Ⅰ)』一七-一八頁。
[21]『哲学マップ』六五頁。
[22]『ヒューム』三六頁。
[23]同掲書、二八-三〇頁。
[24]同掲書、三〇頁。
[25]同掲書、三二-三四頁。
[26]同掲書、三四頁。
[27]「人間知性論摘要」(『人間知性研究』二〇八頁)
[28]『ドゥルーズの哲学原理』四一-四八頁。
[29]『純粋理性批判』一四九頁。
[30]『差異と反復』(上)三三一頁。「明らかにカントは、そのようにして、先験的と呼ばれる諸構造を、心理学的な意識の経験的諸行為を引き写すことによって描いている」
第五章
[1]「〈生きている人のまぼろし〉と〈心霊研究〉」(『精神のエネルギー』)
[2]「講義 信ずることと知ること」(『学生との対話』三四-三七頁)
[3]『ベルクソンの哲学』一一-一四頁。
[4]同掲書、二三-二四頁。
[5]同掲書、六五-六八頁。
[6]『臨床心理学小史』二九頁。「フェヒナーの述べる精神物理学とは、ある刺激に対し、それが変化したことに気付くために加えるべき刺激量の比が一定であることを前提としつつ、微分と積分を利用しながら感覚の量を表すものである。そこでは感覚の変化における最小差異を見出しながら、感覚の量を導く技法がとられている。またデルブーフの中間区分法とは、ある感覚と別の感覚とのあいだの中間を測定することによって、感覚にとっての等しさの対比のようなものを作り出し、結局は感覚の量を数値的に規定するものである。ベルクソンはこの方法も、常識に訴えやすい事例を利用し精神物理学を転回しただけのものと考える。いずれにせよこれらが、感覚を空間化させる試みであることには変わりがない」(『ベルクソンの哲学』九四頁)
[7]『ベルクソンの哲学』六九-七〇頁。
[8]ベルクソンによる似た例えに、「砂糖水の比喩」がある。「私が一杯の砂糖水を準備する場合、何をしようと、私は砂糖が溶けるのを待たなければならない。この些事はたくさんのことを教えてくれる。なぜなら私が待たなければならない時間はもはや、物質世界の歴史空間で一挙に広がるときでさえ、この歴史全体に沿って同じように適用される数学的時間ではないからだ。この時間は私の待ちきれなさ、つまり、好きに伸ばしたり縮めたりできない私自身の持続のある部分に一致する。この時間はもはや考えられたものではなく、生きられたものである」(『創造的進化』二四頁)
[9]『ベルクソンの哲学』七六-七七頁。
[10]算数を持ち出して説明してみよう。アキレスと亀は$${x}$$=100m離れていて、アキレスは$${v_a}$$=10m/s、亀は$${v_b}$$=1m/sと一定の速度移動しているとする(大した速さで走る亀だ)。最初にアキレスが亀がもといた地点に追いつく時間は、$${t_1}$$=$${\frac {x} {v_a}}$$=10sである。この間に、亀は$${v_b}$$$${t_1}$$=10mだけ移動している。さらにアキレスが10mだけ移動するのにかかる時間は、$${t_2}$$=$${\frac {{v_b}{t_1}} {v_a}}$$=$${\frac {{xv_a}^2} {{v_a}^2}}$$=1sである。この間に、亀は$${{v_b}{t_1}}$$=1mだけ移動している。この議論を繰り返せば、$${t_3}$$=$${\frac {{v_b}{t_2}} {v_a}}$$=$${\frac {{xv_b}^3} {{v_a}^3}}$$であり、一般の$${n∈\N}$$に対しては、$${t_n}$$=$${x({\frac {v_b} {v_a}})^n}$$=$${100\cdot{\frac 1 {10^n}}}$$である。$${k}$$回までのステップでかかる時間の合計を、$${S_k}$$とする。すなわち、
$${{S_k}}$$=$${{\sum_{n=1}^{k}}{t_n}}$$=$${{\sum_{n=1}^{k}} 100\cdot {\frac 1 {10^n}}}$$
とする。そして、アキレスが亀においつくまでの時間$${T}$$とは、$${k}$$が大きくなるにつれて$${S_k}$$が限りなく近づいていく値、すなわち極限値である。
$${T}$$=$${\lim_{k \to \infty} S_k}$$=$${\lim_{k \to \infty} {\sum_{n=1}^{k}}{t_n}}$$
$${t_n}$$を足し合わせる行為は、ゼノンのいうように無限に行うことができる。しかし、アキレスが亀のもといた地点まで移動するのにかかる時間$${t_n}$$=$${100\cdot{\frac 1 {10^n}}}$$は、$${n}$$が大きくなるにつれて小さくなり、ほんの一瞬の時間しかない。そのため、かかる時間の合計は有限となる。
確かめてみよう。等比数列の和の公式より、
$${S_k}$$=$${10\cdot\frac{1-\frac{1}{10^k}}{1-\frac{1}{10}}}$$=$${\frac{100}{9}(1-\frac{1}{10^k})}$$
となる。ここで、$${k}$$が大きくなるとき、$${\frac {1} {10^k}}$$は限りなく0に近づく。よって、
$${T}$$=$${\lim_{k \to \infty} S_k}$$=$${\frac {100} {9}}$$
となる。およそ11秒でアキレスは亀に追いつくことがわかった。
[11]ベルクソンは一九一一年頃から相対性理論に関心を抱くようになったらしいが、一九二一年の五月二二日に、ジャック・シュヴァリエがヴィタル街のベルクソンの住居を訪ねた際、次のように語ったという。「……わたしはこのところ大分前から相対性理論の勉強をしている。数学をまたやり始めているわけだが、相対性理論と、空間及び空間的時間についてのわたしの諸見解とが一致していることを指摘するために、覚書を一つ発表するだけにしておこうと思っている。われわれの空間は、彼のいうように、曲がった空間なのかも知れない」。シュヴァリエは一九二二年の二月七日にもまた、ベルクソンが次のように語ったことを報告している。「……現在私は相対性理論を研究している。わたしはアインシュタインと議論をして見たいと思っている」。この「アインシュタインと議論をして見たい」というベルクソンの希望は、一九二二年四月六日に実現する。フランス哲学界の招きでパリに来ていたアインシュタインと言葉を交わし合う機会をベルクソンは得る。あとにも先にも、この二人が公の席で会談を行ったのは、この時だけである。一つの注釈に許された紙幅は限られているため、概要のみの言及としたい。時間が問題となっていることはいうまでもないが、ベルクソンは、常識の立場に立って、知覚に基づく「普遍的時間という概念」を仮定しながらも、この仮定には「相対性理論と相容れないようなものは何もありません」といっている。一方、ベルクソンによれば、アインシュタインは、その相対性理論において、「多数時間」というものを問題にしているが、これらの「多数時間」は、「そのすべてが同程度の現実性を主張しえるものとは決して言えない」のである。結局のところ、アインシュタイン自身は、「物理学の時間」とは別に、「心理的時間」の存在を認めていることが理解できる。しかしベルクソンとアインシュタインの時間の議論が円満に終わったとは到底思えない。ベルクソンは相対性理論を誤解しているとの指摘を受け、後年『持続と同時性』で展開した自説を撤回している(「アインシュタインとベルクソンⅠ」)。相対性精神学の「相対性」が、相対性理論に由来しているのであれば、心理的時間と物理学的時間について議論を取り交わしたベルクソンとアインシュタインの交流はとりわけ深い意味合いを持つに違いない。
[12]「方法としての直観」(『思考と動き』四四-四五頁)
[13]同掲書、四八頁。
[14]「一九八〇年代はじめに映画論の講義を始めたころ、ドゥルーズは、「多くの人がベルクソンの哲学を一種の観念論として受け取っているが、実はベルクソンほど唯物論的な思想家はいない」と語ったことがある。それがとても印象的だった」(『ドゥルーズ 流動の哲学』五〇頁)。ドゥルーズはベルクソンについての革新的な解釈で知られるが、本文中で展開される唯物論的ベルクソン像はドゥルーズの文脈に依拠している。
[15]ここでは、「真実は主観の中にある」と「魂は物質から構成されている」という、相反する観念論と唯物論の架け橋として、ドゥルーズの展開する唯物論的ベルクソンをヒントに記述しているが、あくまでも可能性の一端を提示することにとどまっている。そもそも、この二つの命題を統合すること自体がいくらか無謀な企てであるのだ。「主観が真実である」と「主観は物質から構成されている」は明らかな矛盾である。「主観≠魂」とすることによって、この難問を回避する術はなくもないだろうが、そのためには理論を根底から刷新しなければならない。そのため、この議論を無理にでも理解してもらう必要はないと考える。
[16]『ドゥルーズ 流動の哲学』五〇頁。「ベルクソンにおける差異の概念」(『ドゥルーズ・コレクションⅠ』一九五頁)のなかで、ドゥルーズは「対象に対して、ただその対象だけに適した寸法で概念を裁つこと、まさにこのものに当てはまるが故に、なお概念と呼び得るかどうかの際にあるような概念」を作り上げようといっている。
[17]同掲書、五〇頁。「小林秀雄や西田幾多郎も、このような観念論的ベルクソン解釈と決して無縁ではなかった」
[18]『東方求聞史紀』に登場する正体不明のメモ。「夜の竹林ってこんなに迷う物だったかしら? 携帯電話も繋がる気配はないし、GPSも効かないし、珍しい天然の筍も手に入ったし、今日はこの辺で休もうかな……って今は夢の中だったっけ? しょうがないわ、もう少し歩き回ってみようかしら。それにしても満天の星空ねえ。未聞ぶりといい、澄んだ空といい、大昔の日本みたいだなぁ。タイムスリップしている? ホーキングの時間の矢逆転は本当だった? これで妖怪がいなければもっと楽しいんだけどね。そうか、もしかしたら、夢の世界とは魂の構成物質の記憶かも知れないわ。妖怪は恐怖の記憶の象徴で」
[19]『鳥船遺跡』による。この事例をユングの集合的無意識と結びつけて考える試みはすでに「相対性精神学とは何か」においてなされている。
[20]『物質と記憶』二五頁。
[21]『善の研究』一一八頁。
[22]同掲書、一一六頁。
[23]同掲書、一一六頁。
[24]同掲書、一一六頁。
[25]同掲書、二六頁。
[26]同掲書、一四二頁。
[27]同掲書、一一八頁。
[28]同掲書、一二〇-一二一頁
[29]同掲書、一一八頁。
[30]同掲書、一三〇頁。
[31]同掲書、一三一頁。
[32]同掲書、一三四頁。西田はバークリーとの相違点をここで述べている。「バークレーの有即知というのも余の真意に適しない。直接の実在は受動的のものでない、独立自全の活動である。有即活動とでもいった方がよい」
[33]同掲書、一八九頁。
[34]同掲書、二〇七頁。
[35]同掲書、一九四頁。
[36]同掲書、一四五頁。
[37]同掲書、一三五頁。
[38]同掲書、一二頁。
[39]同掲書、二六頁。
[40]『哲学論文集 第三』「序」(『西田幾多郎『善の研究』を読む』二七一頁)
[41]『西田幾多郎『善の研究』を読む』二一二頁。
[42]『善の研究』三五九頁。
[43]同掲書、一二頁。
結論
[1]古代ギリシア、デルポイの神殿の玄関の柱に刻まれていたという言葉で、(神が人間に向かって)「身のほどを知れ」(自分が死すべき存在であることを忘れるな)という意味の格言と解されてきた。しかし、(プラトンの描く)ソクラテスは、それを「自分の無知を知」り、「自分の魂を配慮」し、いかに生きるべきかを考察することを命じる要求と捉えた。いまそれを著者は、普遍的な自己認識の道こそが相対性精神学の道である、という意味と解しようとしている。
[2]「真実は主観の中にある」に対して、「夢と現実は区別はするが同じ物である」を西田流の純粋経験にそって理解す場合、次のような反論が予想される。西田の純粋経験は主客未分の領域にある。であれば、主観と客観の区別は存在せず、ただ真実在だけが認められることになり、西田の純粋経験を「真実は主観の中にある」に持ち込むことはできない。しかし、西田は「さらば、疑うにも疑いようのない直接の知識とは何であるか。そはただ我々の直覚的経験の事実すなわち意識現象についての知識あるのみである」と述べている。「意識現象についての知識」とは、主観のことであるだろう。この場合の主観とは、真実在を示すための便宜上の表現であると認めることができる。よって、「真実は主観の中にある」と「夢と現実は区別はするが同じ物である」とは矛盾しない。
[3]『哲学原理』三六頁。「しかしこの疑いは、ただ真理の観想に限らねばならない。何となれば、実生活に関しては、我々が疑いから抜け出すことができる前に、しばしば事を為すべき機会の過ぎ去ることがあるから、我々は余儀なく、単に尤もらしく見えることを採用し、或いは二つのことのうち、一つが他に比べて尤もらしく見えない場合にも、時にはいずれかを選ぶことが珍らしくはないからである」
[4]アウグスティヌス『真なる宗教』(または『真の宗教に就て』一一五頁)からの引用。アウグスティヌスは、ここで引用された文に続けて、次のように述べている。「そしてもし汝の本性が可変的であるのを見いだすなら、汝自身をも超越せよ」と。アウグスティヌスは自己の「内部」に止まるのではなく、そこから自己を超越する道を探る。著者も本来であればむしろ、ここの部分まで引用することによって、純粋経験という抽象的な理念の提示からさらに進んで、相対性精神学の実践的・具体的体系とその探求についても論じ、それに喩えるべきだったであろう。
[x]あとがきに代えて。この作品については、あまりに多くのことを詰め込みすぎたので、私も語るすべを持たない。この作品は初学者が理解できるように書いてはいないので、文章を読んで理解できなくても読者の責任ではない。理解できないものを理解できないなりに楽しむことが私たちにはできるはずだからだ。あらゆるところに遊び心をばらまいた。例えの内容や固有名詞から、文体や形式にいたるまで、なんでも手当たり次第に利用した。今度は現実と非現実の見分けがつかなくなるように。なお、この作品の内容は作者の独自見解であり、公式設定を保証するものではない。皆さんの解釈の幅を狭めるものでも当然ない。
参考文献
パスカル『パンセ』前田陽一、由木康訳、中央公論新社、二〇一八年。
下西風澄『生成と消滅の精神史』文藝春秋、二〇二二年。
慎改康之『ミシェル・フーコー』岩波書店、二〇一九年
デカルト『省察・情念論』井上庄七、森啓、野田又夫訳、中央公論新社、二〇〇二年。
デカルト『哲学原理』桂寿一訳、岩波書店、一九六四年。
冨田恭彦『デカルト入門講義』筑摩書房、二〇一九年。
冨田恭彦『観念論の教室』筑摩書房、二〇一五年。
プラトン『国家』藤沢令夫訳、岩波書店、一九七九年。
村田純一『技術の哲学』講談社、二〇二三年。
近藤和敬『ドゥルーズとガタリの『哲学とは何か』を精読する』講談社、二〇二〇年。
アリストテレス『心とは何か』桑子敏雄訳、講談社、一九九九年。
ヘーゲル『精神現象学』熊野純彦訳、筑摩書房、二〇一八年。
長谷川宏『新しいヘーゲル』講談社、一九九七年。
ラ・メトリ『人間機械論』杉捷夫訳、一九五七年。
スピノザ『エチカ』工藤喜作、斎藤博訳(『世界の名著 スピノザ ライプニッツ』)中央公論新社、一九六九年。
茂木健一郎『クオリア入門』筑摩書房、二〇〇六年。
ベケット『名づけられないもの』宇野邦一訳、河出書房新社、二〇一九年。
丸山圭三郎『ソシュールを読む』講談社、二〇一二年。
丸山圭三郎『ソシュールの思想』岩波書店、一九八一年。
貫成人『哲学マップ』筑摩書房、二〇〇四年。
べいこん『相対性精神学序論』紅白幕、二〇二二年。
ヴィトゲンシュタイン『論理哲学論考』丘沢静也訳、光文社、二〇一四年。
古田徹也『はじめてのウィトゲンシュタイン』NHKブックス、二〇二〇年。
奥本大三郎『ランボーはなぜ詩を捨てたのか』集英社、二〇二一年。
ドゥルーズ『ドゥルーズ・コレクションⅠ 哲学』宇野邦一監修、宇野邦一、小沢秋広、小泉義之、財津理、杉村昌昭、鈴木創士、立川健二、前田英樹、松葉祥一、三脇康生訳、河出書房新社、二〇一五年。
ドゥルーズ『差異と反復』財津理訳、河出書房新社、二〇一〇年。
ドゥルーズ&クレソン『ヒューム』合田正人訳、筑摩書房、二〇〇〇年。
國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』岩波書店、二〇一三年。
キルケゴール『死にいたる病』(『世界の名著 キルケゴール』)一九六六年。
松浪信三郎『実存主義』中央公論新社、一九六二年
宇都宮芳明『ヤスパース 人と思想』清水書院、一九六九年。
ラヴクラフト『狂気の山脈にて』南篠竹則訳、新潮社、二〇二〇年。
ソーカル&ブリクモン『知の欺瞞』田崎晴明、大野克嗣、堀茂樹訳、岩波書店、二〇一二年。
オーサダハル「相対性精神学とはなにか」(『幻想茶房合同2』)幻想茶房、二〇二二年。
松浦壮『量子とはなんだろう』講談社、二〇二〇年。
小出昭一郎『量子力学(Ⅰ)』裳華房、一九九〇年。
ベルクソン『物質と記憶』杉山直樹訳、講談社、二〇一九年。
ベルクソン『創造的進化』合田正人、松井久訳、筑摩書房、二〇一〇年。
ベルクソン『精神のエネルギー』原章二訳、平凡社、二〇一二年。
小林秀雄『学生との対話』新潮社、二〇一七年。
檜垣達哉『ベルクソン 生成する実在の肯定』講談社、二〇二二年。
サトウタツヤ『臨床心理学小史』筑摩書房、二〇二二年
ヒューム『人間知性研究 付・人間本性論摘要』斎藤繁雄、一ノ瀬正樹訳、法政大学出版局、二〇〇四年。
カント『純粋理性批判』熊野純彦訳、作品社、二〇一二年。
西田幾多郎『善の研究』講談社、二〇〇六年。
藤田正勝『西田幾多郎『善の研究』を読む』筑摩書房、二〇二二年。
宇野邦一『ドゥルーズ 流動の哲学』講談社、二〇二〇年。
フッサール『デカルト的省察』浜渦辰二訳、岩波書店、二〇〇一年。
アウグスティヌス『真の宗教に就て』大谷長訳、一九五〇年。
『夢違科学世紀』上海アリス幻樂団、二〇〇四年。
『鳥船遺跡』上海アリス幻樂団、二〇一二年。
『東方求聞史紀』上海アリス幻樂団、二〇〇六年
主観と客観http://tanemura.la.coocan.jp/re3_index/3S/si_subject_and_object.html
アインシュタインが語る「宇宙的宗教」とはhttps://note.com/sonson01/n/n785f690c4b95
ヒルベルト『自然認識の論理』https://www.nicovideo.jp/watch/sm24449424
リベット『マインド・タイム』
https://youtu.be/6Gv4o5cJ99g?si=uk0ugcYKOTuDRCed
ドゥルーズの「アベセデール」
https://www.nicovideo.jp/watch/sm1602118
時間は空間から作られる
https://youtu.be/vvV5sz597JY?si=BPDBlSMYr6Xx0n2S
直観という方法
https://www.toibito.com/toibito/articles/%E7%9B%B4%E8%A6%B3%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E6%96%B9%E6%B3%95
アインシュタインとベルクソンⅠ
https://opac.tenri-u.ac.jp/opac/repository/metadata/1131/GKH009404.pdf
*
この作品は上海アリス幻樂団およびZun's Music Collectionの二次創作です。内容はすべてフィクションであり、実在の人物や団体とは一切関係ありません。

