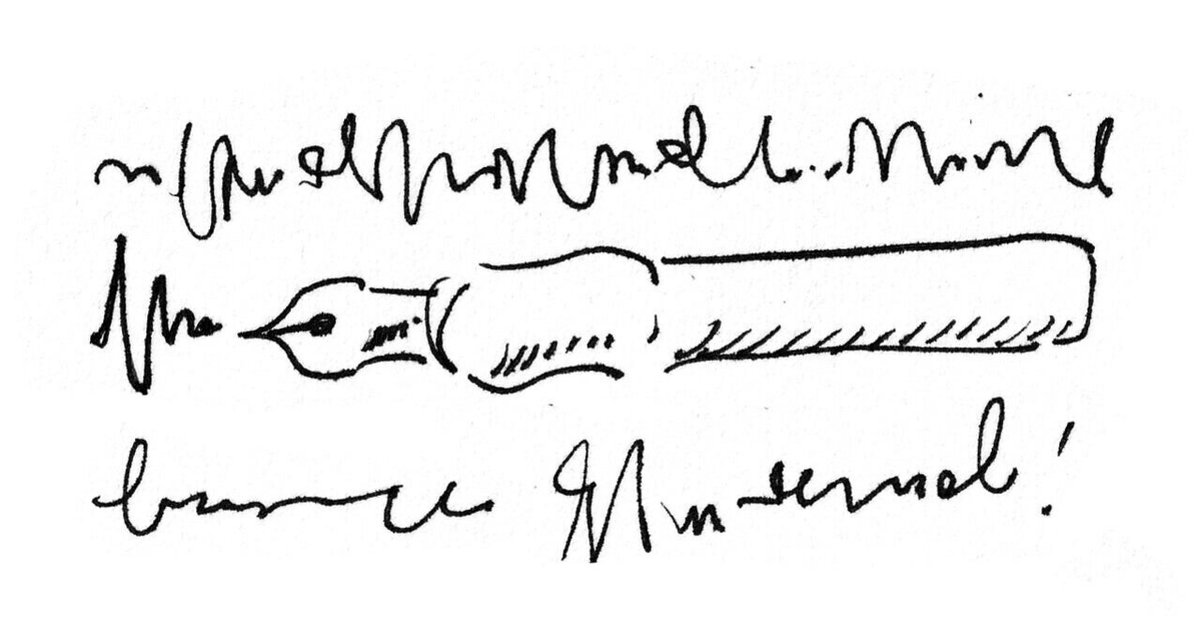
米リーダーに学ぶ、11の最新&戦略的英文ライティング・テクニック
書く能力こそ最高のリーダーシップ
リーダーの能力はDXなんかじゃなく、書くチカラだ、そう主張してやまないのは、ここ数回連続して取り上げているベイカー元国務長官の論説のような素晴らしい”作品“を目の当たりにし、唸らされることが多いからです。
YouTubeでバズるなんていいますが、人を驚かせようとして変わったことを動画にすれば再生数という表面的な数は上がるでしょう。しかし、真に人を感じ入らせ、考えや行動を変えるのは、よい文章ではないでしょうか。
さて、ベイカー氏の巧みなライティング術を解説します。2日前に「否定語を使わないでトランプを全否定し、言葉の合気道を使った」云々の主張をしましたが、その他のポイントは以下です。
1. 見出し(ヘッドライン)に複合的な意味をもたせる
2. 文章の出だしの巧みさ
3. 数字を有効に使う
4. 今まで言語化されてなかった重要な概念を言葉にする
5.流行語を入れて“わかってる感”を高める
6. 能動態を有効に使う
7. 受動態で強すぎる言い方を上手に抑制する
8. カルト的な知識で幅広い年齢層にアピール
9. ベタ表現でも使い方で効果的に
10. 箇条書きの威力
11. クレッシェンド的にラストに向かい熱が上がっていく構成力
解説
1.見出し(ヘッドライン)に複合的な意味をもたせる
Focus on principle, not personality (政党としての理念が先なんだ、候補者個人を出すな)という書き方なのですが、この見出しでほとんどのアメリカ人はノックアウトされると思いますよ。トランプ支持者を含めて。いいライティングとは、短い言葉で多くの情報を伝えることです。
このpersonalityという言葉が実に巧みなんです。
Personalityは個人、キャラクターといういみですよね。これがトランプを指していることは、このタイトルを見た人全員がすぐにわかります。
だからこの短い文章は、「共和党はトランプを全面に出したから負けたんだ」と伝わります。
また後でも触れますが、これはビジネスマンに向けての警句の意味も込めているんです。「経営者が全面に出過ぎると、企業は潰れる」と。
アマゾンのベゾス、フェイスブックのザッカーバーグ、テスラのイーロン・マスク。皆さんはそれらの会社の企業理念がわかりますか?あまりにも創業者のキャラクターが強すぎて、肝心な企業の姿勢が見えてこない。
この短い見出しでベイカー氏は現代ビジネス批判もしています。もっと言うと「組織よりも個人を全面に出す企業は潰れる」との警鐘を鳴らしていると考えます。できるビジネスマンならば、この見出しを見ただけで、ハっとすると思うんですよ。トランプ云々の前に。その意味でこの見出しはビジネスマンも引きつけました。
この文章は命令文になっていることにも注意して下さい。命令文こそ、動詞を最大に有効利用する英語の神髄で、・・せよというこれ以上明快な文章のスタイルはありません。
2. 文章の出だしの巧みさ
いきなり、「『共和党は死につつある』とググってみろ。ご丁寧に追悼の辞がたーくさんあらわれるから。google “the GOP is dying” and countless gleeful eulogies will pop up」という書き出し。
まずググれ、ですよ。
現代の消費者行動に沿った言い回しに、「共和党は死んだ」というパンチの効いた自虐。Gleeful eulogies (大喜びの追悼の辞)という言葉のセンス。
文章は書き出しで勝負とはよく言いますが、まさにここで読者をぐっとひきつけます。
ベイカーさんは相当のおじいちゃんのはずですが、「ググるとか使えるんだ、若いじゃん」と、読者は彼の若さという、いい意味のギャップも感じ、ますます引き込まれます。
3. 数字を有効に使う
アメリカ人の36%が保守派を自認し、25%以上が自分はリベラルだと答えている。(thirty-six percent of Americans call themselves conservatives, more than the 25% who identify as liberals.)
やはり数字を入れることにより、スピーチでもライティングでも説得力、訴求力が高まりますよね。
英語の原文を見て下さい、最初の36はスペルアウトしています。次の25は数字で書いています。これは単に重複を避ける、という文章作法の基本を守っているだけでなく、読者にインパクトを与える手法でもあります。
4. 今まで言語化されてなかった重要な概念を言葉にする
「アメリカは依然として『右寄りの国だ』(it’s still a center-right nation) 」という発言でcenter-right nation右寄りの国、ということばを使いました。
この言葉は僕の知る限りでは、はっきりとそう言い切っている人はいないと思うんですよね。でも事実に基づいた明快な言葉で、このベイカーさんの論説で、キーワードとも言える単語だと思います。
5. 流行語をしっかり入れて“わかってる感”を演出
流行語とはズバリinclusive(インクルーシブ 障害を持った方々など差別やハンディで阻害されがちな人と、普通人との共生する)とWoke(社会正義に敏感な)です。
それぞれ以下の文脈で用いています。Their goals were more inclusive than those contemporary Democratic Party activist (当時の共和党のゴールは現在の民主党の活動家より、よっぽどインクルーシブだった)。
Woke positions on culture aren’t shared by the American mainstream.(文化におけるWoke的なポジションはアメリカ人に共有されていなかった)。
インクルーシブもウォークもわかってるよ、とちゃんと現代の最新問題を理解しているといることを読者に知らせ、“わかってるよ”感を醸し出し、安心させています。
6. 能動態を有効に使う
能動態とは主語+動詞の形、もしくは命令文です。コミュニケーションとして最もわかりやすく、相手に伝わり、命令形は特にダイレクトです。Google(ググれ)、focus on (集中しろ)等の命令形を効果的に遣い、文章の基本は能動態で大変わかりやすいです。
7. 受動態で強すぎる言い方を上手に抑制する
例えば、さきのWoke positions on culture aren’t shared by the American mainstream.(文化におけるWoke的なポジションはアメリカ人に共有されていなかった)。
これはWokeという概念が政治問題化しているため、受動態を使って和らげたのです。受身形はコミュニケーションとしてはダメですが、このように物議を醸すことを出さざるを得ない時に、トーンを和らげる意味で大変有効です。またこれは話者の教養、上品さを感じさせる言葉の使い方でもあります。
8. カルト的な知識で幅広い年齢層にアピール
おかしかったのはご老人のベーカーさんの口から“Qアノン”という言葉が飛び出したことです。
Qアノンとは極右の秘密結社が世界征服を企むという陰謀論で、トランプはそれと戦う英雄とされます。詳しくは雑誌ムーでもお読みいただきたいのですが、思わず笑ってしまった読者もいるのではないでしょうか。
「おーっつ、ベイカーさんやるじゃん。こんなカルト知識をお持ちとは。若いなあ」という感じで。
河野大臣がいつぞやUFOの話に触れた時、好感度が上がりました。カルト知識を披露することは、ああいう効果があるんですよね。
9. ベタ表現でも使い方で効果的に
ここのところです。「選挙に勝つ最も重ような3つのファクターがある。それは経済、経済、経済、だ。The three most important factors that decide elections are the economy, the economy and the economy. 」。
ベタな言い方で、ある種使い古された表現方法ですが、内容はものすごく強く、案外盲点もついています。ベタだからこそ、強力なインパクトを生んだとも言えるでしょう。
10.箇条書きの威力
箇条書きは要点をまとめたり、ポイントをわかりやすく整理するために使うと、大変効果的です。ベイカー氏はこの論説の最後、このテクニックを使っています。
focus on the basics-pro-growth policies, strong national defense, limited government and our unity as Americans (ベーシックに集中せよ。それは、成長支援政策、強力な国防、小さな政府、そしてアメリカ人としての連帯、だ)。
共和党の政策を、この箇条書きはとてもわかりやすく整理しまとめています。こうした箇条書きは、読者の記憶にしっかり残ることも重要なメリットといえましょう。
11.クレッシェンド的にラストに向かい熱が上がっていく構成力
全体の構成を見てみましょう。まずは共和党がネットで叩かれて、期待はずれの党として非難されていると衝撃の事実を出して、読者を引っ張ります。
次に、いやそうじゃないと、否定し、コロナ前、トランプ政権で減税し、歴史的な低い失業率を達成してアメリカを盛り上げたよね、と民主党支持ムードに流されている世論の”記憶“に訴えます。
そしてたたみかけるように、「各種統計でも明らかだけれど、そもそもアメリカは保守の国、右寄りなんだよ」とアメリカ人に「自分の立ち位置を忘れたか」とやんわり恫喝します。
次にバイデン政権の予算使いすぎ、中国の脅威を煽り、「負のレガシーを子供達に残すな。科学で中国に勝たないでどうする」と民主党政権のあやうさを強調します。
そして最後に、Qアノンみたいな陰謀論じゃなく、我が共和党は正論で勝負する。それはあくまで成長戦略であり、経済である。とこう結ぶわけです。
この流れと、弱→強への段階的な、クレッシェンドにも例えられるリズム。
僕は社会人英語ライティング講座を今度やる時、是非このベイカーさんの論説を題材にしたいと思います。
今日は長くなってしまいすみません。
お付き合いいただきありがとうございました。
明日はまた違うテーマでお目にかかりましょう。
野呂一郎
