
アプレンティスシップ(徒弟制度)で世界が変わりつつあるという事実。
この記事を読んであなたが得られるかもしれない利益:アメリカで徒弟制度(apprenticeship)が復活の機運。労働力不足、高卒の時代本格到来に伴う必然なのか。いま、見直されるヨーロッパの知恵。これから世界は日本化するかも。
アメリカが徒弟制度?
アメリカは高卒の時代到来、と以前の記事で申し上げました。
アメリカが歴史的に低い失業率なのは、労働力不足によるものです。
以前は高卒ではキャリアを形成するのに不利だと言われましたが、これだけ大卒の資格を得るためにカネがかかるアメリカでは、高卒は一つの新しい流れになっています。
アプレンティスシップ(apprenticeship)という制度が、いまアメリカで注目されています。
このアプレンティスシップとは、直訳すれば徒弟制度、見習い制度、となります。
もともとはヨーロッパで職人養成のために用いられてきた、若者が職人に弟子入りしながら給料をもらい、技能を身につける制度です。
いわば給料が出るインターンシップのようなもので、これがアメリカでも普及しつつあるのです。
きょうはBusinessWeek2022年8月8日号Apprenticeships make a comeback(職業実習制度が復活)という記事を参考に、アメリカにおけるこの制度の注目度合いを見ていきましょう。
アプレンティスシップとは、結局のところキャリア&トレーニング・プログラムのことです。
人生の早い段階で企業側はスキルをつけさせて、戦力にしようという発想です。

ここ数十年、アメリカもアプレンティスシップを、社会に根付かせようと努力してきましたが、うまく行きませんでした。
しかし、アメリカの産業界は、一人の求職に2社がエントリーしている状況で、募集枠は1000万人を超えています。
アプレンティス復活の機運が整ったのです。
若者も40年ぶりのインフレでこの物価高、勉強しながら給料をもらえるならば悪くない、というわけです。
アプレンティスシップを始めた業界は保険、ヘルスケア、IT、金融と幅広く、一日の数時間は訓練、そして近隣の工場や現場で実習しながらスキルを身に着けます。
これは強いですよ、スキルは学んだだけじゃだめですから。実戦で使わないと、身につきません。身につかないスキルは使えません。
ヨーロッパから学べ
BMWが品質の権化のように語られるのは、アプレンティスシップがドイツに伝統的に根づいているからです。
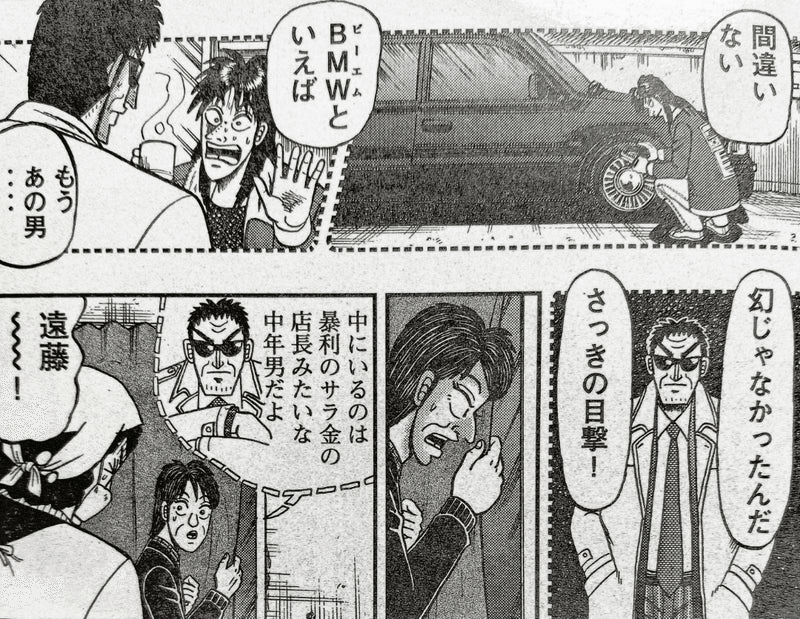
徒弟制度で鍛えられた職人のスキルがドイツの製造現場を支えているのです。
今、ドイツの兵器産業は潤っています、皮肉なことながらウクライナ戦争で発注が殺到しているからです。
でもこれを支えているのもアプレンティス制度なのです。
アメリカは、いま、ヨーロッパからアプレンティス制度を学ぼうと、政治家、企業がこぞってヨーロッパに調査に出向いています。
コロラド州は知事自らスイスに赴き、”スイスモデル”という、アメリカ式とスイス式のハイブリッド型アプレンティスシップを開発しました。
アプレンティスで変わるアメリカ
結局社会が変わるのは、クーデターとか、革命でなくて、単なる人口動態的な数字のせいなのですね。
アメリカの場合は、労働力が足りなくなったことです。
物理的に企業は、23歳から26歳位の大学の学位をもっていてスキルも現場経験もない若者よりも、18歳から21歳くらいのスキルをもって現場経験もある若者が絶対的に必要になったのです。
昨年アメリカでアプレンティスシップを経験した若者は21万人、これが続くとなると企業の意識も変わってくるでしょう。
日本のようにある種の、終身雇用的なシステムが広がってくるかも、です。
若いうちに有償のインターンシップという餌で釣り、スキルを付けさせ、それを発揮すれば食っていける状況を作れば、いやでも他に行けない、企業も安定的労働力で安定した経営が可能になる、というわけです。
アプレンティス反対論に反対する
賢い読者の皆様は、「アプレンティスシップなんて使えねえよ」とおっしゃるのではないでしょうか。
つまり「テクノロジーの日進月歩で、身につけたスキルもすぐに陳腐化してしまうし、育成や教育の内容もどんどん変わるので、学んだことが無駄になるぜ」、というわけです。
しかし、それは心配無用だと思うんですよ。
何故ならば主体は企業だからです。
企業は常に変化の中心にいるから、変幻自在に教育内容、研修内容にチェンジするに決まっているからです。
それでも、教養深い皆さんは「機械的な学習だけじゃ、視野が狭まる。大学行って無駄な教養を身につけることこそ最強」とおっしゃるに違いありません。
僕もそれは、一部とても賛同します(笑)
それはそうと、日本企業もヨーロッパ詣でをして、この際アプレンティスシップを学んできたらどうでしょう。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
じゃあ、また明日お目にかかりましょう。
野呂 一郎
清和大学教授/新潟プロレスアドバイザー
