
乾いたぞうきんを絞るな。
この記事を読んであなたが得られるかもしれない利益:これから未曾有の値上げラッシュが始まるけど覚悟はいい?でも、少々の値上げは喜んで受け入れてあげて、なぜならばそれで労働者が守られるから、というあなたへのお願い。日本のいわゆるQCサークルは旧弊に過ぎないという批判。コストカットの日米差について。
日本の生産現場にいまだはびこる精神主義
日本の生産現場には、こんな言葉があります。
「乾いたぞうきんを絞れ」。

これはコスト削減にあくなき執念を燃やしてきた、日本の工場労働者の哲学です。
こういうとかっこよすぎるかな。(笑)
乾いたぞうきんを絞っても、もう水の一滴も落ちてはきません。
でもさらに絞るのです、無理やり絞るのです、そうすると何とか一滴絞り出せました。
それでも「さらに絞れ」と言われ、絞り出そうともがきます。
しまいには、ぞうきんは破れてしまいました。
やっとゲームオーバーです。
要するにこの言葉は哲学というより、一種の精神論で、それでもあきらめずにやれという現場の管理者からの、無理難題でもあります。
値上げ→コスト削減という悪魔のループ
なんでこんな言葉を思い出したかというと、コロナと戦争のおかげであらゆるものが値上げされるなか、この掛け声の下、いろんな日本のメーカーがコストカットに血眼になってるんだろうなあ、という思いからです。
外国のメーカーも例外じゃありません。
昨年7月1日のThe Wall Street Journalは、食品大手ゼネラル・ミルズの経営努力について報じています。
チェリオスのシリアルで、ベティ・クロカーのケーキミックスで知られる同社は、原材料、パッケージ、トラック輸送に人件費の高騰で、全体のコストが7%上昇しています。この10年で最も大きなコスト増に見舞われているのです。

この記事は戦争前ですから、今はもっと厳しい状況に置かれているはずです。
CEO(最高経営責任者)のジェフ・ハーメニング(Jeff Harmening)さんはこうため息をつきます。
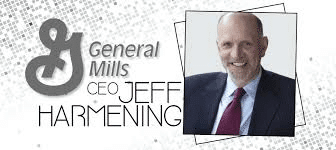
「誰も値上げなんて望まないだろうが、それをせざるを得ない」。
同業者のキャンベル・スープやジャムでおなじみのキャンベル(Cambell)やスマッカー(J.M.Smucker)も値上げに踏み切りました。


ゼネラルミルズの公式見解は、「内部のカットとオペレーションの更なる効率化(internal cuts and running its operation more efficientlyで、コスト削減に努めるしかない」というものです。
内部のカットとは、労働者をクビにすること、ムリムダを取り除くことを意味します。
オペレーションの効率化とは、生産活動の段取りの改善、機械化、IT化と考えればいいでしょう。
コスト削減に見る日米の企業文化の違い
日本流のコストカットが精神主義ならば、アメリカ流はドライで合理的、と言えるかもしれません。
コストカット努力における両者の違いは、まだあります。
それは、日本のコストカットはボトムアップ型、アメリカのそれはトップダウン型であることです。
言葉を変えれば、日本はコストカットをやるとき、QC活動(クオリティ・コントロール運動、小集団で話し合ってアイディアをだす)主体で行い、アメリカはトップダウンの業務改革命令に従う、という違いです。
ボトムアップという名前の強制労働?
QC活動なんて古い?かな。
でも工場だけじゃなくて、銀行などのサービス業でも、まだ小集団活動という名前のサービス残業はやってますよね?
無理やりなんだけれど、あくまで現場で自主的な体のもとで、より苛烈な労働分担を押しつけ、コストカットのアイディアを出させられるのが日本なのですが、僕の目からは強制労働のように見えました。

こうした小集団での改善活動は、仕事外で残業としてやらせられるのが常です。
かりにQC活動で、乾いたぞうきんが絞れたとして、それは働きがいとか、ワークライフバランスとか、働く環境とかにかんがみて、はたしていいことなのかなあ、とへそ曲がりの僕は思ってしまうのです。
もっというと、日頃の仕事だって、理不尽な長時間労働、サービス&つきあい残業、上司の意味のない説教と不合理なことばかり。
QC活動は、”働き方革命”などの掛け声とは正反対の現実の欠片なのかもしれません。
値上げの6月を目の前にしていますが、僕はあえて、メーカーの皆さんにこう言いたいんです。
「いいよ無理しなくて。小集団活動とかでサービス残業してまでコストカットしなくていいから。戦争が終わって、コロナが落ち着いたら、自然に物価が下がるから、あんまり無理して自律神経を痛めつけないで!」。
乾いたぞうきんを絞るのは、もうやめにしませんか。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
では、また明日お目にかかるのを楽しみにしています。
野呂 一郎
清和大学教授/新潟プロレスアドバイザー
