
プロレス新連載③岸田政権、究極の一手としてのプロレス立国第3回まず、サムライ・プロレス世界布武を。
この記事を読んであなたが得られるかもしれない利益:脚下照顧、僕ら日本人は日本の文化という世界遺産の価値が見えてない。プロレスの多様性がエンタテイメント一極に偏っている危険性。世界は日本の精神性=武士道に注目しているのに、それがわかってない日本の武道界、格闘界。
プロレス・ビジネスのしくみ
プロレス立国などと大げさなことを言わなくても、要するにプロレスビジネスの底力を存分に発揮して、WWEとタメを張るようになればいい。
どうしたらいいか。
それは一昨日お話しした、WWEの最新ビジネス動向がヒントになる。
つまりは、オフ・ザ・リングのビジネスをグローバルに展開しろ、ということだ。
プロレスビジネスの仕組みは、ゲート収入と呼ばれる興行の入場料、テレビ放映権、マーチャンダイジングと分類されるグッズ販売が三本の柱だ。
新日本プロレスの場合、これに世界に向けて展開する新日本プロレスワールドという、オンラインでの試合中継サービスが加わる。
これにWWEが始めたような、ドラマを制作しストリーミングで流したらどうか。
誰がWWEの市場独占を許したのか
しかし、その前にやるべきことは、世界展開だ。
新日本プロレス(日本のプロレス)を、もっと世界中に知らしめなくてはならない。
そうすることによって、日本のプロレスが世界的に認知され、世界に
「おぉ、プロレスっていうのは、WWEだけじゃない。サムライ・プロレスっていうすばらしいものがあるんだ」
との理解が進むだろう。
実際、WWEのパフォーマンス・プロレスに、拒絶反応を示す層も多い。
いつから、WWEはよくいえば劇場型スポーツ、悪く言えばマイクパフォーマンスだらけの格闘ショーになってしまったのか。
それは唯一のライバル団体であったWCWが消滅してからだ。
というよりも、WCWは2001年にWWEに買収されてしまったのだ。
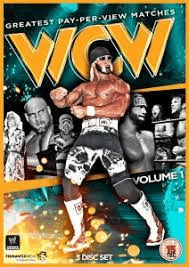
もっとさかのぼれば、90年代の後半にNWA、AWAが崩壊して以来ということになる。
要するに、多団体で競い合っていた時代は、プロレスのスタイルに個性が、多様性あったのだ。
言葉を変えると、WWEは時代に合った”勝てる”ビジネスモデルを確立したといえる。
それは期せずして、WWEの名前にはっきりと刻まれている
そう、ワールド・レスリング・エンタテイメント(World Wrestling Entertainment)WWEだ。

もちろん、「プロレスはもともとエンタテイメントじゃねえか」と気色ばむ向きもあろう。
プロレスがスポーツの王者だった1950年代
しかし、プロレス最盛期と言われる1950年代のプロレスは、そうじゃなかった。
むしろ、昔の新日本プロレス、アントニオ猪木が切った張ったをやっていた時代のプロレスに近い、と言えばわかっていただけるだろう。
不滅の王者・鉄人ルー・テーズが最強王国NWAの華であり、元祖スリーパーホールドのバーン・ガニアの渋いファイトがAWAの象徴であった時代。

プロ・レスリングは、もっと緊張感のある”戦い”だった。
それは日本のファンも、実はその目で目撃している。
1960年代に東京12チャンネル(現テレ東)で土曜日のゴールデンタイムに放送された、「プロレス・アワー」である。
ルー・テーズを中心に、そこに展開されていたのは、力と技のレスリングだったのだ。

今回の連載はあくまで、日本の古き良きプロレスを、プロレス・ビジネスをグローバル化せよとの提言で、こんなことを言うのは反則だが、あえてこれを言いたい。
古き良き、いわゆる”オールド・スクール”と半ばノスタルジー扱いにされる”プロのレスリング”を、国内向けに復活させるのも面白いと思っている。
その理由は、”プロレスアワー”でプロレスの原体験をして、そのままプロレスはこういうものだ、と洗脳されている層がプロレスファンの10%を占めるからだ。
この層は、いまのスピードとテンポだけ速いプロレスに、格闘技と戦おうとしない”ハイスパートレスリング”に辟易し、プロレスから離れている。
この”オールドスクール”層10%に訴えるプロレスを復活させることが、これらの影響力とマニア性の強いファンを再び会場に戻し、国内のプロレスを再ブレイクさせることにつながると思うのだが。
GLEATがやっているじゃないか、という声があるのも知っている。

横道にすっかりそれたが、この問題はまた後日話そう。
エンタテイメントと正反対の”局”を作れ
確かに今のWWEは、ビジネスとしては、完璧だ。
出演レスラーが一秒単位で契約通りに演技するがごとくの、一大絵巻としてのイベントは、それはそれでほぼ完成の域にある。

まさにスポーツ・エンタテイメントだ。
しかし、一方でプロレスから多様性を奪ったことは間違いない。
さあ、もう一つのプロレスの出番だ。
それも武士道をルーツにする、勝負本位のプロレス。
出てくれば、世界中の人がプロレスの多様性復活を歓迎するのではないか
その状態を作ったうえで、WWEにならったドラマでも作って、ストーリーミングで流せばあたるのではないか。
もちろんすでに、プロレスドラマは何本も作られて、ヒットもしている。TOKIOの長瀬智也主演のドラマ「俺の家の話」は記憶に新しいし、20年前には女子プロレスを題材にとった「渋谷系女子プロレス」もあった。

ポイントは、テレビ以外のメディアに進出するということと、海外で展開するということだ。
以下次号。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
では、また明日お目にかかるのを楽しみにしています。
野呂 一郎
清和大学教授/新潟プロレスアドバイザー
