
人事の明日を占う①今年、人事担当者はもっと非常識になるべきだ。
この記事を読んであなたが得られるかもしれない利益:年頭だから、「今年は・・なる、今年は・・すべき、でいくよ。今日は「今年人事担当者は何をすべきか」を考えてみるよ。シリーズで行こうかな。
人事管理は必要か
1996年にハーバード・ビジネス・ジャーナルの編集者トーマス・スチュワートさん(Thomas Stewart)さんが、メジャーなビジネス雑誌フォーチュンで、こんな爆弾発言をしたことがあるんですよ。

それは、
「人的資源管理なんて、官僚的で非効率で、企業の成功にほとんど役に立たない。ぶっ壊すべきだ!」
えぇー、それってHRM(人的資源管理)の全面的な否定じゃん!
でも、あらためてこの人的資源管理界隈を震撼させたスチュワートさんの、この言葉を現代になぞらえて考えてみましょう。
官僚的という悪
ようするに、スチュワートさんは、人的資源管理なるものは、「官僚的」だからダメ、って言ってるんですよね。
官僚的ってなんでしょう。
それは1900年代の初期に、マックス・ウェーバーという偉い学者が規定した、大きな組織を効率的に運用するやり方です。
野呂の授業でも、組織論の鉄板ネタとして取り上げることがあります。
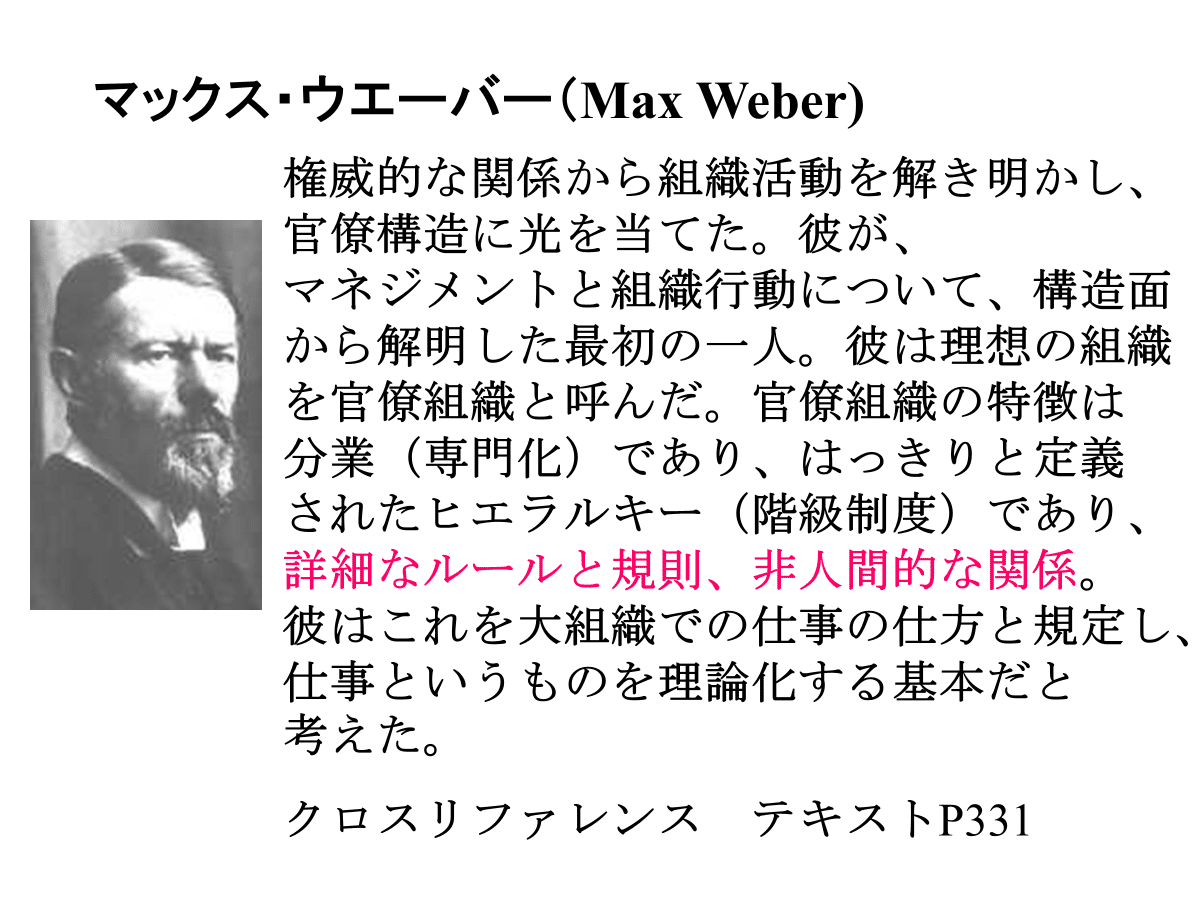
官僚制の特徴をあげてみました

要するに、今の人的資源管理は、仕事はをかっちり型に当てはめたルーティンワークで、試験で選ばれた上長が部下を管理する、ということです。

これを人的資源管理にあてはめて解釈すると、人事部はやたら規則やルールを作りたがるのは、出世のため、となります。
スチュワートさんは、人的資源管理は、単にエリートの人事部員が、出世のために従業員のためじゃなくて、自分たちの保身と出世のために堅苦しいルールを作ってるだけだ、と批判しているわけです。
人事部改革論
なんぴとたりとも、組織のルールを守らせる。
これが官僚制度の良いところであり、悪いところです。
従業員を平等、公平に扱うのはいいのですが、それが組織の創造性を奪い、自由闊達な意見や行動を邪魔しているとしたら、本末転倒ではないでしょうか。
本来、官僚制度は、組織の生産性を高めるために作られました。
役所をイメージするとわかりやすいです、要するに細かい規則をたくさん作り、それを厳格に守らせることによって、効率的な仕事が達成できる、わけです。
しかし、ここに官僚制度の落とし穴があります。
現代における仕事とは、創造的なアイディアであり、ブレイクスルー(画期的な問題解決策)のことです。
堅実な固定化した仕事を積み上げるならば、ロボットや業者に任せればいいのです。
スチュワートさんの「人的資源管理をぶっこわせ!」は、今から考えると「予言」だったのです。

処方箋:脱官僚的な人的資源管理を目指せ
当時も今も、人的資源管理には官僚制度的な要素が多かったわけですが、時代が複雑になり、現代ではさらに規則やルールがやかましくいわれるようになり、企業の成長を防げているのではないでしょうか
例えば、成果主義とは「減点主義」のことです。
でも、プロセスにおいて衆知を集め、理を整え、勇気を持ってことをなしたなら、かえってプラスに評価すべきではないでしょうか。
失敗が続いたとしても、大きな成功をすれば、失敗はチャラにしましょう。
こうした制度こそが、脱官僚的な人的資源管理です。
結論を言うならば、今年、人事部員のあなたはもっと非常識で、柔軟になるべきなのです。
野呂 一郎
清和大学教授
