
日本最大の課題「インドIT技術者をどうやって引き止めるか」。
この記事を読んであなたが得られるかもしれない利益:インド人IT技術者定住が握る日本の未来。地政学的な日本の最大の欠点。外国人にとって住みにくい国、日本。
誰も気がつかない最大の欠点
地政学ということがよく最近言われます。
日本についてよく言われるのは、日本は四方を海に囲まれているから、他国の侵略を受けず、独自の文化が発達した、です。
しかし、長所は欠点の裏返しです。
他国と国境でつながっていないために、領土という感覚、つまり、いつ外国から攻められてくるかもしれないという恐れをほとんど抱かないこと、これが日本の最大の欠点ではないでしょうか。
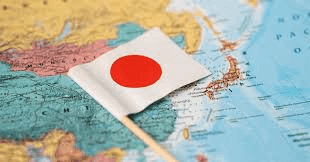
数年前にスロベニアに行った時、それを痛感しました。現地の友人と隣国イタリアのベネチアに行ったのですが、それこそクルマで3時間です。
EU域内でパスポートもいらず、まさに群馬県から新潟県に抜ける感覚です。
こうした環境では人々は国境を接する人々の言葉や文化を学ぶことを、自然に行うようになります。それは自衛のためでもあるし、ビジネスのためでもあるからです。
よくロシアが「拡張主義expansionism」と批判されますが、ああいう大きな国で隣国と地続きだと、人々は自然と恐怖に襲われ、「やられる前にやる」、という精神状態に追い込まれるという説があります。
それが今回のウクライナ侵攻の正体だ、というのです。
なんとなくわかるような気がします。
さて、日本は島国ゆえに、そういう感覚がないのです。
恐怖もない代わりに、外国と共存していかないとならない、という意識もない。全然ない。
少子化の切り札はインド人技術者
ニューヨーク・タイムズWeekly2023年1月29日号は、Japan needs Indian labor for jobs in tech industry (日本はテクノロジー業界でインド人労働者が必要だ)と題して、インド人が住みにくい日本を批判しています。
外国人で初めて区会議員になった、江戸川区議のヨゲンドラ・プラニックさん(Yogendra Puranik)は、こう訴えます。

日本で働いている仲間のインド人からよく相談を受けます。日本人の上司に足を蹴られたので訴訟を起こしたい。
学校で子供が日本人の先生からいじめられている。私が仲裁に入っても、何の進展もない。
職場はまさに鉄のようなヒエラルキーの塊で、上意下達の堅牢なピラミッドだ、変化に対する抵抗が非常に強い。イノベーションとリスクテイクこそが、企業の発展の要だということを知らないのだろうか。
興味深かった、ヨギさんの言葉があります。
「日本人の先生には、インド人の子供が日本人の子供と何か違ったことをするだけで、挑発されていると感じる人達がいる。(some teachers feel challenged if the kid is doing anything differently)」
これは島国に生まれた、我々の性なのかもしれません。
インド人IT労働者のあるある
「東京のインドの移住者Indian Migrants in Tokyo」の著者でベルリン自由大学(Free University of Berlin)の教授メガ・ワダワ氏( Megha Wadhawa)は、こう語ります。
「日本に働きに来るインド人IT技術のほとんどは、日本語も日本文化もよく知らない。それがネックでキャリアを築けず、大方はアメリカやヨーロッパに行ってしまう」
メルカリ、楽天はインド詣で
しかし、一方でメルカリ、楽天はインド人技術者を招聘する窓口をインドに設置、リクルート活動を始めています。
インド人技術者を定着させるには
ヨギさんは、「日本人と外国人の間にほとんどコミュニケーションがない。特にインクルーシブがない」と指摘します。
インクルーシブとは、人種や皮膚の色、性別、ジェンダーなどを理由に、差別をしない思想です。
日本人は、地政学的条件のゆえ、インクルーシブという世界が共有すべきとされる価値観に弱いことは、指摘せざるをえないでしょう。
ヨギさんは「文化交流イベントをやるのも大事だが、もっとインド人に日本語のトレーニングや文化の理解を学ぶ機会を与えるべきだ」と説きます。
言葉と文化の学習機会を提供する、このシンプルなことがインド人ITエンジニアの定着の答えなのかもしれません。
これはインド人だけに当てはまる、というわけではない気がします。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
じゃあ、また明日お目にかかりましょう。
野呂 一郎
清和大学教授/新潟プロレスアドバイザー
