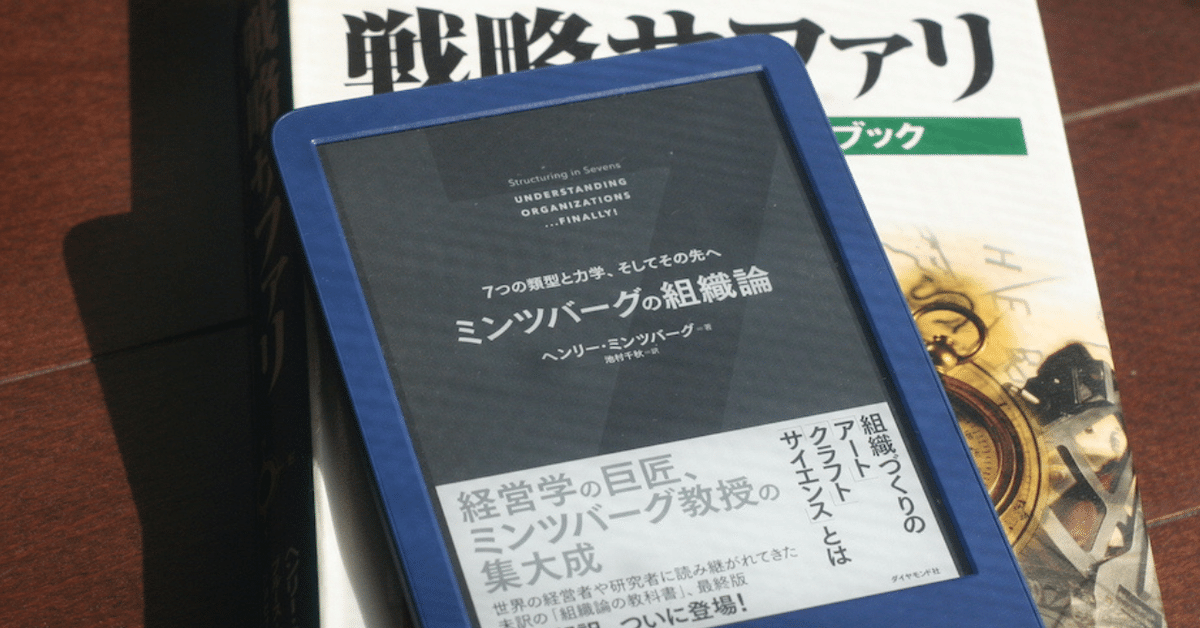
ミンツバーグが示す組織の7つの形態、自分はやっぱりプロジェクト型をめざすかな|55冊目『ミンツバーグの組織論』
ヘンリー・ミンツバーグ(2024, ダイヤモンド社)
戦略サファリに登場する " コンフィギュレーション "
ミンツバーグ教授の本と言えば、「戦略サファリ」を思い出す方も多いと思います。
もちろん僕も戦略サファリは過去に読んでいますが、今回「ミンツバーグの組織論」(以下、組織論)を読んだので、再度読み返しています。
例によって、英語の勉強を兼ねて英語版でよんでいるのですが、でもやっぱり、翻訳版で答え合わせしながら読むことにしました。

戦略サファリでは、それぞれの視点を学校に見立てて、10の異なる視点から戦略の形成について探究していきます。
その中で最後に登場する10個目の学校は ” The Configuration School (コンフィギュレーションスクール)" です。
コンフィギュレーションとは型式とか配置とかを意味する言葉で、ミンツバーグは、文鎮のような、UFOのような、内臓模型のような、独特な図によって、組織の形態と特徴を示しています。
ミンツバーグのコンフィギュレーションで示された組織のタイプは7つで、それはすなわち、以下の通りです。
①The Entrepreneurial Organization(起業家的組織)
②The Machine Organization(機械的組織)
③The Professional Organization(専門的組織)
④The Diversified Organization(多角的組織)
⑤The Adhocracy Organization(革新的組織、アドホクラシーを革新的と訳しています)
⑥The Missionary Organization(伝道的組織)
⑦The Political Organization(政治的組織)
4つの基本的な組織形態と、プラス3つの組織形態
「組織論」では、まず4つの基本的な組織形態が説明されます。それは
①パーソナル型組織
②プログラム型組織
③プロフェッショナル型組織
④プロジェクト型組織
の4つです。
そして後半で、プラス3つの組織形態として
①事業部型組織
②コミュニティシップ型組織
③政治アリーナ型組織
が登場します。
4プラス3で、合計7つの組織形態が説明されるのですが、それは「戦略サファリ」のコンフィギュレーションで示された組織形態の7種類と凡そ一致します。
組織形態を所属した組織に当てはめてみると
ミンツバーグ教授の論調を僕が好きなのは、もしかすると勝手に僕がそう読み取っているだけなのかも知れませんが、「組織論」でプログラム型として説明される、ヒエラルキーがあり、官僚的で、効率性を重視した組織(コンフィギュレーションではThe Machine Organization)と、クリエイティブでイノベーティブでフラットな組織で分権型の組織(コンフィギュレーションではThe Adhocracy Organization、「組織論」ではプロジェクト型)とが登場し、比較され、そしてどうやらミンツバーグは官僚的な組織が嫌いなようで、アドホクラシー側を応援しているように思われるからです。
自分もなぜかずっと官僚的な組織を毛嫌いしています。
そしてなぜ、「チームの力よりも個人の力」と考えていた自分が、組織論に興味を持ったのかと言えば、「個人の力を活かせる組織があるはず」と思ったからで、組織を変革することで、仕事が楽しくなって、個人が力を発揮できて、結果的にパフォーマンスが上がるという仮説を持ったからです。
おそらく「発想する会社!」「デザイン思考が世界を変える」「クリエイティブ・マインドセット」といったケリー兄弟とティム・ブラウンの本を読んで、IDEOという会社に興味を持ったことがきっかけで、「ティール組織」を読んで、これだ!と思い、そして日本のロフトワークという会社にIDEOやティール組織を重ねて、その文化や仕組みを研究の対象としたからでしょう。
特に組織の風土や文化に着目してきましたが、もちろんコンフィギュレーションが変わればそれは文化にも大きな影響があります。
ミンツバーグは、組織形態を7つに分類していますが、厳密に7つに限定しているのではなく、ハイブリッド型についても説明しています。
まったく同じ人間が世の中に一人しかいないように、まったく同じ会社も存在しません。
大きく7つの組織のタイプを示したものの、どれか一つに完璧に当てはまるのではなくて、ハイブリッド型もあるということです。
さてここで、自分が所属してきた組織がどの組織形態であるのかと考えてみましょう。
前職の小さな広告代理店は、会社規模も小さくて、創業者や経営者、権力を持った少数の社員の影響が大きかったので「パーソナル型組織」なんだろうなと思っています。
ビジョンや行動指針などは言語化されておらず、雰囲気を敏感に察して忖度していかなければ、自分の居場所を見つけることができない会社でした。
小さいくせに政治アリーナ型組織の側面があったのかも知れません。
現在の勤務先は学校なので、原則的には官僚的で管理的な特色が強い「プログラム型組織」です。
しかし、学校というのは事務職員と教員というタイプの違う2種類の職種が混在する組織であり、事務職員の組織はプログラム型でありますが、教員の組織は必ずしもそうとは言えません。
特に大学教員に関しては、研究者であり、専門家でありますから、それを束ねる組織は「プロフェッショナル型組織」と言えます。
また、たとえデフォルトがプログラム型であったとしても、リーダーの影響力によって部署単位で組織形態が変わることもあります。
この本の言葉で言えば、「寄せ集めのハイブリッド型」となります。
そしてもちろん僕がめざしているのは、フラットで分権的でクリエイティブな、そして学校全体に対してリーダーシップを発揮する、アドホクラシー型、プロジェクト型の組織です。
そしてもう1社、大学を卒業して新卒で入社した印刷会社の組織形態はなんだっただろうと思い出してみました。
中小企業ではありましたが、クリエイティブ部門を自前で持ち、工場もありました。
そうした制作や製版、そして工場などの部門を考えると、熟練の技など特別なスキルやクリエイティブな力が必要で、プロフェッショナル型のような気もします。
そして、営業職が花形の職種で、当時は創立10年ちょっとでしたが、株式上場をめざす、平均年齢の若い会社であり、プロジェクト型組織の特徴もあったと思います。
また、ヒエラルキーがしっかりしていて、毎朝の朝礼で社訓を読み上げてラジオ体操をするところなどは、プログラム型なのかなとも思います。
バブルの熱に浮かされて、「24時間働けますか?」という CFに象徴される時代に、ヘトヘトの毎日を過ごし、いつかここではないどこかに行かなくてはと思いながらも、いつまでも会社に依存している人の多い、コミュニティシップ型の会社だったとも言えます。
まったく人によって感じ方の違う、ブレンド型のハイブリッド型だったのかも知れません。
メンバーが楽しく働ける組織が一番
ラルーのティール組織やバーンズの有機的組織は、クリエイティブでイノベーティブでありますが、非効率な側面があることは否めません。
それに比較して合理性や効率面を重視しているのがプログラム型の組織、機械的な組織です。
ではプログラム型組織の何が問題なのかと言えば、働いている人が楽しくないということです。
ミンツバーグも
「多くの人にとってプログラム型組織は幸せな職場とは言えない」
と言っています。
個人のビジョンを尊重するとか、やりたいことを提案してもらうとか、心理的安全性の高い職場づくりをするとか、モチベーションを高めるために組織はいろんなことを工夫していますが、人生の中で働く時間はとても長いわけですから、何しろ仕事は楽しくあるべきですよね。
次はES(従業員満足度)について研究しなくてはと思っています。
ワーク・ライフ・バランスという言葉がありますが、ワークだってライフです。
ワークとプライベートを時間で切り分けて、ワークの時間を我慢してプライベートで楽しむと考える人もいますが、仕事自体が楽しいものであったならばどうでしょう?
仕事はやりがいであり、仕事の先に自分自身のビジョンの実現があったならば、時間ではなくて心の中の価値観の持ち方でバランスを取ることはできないでしょうか?
ワークとライフ(=プライベートライフ)のバランスではなくて、ワークをライフの中でどのような価値として捉えバランスを取るかというのがワークライフバランスの本当の意味なのではないかと僕は思います。
なんて、やっぱり最後はいつも同じ結論、感想になっている気がします。
↓ ここでも大体同じことを書いています

参考文献
『戦略サファリ』ヘンリー・ミンツバーグ 他, 1999 , 東洋経済新報社
『ティール組織』フレデリック・ラルー, 2018 , 英治出版
『発想する会社!』トム・ケリー 他, 2002 , 早川書房
『デザイン思考が世界を変える』ティム・ブラウン, 2019 , 早川書房
『クリエイティブ・マインドセット』デイヴィッド・ケリー, トム・ケリー , 2014 , 日経BP
最後までおつきあいいただきありがとうございました。
スキ♡の応援よろしくお願いいたします。
