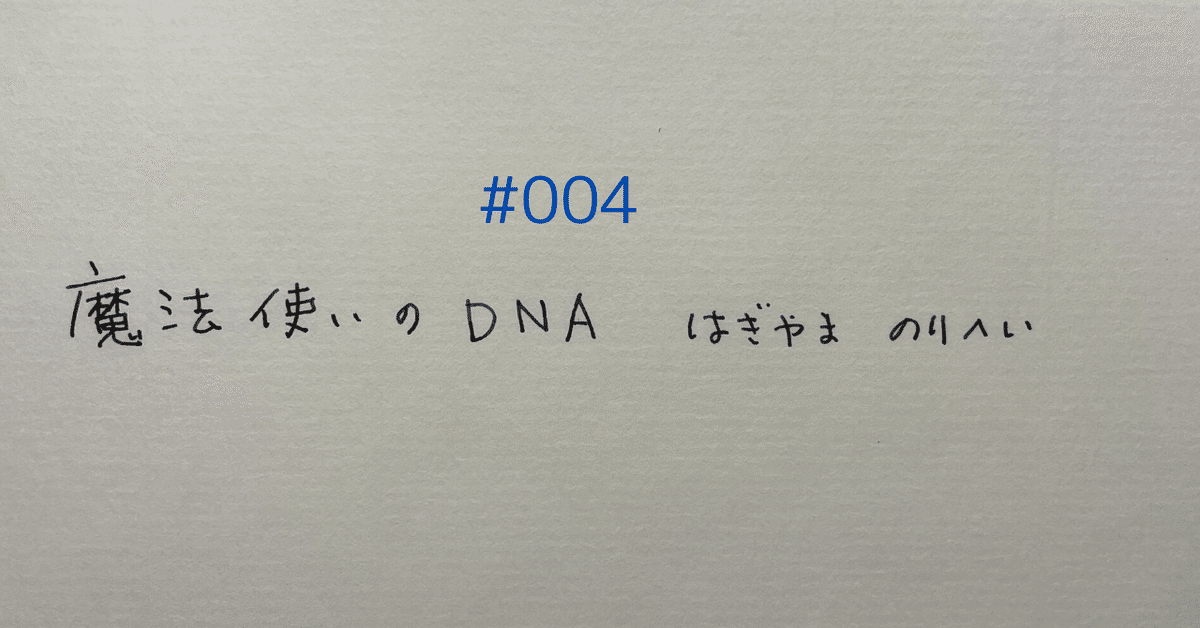
小説「魔法使いのDNA」/#004
4
慎太郎
母は父より3歳年下で、怒りっぽいけど、よく笑うし、よく泣く。そんな母を僕はチャーミングだと思う。
「お母さんは一生とけないお父さんの魔法にかかっているのよ。」と母は言う。
本当に母は父のことを心から愛していて、父がいなくなってからも魔法は一向にとけなかった。
例えばクリスチャンならば聖書の教えがある。人それぞれ、信念や価値観が違い、自分の中に基準やガイドラインを持って生活している。母の場合はその基準が父だった。
どうすれば父が喜んでくれるのか、どう生きることが父の好みなのか。あらゆる基準を父の反応に、そして、亡くなってからはきっと父ならこういうだろうという勝手な推測のもとにおいて、いわば父に依存して暮らしている。
僕も弟も父の血を継いでいて、顔や背格好もだいたい同じ。僕が高校生になった頃からは、親戚や、近所の人から「お父さんにそっくりになったね。」って言われるようになった。
今の町に僕たち家族が住みはじめたのはちょうど僕が小学校に上がる時からで、それまでは父の仕事の都合で何度か住まいを変えた。
実は僕は大阪の豊中というところで生まれた。
父と母は、父の転勤で大阪に住んだ。
知り合いといえば父の会社の同僚しかいない。父も母も関東で生まれて関東に育ってきたので、もちろん親戚も関西にはいなかったし、友だちもいなかった。
大阪の町にふたりぼっち。
お互いが支えであり、寄り添いながら手探りで暮らしてきたので、ますます二人の絆は深まった。
そして、僕が生まれた。
母は世界に父がいればそれで満ち足りていたのだけど、父はずっと子どもが欲しかったんだそうだ。
とはいえ母だって僕が無事生まれることを心から望んではいたし、父と母にとって、そして初孫である父の両親にとっても待望の宝物だったんだ。
僕が生まれた日は土曜日だった。
予定日が迫っているけど、まだそんな気配がなくて、「確か男の子って予定日より遅くなる可能性高いんだったよね?」と何を根拠にしたのか知らないけど、そんな会話をしていたらしい。
土曜の朝、起きると「もしかしたら、破水したかも。」と母が言った。病院がはじまったらすぐ電話して相談することにした。
父は朝一番で歯医者の予約が入っていたので、そわそわと心は落ち着かなかったけれど、仕方なく近所の行きつけの歯医者へと向かった。
父が歯医者から帰ってくると、母はすでに病院に向かったところだった。
「電話をしたら、すぐに来てくださいとのことなので、行ってきます。そのまま入院かもしれないので、着替えやタオルを持ってきてもらうかも。また電話します。」というメモがテーブルに置かれていた。
父が家で上の空でテレビアニメを眺めているところに携帯電話がなった。
電話は母からで、やはり、入院ということになったので、着替えとタオルなどを持って病院へ来て欲しいという内容で、何がどこにあるのかを簡単に説明した。
病院へ行くと母は個室に居た。本来の病室の用意ができてないのでひとまずはここに居てくださいと言われたのだと言った。
簡単にここまでの経緯を父に話したところで昼食が運ばれてきた。
やけに洒落た豪華な昼食だ。「この病院、食事が美味しいのが特徴なのよ」と母が言った。しかも今日は土曜日なので特に豪華な食事らしい。
昼食を済ませると、看護婦さんがやってきていろいろと説明をしてくれた。やはり、破水をしているらしい。ところが陣痛が来ない。このまま陣痛が来ないと危険なので陣痛を促進する薬を、母と父、二人の承諾のもとで使わせてもらうと説明された。
承諾書に父が署名をして、促進剤をつかうと、さっそく陣痛がやって来て、そして、病院のイタリアンの夕食を母が食べる前に、僕は産まれた。お産の後で、母は夕食を摂る気がおきなかったので、イタリアンの夕食は結局、父が食べたのだそうだ。
実家に報告の電話をするために病院の外に出ると、夜空は案外明るかった。
綺麗な満月の夜だった。
子どもって満月に生まれるんだなあ、って思った、と父が言ってたのを覚えている。
父は病院に自転車で来ていた。
父が家に帰る時、母が言った。
「これから私たちは3人で生きていくんだから、気をつけて帰ってよ。」
そうか、家族が3人になったんだな、とあらためて父は思ったんだそうだ。
そう、家族は3人になった。
僕と母が退院して、家で3人で暮らしはじめた。
赤ちゃんはみんな可愛くて、お母さんはみんな母性本能があってやさしい、と思ったら大間違いだ。
産まれて間もない赤ちゃんにも性格があって、頑固だったり、意地悪な性格が見られたりもする。
お母さんだって子どものためなら何でも我慢ができるわけではなくて、嫌なことは嫌だし、例え自分が産んだ子どもであったとしても性格の合う合わないはあるのだ。
どちらかと言えば、僕と母は性格が合わない方だった。
まだ何もわからない赤ちゃんの僕を、母は本気で怒り、その怒っている気持ちを受けとめた僕は赤ん坊のくせに母に真っ向から歯向かったのだそうだ。
父はやさしかった。
父は母にやさしかったが、待ち望んでいた赤ちゃん、つまり僕に対してもこれ以上ないという愛情を注いでくれた。
それが、母が僕に冷たくした原因のひとつでもある。
父の愛情を独り占めしたい母は、僕に対して嫉妬心を持ったのである。
母は父に依存して生きていたので、父の愛を通して、自分の存在意義、自分が世界に必要な人間であることを確認していた。父のやさしさこそが母のすべてであり、アイデンティティであったのだ。
その二人の関係の中に、僕がぽっこりと現れたものだからバランスが崩れた。
父は母と僕が仲良くしているのを見るとそこに、この上ない幸福を感じたと言っていたけれど、母は父が僕と仲良くしていることが少し悔しかったらしい。
僕が生まれて、また転勤で東京に帰ってくるまでの大阪での3年間、僕と母はよく喧嘩をして、母はヒステリックになってよく泣いた。
大阪には友だちも知り合いもいなかったから、相談する人、心の逃げ場がなっかのだろう。唯一の頼りが父なのに、その父が最大のライバルである僕に味方をするのだから。
そんな環境で育った僕は、人の顔色を見る人間になってしまった。子どもながらに自分の正直な気持ちよりも場の空気を優先してしまうんだ。まあ、そうは言っても僕の周りの大体の友だちがみんな顔色を見る子どもだったし、中には自分の気持ちだけしか考えないで行動する勘違いガキ大将みたいな奴もいないことはなくて、そうならなくて良かったと思う。そんな奴は想像力が足りないんだなって思っていた。そう、顔色を見るっていったらなんか姑息なイメージがあるけれど、想像力があるというか、先を読むというか、シミュレーションを心の中で重ねるというか、行動に慎重な人間ということなんだ。
だけど、なぜ母は口癖のように僕に「何度言ったらわかるのよ」というのだろう。たぶん、気を遣う場所が母と僕とでは全然違ったのだろう。
大阪に暮らしていた最後の頃は、母は育児ノイローゼ寸前だったけど、東京に転勤になって、仲良しの学生時代の友人や、会社に勤めていた頃の友人にも会えるようになって、そして僕も成長して聞き分けが良くなって、人間らしい会話ができるようになると、母と僕の気持ちも家族の生活も落ち着いてきた。
正直な話、僕は兄弟なんか別に欲しくなかった。
母ももともと母性愛豊かな、子ども好きの性格じゃなかったから、まさかもう一人なんてとんでもないと言っていたし。でも、心のどこかでは、僕のために兄弟が居た方がいいかな、なんていう思いが実はあったようだ。
そして僕が5歳の時に弟が誕生した。
弟が産まれた日は平日の月曜日だった。
朝起きて、母が予感がするというので父は会社を休んだ。まあ、もともとそろそろだからということで休める体制は整えていたらしい。
僕は幼稚園があったので、母の代わりに父が送り迎えをした。夕方、僕を迎えに幼稚園に父が来て、車に乗ったところで母から電話が掛かってきた。
慌てて自宅に戻ると、自宅の前の通りまでスポーツバックを持った母が出てきていた。さすが、二人目になると準備万端だ。母を車に乗せて、丁寧だけど急いで車を走らせて病院に向かった。
病院に着くと、待ち合いで少し待って、その間に父と僕は母の背中を擦っていた。
名前が呼ばれて診察室に行ったけど、しばらくすると分娩室に移動することになった。
僕と父は分娩室の外の廊下の長椅子でソワソワしていた。
バタバタとして、少し落ち着いてきたなと思ったら、すぐに赤ちゃんの産声が聞こえた。
「もう産まれたのかな?」僕が父に聞くと、父は、「やけに、安産だな。」と言った。
看護婦さんが僕たちの前に来て、
「産まれましたよ、元気な男の子です。お母さんも元気です。」
と言って微笑んだ。
僕と父は肩の力がすっと抜けた。
赤ちゃんはまだ泣いていた。その泣き声を聞いて、
「お前が産まれた時の声はこんなもんじゃなかったぞ、その日に産まれた誰よりも大きな声で泣いてたんだ。なんて、でかい声だ。こいつは大物だぞ!とお父さんは思ったんだ。」と言った。
「じゃ、弟は大物じゃないのかな?」と僕が言うと
「ばか、繊細で上品なんだよ。よく聞いてみろよ、説得力のある美しい泣き声だと思わないか?」と言った。
結局、どうだって自分の子どもは素晴らしいのだ。
弟ができて、家族がどうなったかというと、
すごくバランスが良くなった。
3人は不安定だけど4人は安定感があるんだなと幼稚園児の僕は生意気にも、そう思った。
母は父に依存していて僕をライバル視していた。そしてまた、僕は父の大事な宝物だから、という遠慮を心のどこかに持っていたみたいだ。
で、二人目の子は自分の宝物という論理になるらしい。所有欲というのかな、洋服やカバンやジュエリーなんかにほとんど興味を示さない母にも所有欲みたいなものが少しはあったのかも知れない。
母は感情的で笑ったり泣いたり激しい人だけど、ルールとか規則とか、マナーとか常識とか、そういうことにはすごく厳しくて、それは自分に対しても厳しかったけれど、他人に対する期待も高かった。だから非常識な人を見るとすごく怒った。当然、人の好き嫌いが激しかった。
僕に対する躾も厳しかった。
あいさつはもちろん、お箸の持ち方もうるさく言ったし、嫌いなおかずを残すことも赦さなかった。どうしても食べられない時は自分で食器を洗わされた。
食べる姿勢については、中学生になるまで注意され続けた。
正直、うるさいなあってずいぶん思ってきたけど、今では感謝している。だって、ちゃんとした食事の場所で恥を掻かずに済んでいるのは母のお陰だからね。
弟に対する躾ももちろん僕と同様に厳しかったんだけど、弟は大らかというか、精神的に自由なところがあって、母ともうまく接してきたなあと少し羨ましく思う。
弟は僕と違って人の顔色よりも自分の気持ちを優先できる。時にはそれが裏目に出て、町で不良生徒にからまれて痛い思いをしたこともあったようだけど、家に帰ってくればけろりとしている。こんなことがあって殴られちゃったよ、なんて笑って家族に報告するし、からんできた不良生徒とも最終的には仲良くなっていたりしてるようだ。
僕がどちらかというと理論的なタイプだとしたら弟は感覚的なタイプだ。
僕は言葉をしゃべれるかしゃべれないかぐらいの時には、大好きだった電車の名前をたくさん覚えていて、のりもの図鑑を見ながら、これは南海電車、これは阪神電車とほとんどの電車の名前を言い当てることができた。大阪に暮らしていたので関西の電車が好きで、中でも一番好きだったのは阪急電車だった。
父が通勤するのに阪急電車で通っていて、定期を持っていたので、父が家に居る休日は駅に一緒に出かけていって、ホームの中で電車を見たらしい。
僕は言葉を覚えるのも早かった。大雑把に本を読む父と違って、僕は一字一句をしっかり読むので、絵本を父に読んでもらうと、間違いが多いのが子どもながらにすごく気になった。
幼稚園からピアノを習っていたけど、論理的に考えるタイプとしては、いかに豊かな情景を音にして表現しようかと思うよりも、演奏を手順としてとらえ、プロセスを再現するという感覚だった。だから、純粋に音を楽しめず、ちゃんとした音楽にならなかったんだと思う。それでも小さい頃からピアノを習っていると、さすがに楽譜が読めたので、中学生になってからは少しギターなんかも弾いてみたりした。まあ、自分でいうのも何だけど、才能はないみたいだね。
でも、弟は違った。
弟は音楽でも自由だった。
弟は、特に親父が居なくなってからは僕の真似をとことんしてきたので、僕が興味を持つことには何でも興味を示した。ピアノもやっぱり幼稚園から習ったし、小学生からはギターも弾いた。僕はピアノの練習があまり好きじゃなかったけど、弟は練習というにはあまりにも自由だったけれどよく音を出していた。
もっと大きくなってからは、ギターをぶら下げて生活しているんじゃないかという程にギターに熱中していた時代もあった。
型にはまらない自由な発想をできる奴で、僕は弟のそんなところを尊敬している。
父の水色のギターは弟に譲った。実は僕だって欲しくなかったわけじゃない。僕にとっても父の形見だし、ギターを通しての父との思い出は弟よりもきっと僕の方がある。
でも、父のギターを活かせるのは残念ながら僕よりも弟なんだろうなと思ったのだ。
#004を最後までお読みいただきありがとうございます。
#005は2/13(月)に配信します。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
