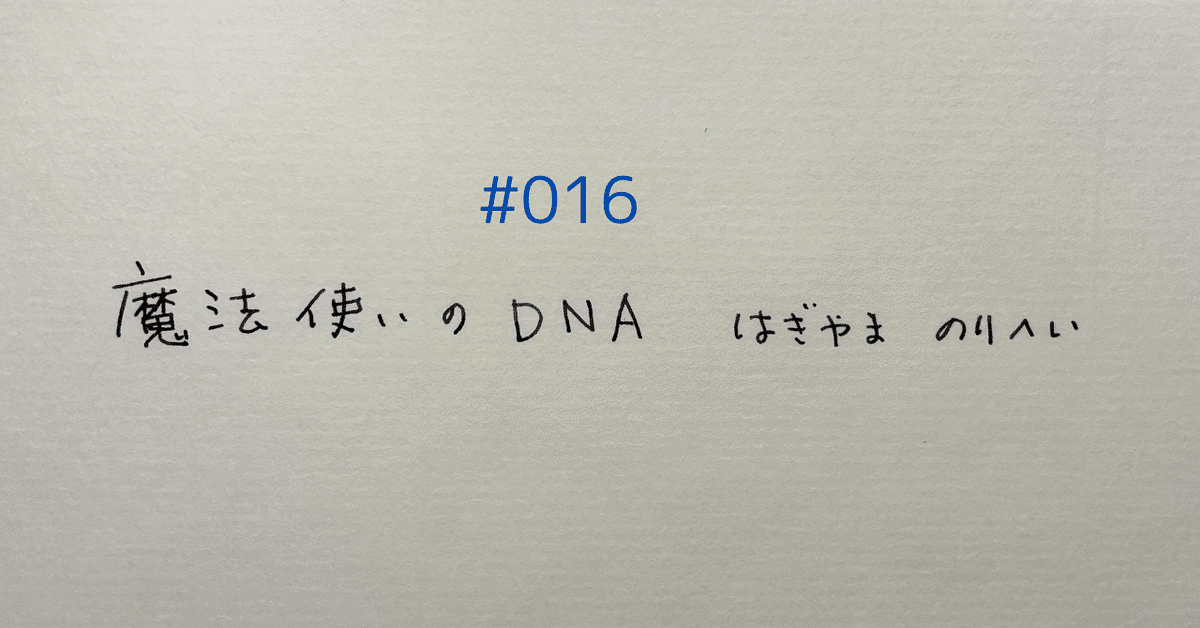
小説「魔法使いのDNA」/#016
16
慎太郎
昔、それは父の病気が判明する前の年の夏休みのことだった。
父の会社の夏休みは一斉休暇ではなくて、決められた期間の中で日を選んで社員が各自で夏休みの日程を決めるルールだった。
多くの社員はお盆の時期を選んで休んだけれど、僕の父もやはり毎年お盆の時期を選んで休みを取って、そして祖父母の家に行った。
さらにもう少しだけ夏休みの日数があったので、お盆以外の平日にも休みを取り、僕と弟を、プールやトミカ博や、そして水族館にも連れて行ってくれた。
その日、父も僕も休みだったのだけれど、特にどこかへ行く予定はなかった。
あったとしても、きっと僕は行きたくないと言っただろう。
その時、僕は小学3年生で、入学以来の仲の良い友だちがいた。
親友と呼ぶには僕たちは幼なすぎたけれど、きっと今なら親友と呼んでいるだろう。
友だちの名は翔馬と言った。
僕はどちらかといえばおとなしい子どもで、外を飛び回って遊びまわるタイプではなかった。
両親の意向で小学生のバスケットボール、いわゆるミニバスのチームにこの年から参加していて、ミニバスは楽しかったけれど、例えばレゴブロックであるとか、家の中で遊ぶことも実は好きだった。
翔馬は僕の友だちの中では活発な方で、ボールを使ったりして、外でもよく遊んだ。
でもやっぱり、僕と同じようにトミカやプラレールやレゴブロックが好きで、僕と趣味が共通していて、お互いの家を行き来して遊ぶことも多かった。
そんな翔馬が父親の仕事の都合で京都に引っ越すことになった。
転校のことは1学期の終わりに先生から伝えられた。
翔馬一家は夏休みの間に京都に引っ越していく。
夏休みが終わるといつものように学校がはじまるけれど、いつもと違うのは翔馬がいないこと。
そして父が休みだったその日こそが、翔馬が引っ越していく日だった。
その日の前日に僕は翔馬と遊んだ。
翔馬の家は引っ越しの準備でたいへんだったので僕の家で遊んだ。
夕方までに僕の部屋で遊んで、夕方に翔馬の家まで送って行った。
玄関にもたくさんのダンボールが積み上げられていて、ああ、本当に引っ越すんだなと思ったら胸が熱くなった。
「明日、京都に行くんだ。」翔馬が言った。
「明日も会える?」僕が聞いた。
「うん、たぶん。お昼過ぎたら。」
次の日、僕は午前中、学校のプールに行く予定の日だった。
すごく暑くなりそうな予感の日だった。
僕は気が進まないまま、だらだらとプールの準備をした。
予定の時間になっても家を出ないので、母が僕のことを叱った。
「休むならハッキリしなさい!休まないなら早く行きなさい!!」
僕は本当は行きたくなかった。
だって翔馬が来るかも知れない。
昨日の翔馬との会話を母に話した。
母は翔馬の母と仲が良かったので、僕が知らない翔馬の家の引っ越しの段取りを知っていた。
母が言うにはトラックの積み込みは業者に任せているから手伝わずに指示をするだけで、それもおそらくは午前中のうちに終わる。
そしてどこかで昼ごはんを食べて、そして自分たちは新幹線で京都へ向かう、ということらしい。
「午前中には翔馬くん来ないから、慎太郎はプールに行ってきなさい。」
と母は言ったけれど、僕はそんな気持ちにはなれなかった。
プールのはじまる時間が15分くらい過ぎてから僕は不貞腐れて家を出た。
水着は持ってきたが、学校に向かうつもりはなかった。
翔馬が僕の家に行くのに通る道が見渡せる公園で時間をつぶそうと思った。
まだ朝だというのに日差しが強くて暑い日だった。
髪の毛から汗が頬を伝ってあごから滴り落ちた。
目の縁からも汗が止まらなくて、口の中にも少し入った。
しょっぱかった。
公園で1時間ほど時間をつぶして家に戻ったら、父が庭にいて、植物に水を遣っていた。
「プールには行ったのか?」と父が聞いた。
「行ってない。」と僕は正直に答えた。
「どこに居たんだ?」
「公園。」
「暑かっただろう。早く家に入って何か飲め。」
父は怒らなかった。
「お父さん、誰か来なかった?」僕は聞いた。
「いいや。誰かって友だちか?」父が聞いた。
「いや、何でもない。」僕は父の質問に答えずに家の中に入った。
買い物に行っていた母と弟が帰ってきて、家族みんなで昼ごはんを食べた。
冷たいお蕎麦だった。
ざるに盛ったお蕎麦をつけ汁につけて食べる。
この暑さにも関わらず父は相変わらずの食欲だったけど、僕はいつもより食が進まなかった。
もう少しで食べ終わりというところでインターホンが鳴った。
モニターを確認すると翔馬の顔が見えた。
僕は「ごちそうさま」と言って、急いで玄関のドアを開けた。
翔馬を僕の部屋に通して、レゴブロックで遊びはじめたら、母が扇風機を運んできてくれた。
いつもなら僕の友だちが来ると、一緒に遊ぶと言って弟が部屋に入ってくるのだけれど、父が図書館に行くというので、弟は父にくっついていった。
僕も翔馬もあまりおしゃべりな方ではないので、無言で黙々と遊んだ。
僕たちはレゴやミニフィグと呼ばれるレゴの小さなフィギュアを使って戦闘シーンなどを再現し、それを親のデジカメで撮影して、写真を並べてストーリーを作るストップモーションアニメーションを作っていた。
編集は父に教わりながら僕がするのだけれども、もうすでに翔馬との合作で作品を仕上げていて、2作品目がもうすぐ完成する。
その2作品目の素材に使う写真を最後に二人で一緒に撮影していた。
母がアイスを差し入れに入ってきて、レゴ作品を背景に二人の記念写真を撮ってもらった。
父と弟が図書館から帰ってきて、僕たちの部屋に顔を出した。
「翔馬くん、元気でな。」
「うん。」
「慎太郎が大きくなったら、二人で京都の大学に行けばいいよ。」と父が言った。
翔馬は少し驚いたような顔をして、そしていつものニコニコ顔になった。
「はい、そうします。」とハスキーな声で元気に言った。
「でも、国立だぞ。」と父が言った。
「そうしたら、お父さんも時々京都に行ける。」父はうれしそうだった。
そして僕は大学生になった。
あの日から、大学は京都、とずっと思っていた。
父がどの程度本気で言った言葉なのかは知らないけれど、暗示にかかってしまい、「大学は京都」と僕の身体や心に染み込んでしまったらしい。
父の言う通りに京都の国立大学を目指したけれど、残念ながらその大学は僕には難関すぎた。
それでも父の言った「大学は京都」を運命として受けとめて、翔馬と再開し青春を一緒に過ごすことをモチベーションにして勉強に励み、京都御所の近くの歴史ある大学へ進学することができた。
翔馬とは年賀状の挨拶だけだったけれど、やりとりはずっと続いていた。
高校2年生の夏休みに、受験を考えているいくつかの大学を見学するために一人で京都へ行った。
翔馬が「うちに泊まれよ。」と言ってくれた。
京都駅の京都タワー側の新幹線出口の改札のところで待ち合わせをした。
顔を合わせるのが小学生以来だったのでお互いにわかるかどうか不安だったけれど、案外わかるものだ。
僕に気づいて近づいてくる翔馬に僕も気がついた。
「久しぶりやな。」
「ああ、久しぶりだね。」
関西弁を話す翔馬が少し不思議だった。
到着したのがお昼前だったので、挨拶もそこそこに、駅から少し歩いたところにある2件並んだラーメン屋の片方の店に入りラーメンを食べた。
親友との久しぶりの再会だった。
考えてみたら、翔馬と給食以外の食事を一緒にするのは初めてだった。
そして、はじめて食べた京都のラーメンは、僕がイメージしていた京都のあっさり薄口のものとはまったく違っていた。
醤油ベースの好い匂いが店内を満たしていて、食いしん坊な高校生の食欲を刺激した。
ちょうどお店は混み出したところで、中に案内されるのに少し待たされた。
2階にある席に案内されて、向かい合わせに座った。
落ち着いてまじまじとお互いの顔を見た。
翔馬の顔に小学生の時の面影を見つけてなんだかうれしくなった。
「まさか、また会えるなんて思わへんかったわ。」と翔馬が言った。
「俺も。」と僕が言った。
「夏休みのあの引っ越しの日が一生の別れやと思った。」と翔馬が笑った。
「もう2度と会えない別れだったら、死んでしまったのと変わらないな。」と僕が言った。
「しょうもないこと言うたらあかん。こうしてまた会えたやないか。」と翔馬はうれしそうに言った。
ラーメンがテーブルに運ばれた時、ドンブリの中のスープが真っ黒なことに驚いた。
一口食べてみたら、見た目ほどには濃い味ではなかったことにも驚いた。
食べ終わった時には僕はすっかりラーメンに魅せられていた。
そしてその2年後からはじまる京都での4年間の学生生活の中で、これまた魅力的なチャーハンと一緒に何百杯かのラーメンを消化することになる。
「新福菜館」という戦後に屋台からはじまったというラーメン屋だった。
店の外に出ると灼熱の太陽が容赦なく二人の頭上に降り注いでいた。
話には聞いていたけれど、京都の夏の暑さは半端じゃない、というのが京都に到着して2時間も経たない間での僕の感想だった。
地下鉄とバスを使って、市内にある大学を3校まわって、翔馬の家に行った。
翔馬の家族は僕を歓迎してくれた。
「慎太郎くん、久しぶりね。昔の面影残ってるわね。」と翔馬のお母さんも僕との再会を懐かしんだ。
10年の月日が肌や髪の艶を少し変化させてしまったけれど、翔馬の家で遊んだ時に、よくジュースやお菓子を出してくれたあの優しいお母さんだ。
幼稚園児だった妹は中学生になっていた。
翔馬にあまり似ていなくて、結構可愛かったので照れくさかった。
お父さんとは昔はほとんど話したことはなかったけれど、この夜はたくさん京都の見どころを教えてくれた。
そして「大学生になったら時々うちにご飯でも食べに来るといいよ。」と優しい言葉をかけてくれた。
自分の父親を思い出して、少し切なくなった。
次の日は大学を見学しがてら、近くにある金閣寺や龍安寺を観光した。
夏休み中で授業はないのだけれど、クラブやサークルの活動で大学には案外たくさんの学生がいた。
ダンスの練習をする女子学生が眩しかった。
ダブルダッチという縄跳びを楽しそうに練習する学生たちがいた。
そしてスティックを回してジャグリングを練習している学生を見た時、なにか胸の奥から込み上げてくるものがあった。
もう1日、翔馬の家に泊めてもらって、次の日は京都駅に近い有名な真言宗のお寺、教王護国寺を拝観して、また一緒にラーメンを食べて、そして新幹線に乗り帰路に着いた。
#016を最後までお読みいただきありがとうございます。
#017は5/8(月)に配信します。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
