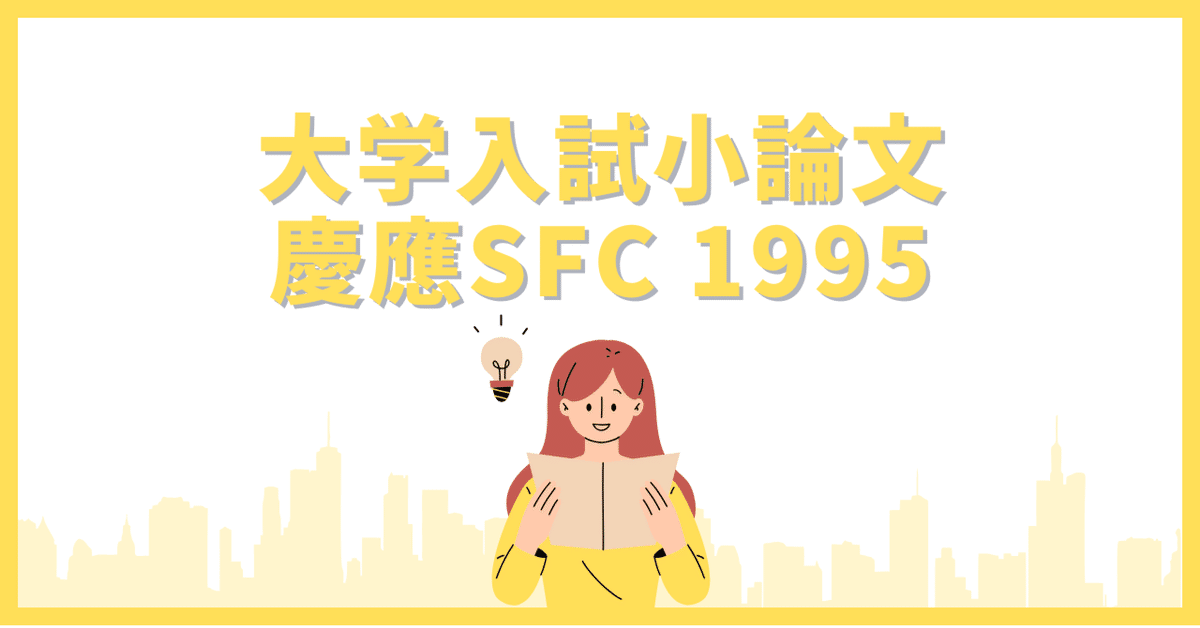
【大学入試小論文】慶應義塾大学SFC総合政策学部1995年度の解答例
慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)は、常に新しい時代に応じた学問と実践を追求する場として知られています。その中でも総合政策学部の小論文試験は、受験生の思考力、創造力、そして社会への洞察力を問うユニークな形式が特徴です。今回取り上げる1995年度の課題も、まさに「固定観念に縛られない柔軟な発想」を求めるものでした。
この記事では、この課題に対する具体的な解答例を提示するとともに、求められる論理展開や発想のポイントを詳しく解説します。過去の課題に触れることで、慶應SFCがどのような人材を求めているのか、その本質に迫るヒントを得ることができるはずです。それでは、1995年度の課題を読み解きながら、SFC合格への道筋を探っていきましょう。
慶應義塾大学SFC総合政策学部1995年度より
【改題】未来を構想し切り拓くには、一見混沌とした状況を洞察する知的心構えが必要です。未来にはばたいていくきみたちは、どのような知的心構えを持とうとしているのでしょうか。以下、提示された文章の論点に言及しながら、あなたの考えを1000字以内で述べなさい。
ある人の例【1995年度】慶應義塾大学SFC総合政策学部の解答例
私たちが未来を構想し切り拓くためには、不確実性と秩序が交錯する現実を洞察し、新たな価値観を創出する知的心構えが必要である。この課題において、重要なのは「意味の根本的な不確実性」を認識し、それにどのように向き合うかである。従来の固定観念や伝統的な視点に固執せず、新たな解釈と対応を模索する柔軟性が不可欠だ。
不確実性の時代において、社会は分断や対立に直面することが多い。しかし、こうした分裂や不安定性に注目するだけでは未来を切り拓くことはできない。むしろ、私たちはその不確実性を前向きに捉え、創造的な対応を図るべきである。たとえば、新型コロナウイルスがもたらした混沌とした状況においても、利害や立場の違いを尊重し、連帯しようとする姿勢が必要だった。
新型コロナウイルスの影響は、人々の職業や生活環境によって大きく異なる。高齢者やその家族にとっては感染リスクを最小限に抑えることが最優先だが、経営者にとっては店舗の存続が生活を支える重要な課題である。このような利害の不一致は、しばしば対立を生み出し、時には店舗への脅迫や嫌がらせといった行為に発展する。しかし、一方で、不確実性を共有し連帯しようとする例もあった。海外では医療従事者を称えるため、定時に拍手を送る習慣が生まれた。このような行動は、不確実性の中で秩序を共同で築こうとする努力の一つであり、混沌とした状況において目指すべき知的心構えを示している。
私たちは、不確実性に直面したとき、対立を深めるのではなく、対話や協調を通じて新たな秩序を創出する態度を育むべきである。他者と積極的にコミュニケーションを図り、相手の立場や背景を深く理解しようと努める姿勢が重要だ。このとき、状況全体を一面的に捉えるのではなく、個別の声や視点に耳を傾けることが不可欠である。そうしなければ、表面的な理解が誤解を生み、対立や差別を助長する危険性がある。
未来を切り拓く知的心構えとは、不確実性に意味を与え、新たな価値を創出することである。不確実性は不安を伴うが、それは同時に可能性を秘めた状態でもある。この可能性を見出し、社会の分裂を変動へと昇華させることが、私たちの果たすべき役割である。混沌の中から秩序を生み出す意志を持ち、他者との対話を通じて共創の未来を目指すことが、これからの時代に必要な知的心構えであると私は考える。
【一般論】これからの持っておくべき知的心構え
柔軟性と適応力: 急激な変化や未知の状況に対応できる柔軟性と適応力が必要です。新しい情報や技術の進展に素早く対応し、変化をポジティブに捉えることが重要です。
学習意欲: 継続的な学びとスキルの向上が不可欠です。新たな知識や技能を身につけ、変化する環境に適応できるように努力しましょう。
協働力: グローバルなつながりがますます重要となります。協力し、他者との連携や異なるバックグラウンドからの意見を尊重することが求められます。
問題解決力: 複雑な問題に対処できる能力が求められます。効果的な問題解決スキルを養い、創造的かつ効率的な解決策を見つけることが大切です。
情報リテラシー: 大量の情報が利用可能な中、信頼性のある情報を見極める能力が不可欠です。情報の取捨選択や批判的思考を養いましょう。
持続可能性への配慮: 環境への意識や社会的責任感が求められます。個人や組織の行動が地球全体に及ぼす影響を考え、持続可能な選択を意識的に行うことが重要です。
精神的な強さ: ストレスや挫折に対処し、精神的な強さを養うことが求められます。メンタルヘルスに対する理解とケアが重要です。
