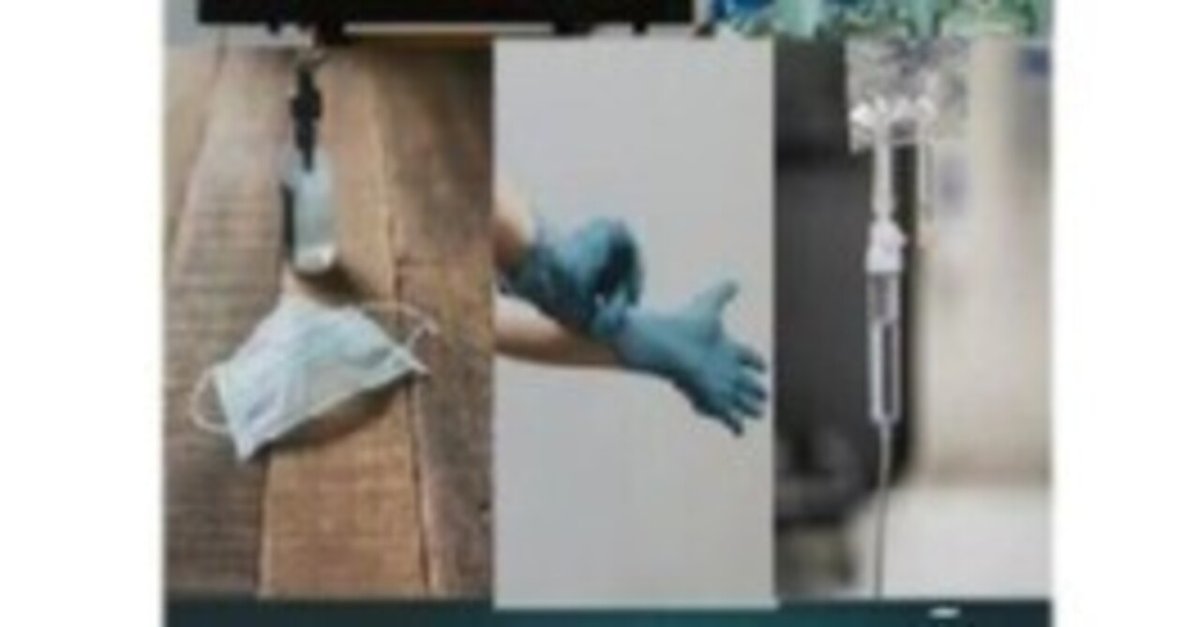
「悲哀の月」 第49話
「来生先生。受け入れ要請が来ました。患者さんは二十代前半の女性と言うことですが、どうしますか」
電話を受けた沙耶は、そばにいる来生に確認を取った。現在は患者が退院したことで一息ついていたところだった。だが、緊急要請を受けたことですぐにその和やかな空気は吹き飛んだ。話していたスタッフの表情は一瞬にして引き締まった。
「二十代前半の女性か。症状はどうなの」
固い声で来生は聞く。
「現在は軽度の肺炎の疑いがあるそうです。熱は三十九度。体には倦怠感があって、咳も止まらないとのことです。隊員が部屋に入った時には、自力で起き上がることも出来なかったという話です」
聞いた情報そのままを沙耶は読み上げた。
「そうか。ベッドは一つ空いたわけだからな。受け入れるとしよう」
「わかりました」
沙耶はすぐに受け入れる旨を伝えた。
患者が運ばれてきたのは、それから十分後のことだった。毎度のことながら慌ただしい。三人の救急隊がストレッチャーを押してきた。
「とりあえず、軽症者病棟に回してくれるかな。そこで検査しよう。どの程度の進行具合か。その結果を見てからその後のことは決めるから。報告を聞いた限り、若い人とはいえ決して、楽観できそうにないからな。この患者さんは」
来生はストレッチャーに向かって歩きながら的確な指示を出した。
「はい」
頷きながら看護師もストレッチャーを追いかけていく。
「大丈夫ですか。病院に着きましたからね。もう少し頑張って下さい。部屋に入ったら検査させていただきますから」
一足先に追いついた来生が患者に声を掛けた。目は、ストレッチャーの上で激しく咳き込む患者へ向ける。
「あれっ、里奈さんじゃないか」
が、患者の顔を認識するなり来生は驚きを見せた。思わず足が止まりそうになってしまったほどだ。
「本当だ」
「里奈さんだわ」
ストレッチャーを押している看護師もそれは同じだ。足こそ止めなかったものの、お互いに顔を見合わせている。何しろ、ストレッチャーに乗せられて病室へと運ばれようとしている患者は、つい二週間ほど前まで一緒に働いていた仲間なのだ。誰もが退職した後は平穏に過ごしていると思っていた人である。病棟のスタッフは皆、いずれ行うであろう挙式に出席することを楽しみにしていた。コロナに感染し病院に運ばれてくるなどとは誰一人として予想していなかった。
だが、当の本人はそれどころではない。激しく咳き込んでいる。顔も赤くなっているため、余程苦しいのだろう。この様子だと、今自分がどこにいるのかもわかっていないはずだ。第一、里奈だって最近まで働いていた病棟に運ばれて来たくはなかっただろう。自分の意志が示せるのであれば、絶対に他の病棟を選択したはずだ。それなのに、ここに来たと言うことは自分の意志を示すことは出来ないのだろう。とにかく助かりたい。その一心で緊急要請をしたと推測できる。そうなると、症状は決して楽観できないことになる。
ストレッチャーを押しながらもスタッフは、里奈の症状に関して限りなく重いと推測していた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
