
カレーとリズム 水野仁輔さんが聞く小野員裕さんの文章のコツ
以前、こんなnoteを書きました。
文章がうまくなるのであれば、素材はカレーじゃなくてもいいんですが、縁あって「カレーの学校」というところに通い、そこからカレーの専門家然とした知り合いが一気に増えて、カレーに関する情報が身の回りに多いので、プライベートなnoteでは、カレーについて書くことがあります。
カレーの学校の同窓会のページに「カレーで美味しい説明文を見たことがあれば、どこで見たのかを教えてください。」というコメントとともに上記のnoteを投稿したら、水野仁輔さんが「浅草ブックマーケットのトークイベントが参考になるかも」と、ご自身が登壇するイベントを教えてくれました。
今週末は、浅草にてブックマーケット。土曜にカレー食べ歩きの第一人者、小野さんと対談します!
— AIR SPICE / イートミー出版 (@AIRSPICE_mizuno) July 10, 2023
カレーの本:マニアック対談 ~魅力的な文章の書き方を教わりたい~
ホスト(生徒):水野仁輔とカレーの寺子屋
ゲスト(教師):小野員裕
日時 : 7/15(土)15:00~16:30
https://t.co/RPEPRD5UDi pic.twitter.com/uuSgZPbowt
土曜は予定があることが多いですが、たまたま空いてる時間だったので、行ってきました。

会場は、住んでる場所から徒歩15分といったところ。開場時間の14時半にゆるゆると家を出ました。猛暑日が続いた週の週末でしたが、さいわい曇っていたので、そこまで汗もかかずに会場に到着。
私はぜんぜん存じ上げなかったのですが、小野員裕(おのかずひろ)さんは、横濱カレーミュージアムの初代名誉館長なんですね。水野さんは、大学生になり上京した時、小野さんが書いた「東京カレー食べつくしガイド」を抱えて食べ歩きしていたそうです。小野さんがカレーのエッセイを書き出したという『週末はカレー日和』と一緒に、二人のトーク中にAmazonでポチりました。
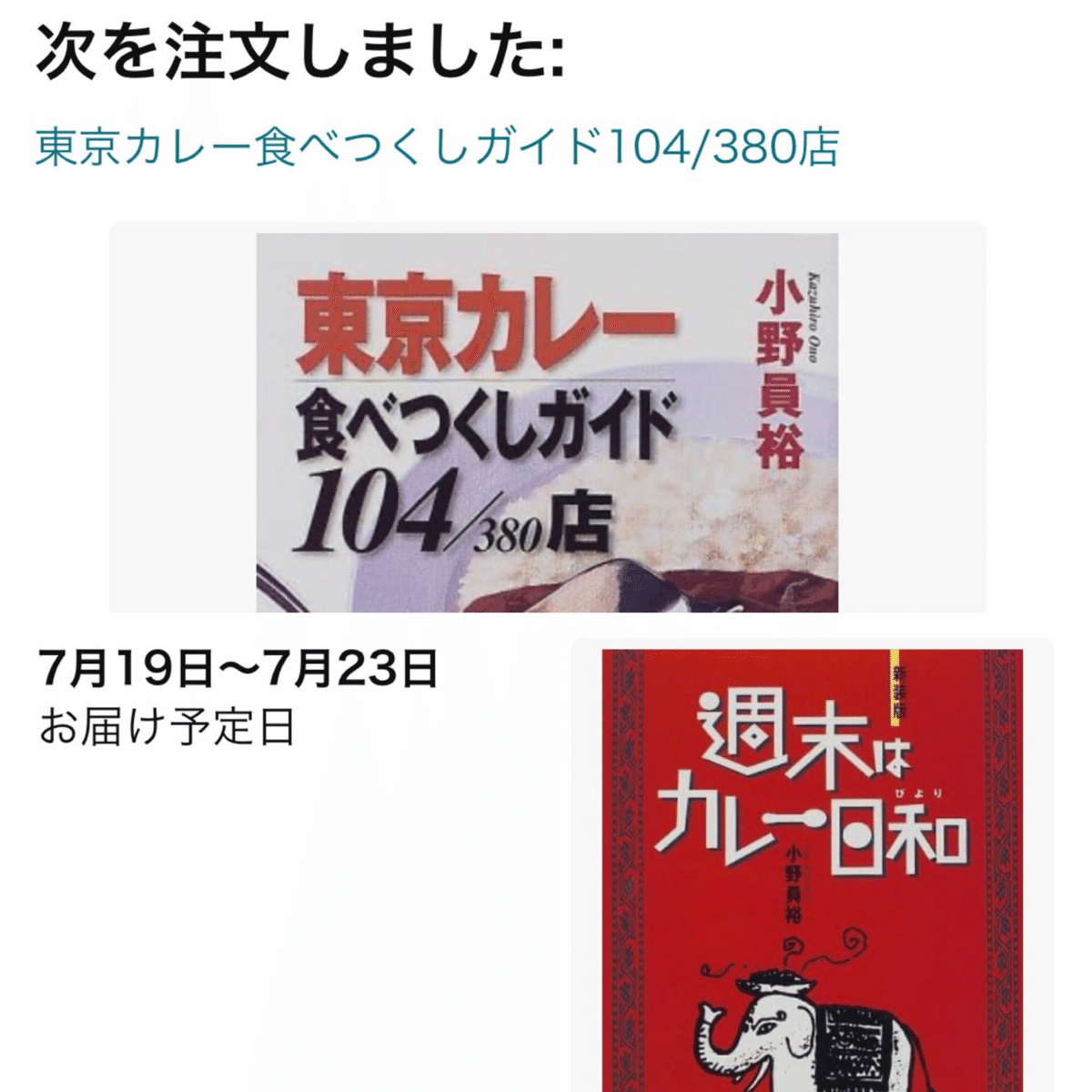
食べつくしガイドのほうは、なんとお店への許可取りなしで掲載しちゃったそうで、勝手に星をつけられたので腹を立てたお店から、小野さんが出禁になったこともあったとか。。こわいですね。今だと炎上じゃ済まないし、出版差し止めになりそうなお話です。水野さんは、食べつくしガイドの星の評価と、自分の評価が結構近かったそうで、そこで親近感を持たれていたようでした。スパイシーで、さらっとしていて、米に合うカレーですね。シンプルでいろいろと足し過ぎないものが、お二人とも好みだそうです。
で、今日の本題は、小野さんと水野さんの馴れ初めなんかじゃなくって、どうやったら、いい文章が書けるのか、です。
小野さんの文章
小野さんは、もともと、小説家を志していたほどで、特に「火垂るの墓」の野坂昭如さんが好きだとのこと。彼の助詞を省きがちな文章は今でも影響があるといいます。ただ、ブログや書籍にする時は誤植ととられかねないこともあって、行き過ぎた省き方はしないけれど、エッセイの時には、そんな感じで書くこともあるそう。
大事にしているのは、リズムだそうです。島崎藤村の「初恋」のような七五調のようなリズムが好きだそう。
まだあげ初めし前髪の 林檎のもとに見えしとき 前にさしたる花櫛の 花ある君と思ひけり
ですね。緩急をつけて、言い回しでは重複を避けるくらい。
小野さんは、正確に味の表現したい、お店の人のこだわりはちゃんと伝えたることを大事にしているそう。人柄からにじみ出るものが、いかに反映されてるかにも気をつけているそうです。
水野さんが、新刊を読んだ感想で、これが小野さんの文章の特徴なんじゃないか、という話が興味深かったです。
紹介の文章の間に会話が入る。例えば、
「〇〇カレーをお願いします」
ご隠居が来る。~が来る。
・
・
「はいカツカレーです」
これは、文章の中の景色を変えたい、場面転換のため、だそう。意図的にリズムを変えたり、作ったり。やっぱりリズムを意識されてるそうです。
また、友達からのおすすめ情報が入るのもいいですよねー、と水野さん。文章中、小野さんの友人のセリフが挟まります。
「小野ちゃんにあのカレーライスの評価聞きたいなぁ」
「小野ちゃんが好きそうなカレーあんのよー」
といった具合に。
誰に語ってるかわからない、心の声も特徴的だ、と水野さん。
これがダメだね。
この店、大好き。
そうそう、大穴狙いで買った馬券はハズれました。
みたいな文章。
あと、
パジェロミニに乗ってたころ、
出版社の営業時代、毎日のように訪れてたような場所
当時、玉ねぎが嫌いで避けていた
みたいな文章は、読者が書き手の小野さんを身近に感じるんじゃないかということでした。よく見てんなー、水野さん。
あと、水野さんは、小野さんの文章に色気を感じるとのこと。
小野さんは、根がスケベだからかなーと言いつつ、飲み友達の女の子との距離感のような、登場人物やエピソードで内面が出るしかないようなことが出ているせいかも、というお話でした。
直接、参考にして、自分の文章がよくなるような話ではなかったかもしれませんでしたが、何を伝えたいかを明確に持つこと(私は味を正確に伝えるのは難しそうだけど…)が大事で、あとは、自分の内面が出るエピソード、カレーと生活をつなぐ身近なコメントはちょっと意識してみようかと思いました。
新刊のお話
今回のイベントは、こちらの本の出版がきっかけでした。懐かしい黄色いカレーを紹介する本です。もともと本に掲載の店のラインナップは手元にあって、ブログにも書いてあるので、あとはお店の許諾を取るだけ… だったそうですが、古いお店、老夫婦がやっているお店ばかりで、許可取りが大変だったとか。最近「紹介してやるから、金よこせ」系の人たちが来ることもあって、同類と見られることもあったとか。
「金とられるんじゃないの?」「うちはいらない」「細々とやるし、後継ぎもいないし、うちはいいよ…」といった反応のお店が多かったそう。これまでもメディアと無縁でやってきた店も多く、結局、80軒のリストから掲載に至ったのは50軒になったようです。
いくつか新刊に紹介されていた店を挙げると
東青梅はさすがに遠いですが、二か月に一度、所用で訪れる(怪しくはない用)入谷の東嶋屋には行ってみようと思いました。
普段生活する街で食べるカレー、おいしいものを食べてやろうという肩に力を入れて食べに行くものではないので、この本を脇に抱えて、気軽に、街の食道、蕎麦屋、洋食屋、中華を周ってみるのもよいと思いました。
対談では、許諾が得られなかった、本には掲載されていないお店の紹介もありました。興味があれば「カレーの寺子屋」を聞いてください。小野さんとの対談回は、たぶん137時間目からです。
会場からの質問コーナー
Q. 本を作る喜びは?
A.
(小野さん)自分のヨロコビを誰かに伝えたい。自己顕示欲かな?
(水野さん)自分の頭にあるものを形にしたい。伝わるかどうかは二の次
Q. 次を書こうと思う動機
A.
(小野さん)特別ない。今は、自費出版でもいいから小説書きたい。銀英伝みたいなの書きたいけど…壮大すぎるなぁ。
(水野さん)毎回、反省点が多い。次はきっともっとうまくいくはずだ、が動機。
Q.ゴールがあって本つくる? 文章が先? 写真が先?
(小野さん)最初に本の完成イメージある。書くことも、食べた瞬間に、書くことが決まる。前日の晩に、明日、あのお店行くと、たぶんこんな感じになるんだろうなぁと想像してから行く。予測と違ってても、そこを補正する。食べてる時に、(あれ、こいつやなやつじゃん)と思えば、書きたくないなー、という気持ちも…
黄色いカレー以外に紹介されていたお店
おいしいカレーの話の合い間に出た店のリンクを貼っておきます。ザ・カリは行ったことがないので、行かねば!
あと、すでに無くなってしまったお店の話がおもしろかった。二人が惜しみながら語られた雰囲気がちょっとよかったです。今はない店を紹介されても行けないし… とも思いましたが、「思い出のあのカレー」「あのカレーの名店」をまとめた本があってもいいな、と感じさせるお二人の雰囲気がありました。
小野さんのブログはこちら
今回、紹介されたカレー店以外にもいろんなカレーが紹介されてます。
カレー - 元祖 カレー研究家 小野員裕 (onochan.jp)
実は、ラーメンも充実してます。
いいなと思ったら応援しよう!

