
今週は校長も夏休みです。 【週刊新陽 #19】
みなさん、旅は好きですか?
私は、新しい景色や文化に触れることができるので旅が好きです。
とはいえ、この2年近くで行きたい先リストは溜まる一方。リストを消化できる日が待ち遠しいです(せめて気分だけでも・・・トップ画像は2017年夏・テルアビブの地中海の写真です)。
今週は私も夏休みをいただいて、家でのんびりすごす1週間となっています。
高校の部活はどんな感じ?
夏休みに入ってすぐの8月5日、部活動体験会を開催しました。
新陽高校には17の運動系部活と13の文化系部活があり、入部は自由です。ざっくりですが加入率は5割程度。ちなみに顧問の先生も立候補制です。
生徒も先生も、自分がやりたい活動を主体的に行う。それが新陽の部活動です。(学校Webサイトの部活動紹介も合わせてご覧ください。)

今回は9つの部活が体験できるということで、100名以上の中学生が参加してくれました!


各部の生徒と先生が迎える中、すこし緊張した様子の中学生もいましたが、一緒に身体を動かしたり説明を聞いたりするうちに、徐々にほぐれたようです。
終わった後のアンケートでは、中学生から
「チームの雰囲気が良くてすごく楽しかったです。」
「先輩方が皆さん優しかったし、緊張しないように声をかけてくれて嬉しかった!」
「初心者でしたが優しく親切に指導してくださったので、楽しく体験できました。」
といった感想が多く寄せられ、付き添いで来られた保護者の方々からも
「上から押しつけない新陽高校さんの特徴が出ていると感じました。」
「先生だけでなく生徒さんが教えているところが良かったです。」
などのお声をいただきました。皆さま、暑い中お越しくださってどうもありがとうございました!
今後も、パスポートセミナーやオープンスクールを開催しますので、受験生の皆さまはぜひWebサイトをチェックしてください。
吹奏楽コンクールに招待されました♪
先月、ある日の休み時間に教室を覗きながら廊下をうろうろしていたら、「校長先生!」と呼び止められました。
振り返ると、息を切らしながら紙を持って立っている3年生。私を見つけ、追いかけて走ってきてくれたみたいです。
真剣な表情で「8月7日は空いていらっしゃいますか?」と言いながら、差し出されたのは『ご招待状』と書かれたカードと、A4サイズの『第66回全日本吹奏楽コンクール北海道予選 札幌地区大会開催要項』。

吹奏楽部がコンクールに出場するので聴きに来てほしい、と誘ってくれたのです。「よろこんで」と返事し、コンクール当日、札幌コンサートホールKitaraへ行ってきました。
オリンピックのマラソン競技で熱戦が繰り広げられていたこの日(実際、札幌の気温も高かった!)、こちらも負けないくらい熱い演奏が聴けました。
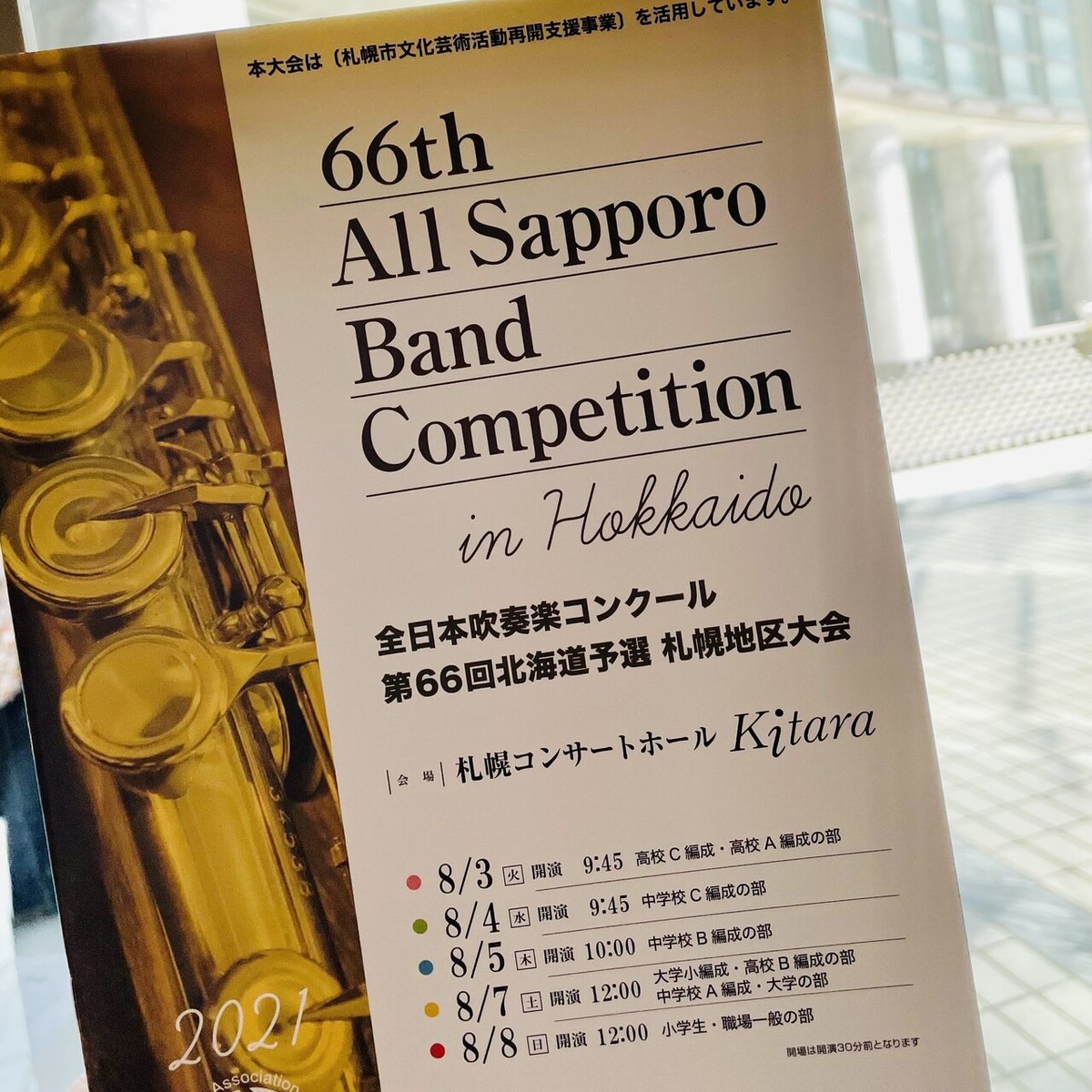
結果は惜しくも銀賞でしたが、コロナ禍で練習も思うようにできないなど様々な困難の中で、精一杯やった生徒たちを誇りに思います。
また、本番に向けて全力を出すことや、本物の環境(Kitaraの大ホールは知る人ぞ知るすばらしい音響環境)での競演は、かけがえのない経験となったに違いありません。
本で旅する夏休み
子どもの頃、夏休みの宿題は8月31日にやるタイプ。
中でもいちばん腰が重かったのが読書感想文でしたが、本を読むのは好きでした。
社会人になってからは、旅先でまとめて読むことも増えましたが、今年はステイホームの夏休み。積読(つんどく)になっていた本や、読み直そうと思っていた中から、「旅」をテーマに数冊ピックアップしました。
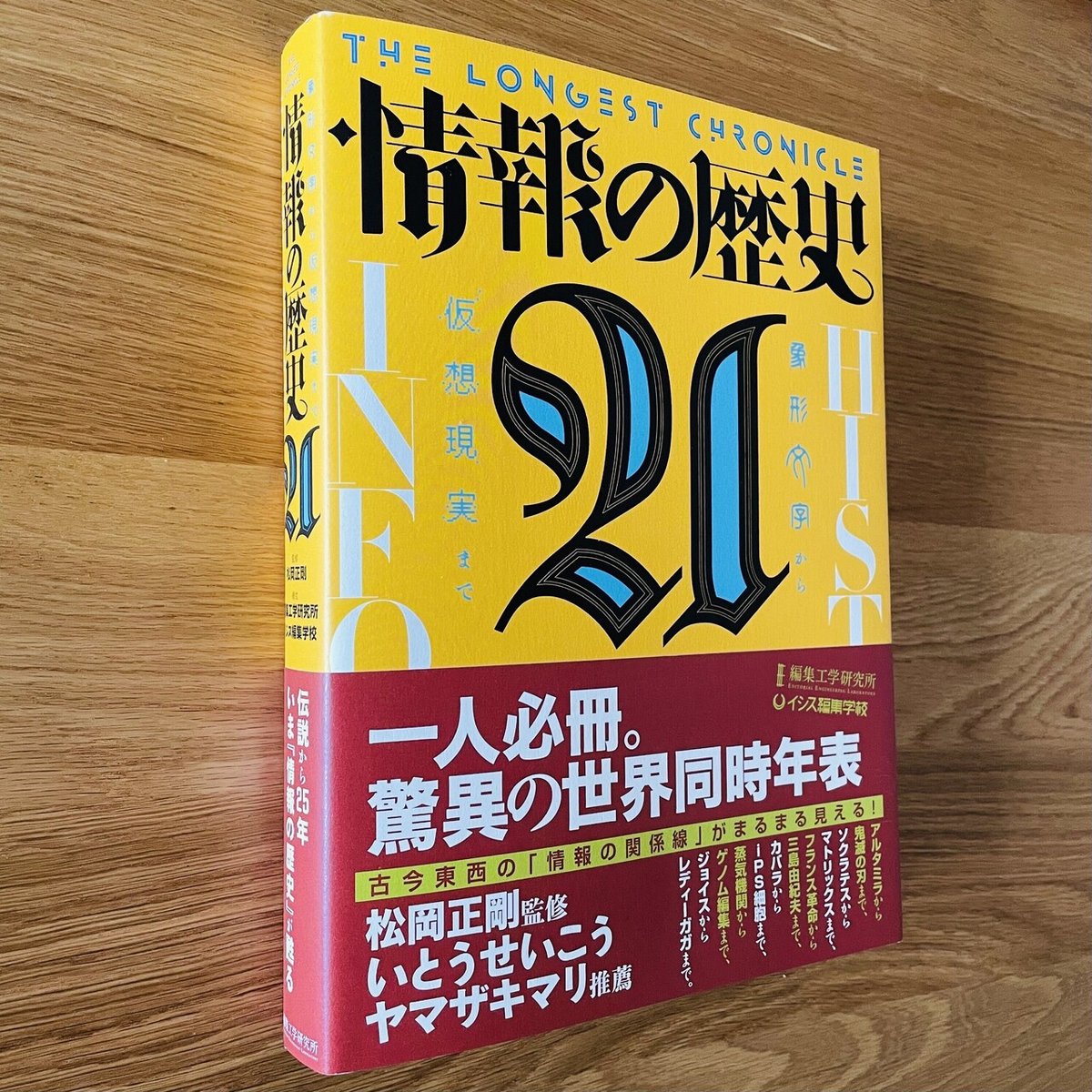
■時間を旅する・・・『情報の歴史21: 象形文字から仮想現実まで』松岡 正剛 (監修), 編集工学研究所 (著, 編集), イシス編集学校 (著, 編集)
尊敬する人生の先輩でありながらとても気の合う友でもある方から贈っていただいた本です。子どもの頃から年表や辞典が好きだったなぁと思いながらパラパラと見るつもりが、すっかり読み耽ってしまいました。
帯にあるように「古今東西の情報の関係線」が見える一冊です。

■宇宙から、古代を旅する・・・『宇宙考古学の冒険 古代遺跡は人工衛星で探し出せ』サラ・パーカック (著), 熊谷玲美 (訳)
こちらもお勧めしていただいた本。
「宇宙考古学」という分野があるのをご存知ですか?
人工衛星データを分析して遺跡を見つけるということらしいのですが、小学生の頃にアニメ「太陽の子エステバン」にハマり、大学時代は友達と「宇宙論(と勝手に名付けた妄想の数々)」を語って夜を明かした私には、たまらない本。とにかくワクワクします!

■言葉の旅・・・『LOST IN TRANSLATION/翻訳できない世界のことば』エラ・フランシス・サンダース (著), 前田まゆみ (訳)
こちらは詩集のような、絵本のような、辞書のような、美しい本です。
昨年から今年にかけて、東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTで開催されていた企画展「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」で出会った本。他の言語に訳せない言葉が集められています。
「ぼけっと(する)」「木漏れ日」「侘び寂び」など、訳せない言葉は日本語に多いというのも面白い。ちなみに「つんどく」もありました(笑)。

■旅する前の一冊・・・『北海道の歴史散歩』北海道高等学校日本史教育研究会編
山川出版社と聞いて懐かしく思う方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。高校の「日本史」「世界史」の教科書で有名ですね。
その山川出版社さんが出している歴史散歩シリーズは、PwC時代の上司に教えてもらって以来、高知県、宮崎県、福島県、と買い揃えて、今回北海道が加わりました。
高校の日本史教育研究会の編纂というのもなんだか身近に感じるので、次の休みにはこの本を片手に散歩しようと思います。
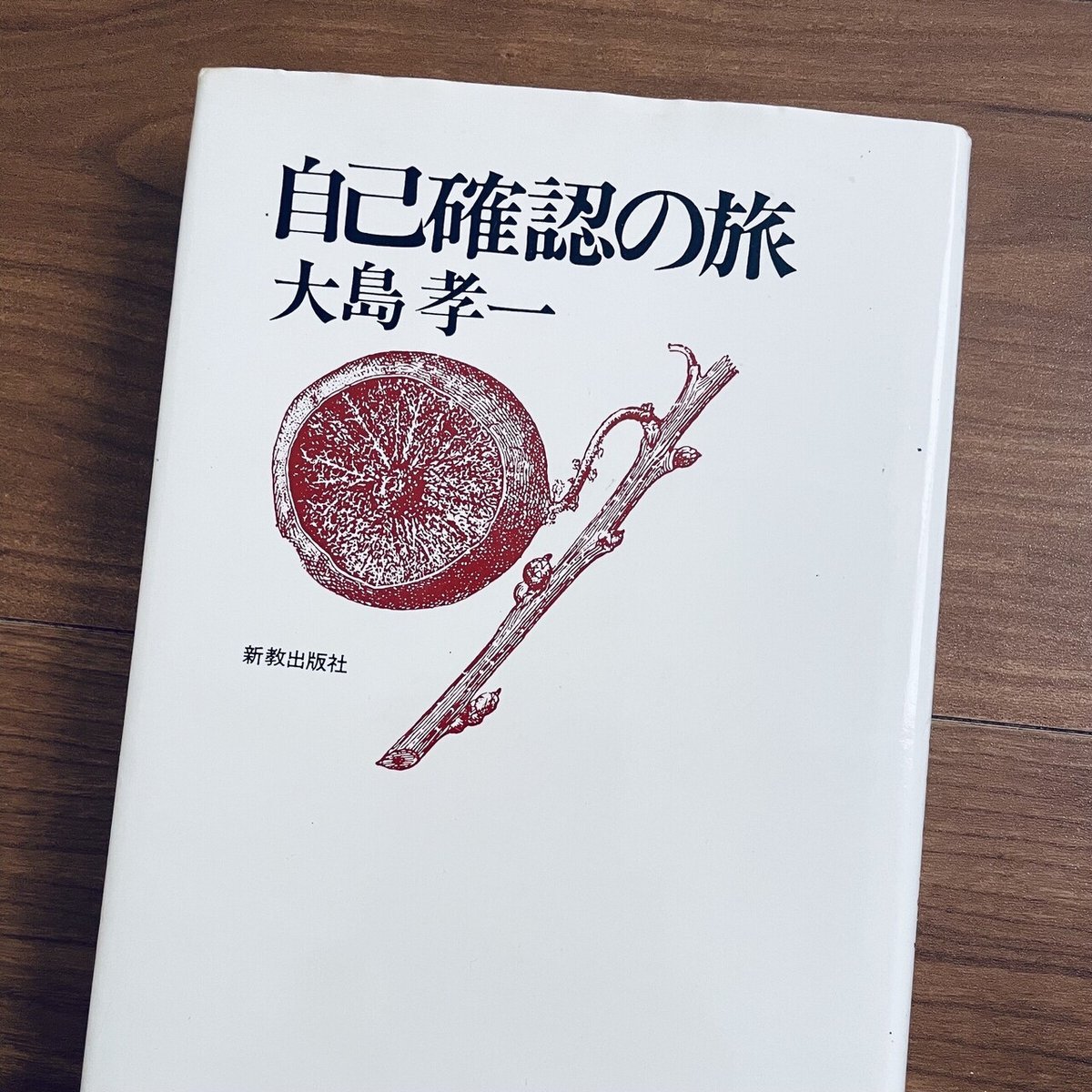
■『自己確認の旅』大島孝一 (著)
こちらは、母校である女子学院(JG)の院長を1966年から1980年まで務められた大島孝一先生の本です。
学園紛争など、学校教育のあり方を見直す大きな変革期に院長だった大島先生のキーワードが「アイデンティティ」だったそうです。
学校教育に携わるようになってから、自分自身の教育観がどうやってできたのか、考えるようになりました。両親から影響を受けているのは間違いありませんが、同様に自分のアイデンティティを確立したのは中高時代のようにも思うのです。
そこで、JGに関する本や資料を読んでいるうちに出会ったのがこの本。私は1988年入学なので、大島先生のお話を聞くことは残念ながらありませんでしたが、本を通して学校長としての想いや葛藤に触れた気がしました。
【編集後記】
部活動体験会があった日、校内を歩いていると、中学生を見送ったあと集まっている各部の部員たちの姿を見かけました。どうやら体験会のリフレクションをしていたようです。先生たちは少し離れて見ていたりファシリテーター役であることが多く、これもまた新陽高校らしい光景だと感じました。
