
異質?『星のカービィ3』の奇妙な冒険
あいつが かえってきた!
最近のゲームってむずかしすぎ。
もっとサクサク遊びたいよね。
だからあいつが帰ってきた。
みんなが遊べる、一緒に遊べる。
星のカービィまたまた登場!
……らしい。
上記は公式ページより引用
WiiUのVCのプレイ映像
別に3作目ではない『星のカービィ3』
『星のカービィ3』は1998年3月27日にスーパーファミコン用ソフトとして発売されたアクションゲーム。任天堂の中でもトップクラスに有名なキャラクター「カービィ」を主人公とした作品で、星のカービィシリーズのアクションゲームとしては5作目となる。前作は名作『星のカービィ スーパーデラックス』となるが、それとは雰囲気が違う。ちなみに、シリーズ全体でいうと9作目だ。
「雰囲気が違う」要因としては、生みの親でもある桜井政博さんが関わっていないことがあるかもしれない。私はつい最近まで星のカービィシリーズ全てに桜井さんが関わっていると思っていたのですが、そうではなかったということを知りました。
見た目とは裏腹に謎解き要素があり、すべて解かないとラスボスには会えない。また、難しいミニゲームも複数存在し、達成度を100%にすることは非常に難しい。発売当時、実機で100%クリアした人はほんの一握りしかいなかったのではないだろうか。それくらい、完全クリアを目指すとなると難易度は高くなる。
今回は「NintendoSwitchOnline」の特典でもある『スーパーファミコン NintendoSwitchOnline』でプレイしています。巻き戻し機能とかいうズルを多用しまくっております。私はあまり「星のカービィシリーズ」をプレイしてきていないので悪しからず。

カービィ、2Pのグーイ、仲間の3人乗り
なぜ、こんな時期に!? 不遇な発売タイミング……
『星のカービィ3』は、パッケージ販売された任天堂製のソフトとしては最後の作品となる。1998年といえば、既にNintendo64やプレイステーション、セガサターンなどの次世代機が発売され、大活躍していた時代。そんな中で発売されたSFC用ソフトはテレビCMもされず、認知度は低く、カービィシリーズの売上としては36万本とかなり低いらしい。『スーパーデラックス』の売上が144万本と考えると、すごい差だ。
ちなみに、同時期に他のハードで発売されていた作品は『ヨッシーストーリー』『ゼノギアス』『ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド』などなど。なぜ、こんな時期にSFCのソフトを……。

実際は発売時期が少しズレてますけど、参考までに……。
シリーズお馴染みのアクションと新しい仲間
『星のカービィ』の代名詞と言っても過言ではない「吸い込み」と「コピー能力」は健在。フワフワとしたアクションは『スーパーデラックス』と比較すると少しもっさりとした印象があった。空を飛ぶアクションはかなり重く、遅い。『スマブラ』のような感覚で動かすと痛い目を見ることになる。
カービィの仲間として、『星のカービィ2』から登場したリック、カイン、クーの3匹に加えて、さらにナゴ、チュチュ、ピッチの3匹が新登場している。マリオのヨッシーのような感覚のキャラクター。コピー能力によって、仲間に乗った際のアクションが変わるので、扱いが難しい。ただし、かわいい。

ピッチ、かわいいぞ
お……お前、だれだ……?
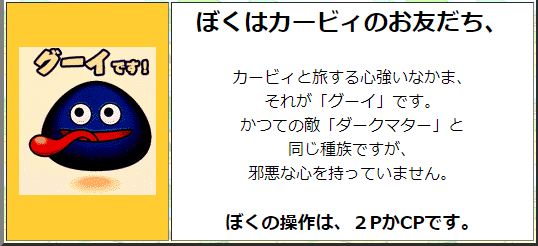
かわいくない
かわいらしく、絵本のような優しいグラフィックとサプライズ
本作はクレヨンや色鉛筆、水彩画のような暖かみのあるグラフィックが特徴だ。ディレクターである下村真一さんの特色なのか、他の担当作品の『64』や『夢の泉デラックス』も同様に優しさ溢れる色彩が素晴らしい。
SFC最後期とも言える本作ならではなのか、結構やりたい放題やっている。『新・鬼ヶ島』からどんべ&ひかり、『メトロイド』からサムス、メトロイドがゲスト参加している。初見時にはかなり驚いた。
余談。キツネとタヌキのボスがいるのだが、ダメージを与えた際に、それぞれ赤色と緑色に点滅する。色と動物の関係……。見覚えがあるような気がする。

急に出てきてビックリする
安心! いつも通りの素晴らしいBGM
音楽担当は多くのカービィシリーズを手掛けてきた石川淳さん。1作目から担当しており、『毛糸のカービィ』のインタビューでは「カービィサウンドの創設者」とも呼ばれていたお方。
名曲が多いですが、一部を取り上げると「サンドキャニオン1」は某動画サイトでもネタにされてたような気がしする。私は今回プレイして、初めて原曲を知りました。「サンドキャニオン2」は「グルメレース」としても有名な一曲ですね。こんなところでも使われているのか、と驚いた。全体的に安定したカービィサウンドで安心。
個人的には「リップルフィールド1」がカービィらしく、爽やかな曲で好きです。
概要欄にはトラックリストがあって便利
敵キャラのデザインがキモい
タイトルで「異質」と言ったのはここの要素が大きい。ワドルディやウィスピーウッズといった、かわいくデザインされた敵キャラが多いイメージだったのですが、この『星のカービィ3』では私のイメージから外れたデザインが多く、衝撃的でした。ここを意識し始めてから、「まさか、桜井政博がこんなことをするはずが……」と疑念を抱くようになりました。
特に、以下のデザインのシリーズのキャラが嫌いで、出てくるたびに「お前らはカービィの世界から消えるべきだ」と画面に話しかけたくなるレベルでした。また、バタモンという「偽カービィ」のようなキャラの存在も不気味だった。

君たちはここに存在してはいけないんだよ
子供では無理? 謎解きの難易度の驚異的高さ
『星のカービィ3』では、各ステージにある条件を満たすことで「ハートスター」を手に入れることができ、すべて集めることで最終ステージが解放され、ラスボスへの挑戦権を得られる。この「ハートスター」集めが非常に大変。
各ステージにある条件はほぼノーヒント。1回目で条件を推測して、2回目で答え合わせをするのが通常の攻略法だろう。もちろん3回以上試行錯誤することも少なくはない。一部では決められたコピー能力+仲間を連れていないといけないといった厳しい条件もあり、攻略情報を見ないで完全にクリアするのは骨が折れる。

カイン+スパークがないと正解がわからない仕掛け
これが真の姿、地獄のミニゲームたち
100%クリアの大きな壁となるのが3種類のミニゲーム。それぞれクリアすることで、達成率が1%ずつ上がる。セーブデータ選択画面の「OPTION」を押すことで出てくる「M」「J」「B」の3つ。

「M」
「M」は各ステージで登場した5つのミニゲームが楽しめるモードの「MG5」。これらは反射神経や動体視力、瞬間記憶能力などが必要とされる。5つのミニゲームを各3問ずつ正解しなければならない。1問でも間違えたら終わり。つまり、15問連続正解しなければクリアとはならない。地獄。

「J」
「J」は100%クリアの最大の壁と言っても過言ではない。本編のステージクリア後にある、おまけのジャンプを改変したミニゲーム。腕を振るカービィの動きを見ながら、タイミングよくボタンを押し、10回連続でセーフゾーンに着地すればクリアとなる。上限はないので、友人と連続成功回数を競い合うのも良いかもしれない。
超絶地獄。

タイトル画面のかわいさに騙されるな
最初は10個中セーフゾーンが9個あり、かなり優しいのだが、これは私達を油断させるための罠。

ちょろい
1回クリアするごとにセーフゾーンは減り、最終的にはセーフゾーンが1つのみの状態になる。10回連続クリアするためには、この状態で3回はジャンプを成功させなければならない。もちろん1回でも失敗すれば最初からだ。

ナイスジャンプ!
ちょ、ボタン、間違えた……ッッッ!!!!

オイオイオイ
死ぬわ、アイツ
「B」
「B」はいわゆるボスラッシュ。本編のボスとの6連戦。コピー能力使用禁止、2Pキャラのグーイの呼び出し禁止、仲間との合体禁止という厳しい制約の上に途中の回復も用意されていない。クリアすることで、エンディングや各エリア開始時のデモ映像などが自由に見ることができるモードが解禁される。まぁまぁ地獄。

読み方は「ボスブッチ」
これらのミニゲームをクリアして、やっと100%クリアとなる。最初に言ってた「最近のゲームってむずかしすぎ。もっとサクサク遊びたいよね」ってなに?????
なお、NintendoSwitchでは巻き戻し機能があるため、根気があればクリアは容易となっている。
新しい「カービィ」の世界が垣間見える一作
私があまりシリーズをプレイしていないこともあり、こんなカービィもあるのか、と思わされた一作でした。20年以上前のゲームなので、今プレイすると多少操作性に違和感を抱くこともあるが、それ以外はさすが「星のカービィシリーズ」と言ってしまう仕上がり。謎解きは難しいが、自力で考えるのも面白い。なんといっても巻き戻し機能が超強力。レトロゲームならではの理不尽な場面も怖くないので精神的に楽。ミニゲームやボス戦などでは大活躍することだろう。あえて、当時と同じように巻き戻し機能を縛るのもまた一興。NintendoSwitchOnlineに加入している人は、機会があれば触ってみてほしい。

念願の100%
それでは。
おわり。

走ったときに、風圧で顔がブワッてなるのが地味に良かった
いいなと思ったら応援しよう!

