
社会福祉士になれば色んな仕事で活躍できます

こじ☆のぼるです。よろしくお願いいたします。
![]()
今回は社会福祉士は色々な仕事ができるという話です
1 地域包括支援センター
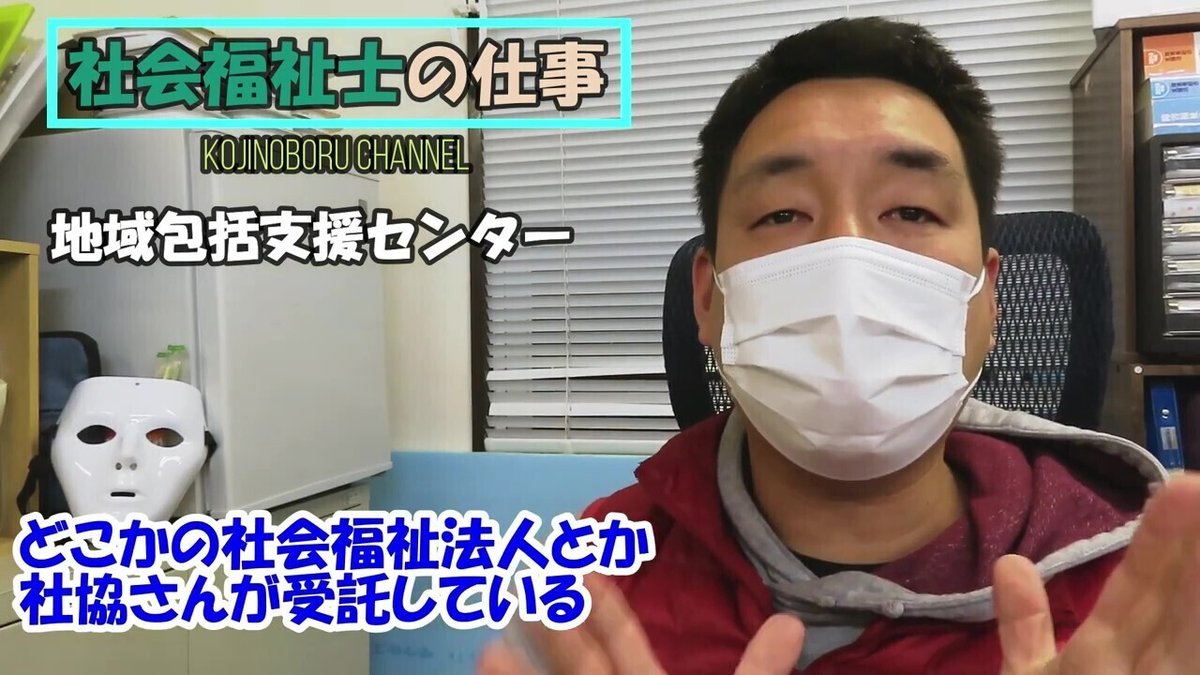
社会福祉士の中で唯一必置とされている機関です。他にも看護師、介護支援専門員がいます。大体の地域包括支援センターはどこかの社会福祉法人や社協が受託してます。
2 介護支援専門員
介護支援専門員という資格があります。社会福祉士を持ってる方が介護支援専門員として働いていこともあります。
3 介護施設の相談員
特養老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホームに相談員の方がいらっしゃって入退所の調整などをしています。
4 相談支援専門員

基幹型相談支援センターは市町村に1つ設置していくように言われています。相談支援事業所の中心を担う役割、障害に関する相談の窓口や研修や人材育成を担っています。また各市町村の委託相談支援事業所、専門的な相談援助で事業所に業務委託されてるケースがあります。
指定特定一般相談支援事業所では計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援をします。計画相談支援はサービス利用計画の作成でプランを作ってそれに基づいて市町村が受給者証を発行します。
地域移行支援と地域定着支援は精神科病院や施設に長く入院されてる方に対して退所や退院を促進し、おうちを探したりとか地域に戻られた時にお手伝いをする仕事で、地域定着支援は一人暮らしを始めてからのお手伝いをします。
指定障害児相談支援は障害児の方を対象とした支援で担い手が少なくて問題になっております
5 医療ソーシャルワーカー

総合病院などに配置されていて退院時の相談や最近では診療報酬も算定できるようになっております。一般の病院でもMSはいますし精神科病院では精神保健福祉士がいる場合が多いです。精神保健福祉士と社会福祉士のダブルライセンスの方が結構いらっしゃいます。
6 公務員
1つは厚生労働省で働いている国家公務員です。民間の事業所で経験を積んだ方が働かれてることもあります。現場から厚生労働省に行ったような人もいます。
続いて県の職員です。都道府県の管轄なので児童福祉士や医療ソーシャルワーカーが多いです。
次は市町村で生活保護や障害、高齢、児童などケースワーカーが多いです。
7 社会福祉協議会

全国・都道府県・市町村にあります。ボランティア・人材育成、採用活動、地域福祉などをしています。
都道府県では人材育成が主です。
市町村では直営の社会福祉、特養、障害事業所を持っていることがあります。
地域では社会福祉協議会を持っていたり自治会、民生児童委員の活動サポートなど、地域に根ざしたコミュニティワークを展開しています。市役所とかから事業を受託して生活困窮や福祉サービス利用援助事業で金銭管理、権利擁護センターでは虐待などを取り扱います。
8 事業所のスタッフ

ケアワーク、ケースワークで現場の直接支援に当たる社会福祉士も多いです。
・居宅関係
高齢者、障害者の方でホームヘルパー利用して生活されてる方は多いです。介護福祉士が多いです。
・通所関係
高齢ならデイサービス、障害なら生活介護、日中活動系なら就労持続支援、その他自立訓練や就労移行などがあります。児童関係では放課後デイサービスや児童発達支援などもあります。
・入所関係
高齢なら特別養護老人ホームや介護老人保健施設、障害なら施設入所支援、短期入所支援、その他生活保護、母子生活支援施設、児童養護施設などがあります。

社会福祉士は働く場所が多岐に及んでいて、いろんな専門性を問われるのでいろんな分野や選択肢があります。最初これがいいと思ってても合う合わないはあると思います。もし合わなかったとしても他にも選択肢があることを知っておいてもらえたらなと思います。
今回はここまでにさせて頂きたいと思います
今回も閲覧して頂き、有難う御座います(^^)/
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
