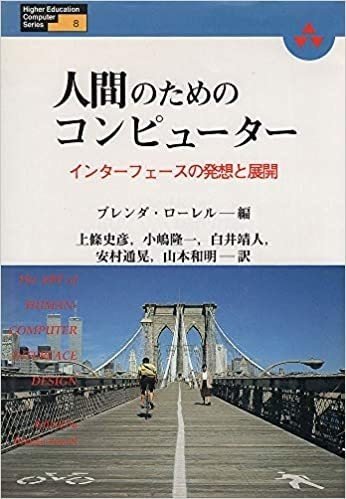COVID-19からの学び1:無駄こそが大事
コロナ禍で起きた、かつてみないスピードのデジタル化
(下の引用ツイート)
— Nobi Hayashi 林信行 (@nobi) March 30, 2020
あなたの会社のデジタル移行を推進したのは?
A)CEO
B)CTO
C) #COVID19
—
では、中国の大気汚染を抑えるのに成功したのは?
A)中国共産党
B)中国外の圧力
C)COVID19
貧富の差やオーバーツーリズム、満員電車や過労は?
騒動が終わった収束した時、我々が戻るのはどちらの世界? https://t.co/NkNf6XK3O5
コロナ禍、英語圏でこんなツイートが流行った。
実際、COVID-19(新型コロナウィルス)による外出自粛が広がる中、Zoomなどのソフトを使ったビデオ会議が、世界中に一気に広がった。
ちょっと前までITが苦手そうだった人まで「次回のミーティングはこちらで」と慣れた様子でZoomミーティングのURLとパスワードを送ってくる様子に何度か驚かされた。
私もイタリアでお城のような家に住むファッションデザイナーから、ボストンに住むテクノロジー系アーティスト、京都の庭づくりの職人、百貨店の店員まで幅広い人とZoomでトーク番組やミーティング、飲み会などを行なった。
パソコンそのものの普及や、インターネットの利用、ソーシャルメディア、スマートフォンなど、さまざまなデジタルテクノロジーが世の中に浸透する様子を目の当たりにしてきたが、ニーズに駆られて広がったこの4〜5ヶ月のビデオ会議に勝るスピードのデジタル化(デジタルトランスフォメーション)は見たことがない気がする。
しかし、それに合わせてさまざまな問題も生じている。
特に「Zoom疲れ」などと呼ばれている心理的ストレスの問題を耳にすることが増えてきた。
これは十分に予見できたことで、私もMacFanという雑誌の3月末発売号のコラムでもこれを予言していた。
でも、もしかしたらデジタルツールに慣れ親しんでいるデジタルネイティブの世代は、感じ方が違う部分もあるのかも知れない、と思っていたが、先週、急速なデジタル化はデジタルネイティブに取ってもストレスの大きなできごとだと知る機会があった。
金沢美術工芸大学での遠隔授業だ。私は河崎圭吾教諭の誘いで2019年度より同学の客員教授として年に1〜2回の講義を行なっているが、先週、約1年ぶりの講義をZoomで行ったのだ。
学校オンライン化がもたらす心理的負担
1年に1回の頻度では、生徒の素性や能力、関心事も知らないままで、普通に講義をしてしまうと、どんな生徒かもわからずに一方的に講義する形になってしまう。そこで授業に先立って提出してもらう事前課題を用意した。
どうせならテクノロジーの精通度や、どんな考えや価値観を持っているかや、そしてコロナ禍にどんなことに困っているかを知りたかったこともあり、「外出自粛をつづけながら、より良い学びを可能にするシステムの提案」をテーマにした。
たくさんの興味深く示唆に富んだ提案があった。優秀な提案も多かったので、興味のある企業にはヒアリングでもしてもらいたい。これまでもスカパーなどいくつもの大企業とプロジェクトを進めてきた学生たちなので、詳細の発信は学生たち本人に任せたい。
だが大まかに分類すると、以下の2つの提案が多かった。
(1)雑音を排除したコミュニケーションが生み出す不快さ
(2)隙間時間をなくしたことが生み出す不自由さ
(1)は、私もMacFanのコラムで指摘した点だ。デジタルツールの多くは、効率化重視でつくられていて、それ故に使う側も効率を重視してしまいがちだ。
コミュニケーションツールの、ビデオ会議では、実際には世界各地に散らばって離れ離れにいる人たちが、やや至近すぎるくらいの距離でお互いの顔を正面から覗き込むようにしてコミュニケーションをすることを前提につくられている。話している人の声は、相手との距離に関係なく均等な音量で届く。小さな雑音も均等な音量で届くので、人数が少しでも多くなっていると、誰かが話をしている間は他の人はミュートにして一切の物音を発せず聞き役に徹するといった形での話し合いになることが多い。
話す側は相槌や笑い声といった反応もない中、相手が本当に聞いてくれているのかもわからない不安にかられながら暗中模索でひとしきり話しては、他の人に話を振るスタイルだ。これは教員だけでなく、聞いている側の生徒も疲れる。
課題では聞いている人たちのリアルタイムの反応を話者に返すための仕組みの提案であったり、例えば隣の席の人や、同じ班の人の授業中の私語が聞こえてくる実際の教室のような空間的概念を取り入れる提案が目立った。
これもまさに私がMacFanのコラムで指摘していたものだが、他の多くの人も、同様のフラストレーションを感じているのだろう。最近、周囲を見渡してみても、そういった試みを目にすることが多い。
例えばspatial.chatというロシアのサービス。これはまさに画面上に仮想空間をつくっては利用者をアイコンとして表示。自分のアイコンを動画や他の人のアイコンに近づけると、近づいた動画や人たちの声は聞こえやすくなるが、それまで聞こえていた動画や人たちの話し声は音が小さくなり、現実世界のような音の空間が再現されている。
ライゾマティクスも、緊急事態宣言中、毎週金曜日に開催していたイベントの後で、同様の音空間を使った実験を行なっていた(Twitchというサービスを基盤にして独自に開発。そこで真鍋大度さんがDJをしていた)。
「授業中の私語」など、先生によっては言語道断で、まったく無駄なもののように思えるが、学生たちがリラックスした気持ちで授業を楽しむには、実はこうした無駄や遊びの部分があることこそが大事なのかも知れない。
(2)の「隙間」というのも、まさにそうした無駄の話だ。ある生徒は、ZOOMでの授業だと、朝起きてベッドの目の前のパソコンの電源を入れたら、もう教室にいる。これだと授業に向けての気持ちの切り替えができない、と指摘していた。通学時間であったり、学校についてから廊下などを歩く移動時間。これもまったく無駄なようでいて、そこでしばらく会っていない友達とのセレンディピティが起きていたり、部活の話をしたり、気分の切り替えなどが行えていた。
しかし、仕事や学校生活が効率一辺倒でつくられたデジタルツールで置き換えられたことによって、そうした本来大事だった「無駄」が突然、切り捨てられたのだ。
無駄こそが大事
今のデジタルツールの多くは、こうした「身体性」をまったく考慮せずに、ただ「用を成す」こと、仕様書に列挙された機能を提供することだけを念頭に作られていることが多い。
「効果的」、「効率的」、「機能的」かつ「実用的」であることに「最適化」はされているが、使う人の気持ちへの思いやりが少ない。
心地よかったり、高揚感をもたらしたり、ポジティブな議論を促したりとかそういうものがない。
ヒトとコンピューターではつくりが違う。
ヒトは休みなく情報の洪水を浴びれば疲れてしまう。また次の仕事、次の勉強への切り替えに時間がかかる人もいる。デジタルコミュニケーションでも、会議でも全員と目を付き合わせて行うのでは疲れてしまうのでよそ見をするくらいの遊びも必要だし、あいづちや私語といった雑音も必要だ。
多くの人がデジタル漬けになることで、今、改めて、こうした「無駄」と見なされていたことが大事だったかと実感した人も多いはずだ。
奇しくも、私は昨年のカナビ(金沢美術工芸大学)でも、「これから無駄がいかに大事になるか」という話をしていた。
3時間以上の講義の内容は多岐にわたったが、扱った中心テーマの一つはAI時代をどう捉えるかだ。AIが、人間を上回る能力で物事を認識し、処理してくれるAI全盛時代、人がそれに対抗しようとしても意味はなくなる。
そんな時代の人間において求められるのが「無駄」を作り出すことではないかという話をさせてもらった。
それまで多くの人にとって
それまで多くの人が関心を持っていなかった地を探究して新しい「価値」を発見するマルコ・ポーロのような探究型、あるいはそれまで価値のなかった物事に、新たな価値を見出し宇宙のように広い世界をつくりだす千利休のように新しい価値を定義する価値創造型。
特に後者は、少なくともAIが人間の道具である間は、出てこない利用法だろうし、そもそも自分と同じmortal(モルタル=いずれは死ぬ)である人間が定義した価値だからこそ、他の人も共感できると思う。
人を魅了する奥深いストーリーづくり、世界観づくり、そして審美眼、こういったものこそが、少し未来、他の人々の共感を伴って、そもそもどのような価値観から生まれAI技術を採用するのか、といった選択にも関わってくるのではないかと思っている。
インターネットやソーシャルメディアの広がりは「共感」や「反感」といった心理であったり、そもそもの「人と人のつながり」など極めて人間的な部分を増幅してきた、というと身に覚えがある人も多いのではないだろうか。
デジタルツールが進歩して、人の生活の中で大きな役割を担えば担うほど、実はそれを使う人の「人間的な部分」こそが重要になる。
「生人間力(なまにんげんりょく)」というのはeatKanazawaというイベントで中島信也さんが放った、なんとも力強い言葉だが、これからの時代はまさにそれが重要であり、そうした「生人間力」を増強するための道具は、人の身体性を考慮したものでなければいけないと考えている。
人に馴染む道具は、テクノロジーだけでは生み出せない
もし、世界的にも成功しているアップル社の製品が、そうした手に馴染む道具であることに共感する人が多いのなら、きっとそこに学びがあるはずだ(もちろん、すべての人が1つの価値観になびくことはなく、それだから世界は面白い)。
そうやって振り返ってみると、アップルの製品づくりは、初代Macを開発している時から、利用者の視点を持ち込んでくれるデザイナーだったり、心理学者や文化人類学者といった人も巻き込んで、極めて奥の深いディスカッションを積み重ねてつくられてきた。
初代Macをつくった時、アップルは、ただマウスを使って操作するコンピューターをつくっただけではなく、そういうコンピューターのためのアプリはどのようにしてつくられ、どう売られ、どう使われるべきかといったことまで、きっちりと議論をして、Human Interface Guidelineというガイドラインにまとめている(iPhoneも同じで、同様のガイドラインがつくられている)。
Macの何年も後に、表層だけを真似してでてきたマウス操作環境では、例えばアプリによって「OK」ボタンと「キャンセル」ボタンの並びが左右逆になっていたりといったチグハグさがよく見られたが、Macではそうしたことがなく一貫した使いやすさを提供していた。
ウィンドウの角が丸みを帯びていることも、メニューが常に上に表示されていることにも、目に入るすべてが膨大な量のディスカッションの結論であり、しっかりと説明できる理由があった。
有益なディスカッションのいくつかは、今では絶版になってしまっているが、ブレンダ・ローレル氏が編纂した書籍「人間のためのコンピューター /インターフェースの発想と展開」にまとめられている。
だが、今、我々が日常的に使っているデジタルツール(アプリなど)をつくる人の多くは、そうしたことを学ぶこともなく開発をしている。中にはビジネス書や雑誌などに、アプリ開発が仕事として旬だからとか、儲かるからとはやしたてられ、手っ取り早く学べる本と、手っ取り早く学べるスクールで学んだ、という人も少なからずいるかも知れない。
もちろん、きっかけがそうであっても、ユーザーの気持ちを察したり、感じたりしようという姿勢からユーザーに配慮した開発をしている人もいるかも知れない。そういう人は個人的に応援したい。
ただ一方で、ただ「用を成す」だけのアプリでいいじゃないかという人も、それなりにいることだろうと思う。実際、世の中には、ただ用を成せばそれで満足で、使い勝手を向上させる工夫などは余計だという考え方の人たちも少なからずいる。ここは二十年以上色々な人と議論を重ねてきた経験から語ると、交わらない線で、人によって価値観も違えば、仕事の内容も、考える姿勢や方法も千差万別だ。ニューロダイバーシティーという言葉もある(神経多様性または脳の多様性などとも訳される)。
求めるものは多様であってもいいが、これまでのデジタルツールの多くが、作る人も、それを評する人も、機能/効率/スペック側の人たち側への偏りが多かったように感じている。
ビデオ会議が、デジタル音痴の人も当たり前に使うようになってきた今、もう少し、そういった「デジタル苦手」な人たちも「使いにくいものや不快なもの」には、どうしてそう感じているか、どうなったらよくなりそうかも考えた上で声をあげて欲しい。
ツールをつくるエンジニアの多くは、課題解決を生業としており、気づいていない課題は解決できないが、認知した課題に対しては高い解決能力を示す人も多い。
最後に、ここ4〜5年の私を振り返ると、あまり仕事もせずにふらふらと遊びあるいていることが多かったが、これもまさに「次の時代は無駄こそが大事」という嗅覚がどこかで働いていたかも知れない。
「昨日の仕事のつづき」に追われる毎日からは、何の進歩も豊かさも生み出さない。
人は、仕事に追われる毎日から解放され、何か他の新しいものに目を向け探求する「余裕(=無駄)」があってこそ、真に豊かさを生み出せるのではないか。実際、人々の気持ちを豊にする多くの文化は、そうした「余裕」からこそ生まれてきたのではないか、という思いが強まっている。
そう考えると、この4〜5年は、無駄であって無駄ではないと強く思った。
いや、無駄か無駄でないかは、実はそれを受け止める心持ち次第の問題のような気もしている。
これからも適度な「無駄」のバランスの模索を続けたいと思う。