
【全文公開】障害を持つ、ということを想像できますか?
大学で、発想に関する講義をしています。
発想は誰でもできるはずなのに、「できる人」「できない人」の差が激しい領域。
でも、「発想法」というある程度体系ができてる考え方やツールを学べば、鍛えることができます。
つまり、誰でも発想を出せるようになるのです。

発想が出ない理由は?
いくつか要因はありますが、間違いなく言えるのは、
・他の立場を想像できないこと
です。
さらにそれができない理由は、
・やったことがない
・やり方がわからない
・想像すると発想が出る仕組みを知らない
ということに。
他の立場を想像する理由は?
仕事で企画を考える時、そのサービスを利用する人は「自分を含めて多数の他人」です。
そのため、この「多数の他人」がどういうことを求めてるのか?何が課題なのか?どうすれば快適なのか?を的確に知って答えを出す必要があります。
その場合の「他人」は自分ではない人、ということですが、「自分とは違う属性の人」と考えることで、違いが明確になります。
単純化した例ですが、
外国人→言葉
高齢者→IT系の知識
子供連れ→両手がふさがる
子供→漢字、ボタンの高さ
ライトゲーマー→難易度、説明
などなど。
サービスを利用する人たちを考えて、その人たちが快適に使える配慮が求められます。

脱線:
自分がゲームを作ってる時は、自分の遊びたいものを作ってました。
他の立場を想像するやり方は?
漠然と「他の人を想像しましょう」では、なかなか具体的に分かりません。
一番確実なのは「特徴、条件」を定め、自分にはない属性のことを配慮すべき項目にする、ということです。
言い換えれば、「行動に制限を加える」ということ。
先程の例で考えます。
外国人→言葉
webページなどでは、英語を用意したり、UIを世界標準にしたり、グラフィカルな表現で誘導したり、という「多くの日本人向けの作り方」ではない作り方を考えるのが普通です。
この時の配慮は、外国人だけが恩恵を受けるだけではなく、普通の日本人ユーザーにも便利になる部分があるのもご注目ください。
高齢者→IT系の知識
平易な説明にする、プロセスで脱落しないよう全体像と現在位置を常に明示する、やり直しが簡単、などを心がけるでしょう。
これも大多数の人に使いやすくなる方策です。

子供連れ→両手がふさがる
建物の導線で障害物をなくす、レジ横に荷物を置ける台を設置、片手で操作が完了できるようにする、取り出し口をかがまない高さにする、など。
web系では、申し込みなどのプロセスで、赤ちゃんが泣いて中座しても大丈夫なように途中保存を頻繁にできるようにする、なども便利になります。

子供→漢字、ボタンの高さ
表記をシンプルにする、グラフィカルな誘導、高さを二つ用意する、など。
こちらも多くの人に便利として提供できます。

ライトゲーマー→難易度、説明
ゲーマー向けじゃないゲーム仕立てのサービスなどで有効です。
間口を広げたい、あまり機器の操作に慣れてない人も操作しやすいU I、などは、すべてのデジタル系サービスで利便につながります。
他の人を想像する=違いを理解する
これらの行動の基本は
・一般的な属性ではない、違いを認識
・違いに配慮する
ということです。
違い、はあらゆる立場で発生します。むしろ違わないことの方が少ない。程度が異なる訳です。
この考え方をもっと極端に振ってみれば、より発想は出やすくなります。
障害を持つ人=違いの大きい人
自分も視力は弱く眼鏡なしには生活できません。
でも、障害とは言えないレベル。視力もさらに落ちていけば、法律の定める「障害者」という認定を受けることになります。シームレスに繋がってる部分もあります。
現在「障害者」と認定されている人は、違いの大きさに不便を感じているケースが多々あります。
発想をする、という事例で、自分が「なんらかの障害を持つことになったら?」という仮定は、非常に切実で、想像しやすい方法です。
ただ、周囲に障害を持つ人がいない場合、考えることがないだけです。
発想法の練習として障害を考えてみることの利点
自分は、視覚障害を持つ人向けの情報提供サービスを構築中。
さまざまなサービスで、「視覚情報が無くても使えるか?」という視点で全てを設計します。
その時に出来上がったものは、実は外国人、高齢者、子供、IT知識が少ない人、にも有効になるのです。
また、条件がシンプルです。
視覚情報がなくてもサービスを利用できる=音の活用、進行制御、状態情報の提示
などを仮定に基づいて設計しやすい。
まとめると、
利点1
仮定がしやすく具体的な対策を考えやすい
利点2
多くは通常利用者にも便利になる
利点3
障害を持つ人への理解が促進
です。音の出る信号、などは分かりやすい実装例。

学生にも活用中
学生は、企画経験が少ないのは当然ですが、状況の違う他者との交わりも少ない。
なので、なのでなかなか発想しなさい、だけではアイデアは出てきません。
自分は「●●●という状態の人が使えるサービスを考えなさい」など、ユーザー像=条件の絞り込みを提示します。
これにより、他者を想像するクセが付き、さらに障害を持つことの不便への理解も進みます。
障害を違いと考え、日頃から考えること
障害者サービスやサポートは、配慮すべき事も多く、また、その配慮に対する指摘も厳しいものがあり、簡単に考えるべきではない、という風潮があります。
この記事で「障害者」という表現を使ってますが、この単語についても配慮不足を指摘する意見もあります。
ちなみに自分は音声合成を扱ってます。
「障がい者」を「さわりがいしゃ」と読むエンジンで視覚障害を持つ人が困っている事例を当事者から指摘され、「障害者」というこれまで使われてきた表記を使います。
配慮は必要で、自分でも心がけます。ただ、特別視して誰でもが考えるべきではない、という考え方になるのは反対です。
勉強不足の人が考えるべきではない、ではなく、勉強すれば良いのです。それには、もっと日頃から障害ということを普通の条件として考えることができなければ、知識の拡散や多くのアイデアや実装は行われません。
当事者からのご意見は是非いただきたい
すべての障害に対する知識は持ってません。自分ができるところから考えて動いています。
知識不足からくる不具合も絶対あります。ぜひ、ご意見はいただければ嬉しいです。
宣伝:
外国人+駅
という「立場」と「サービス」を絞ることで、発想を出しやすくする考え方を本にしました。
ここから先は
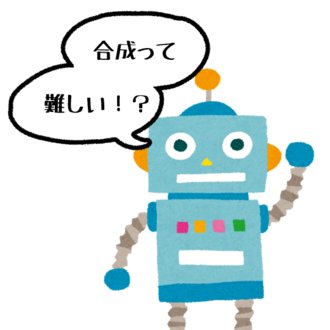
障害のある友人との交流日記
様々な障害を持つ友人がいて、一緒に活動するだけで、様々な知見が得られます。無力を感じることも。 でも、少しでも自分の気づきを世の中にシェ…
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
まだまだ色々と書きたい記事もあります。金銭的なサポートをいただけたら、全額自分の活動に使います!そしたら、もっと面白い記事を書く時間が増えます!全額自分のため!
