
校長先生のつまらない話。生徒=顧客、というスタンスから考えてみる。
タイトル画像:校長先生っぽい4人のイラスト
校長先生といえば
「はい、皆さんが静かになるまでに五分かかりました」
でお馴染みです。
しかし、サービスとして学校経営を考えると、おかしなことだなー、と。
とは言え。
そう簡単に学校や教育は変わりません。せめて、校長先生の話だけでもこんなやり方にならない?という記事です。
校長先生の話って面白い?
面白いですか?
心に残ってますか?
多分、多くの人はNO!じゃないでしょうか。自分は一つも記憶がありません。いや、なんでこんなつまらないことをこの人は朝の時間に人を集めてしゃべってるんだ、という内容。
では、
・面白い話
・記憶に残る話
って一般的にはなんでしょう。
色々な考え方をする生徒たちに比較的共通するのは、漫画やアニメや音楽やテレビ番組。今ならテレビをYouTubeに置き換えた感じ。
そこがメディアで、その中のコンテンツです。
面白くないのは当たり前
校長先生の話は校長先生が考えてるのでしょうか?
そもそも面白い話、というのを作るのは大変。相当のスキルが必要です。
毎週何か話さないといけない校長先生にそのスキルはあるのでしょうか?たぶん、教育委員会の年代や仕事の近い人たちの間では面白い話ができてるかもしれません。
しかし、年代も立場も違う生徒たちに通じる面白い話ができてるでしょうか?などと質問形式にするまでもない。100%に近い数字で、面白くない、と断言します。
なぜか。
恐ろしい事実を知りました。
2018年10月26日金曜日放送、「チコちゃんに叱られる!」で、「校長先生の話はなぜ長い?」というクエスチョン。
その答えが、
・ネタ本がある
・それに自分の話を付け加えるから
さらに、番組中、尾木ママのコメントとして「校長先生の7〜8割は使ってるのでは?」とのこと。

画像:「校長先生 ネタ本」で検索、結果表示ページのキャプチャー
じゃあ、ネタ本がつまらない?とも考えられます。
ということでいくつかのネタ本を見ると…ほぼ『説教臭くて教訓を伝えることが目的になっている』内容が多く、確かにつまらん。さらにそこに「校長先生の意見」もくっつけるので、自然に長くなります。
こういうサービスに頼らず頑張っている校長先生も当然いるでしょう。さらに、本当に生徒が喜んでいる話ができてる先生も。
でも、ほとんどが面白くない話をして、面白くない話を聞かされて、という朝礼の風景が繰り広げられているのです。
つまらない理由は『説教臭いから』ではない
校長先生の話として、なんらかの教訓は込めたいでしょう。
問題は、その演出です。
スラムダンクで有名な安西先生のセリフがあります。
あきらめたらそこで試合終了だよ
これだって教訓的。でも、出自が人気コミック。展開の話なども絡めながらこのセリフを引用すると、結構良い話ができます。
つまり、
昔々あるところに・・・
ではなく、
君たちもご存じのスラムダンクでこんなシーンが
の方が良いわけです。
ちなみに、安西先生、どんな人格者なんでしょうか。名言の宝庫です。ググっただけで、山ほど。
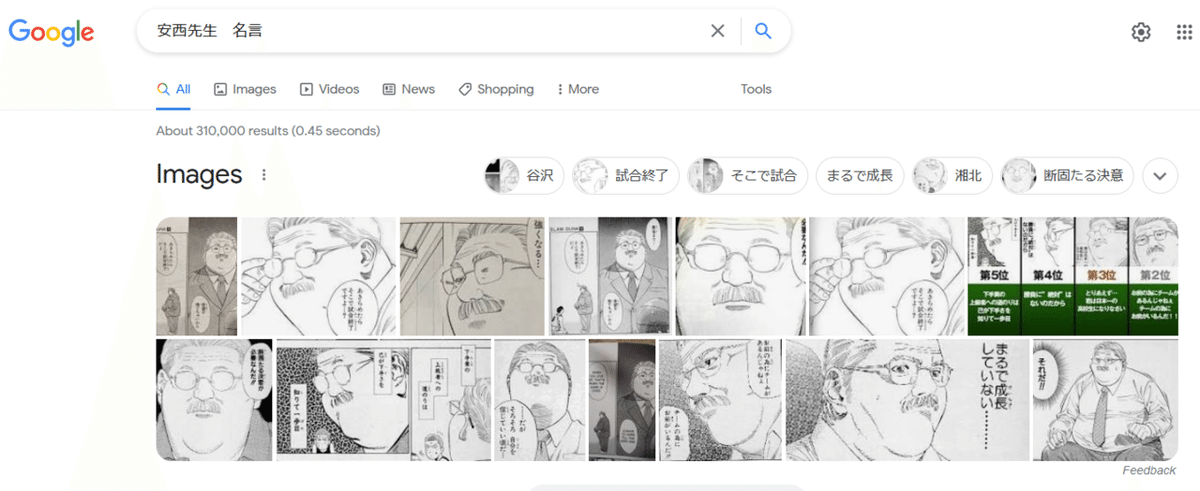
画像:「安西先生 名言」でグーグル検索した結果の画面キャプチャー
もちろん、今の生徒に通じないかもしれません。
つまり、「今の生徒が関心があるメディアやコンテンツから引用」をすれば良いのです。
教育者が書いたネタ本にこの姿勢はあるでしょうか。というか、出版されている時点で古くなってます。
生徒にもっと関心を持とうよ
教育界が見ている『生徒像』と、実際の『生徒』は違います。とんでもなく違います。
生きていて、一人一人が必死に毎日を乗り越えて言ってるのです。いわゆる「モデル化された生徒像の分類」などに、下手したら誰一人はまらない。
生徒は統計や研究資料の中にいるのではなく、目の前にいるのです。
生徒と会話してますでしょうか?
毎日、「今スマホで何を遊んでるの?」「どんな有名人が好きなの?」「ゲームやってる?」「使ってるキャラなに?」「誰にあこがれて部活やってる?」「好きなユーチューバーは?」など、毎日毎日聞きまくるだけでも新たな気づき『しか』ないでしょう。
もちろん、尋問の様に呼び出して聞き出す、などでは生徒も心を開いた会話はしてくれません。自分でも様々なメディアやコンテンツに触れて、知識のアップデートをしておかねばいけません。
時間が無い?
その変な連絡会議をメールに切り替えれば、1日1時間空きます。
とか書いてますが、自戒です
上から目線っぽい書き方をしてみましたが、実際にはなかなかうまく時間が取れないのは存じております。自分も大学生に教えているのと、現役のコンテンツやサービスの企画が仕事なので、アップデートは必須と思いながら、なかなか手が付けられません。
若者という消費者に立ち向かうには、カロリーが高い動きをこちらがしてないと、まったく相手にされません。ご自身が子供の頃のことを思い出してみてください。話が合わないから、話も弾むわけがない。
ということで。
頑張って色々と情報は拾います。
とはいえ、効率的な方法もあります。
知った気になる、でも十分
ゲーム会社にいるときに、外部の方と話をする際、仕事がらみでは当然ゲームの話をすることに。
でも、出版される全てのゲームを体験しておくことは不可能。
どうしたか。
詳しい人にヒアリングしました。また、簡単に概要だけでも調べておく。
この程度であれば、毎日何時間も時間を費やすことはありません。
常にこれを心がけておけば、「・・・と聞いてます」という文脈で、新しい情報の話は最低できます。なにも100%知る必要は無い。
頑張れ先生
昨今の生徒間のはやり、という講座を毎月開いてもいいかもしれません。
少なくとも自分の顧客対象者のことを知らずに、あーだこーだ押し付けてもうまく行くわけがありません。
大きな言い方をすれば、教育だけ高尚で他のサービスと違うということはなく、1サービスの一つ。常に良いサービス提供のための努力が必要なのです。
その一つがこの『生徒の流行』を知ること。
なんならnoteでそういうサークルを作ってみるのも面白いかも。
いいなと思ったら応援しよう!

