
【第601回】 日本のアニメは世界から排除されてしまうのか!?新たなる国連からの圧力?(2024/10/30) #山田太郎のさんちゃんねる 【文字起こし】
文字起こし元の配信動画
発言者:
(山田さん) 山田太郎 参議院議員
(小山さん) 小山紘一 政策秘書・弁護士
今日の内容
(山田さん)
はい、山田太郎の「さんちゃんねる」始まりました。本日は第601回ということで、「日本のアニメは世界から排除されてしまうのか」というテーマでお話ししたいと思います。
現在、国連からさまざまな要望があり、状況は非常に深刻になっています。このあたりについて、しっかりとお伝えしていきたいと思います。
さて、本日は大きな動きが2つありました。1つは女子差別撤廃委員会に関する話題で、かなり盛り上がっていますが、もう1つはニュースではほとんど報じられていない内容です。
国連人権理事会が「ビジネスと人権」に関する作業報告書を出しており、これが波及すると、日本のアニメーション業界に大きな影響が及び、いわゆる「排除」の危険性も生じかねない状況です。この件については、しっかりと対応する必要があると考えています。
今週の山田太郎

(山田さん)
今週の動きですが、非常に忙しい1週間でした。まず、衆議院選挙があり、自民党は大敗を喫しました。今後の展開については注視が必要で、11日に首班指名が行われる予定ですが、それまでに新たな体制が議論されると思われます。どうなるかは不明ですが、引き続き見守っていく必要があります。
各種の応援活動にも参加しました。「表現の自由を守る」と宣言している候補者を応援したりしましたが、選挙は大変なものでした。また、選挙以外にも、「国連の方」から様々な要請がありました。
例えば、女子差別撤廃条約に関する外務省や関係省庁、男女共同参画局などとの打ち合わせ、さらに「ビジネスと人権」に関する人権理事会の要請についても、外務省とやり取りを行いました。
そのほか、経済産業省やデジタル関係企業、障害者政策に関する打ち合わせも行い、選挙や政局とは別に、様々な動きがあった1週間でした。
国連人権理事会「ビジネスと人権」作業報告書
(山田さん)
それでは、1つ目の重要なテーマである「国連人権理事会の『ビジネスと人権』作業部会報告書」について話を進めていきたいと思います。この報告書ですが、発表されたタイミングが意図的だったのかは分かりませんが、10月18日に「日本のアニメは労働搾取」という内容の記事が出ました。Netflixなどのプラットフォームからの排除もあり得るとのことです。この件について、小山さんから記事の内容を簡単に報告してもらいたいと思います。

(小山さん)
国連の報告書が出たのは5月28日ですが、その後、9月9日に官邸でコンテンツ産業官民協議会が開催されました。これを踏まえて、日経が10月18日に報じた内容によると、国連は5月28日の調査報告書で、アニメーターの低賃金や過度な長時間労働、不公正な請負関係、クリエイターの知的財産権が守られない契約などを指摘し、搾取されやすい環境が作り出されていると結論づけています。
さらに、日本のアニメが「人権を侵害して作られた作品」と見なされる場合、米国のNetflixやAmazonといった動画配信サービスを提供する海外企業、あるいは人権意識の高い海外消費者による不買運動につながる可能性があると指摘しています。

(小山さん)
この調査は昨年から行われており、今年7月2日には調査を行ったイェオファントン氏が再来日し、日本の関係者と意見交換を行いました。その際、日本アニメフィルム文化連盟の内山氏が、NetflixやAmazonから日本のアニメ作品が排除される可能性について質問すると、イェオファントン氏は「それは常にあるリスクだ。人権侵害を改める必要がある」と答えたとされています。この発言は、日本に人権侵害が存在するという見方を含んでいるようにも受け取れます。
(山田さん)
特に欧米において、人権侵害が認識・認定されると、企業のコンプライアンスに基づき、その作品がそもそも扱われなくなる可能性が高まります。実際、私のところにも外資系の配信会社やプラットフォーマーから問い合わせがあり、この問題を強く指摘してきました。
このように、日本のコンテンツを積極的に海外に輸出しようとする動きがある一方で、この問題を放置すると、結局「日本のマンガ、アニメ、ゲームは人権を侵害しているものだ」と、一方的に決めつけられ、海外への輸出が全くできなくなる可能性が懸念されます。こうした事態を避けるためには、ビジネスと人権における論点をしっかり把握し、外務省とも連携して反論すべきだと考えています。
この問題について、日本国内では「大げさだ」「極端だ」といった意見も見られますが、欧米では人権問題にフックがかかると、即座に取り扱いが停止されるリスクがあるため、慎重に対応する必要があります。
今日は、この件が「言われなきこと」なのかどうかを検証しながら、皆さんにお伝えしていきたいと思います。放置すると非常に深刻な事態に発展する可能性があると考えています。

(小山さん)
もう1つ重要な点があります。「成長と衰退の分岐点にある」という内容の記事では、日本総合研究所の安井研究員が「アニメ制作スタジオの自助努力だけでは現状打開は難しく、業界の構造が非常に硬直しているため、政府による介入が求められる状況だ」と指摘しています。
また、三村小松法律事務所の田邊弁護士も、「政府の協議会を通じて業界の実態や課題を共有し、具体的な改善策に落とし込むことが重要であり、業界全体で取り組む姿勢を示す必要がある」と話しています。
このように、日本アニメ産業の持続的な成長には、制作現場の持続可能性が不可欠です。そのためにも、元となった国連の報告書について理解する必要があります。報告書の原文は英語で書かれており、事実と大きく乖離しているのではないかという懸念があるため、重要な部分を翻訳・抜粋し、確認を行いました。

日本のアニメーション市場は成長しているが、初任給は150万円と低く、収益増と格差が存在。
業界で約30.8%がフリーランスや個人事業主として働き、労働法の保護が受けられない。
過剰な長時間労働や不当な下請け関係が継続しているが、制作会社には罰則がない。
クリエイターは知的財産権を十分に保護しない契約を結び、搾取されやすい環境が生まれている。
(小山さん)
その後、アイドル業界についても一部言及されていますが、本日はアニメ産業に焦点を当てるため、割愛します。国連特別報告者の役割についても触れておきたいと思います。

(小山さん)
外務省の説明によると、国連特別報告者とは「特定の国の状況や特定の人権テーマについて調査・報告を行うために人権理事会から任命された独立専門家」を指します。
この独立専門家は特定の国を代表しておらず、見解は独立した資格で表明されます。また、報告書に含まれる勧告には法的拘束力がなく、日本政府の公式見解としても、特別報告者の見解は個人の資格に基づくものであり、国連やその機関である人権理事会の公式見解ではないとされています。
(山田さん)
以上のように、この報告はあくまで個人の見解として発表されたものであり、国連を代表するものでも、法的拘束力を持つものでもないことを、改めて確認しておく必要があります。
しかし、現実的にはどのような影響があるのか。また、過去と現在で状況がどのように変化してきたかについても説明していきたいと思います。私自身も、2019年の参議院選挙公約にこの問題を掲げたことがあるため、その内容を振り返りながらお話しします。

(山田さん)
確かに、2019年の公約において、私も次のような点を挙げました。アニメ業界では、動画担当者の平均年収が125万円程度で、毎日の労働時間は約10時間に及ぶという調査報告がありました。
また、労働基準法や下請法の法的な抜け穴に置かれている可能性があることや、アニメーション業界全体の売上が制作者に公正に分配されていないこと、プロジェクト管理や法的ガイドラインの整備が必要であることなどです。
これらの公約は、当時さまざまな調査結果を基にして掲げたものでしたが、現在の状況はどのように変わってきたのでしょうか。現在、国民民主党の玉木氏が「手取りを増やす」と掲げる中、私もこの業界で実際に手取りを増やすためには何を是正すべきかについて取り組んでいます。
アニメ産業の労働実態

(山田さん)
2019年の調査段階では、この問題がどのような状況だったかについて、JaniCAの調査結果も参考にしていきます。アニメーション制作者の職種別年収や年齢、勤務年数についてですが、特に赤い四角で囲まれた部分に注目すると、動画担当者の年収は125万円と非常に厳しい状況であり、勤務年数も4年と短期間です。これは職種によって大きな差があることも示しています。
例えば、制作監督のような職種では、年収が1500万円の人もいれば、500万円程度の人もおり、幅があります。しかし、CG制作や動画チェック、動画そのものを作成している現場の制作者たちの年収は総じて非常に低く、厳しい労働環境に置かれていることが調査で明らかになっています。

(山田さん)
では、具体的にどのように状況が変わってきたのかについて、同じJaniCAが2023年に実施した最新の調査結果があります。2019年の調査と比較すると、状況は大きく改善されているようです。まず、動画担当者の年収を見ても、平均は263万円と約2倍に増加しています。中央値は243万円で、大体240万~260万円の範囲に収まっており、かなり改善されています。
このように、2023年の状況はかなり改善しているはずですが、それにもかかわらず国連の報告が過度に低い数値を基に議論しているのではないかと危惧しています。この間、実質的な改善が進んでいることも、ぜひ理解していただきたいと考えています。
(小山さん)
また、経済産業省もこの問題に関してレクチャーに参加しており、「年収150万円」という古いデータは現在の実態と異なるのではないかとの指摘もありました。

(山田さん)
状況の経年変化も確認する必要があると考えていますので、これについてもJaniCAや芸団協の調査を見ていきたいと思います。具体的には、2009年のJaniCA調査によると、アニメーター全体の平均年収は255万円でした。
その後、2015年の調査では332万円、2019年には一部の動画アニメーターの年収が低かったものの、アニメ制作全体の平均は440万円で、中央値は370万円でした。
そして2023年には、平均が455万円、中央値が422万円となり、ここ数十年年収が上がらなかったと言われていた中で、アニメーターの現場を含めて賃金の改善が見られるようになりました。
それにもかかわらず、国連の関係者が「あたかも日本のアニメ業界全体が未だに問題を抱えている」と発言しているのは、少し疑問に思います。
(小山さん)
オレンジの矢印で示した部分についてですが、2019年には山田さんが待遇改善や手取りの増加、長時間労働の是正を掲げていました。2019年から2023年にかけて状況はどのように変わったかというと、平均労働時間は1日約9時間となっています。
(山田さん)
私が公約に挙げた当時は11時間ほどで、2015年頃の報告書でもそのようにされていましたが、現在は9時間未満まで改善されています。
(小山さん)
待遇が改善された背景には、コロナ禍でアニメ業界が需要増で潤ったこともありますが、それ以外にも様々な施策が進められてきたことが要因と考えられます。

(山田さん)
次に、フリーランスの状況についても取り上げてきたので、フリーランスの対応や実態について見ていきます。こちらもJaniCAの調査を参照しますが、2019年時点でフリーランスの割合は5割超、正社員は15%でした。しかし、人手不足や巣ごもり需要の影響もあり、2023年にはフリーランスが30%、正社員が40%と正社員が増加し、比率が逆転しています。
(小山さん)
このように、国連の特別報告者も定点で評価するだけでなく、動向を見て判断すべきです。
(山田さん)
彼らは直近の情報も得ているはずですが、悪い面ばかりが取り上げられ、「労働環境が悪く、日本のアニメや漫画はこのような環境で作られている」といった一方的な印象を広められる筋合いはないと考えています。

(山田さん)
アニメーション制作者の年収についても、平均が455万円、中央値が422万円と改善が見られます。十分とは言えないかもしれませんが、業界全体の構造を考えると、他の産業と比較しても大きく遜色があるわけではありません。
ただし、年齢別に見ると、若年層の年収にはさらなる見直しが必要です。中高年層を含めた職種ごとの比較も踏まえ、この実態をしっかりと理解していただきたいと思います。
(小山さん)
このデータを見ると、確かに20~24歳の初任給にあたる層の平均年収は196.6万円と低めで、200万円には届きません。しかし、それでも150万円という数字がどこから出てきたのかは疑問に思います。

(山田さん)
NAFCAの調査結果を見ると、職種ごとにフリーランスが多い分野がある一方で、制作関係やCG、美術、撮影など現場に近い職種では、正社員や契約社員が多く、アルバイトも含めると約8割が雇用契約に基づいて働いています。したがって、「アニメ業界全体がフリーランスに依存している」との見方は一部誤解があるかもしれません。

(山田さん)
1日あたりの労働時間を雇用形態別に比較すると、意外にも正社員や契約社員の方が長時間労働している傾向が見られます。短時間労働が多いのはフリーランスで、正社員や契約社員には長時間労働が目立ちます。
これは、フリーランスが自己裁量で働きやすいことや、専門性の高い分野ではフリーランスを選ぶ傾向があるためと考えられます。こうした点を考慮すると、「アニメ業界が長時間労働・低賃金である」という見方は、やや異なった様相を帯びてきます。
次に、雇用形態別の手取りについても傾向を見ていきたいと思います。

(小山さん)
こちらの文章についてですが、NAFCAのレポートからそのまま抜粋した内容です。社員の収入は早期に頭打ちとなり、フリーランスより労働時間が長いとされています。契約社員を含めた社員とフリーランスを比較すると、収入の中央値は社員の方が高いものの、労働時間の中央値も社員の方が長く、時給換算すると両者に大きな差はありません。
さらに、収入の上限を見ると、フリーランスには年収1000万円に近づく、あるいはそれを超える人も少数ながら存在する一方で、社員の年収上限は約840万円、契約社員では720万円に留まっています。
社員は安定しているものの、特に豊かな状況とは言えない実態が見て取れます。このことから、私たちは「偽装フリーランス」は許容できませんが、真にフリーランスを希望して業務委託契約で働き、時間や収入もある程度自分でコントロールしている人たちも存在することが分かります。

(山田さん)
したがって、国連の報告で「日本は長時間労働で収入も低く、搾取が行われている」という印象が与えられた背景に疑問を感じます。NAFCAの2023年の調査では、アニメ業界の年収についても回答者の想定年収が示されていますが、これを厚生労働省の「国民生活基礎調査」のデータと比較してみましょう。

(山田さん)
この調査によると、日本全体で最も多い年収層の中央値は400万円、平均は524万円となっています。アニメ業界の年収が特別に低く、搾取されているとまでは言えない状況になってきているのではないでしょうか。
確かに、私が初めて公約に掲げた当時、JAniCAの資料にもあるように、アニメ業界の年収は非常に低く、問題視されていました。しかし、その後、フリーランス新法や業界・政治の双方の努力により、状況は大きく改善されてきたと考えています。

(山田さん)
このデータは世帯ごとの年収や一人あたりの収入を基に比較したものです。こうした数値と比べた際に、本当に日本のアニメが「労働搾取の産物」であり、NetflixやAmazonが取り扱いをやめるべきなのかという国連の主張について、私は非常に疑問を感じています。
(小山さん)
JAniCAの継続的な調査によれば、アニメーター全体の1人あたりの平均年収は455.5万円、中央値は422.5万円となっており、日本の全世帯の中央値と比較しても遜色ありません。したがって、どのような基準で「搾取状況にある」と判断されているのかについても、再確認が必要だと思います。
(山田さん)
ぜひ、国連の関係者には来日した際に私に直接インタビューをしていただきたいと考えています。日本が「バラ色の状況」だと言うつもりはありませんし、改善すべき点はしっかりと改善する必要があると考えています。
しかし、事実に基づく正確な情報をもとに、適切な勧告が行われることを望んでいます。さもないと、その勧告が独り歩きし、「日本は労働環境が劣悪」というイメージが広がってしまいます。
外資系企業からも「このままでは日本のアニメを扱えなくなる可能性がある」との問い合わせを受けたことがありますが、事実は異なることを強調したいと思います。
フリーランス新法施行までの経緯
(山田さん)
では、フリーランス新法の施行までの経緯や背景についても触れていきたいと思います。「何もしていない」「保護されていない」といった指摘がある中、フリーランス新法はこうした問題に対応するために制定されました。もちろん、現在の状況が理想的だとは言えませんが、どのような努力がなされてきたかについても詳しく見ていきたいと考えています。

(小山さん)
この資料は、公正取引委員会の公式ウェブサイトに掲載されている内容です。2024年11月1日から、フリーランスの方々を対象とした新しい法律、いわゆる「フリーランス新法」が施行されます。このサイトは非常に分かりやすくまとめられており、フリーランスの方々だけでなく、その他の皆さんも一度ご覧になると興味深い内容が多いかと思います。

(小山さん)
フリーランス新法に違反した場合についても、サイトで説明されています。例えば、違反した場合には行政の調査を受け、指導や助言が行われるほか、必要な措置の勧告がなされる可能性があります。勧告に従わない場合には、企業名の公表や罰金が科されるといった罰則も適用されるため、フリーランスのアニメーターもこの法律によって保護されることになります。
(山田さん)
だから「国連の方」から来た人々や関連報道に対しては疑問が残りますが、特に2023年の調査がフリーランス新法の成立後であったことを考えると、改善のための法律が既に存在しているという事実が考慮されていないようです。
この新法は昨年4月に成立しているため、国連側も知っているはずですが、報告では反映されていない点はおかしいと感じます。より精密な調査が求められるのではないでしょうか。
さて、フリーランス新法について具体的な禁止行為にも触れておきたいと思います。この法律では、例えば以下のような行為が禁止されています。

勝手に報酬の受領を拒否する
報酬を一方的に減額する
不当な返却要求や買いたたきを行う
他の業務を強制して不当な利益提供を求める
何度も修正を要求し、費用を支払わない
これらの禁止行為は、現場で実際に起きていた問題に対応するために設けられたものであり、この法律の意義は大きいと言えるでしょう。
(小山さん)
このフリーランス新法は、下請法の規制をある程度スライドさせて、フリーランスとの取引全般に適用しようというものです。ただし、フリーランスとある程度継続的な取引がある場合、例えば1ヶ月以上の業務を行うケースが対象となっています。

(小山さん)
特に注目すべきは、ガイドラインに記載された禁止行為の「買い叩き」と「不当な経済上の利益の提供要請」です。買い叩きは低賃金に対する牽制となり、不当な利益提供の要請は知的財産を搾取する行為への対策です。
公正取引委員会と厚生労働省が出したガイドラインでは、買い叩きに該当する具体例が示されています。例えば、短期発注によりフリーランスに追加の費用が発生するにも関わらず、通常の報酬より低い額を支払うことは買い叩きに該当します。
また、知的財産権が含まれる成果物の委託において、フリーランスと協議せずに通常より低い対価を設定することも、知財の搾取として禁止されています。
さらに、不当な経済上の利益提供の禁止についても、知的財産権の譲渡や使用許諾に関して、協議や適正な対価の支払いが行われない場合は違反と見なされる可能性があります。つまり、フリーランスが本来持つべき権利を不当に取り上げて使用することは許されないと明記されています。
(山田さん)
このように、フリーランス新法では、具体的な規制を通じて、フリーランスの収入を確保し、適切な労働環境を整えるための施策が講じられています。この法律はアニメや漫画業界に限らず、新たな働き方が広がるあらゆる産業に影響を与えるものです。私も国民民主党の活動の一環として先駆けて取り組んできた自負がありますので、玉木さんとも一緒に進めていきたいと思います。

(山田さん)
フリーランス支援に関して、これまでどのような成果があったのかを振り返りたいと思います。我々は公約として、下請法の見直しが必要であると強く訴え、取り組んできました。
また、フリーランスの現状や定義も曖昧であったため、フリーランスとフリーター、あるいは労働者との違いを明確にするよう政府に求めてきました。基本的にフリーランスは個人事業主ですが、その定義を明確にすることが重要だと考えています。
(小山さん)
また、ガイドラインの策定や下請中小企業振興法の改正も行われ、特にアニメーターや声優など、委託契約が多い職種にも法的な適用が及ぶようになりました。
この「下請中小企業振興法」は、親事業者と下請事業者が協力して下請企業の体質強化を図るためのもので、金利優遇などの金融支援も含まれています。2021年の法改正により、アニメや声優業界も支援対象に加えられた点が大きな進展です。
(山田さん)
下請法の見直しも引き続き必要とされており、フリーランス新法だけではカバーできない部分もあります。しかし、フリーランス新法により、多くのフリーランスが保護され、権利を確保できるようになったことは大きな成果です。
私が2019年に自民党に加入して以来、公約に基づき下請やフリーランスの問題に取り組み、彼らの手取りを増やすことが産業政策に繋がると確信してきました。そして、ついに念願のフリーランス新法の制定に至ることができたと感じています。
フリーランス新法が施行される以前に、どのような課題が存在していたのかを整理したいと思います。これは2019年から2020年頃に「さんちゃんねる」で取り上げてきた内容で、覚えている方も多いかもしれません。

(山田さん)
日本にはもともと「下請法」があり、下請け事業者を保護する法律として機能していましたが、実際にはこの下請法が適用されない領域が存在し、特にアニメーターなどの現場クリエイターが苦しむ原因となっていました。
労働契約には大きく2種類あります。1つは雇用される「労働契約」、もう1つはフリーランスとして働く「請負契約」です。雇用契約の下では、労働基準法や最低賃金法によって様々な保護が受けられ、育児休業制度や休暇制度も整備されています。このため、企業規模にかかわらず雇用契約の労働者はある程度守られてきました。
一方で、フリーランスは独立した個人事業主であり、雇用関係がないためにこうした労働法の保護が及びません。さらに、下請法が適用されるのは発注側の資本金が1000万円を超える場合に限られていました。
資本金が1000万円以下の発注企業については法律の適用がなく、「下請けが保護されない領域」が存在していたのです。この点が非常に大きな問題となっていました。
下請法は独占禁止法の「優越的地位の乱用」に関する特則とされていますが、独占禁止法を直接適用して保護するケースはこれまでに一件もありません。下請法は、対象となる行為や条件が明確に規定されているため、適用しやすい法律とされています。しかし、フリーランスが多い領域では、この「保護なし」の領域が問題になっていました。

(山田さん)
2019年のJAniCAの調査によると、アニメ業界ではフリーランスや自営業者が圧倒的に多く、これらの個人事業主が下請法の保護から外れていた状況が明らかになっています。
一方、発注側のアニメ制作業者の約38%が資本金1000万円未満、さらに25%が資本金1000万円ちょうどで、下請法の適用を免れるギリギリのラインに位置していました。このように、半数以上の制作会社が下請法の適用外で、発注を受けるアニメーターたちは保護されない状態に置かれていたのです。

(山田さん)
また、我々が独自に調査したところ、資本金が1000万円の会社でも売上が120億円、従業員が124名と、実質的には大規模な企業も存在していましたが、下請法の適用外となるケースがありました。
これに対して、私は段階的な基準の導入を提案し、例えば売上が5億円、または従業員が50人以下の制作会社に限定して下請法を適用外とする案を検討しました。資本金1000万円という基準は、実質的な規模を反映していない場合が多いためです。
かつては株式会社を設立するには資本金1000万円が必要でしたが、現在では1円から設立できるため、資本金が企業の実態を反映しなくなっています。そのため、下請法の適用基準を資本金ではなく、従業員数や売上高などの規模で判断すべきだという意見が出ています。
ただし、全ての小規模事業者に下請法を適用すると、手続きやコストの負担が大きくなるため、柔軟な対応も必要です。例えば、2〜3人の会社が小さな発注を行う際に厳格なルールを適用してしまうと、かえって取引が滞る可能性があります。このため、1000万円という基準に固執するのではなく、状況に応じた線引きが求められています。
この問題は国会でも議論され、2020年3月の通常国会で私が自民党議員として初めて質疑に立った内閣委員会でも取り上げられました。

(山田さん)
当時、フリーランスの定義が明確でなかったため、内閣官房の西村担当大臣にフリーランスの定義について質問したところ、内閣官房で整理を進めると約束していただきました。これがフリーランス新法の制定に向けた第一歩となりました。

(山田さん)
その後、フリーランスの実態調査も行われ、取引先とのトラブルが頻発している実態が明らかになりました。例えば、約3分の1が契約書を交わさず、報酬を一方的に減額されるなどの問題が指摘されています。

(山田さん)
また、当時はフリーランスの対象人数が各機関によって異なり、内閣府では341万人、中小企業庁では472万人、厚労省では367万人と、ばらつきがありました。内閣官房が政府全体で統一調査を行い、フリーランスの定義や範囲を明確にしました。

(山田さん)
さらに、フリーランスのガイドラインでは、「実店舗を持たず雇用者もいない事業主や、1人社長であり、自身の経験やスキルを活用して収入を得る者」という定義が示されましたが、個人的には「基本的に個人事業主」とするべきだと考えています。
フリーランス新法において、特に問題視されたのが「1人社長」の扱いです。フリーランス新法の適用範囲は、基本的に発注される側が1人で働いている場合に限られます。例えば、2~3人のグループで仕事をしている場合には、適用の対象外となり、下請法でしか保護されません。
そのため、「1人で仕事をしているからフリーランス」という定義が果たして適切なのか疑問が残ります。フリーランスであってもグループで発注を受けることはあり、そのようなケースがフリーランス新法の対象外となることが課題です。
それでも、1人親方のような個人事業主に対するカバーはフリーランス新法の制定によって改善されました。資本金1000万円という基準についても、自民党に所属してから私が議論を重ねてきました。

(山田さん)
下請法の適用を受けない企業の中には、売上が120億円に達する規模の大企業も含まれていますが、資本金を1000万円に抑えることで法の適用を回避している例もあります。このような状況に対しても、資本金基準に代わる対策を検討すべきという提案を行い、フリーランス新法が策定されるきっかけになりました。
こうした取り組みの結果、2023年4月28日にフリーランス新法が成立し、さらに広範囲でフリーランスや小規模事業者を保護する体制が整えられました。

(山田さん)
先ほどの国連の件に戻りますが、国連の方々が日本でヒアリングを行ったのは2023年の7月から8月にかけてでした。つまり、この時点でフリーランス新法について知っていたはずです。
フリーランス新法は4月28日に成立して大きな話題にもなったため、7月のヒアリングで話が出なかったとは考えにくいのですが、報告書には一切触れられていません。

(山田さん)
さらに、11月1日から施行されるフリーランス新法に関しても記述がなく、日本について「労働搾取が行われ、低賃金で長時間労働の現場がある」とだけ記載されています。
(小山さん)
これは、公正を欠く内容ではないかと疑問を抱きます。報告書の執筆にあたり、最新の情報を意図的に省略したのか、単なる失念なのかは不明ですが、実態と異なる印象を与える内容となっています。

(小山さん)
実際、文化庁や動画協会(AJA)はフリーランスのアニメーターを不当な契約から守るため、業務委託契約のガイドラインを策定しています。今年の1月に発行されたこのガイドブックには、個人の制作者(フリーランス)と発注者である制作会社が適切な契約を結ぶための指針や、契約のひな形も掲載されています。

(小山さん)
また、フリーランス新法に基づき、請求や支払いにかかる消費税や所得税の取り扱いについても法律に準拠して行うよう求めています。このように、文化庁と業界が協力してアニメーターを保護する取り組みを進めているにもかかわらず、それが国連の報告書やそれを元にした記事に反映されていない点には意図を感じます。
関係者はきちんと対応しているはずですが、外務省に「どの関係者と会ったのか一覧を出してほしい」と依頼したところ、「個人資格で来ているため、自由にさまざまな人と会っており、我々として一元的に把握はしていない」との返答がありました。
日本の産業が危機的状況にさらされている中で、政府がこのような対応で良いのか疑問が残ります。この国連の報告書をもとに日本が実際に排除された場合、どのように対応するのかという問題もあります。

(小山さん)
政府がビジネスと人権に関して何もしていないわけではありません。実際に「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定しています。ビジネスと人権の概念は、2005年にハーバード大学ケネディスクールのジョン・ラギー教授が国連事務総長特別代表者として提唱し、2011年に「ビジネスと人権に関する指導原則」が発表されました。
これは条約や法令ではなく、法的拘束力はないものの、影響力を持つ取り組みであり、日本政府も2020年に行動計画を策定しています。
(山田さん)
にもかかわらず、タイミングを見計らったかのように、10月には日本に対する批判的な記事が出され、実際に調査も行われているのにあのような報告書が発表されるという状況に対しては強い抗議を表明し、自制を求めていきたいと思います。
女子差別撤廃委員会 第9回報告書に対する最終見解
(山田さん)
さらに、本日取り上げたいのは「女子差別撤廃委員会」の日本に対する第9回報告に関する最終見解についてです。この報告でも、日本の漫画やアニメ、ゲームが再び標的にされており、非常に憤慨する内容が含まれています。最近のニュースでも報じられているため、これについても丁寧に見ていきたいと考えています。

(山田さん)
この件には前哨戦があり、2021年9月頃から第9回の報告書の準備が進められ、その後コロナの影響で対面審査や最終見解が遅れていました。10月末に女子差別撤廃委員会から最終見解が出るため要注意だと以前「さんちゃんねる」でもお伝えしました。外務省とも協力し、毎日のようにやり取りしながら、この対面審査でどのような質問が出るかを確認していました。

(山田さん)
実際、2021年12月頃から外務省や男女共同参画局とも協議を重ね、変な方向に進まないよう調整を続けてきました。例えば事前質問表では、「女性および女児に対する性暴力を助長するポルノ製品の禁止に関する措置」についての質問がありました。

(山田さん)
これに対し、日本政府は、わいせつや児童ポルノに関する法律に基づき、違反には厳格に対処していると回答し、インターネット上の不適切なコンテンツにも監視を強化していると説明しています。

(小山さん)
第7回・第8回の最終見解では、マンガ・アニメ・ゲームに対する懸念が示されていましたが、第9回ではそのような指摘は見られず、日本政府も「今回の審査では関連がない」との立場をとっていました。

(小山さん)
特に、「ポルノ製品」という表現について、漫画やアニメ、ゲーム等が含まれるのかを確認したところ、日本政府は「含まれないと考えている」との見解でした。また、対面審査で漫画やアニメに関する質問があった場合も「これらはポルノ製品ではない」と毅然と対応するとの立場を、2021年の段階で外務省は明確に示していました。

(小山さん)
その他の情報として、事前質問表や対面審査の質問がどのように最終見解に反映されるかを確認したところ、女子差別撤廃委員会のメンバーが独自に作成したり、国内団体から寄せられた意見を基に作成することが分かりました。
最終見解は、委員会メンバーの個人資格で作成されたものであり、国連の公式見解ではないことも明らかです。勧告には法的拘束力はなく、日本政府としては反論する義務はないが、必要に応じて反論は可能とのことです。

(山田さん)
2024年10月17日に行われた対日審査でも、漫画やアニメ、ゲームに関する質問は一切ありませんでした。これは、国連側が日本のコンテンツに対して問題視していないことを示すものだと考えています。

(山田さん)
にもかかわらず、最終見解には「ポルノグラフィー、ビデオゲーム、マンガ、アニメーション製品が女性や少女に対する性暴力を助長する可能性がある」と記載されています。
(小山さん)
ここで興味深いのは、過去の第7回・第8回の見解では「助長する」と断定的に書かれていたのに対し、今回は「助長する可能性がある」と表現が変えられている点です。
おそらく、十分な根拠がないため断定を避けたのではないかと考えられます。この微妙な表現の変更には意図が感じられ、断定から「可能性がある」への変更は、委員会が慎重に表現を選んだことを示唆しています。

(山田さん)
女子差別撤廃委員会の最終見解に関して、委員会は「差別的なジェンダー固定観念が女性や女児に対する性的暴力を強化している」と断言し、「ポルノやビデオゲーム、アニメ製品の生産と流通に対して法的措置と監視プログラムを実施すべき」と強く勧告しています。
この勧告に基づき、日本政府に対して行動を求める声も上がっていますが、これにより「漫画やアニメ、ゲームは問題を助長しているものであり、監視や法規制が必要だ」という印象が広がる可能性があります。
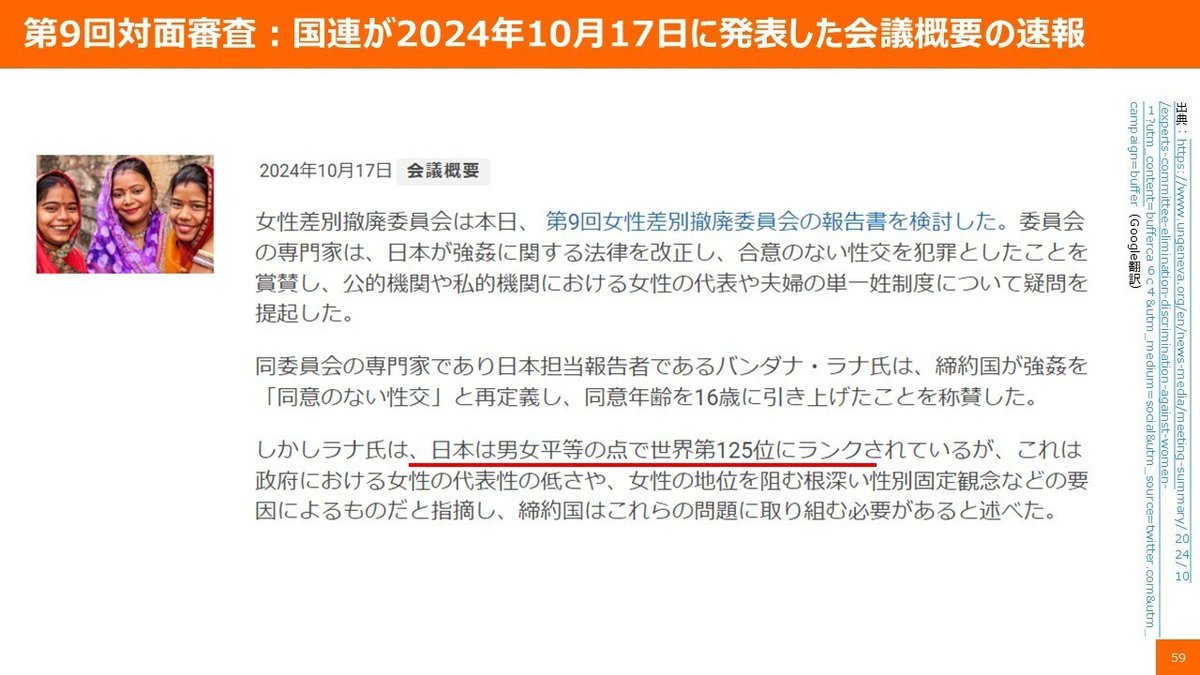
(小山さん)
10月17日に行われた対日対面審査では、外務省の知らないところで国連から会議概要の速報が出されました。その中で、ラナ氏が「日本は男女平等の点で世界125位にランクされている」と述べましたが、これは現段階で正確ではありません。

(山田さん)
この「ジェンダーギャップ指数」については文科省などでも指摘され、日本が低評価を受けているとされていますが、その評価の内訳も理解する必要があります。

(山田さん)
具体的には、ジェンダーギャップ指数は「健康」「経済参画」「教育」「政治参画」の4つの局面で構成されています。日本は「教育」と「健康」の分野で高い評価を受けており、ここではジェンダー平等が進んでいます。
しかし、「経済参画」では賃金格差が見られ、「政治参画」では女性の参画率が低く、特に政治分野での遅れが全体の評価を大きく引き下げています。政治分野において男女の比率が低いため、日本全体がジェンダー不平等であるかのように見られがちですが、実際の評価ポイントを理解することが重要です。
政治参加の遅れは確かに課題ですが、他の分野での取り組みを含めて日本の実態を公正に評価することも大切だと考えています。
(小山さん)
文部科学省の令和3年の政策に関して、2019年のジェンダーギャップ指数で日本が過去最低の121位となったことを課題として挙げていますが、その対応として「子どもを性犯罪等の当事者にしないための安全教育推進事業」を掲げており、根本的な問題を理解していないと感じます。
ジェンダーギャップ指数で評価されているのは、むしろ女性の政治参加などにおける遅れです。これに対する取り組みとしては、女性も政治に参加できる可能性を教育の中で示すなどが、的を射た施策が必要ではないでしょうか。

(山田さん)
また、ジェンダーギャップ指数(GGI)だけが唯一の評価指標ではありません。ジェンダー開発指数(GDI)やジェンダー不平等指数(GII)も存在し、これらは国連開発計画(UNDP)が発表しているものです。
GGIが世界経済フォーラム(WEF)という民間団体によるものである一方、GDIやGIIは国連機関によるもので、より多面的な視点を提供します。実際、GIIでの日本の順位は193カ国中22位で、決して悪いとは言えません。
にもかかわらず、評価基準をジェンダーギャップ指数のみに限定し、日本のジェンダー政策全体が劣っているかのように捉えられるのは偏った見方です。さまざまな指標を公正に評価し、改善すべき点と良い点の双方を考慮することで、より適切な政策が形成されるはずです。
(小山さん)
ジェンダーギャップ指数(GGI)が低いという課題に対して、まずは女性の政治参画や経営者の増加を目指すのが妥当な取り組みです。しかし、それとは関係のない「子どもへの性被害防止」のような施策が追加されているのは、GGIの改善とは直接関係がないと思われます。
さらに、最新のGGIでは日本は118位となっており、以前の121位より改善されていますが、国連では一年前の過去最低の順位を引用しており、文科省も最悪の数字を前提に自虐的な評価を行っている点に疑問が残ります。
国連の指標を利用せず、悪い数値だけを根拠にするのは、フェアな調査とは言えません。改善されている点を無視することは偏向的な印象を与え、日本の状況が不当に悪く評価される結果になります。
今日のまとめ
(山田さん)
ビジネスと人権の観点からも、日本のアニメ業界が改善に向けて努力を続けてきたことは事実です。しかし、国連からの指摘により、欧米を中心に不買運動が広がる可能性が懸念され、業界全体が危機にさらされています。
例えば、フリーランス新法が2023年4月に成立したにもかかわらず、7月のヒアリングでその存在に触れられなかった点など、日本の取り組みが意図的に無視されているように感じます。こうした偏向的な扱いには、強い抗議が必要だと思います。
(小山さん)
経産省や文化庁、内閣府など、政府全体で日本のコンテンツ産業を推進しようとする動きが強まっている中で、国連の人権理事会の特別報告者からは「日本のアニメ産業は搾取的である」とされ、女子差別撤廃委員会からは「日本のポルノ、ビデオゲーム、アニメーションは女性や女児に対する性暴力を強化している」と指摘されています。
もしこのような偏見に基づく見解が国連の根拠として世界に広められ、日本のアニメがそのように認識されると、日本のコンテンツ産業にとって大きな打撃となりかねません。
(山田さん)
特に女子差別撤廃委員会の報告書では、「日本の漫画やアニメが性別や性的指向に基づく暴力を助長している」と断定的に言われているような内容です。
しかし、実際にはそのような事実はなく、これが世界に広まれば、日本のアニメ産業は非常に厳しい状況に置かれる可能性があります。このため、こうした偏見に対してしっかりと反論し、国際社会で日本の立場を守る必要があると感じています。
(小山さん)
国連の人権理事会や特別報告者の独立性は重要ですが、調査が適当なのか、あるいは恣意的なのか、疑問が残る点が多いです。2019年から私たちもアニメーターやフリーランスの支援に取り組み、厳しい声も聞きながら改善を続けてきました。それにもかかわらず、こうした努力が全く評価されないのは残念です。
(山田さん)
必要であれば、ニューヨークの国連本部に赴き、直接訴えることも検討しなければならないかもしれません。実際、過去には新サイバー犯罪条約に関しても現地で強く働きかけた経験があります。
(小山さん)
ただ文句を言って「ダメだ、おかしい」と叫ぶだけでは解決しませんが、今回の件は本当に危機感を覚えています。これまでにも、いわゆるポリコレ問題の影響で、日本のアニメが「女性を搾取している」と見なされ、ミニスカートを履いたキャラクターが描かれているだけで搾取と指摘されるような状況がありました。第7回・第8回の女子差別撤廃委員会の最終見解でも同様の内容が示されており、今回もまた出されてしまったことが残念でなりません。
そのため、報告書が発表される前から外務省や内閣府、男女共同参画局と連携し、対面審査において適当な発言がないよう注意を払ってきました。実際、対面審査では何も言及されなかったため、「国連も反省したのか」と思っていたのですが、結局、調査もせずに問題視する内容を含む報告書が出されてしまったのは非常に残念です。
(山田さん)
昨今、海外からの外圧が強まっており、表現の自由を守るために引き続き尽力していきたいと考えています。また、政治の動きに加え、日々の生活や国民の手取りを増やすための地道な努力も重要です。
フリーランス新法の成立は多くの人々と協力して実現したもので、業界全体の意識も少しずつ変わってきていると感じます。もちろん、すべてが理想的な状態とは言えず、厳しい状況にある職種もありますが、こうした改善の取り組みを評価しないまま、国連など外部から一方的に批判されることには強く反対します。
もちろん、日本のアニメ業界に改善すべき点があることは事実で、指摘されるべき部分もあるかもしれません。しかし、それらは事実に基づいて行われるべきです。
もしこのような不確かな批判が世界中に広まれば、不買運動や企業のコンプライアンスの影響で日本のアニメが使用されなくなる可能性があります。そうなれば、アニメ産業そのものが大きな危機に瀕し、搾取の議論どころではなくなってしまいます。
(小山さん)
日本のアニメが海外で売れなくなれば、アニメーターや制作会社、制作委員会に出資している人々すべてに大きな打撃が及び、生活に困る人々が増えるでしょう。こうした状況を避けるためにも、事実に基づいた適切な対応が求められています。
(山田さん)
本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

