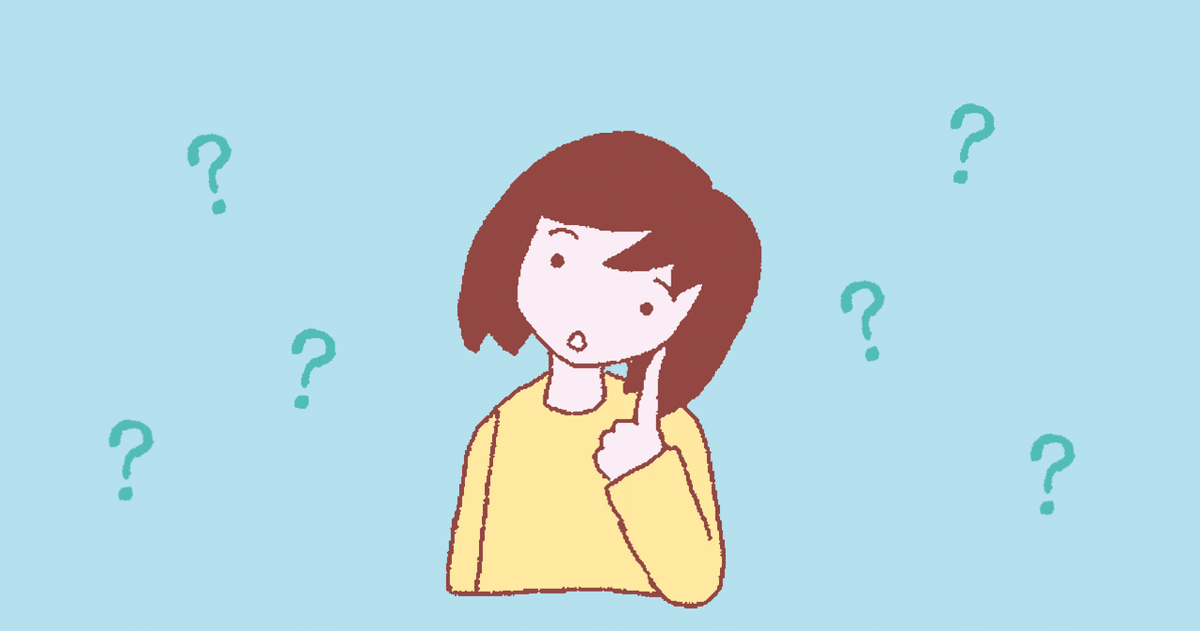
その他のちょっとしたコツ〜小説新人賞の攻略法(16)
崖っぷち作家のニジマルカです。
「新人賞の攻略法」16回目です。
今回はちょっとしたコツです。
15回目はこちら。↓
質より量
なんとなくの感触でいうと、長編を10作くらい書けば、文章も、構成も、問題ないレベルになると思います。
文庫換算で2500ページ。
文字数でいうと100万文字を越えるくらいでしょうか。
いままで書いてきた原稿を数えてみるといいです。
物語として完結している原稿で、短編を混ぜてもいいでしょう。
(できれば長編だけ数えた方がいいです)
自分自身を振り返ってみても、ごちゃごちゃ悩むより、10作書いた方が早かったと思います。
もっと言えば、10作も書いてないのに悩んでもしょうがないです。
圧倒的に量が足りていません。
逆に言うと、10作も書いてないのに諦めるのも早いということです。
10作くらいのところで1つ壁を越える感触があるので、ひとまずそこを目指すのがいいと思います。
出版できない賞なら取らない方がマシ
ちょっと言い過ぎかもしれませんが、地方の新聞社がやっている文学賞とか、地方の自治体がやっている短編賞とかは、取らない方がいいと思っています。
私はある企業の賞を取ったのですが、そこから出版できませんでした。
それから、改めて受賞するのにかなり苦労しました。
たとえ小さな賞でも、取ってしまうと、妙なプライドを持ってしまうものです。
「自分はこれでいいんだ」と勘違いしてしまうのですね。
「もう賞を取っている」と思うと、挑む姿勢が薄れます。
出版できていない以上、常に挑戦者でなければならないのですが、しょうもない実績があると、安全策を取ってしまうのです。
どうなるかというと、うまくいった路線をそのまま踏襲するようになるのですね。
それでうまくいけばいいですが、うまくいかなくても、「いや自分はこの路線で受賞したんだから」と同じようなものを書いてしまいます。
すると、大げさに言えば「過去の栄光にしがみつく人」みたいになってしまうのです。
地方の文学賞を取っても、短編賞を取っても、ほぼ出版できません。
多少は自信がつくかもしれませんが、ほとんどの場合、そんな賞は荷物になるだけです。
荷物は邪魔になります。
荷物があると、思いきり飛ぶことができないからです。
何も持っていない人の強みはここです。
手に何もないからこそ、思いきり飛べるのです。
小さな賞を取って喜んでいる場合ではありません。
2,3日喜んだら、すぐにそのことは忘れて、また挑み始めましょう。
賞状とか盾とかもらっているなら、いっそ捨てるのも手です。
(私は捨てました。「すぐに手に入るのだから捨てても問題ない」と強気でいきましょう)
壁にぶつかったら得意技を封じてみる
何年も同じところでつまづくことがあります。
たとえば自分の場合だと、ずっと三次選考を越えられずに苦戦しました。
そういうときは、得意技を封じてみるのがおすすめです。
得意技とは要するにウリのことです。
誰しも、自分のウリ(武器)を持っているものです。
たとえば、キャラを作るのが上手いとか、ひねったストーリーが上手い、文章が上手い、といったことですね。
さて、ここで、よく考えてみましょう。
あなたは、すでに自分の得意技を生かして勝負しているはずです。
つまり、ウリで勝負しているのですね。
でも、うまくいっていないのです。
だったら、それはウリではありませんよね。
なぜなら、買われていないからです。
あなたのウリはウリとして機能していません。
得意技を使っても、負け続けているのです。
ですから、一度、得意技を封じてみましょう。
それが難しければ、少なくとも、「得意技の他に別のものでも勝負してみよう」と考えてみてください。
だいたいにおいて、壁にぶつかったときは、「やりたくないなあ」と思っていることが答えです。
「やりたくない」どころか、「それはないでしょ」「そこまで堕ちたくない」「ないわ〜」と思っていることが大正解だったりします。
「挑戦する」というのは、そういった「ないわ〜」と思うところに踏み込むことを言うのです。
今回のまとめ
新人賞の攻略法16回目「その他のちょっとしたコツ」でした。
1.10作くらい書くまでは悩んでもムダ
2.出版できない賞なら取らない方がマシ
3.壁にぶつかったら得意技を封じてみる
次回は「基礎知識まとめ」です。↓
それではまたべあー。
