
「太陽と大地の聖地」をつなぐレイラインの神秘とは? 真田一族の本拠地・上田のもうひとつのロマン
日本遺産普及協会では、各地域の日本遺産に関する知識を深めるため、定期的に「日本遺産勉強会」を開催しています。8月のテーマは、長野県上田市の『レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」~龍と生きるまち 信州上田・塩田平~』でした。今回は塩田まちづくり協議会の事務局長である藤森靖夫氏が参加し、日本遺産ストーリーを解説していただきました。また、地元の「信州上田・塩田平検定」にも挑戦する機会がありました。
上田市について
長野県上田市は、東京から約190kmの距離にあり、北陸新幹線を利用すれば最短80分でアクセスできます。上田城跡がある上田駅周辺、真田一族と深い縁を持つ真田地域、スキー場が点在する菅平高原など、人気の観光地が数多くありますが、今回は別所温泉で知られる塩田平地域に焦点を当てます。

今回の日本遺産の中心である塩田地域には、弘法大師ゆかりの弘法山がそびえており、そこからは田んぼ、ため池が広がる自然豊かな地域を眺めることができます。江戸時代には「塩田三万石」と言われたほど、昔から米づくりが盛んだったこの地域に、果たしてどのような日本遺産があるのでしょうか?

ストーリーと構成文化財
日本遺産4つのキーワード
以下は、今回の日本遺産のストーリーです。
独鈷山と夫神岳から扇状に開ける地・塩田平は、古来「聖地」として、多くの神社仏閣が建てられている。山のふもとにある信州最古の温泉といわれる別所温泉、「国土・大地」を御神体とする「生島足島神社」、「大日如来・太陽」を安置する「信濃国分寺」は、1本の直線状に配置され、レイラインをつないでいる。夏至と冬至に、鳥居の中を太陽の光が通り抜け、神々しくぬくもりのある輝きを享受できるのだ。先人たちが、この地が特別であると後世に伝えようと遺した様々な仕掛けは、今も、訪れる人びとにパワーをチャージさせる。
このままではやや複雑なので、全36件の構成文化財から成る日本遺産を、次のようなテーマごとに、一つずつ深掘りしていきました。

①信州の学海
上田は、険しい山々に囲まれた盆地ゆえに、本州では一番雨の少ない地であり、「おてんとうさま」が毎日のように微笑む穏やかな気候が特徴的です。信濃国分寺が置かれたこと、鎌倉北条氏の一派が終の棲家としてここを選んだ理由でもあるとされます。
同時に、平安時代や鎌倉時代にかけて数多くの寺社が建てられ、全国からたくさんの学僧が訪れ、寺で修行をしたことから、塩田は「信州の学海」と呼ばれるようになりました。

別所温泉にある安楽寺の”日本唯一の木造八角三重塔”や全国的にも珍しい北向きの本堂である北向観音堂(常楽寺)が有名です。長野市の善光寺は阿弥陀如来が南向きに祀られており、北向観音堂と南北で向き合っています。善光寺が来世での往生を願う場所であるのに対し、北向観音堂は現世での利益を祈る場所とされており、両方に参拝することで、現世と来世の両方のご利益を得られると言われています。

②神宿る「山」への祈り
上田の少雨な気候は、風雨による災害からこの地の暮らしを守ってきました。しかし、その反面、神は時に干ばつといった試練を人々に課してきました。そこで、人々は水源となる山々に神を崇め、祈り、恵みの雨を願ってきました。

500年以上の歴史を持つ雨乞いの祭り「岳の幟(たけののぼり)」は、その色鮮やかな幟(のぼり)が特徴的です。この幟には「下り龍」が描かれており、水を司る龍神への祈りを象徴しています。祭りでは、夫神岳(おかみだけ)山頂に祀られている九頭龍神「龗(おかみ)」を山麓の別所神社までお連れする儀式が行われます。

③祈りの言葉は「アメ フラセタンマイナ」
塩田平では、ため池を作って水を蓄え、その水を田んぼに流し込むことで温め、稲の生長を促してきました。こうして塩田平は「塩田三万石」と呼ばれる、上田屈指の穀倉地帯へと発展しました。このため池でも「百八手」と呼ばれる雨乞いの祭りが行われています。祭りでは、大勢の人々が池の周りを取り囲み、たいまつに火を灯して立ち上る煙の中で「アメ フラセタンマイナ」と唱え、雨を祈願します。
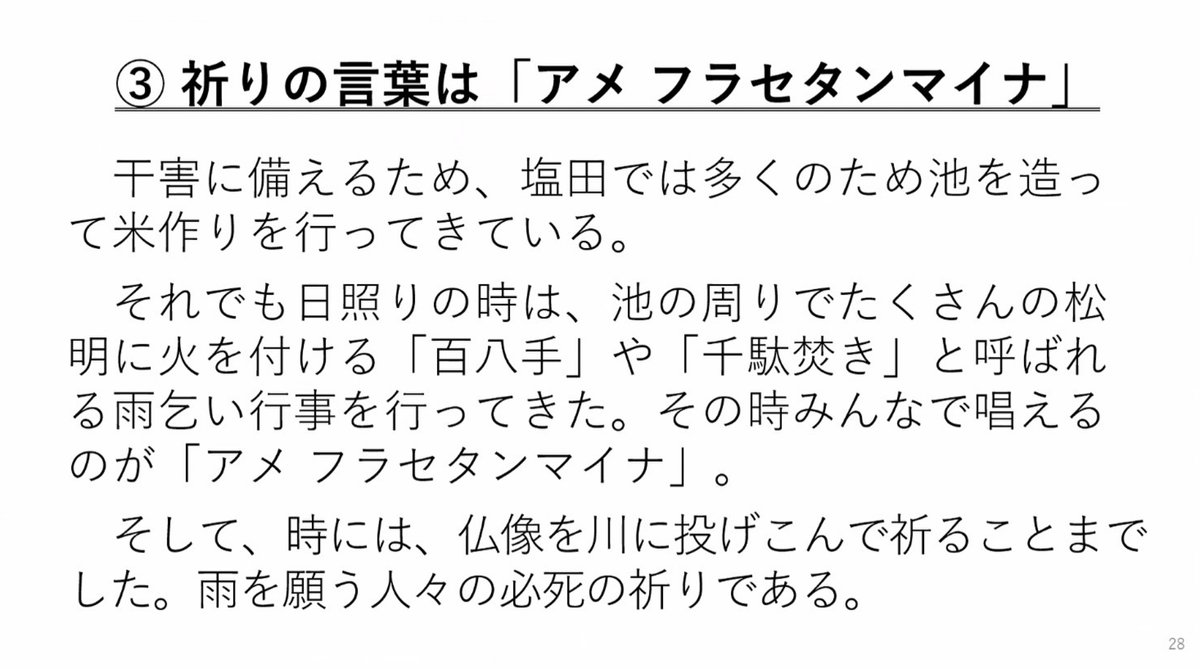
ため池は稲作に欠かせない水を提供するだけでなく、マダラヤンマなどの生き物たちの命も育んできました。また、ため池にまつわる人柱やカッパの伝説は、人々が池に神を崇めていたことを物語っています。
雨が降らず困窮する時、人々は時に荒々しい方法を取ることもありました。路傍のお地蔵様を川に投げ入れるという行為です。この時も、祈りの言葉は「アメ フラセタンマイナ」。お地蔵様を怒らせることであっても、龍(雨)と再び巡り会うことを強く願っていたのです。

塩田平には広範囲にわたってため池が点在しており、江戸時代には上田藩内に300以上のため池があったと言われています。現在、塩田平土地改良区に登録されているため池は41ヶ所あり、その貯水量はおよそ300万トンに達します。一般家庭が年間に使用する水の量が約300トンとされているため、このため池群だけで1万軒分の水を賄うことができる計算になります。
さらに、これらのため池は2010年に「全国ため池百選」に選定されました。長い歴史の中で守り受け継がれてきたため池が、現在も維持・管理されている点が評価されたそうです。これらのため池の一部は「いたずらなカッパ」や「いのしし騒動」、「人柱伝説」など、地域の民話にも登場し、その存在が深く根付いています。

④未来への懸け橋
信濃国分寺、生島足島神社、別所温泉は一本の“レイライン”(夏至の日の出の際、太陽が地上につくる光の線)で結ばれており、夏至と冬至には生島足島神社の鳥居の真ん中を太陽の光が通り抜けます。

信濃国分寺三重塔には、太陽の化身とされる「大日如来」が安置されており、まさに「太陽の聖地」と言える場所です。一方、レイライン上に位置する泥宮と生島足島神社では、それぞれ泥と土を御神体として祀っており、大地を象徴しています。こうした背景から、塩田平は「太陽と大地の聖地」として、日本遺産のストーリーに位置付けられています。

日本遺産推進の取り組み
日本遺産推進の目的と取り組み
上田市では、日本遺産を通じて、①全国に情報発信し、多くの人たちに訪れてもらい、②地元の人たちを中心に、地域の魅力・文化財をよく知ってもらうため、行政と地元団体が協働で多くの取り組みを行っています。


日本遺産 信州上田・塩田平検定
多くの取り組みのなかで、一番注目すべきは昨年から始まった「日本遺産 信州上田・塩田平検定」。4択問題が50問出題され、80点以上で合格という形式ですが、記述式の問題が含まれるステップアップコースも実施予定です。
今年は12月14日(土)に、長野県上田市の塩田公民館大ホールで行われる予定で、受験料は一人1,000円(中学生以下は無料)となっています。
勉強会で紹介された問題は以下の通り。



↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解は順に「2. 大日如来」、「1. 約900mmで全国平均の約半分」、「4. 天台宗」でした。勉強会に参加した方々からは、「合格ラインが高く、難しかった」「日本遺産検定(3級)よりも難しい」といった感想が寄せられました。
この検定は現地でのみ受けられます! 検定をきっかけに、皆さんもぜひ信州上田・塩田平を訪れてみてはいかがでしょうか?
オンライン勉強会のお知らせ
10/9(水)20:00〜21:00にオンラインで勉強会実施!
『【無料】60分で解き明かす!日本一危ない国宝「投入堂」と、世界屈指のラドン泉「三朝温泉」の秘密【鳥取三朝町よりライブ配信】』
「日本一危ない国宝」と呼ばれる神秘の建築物「投入堂」、世界屈指のラドン泉「三朝温泉」。日本遺産に認定された「六根清浄と六感治癒の地」の魅力を地元・鳥取県三朝町よりライブ配信で紹介します。
登録は以下のページから可能です。(pietixへの登録・申込が必要です。)
日本遺産検定のご案内
合格して日本遺産ソムリエになろう。
日本遺産検定・3級公式テキストのご案内
日本遺産検定を受けるならぜひ読んでおきたい唯一の公式テキストです。受験に向けた知識のみならず、日本の文化遺産に興味のある方にぜひおすすめしたい1冊です。
