
子どもが苦手なアナウンサーの私が、 メディア・リテラシー教室で子どもたちから教えてもらったもの
はじめまして。アナウンサーの大橋拓と申します。ふだんは「ニュース シブ5時」という番組のリポーターを担当しています。
アナウンサーってどんな人ともコミュニケーションは得意でしょ?と思われるかもしれませんが、実は私、つい最近まで、子どもとの会話が苦手でした。
なんというか、どう接していいかよくわからなかったんです。子どもたちへのインタビューでは、うまく言葉が引き出せずに苦労してきましたし、親戚の子どもには会話どころかいきなり体に乗っかられてタジタジ…ということもありました(距離感がつかめない)。
でも、ある仕事を担当することになり、そんな自分がガラッと変わりました。それは、小学生とオンラインでつながり、「メディア」のことを考える教室の進行役、という仕事です。
うーん、難しそう、と不安に思っていたのですが、始まってみたら・・・楽しい。
なんだか楽しい!
子どもたちの想定外の反応にドキドキすることもありますが、「伝わっている!」という実感がこんなにあるのは、アナウンサーの仕事を始めて一番かもしれません。
今回は、子どもが苦手だった私が、担当する「つながる!NHKメディア・リテラシー教室」を通じて、子どもに教えてもらったことを書いていきたいと思います。
メディアのパワーを思い知った学生時代
ふだん私は「ニュース シブ5時」のリポーターを担当していますが、最近は、テレビで伝えるだけじゃなく、ウェブ記事を書いたり、SNS用の動画を作ったり、といった仕事もしています。
私が「メディア」の威力に気づいたのは、大学時代。当時私は、自分で立ち上げたダンスチームの活動に情熱を注いでいました。学園祭の公演に観客を集めるにはどうすればいいか・・・
必要なのはインパクトに違いない。そう考えた私は、クラシック音楽をBGMに“腰のキレ”を重視するPR動画を作ることにしました。みずから踊って撮影して編集。
当時、YouTubeなどの動画共有サイトはまだまだれい明期でしたが、投稿すると再生回数が瞬く間に伸び、なんと海外からもコメントがついたのです。学園祭にもたくさんのお客さんが来てくれ、動画やソーシャルメディアの力を存分に感じることになりました。

一方で、ダンスの活動では、ちょっと複雑な気持ちも味わいました。
あるテレビ番組に出ることになったときのこと。収録でダンスを披露したあと、スタジオでトークをしたのですが、それが放送された時には、自分に対する出演者のツッコミが際立つように編集され、笑い声も追加されていたのです。
その編集を「うそ」とは思わなかったものの、「あ、こうやって編集するんだ・・・」と何とも言えない気分になったものでした。
子どもたちと「メディア」を考える!
今、私が担当している「つながる!NHKメディア・リテラシー教室」は、こうした「動画の編集」や「画像の加工」などについて、その狙いや意味、「どこまで許される?」といったことを、小学5・6年生を対象に、全国の小学校4クラスをつないで子どもたちと一緒に考える、オンライン形式の体験教室。ことしから始まったばかりです。
メディア・リテラシー教室の台本制作を担当したのは、Eテレの「メディアタイムズ」というメディア・リテラシーについて学ぶ番組を制作したチームです。
検討には進行役のアナウンサーとして私も参加しました。そして、完成した台本を読みながら、戸惑う部分はないかな?とか、どんな言葉をかけたらおもしろく感じてもらえるかな?とか、いろんな反応を想定しながら、家で何度も何度も練習しました。
画面の向こうの子どもたちから即反応!「うわ、伝わっている・・・!」
ことし1月。迎えた、初めての本番。とても緊張しました・・・。
こちらからの「こんにちは~!」という呼びかけに、画面越しに、「こんにちは~」と元気いっぱいの返事をしてくれる子どもたち!!!
一気に緊張が解けました。
うわ、伝わっている・・・!

これって、ふだんテレビでしゃべるときとは全然違う感覚です(テレビでも画面の向こうをイメージしてはいるのですが)。
この教室では、子どもたちが自分の言葉にすぐに反応してくれている。手を振ったら、振り返してくれる。こちらが質問すると、一生懸命考えて答えてくれます。
もちろん、わからないときは反応がやっぱり鈍い・・・。
当然ですが、進行に対しての「そんたく」はありません。でも、だからこそ、わかってもらおうとあの手この手でがんばります。その結果、子どもが「うん」とうなずき、「伝わった!」という瞬間があれば、ものすごくうれしいのです。
教室ではおよそ1時間半にわたり、4校の違う地域の子どもたちが自分の意見を発表しあいます。
画像や動画の使い方について、こんな話し合いをしたとか、こんな感想を持ったとか、いろんな意見を交わすことで、同じ画像や動画でも、人それぞれ意図や受け取り方が違うことがわかります。おもしろい意見が出たときには、学校を超えて笑いも起こります。
オンライン休み時間はかならず“じゃんけん”になる謎
メディア・リテラシー教室は45分×2コマの教室。間に休み時間を10分とります。
実はこの10分間の休憩時間、最初は休憩時間なので、画面に「フタ」をして見えないようにしておこうとスタッフは考えていました。
1コマ目が終わり、休憩時間に入ると思わぬ出来事が。4分割画面のまま、子どもたちが自由にオンラインの交流を始めたのです。みんな、カメラの前に集まってくる・・・!
最初はモジモジ。そのうちクイズを出し合ったり、教室で飼育している動物を見せたり・・・
そして、必ずみんながやるのは、じゃんけん!!

学校が違えば、教室のつくりも、飼っているものもいろいろ違う。オンラインで思いっきり遊ぶ休み時間。予想もしていなかった、うれしいハプニング!
コロナ禍で、多くの学校で学校行事が中止や延期になったと聞いています。
実際、子どもたちの毎回の感想を見ると、「他校の小学生と一緒に学んで楽しかった!」とか、「休憩時間の他校のみんながおもしろい!」という声がとても多いです。
こうして、遠くの地域の子どもたちがオンラインでつながり、交流を全力で楽しんでいる様子を見て、私自身も元気をもらい、幸せな気持ちになりました。
みんなカメラぎりぎりまで前のめり!どんなことを学ぶ教室?
実際どんなことをこの教室で学ぶのか、少しご紹介します。例えば、「動画の編集」では、「インタビュー」をテーマにしています。

まず、「小学生がメイクすることに賛成?反対?」という架空の街頭インタビューを見せます。
動画の中では、メイクに賛成が5人で、反対が1人。でもこのインタビュー、本当は12人に話を聞いていて賛成が6人、反対が6人でした。それを意図的に、賛成の意見が多くなるように編集していたのです。
この時点で、子どもたちにこうした編集をどう思うか聞くと、賛成を多く使ったことに違和感があるという声が続出します。
ところが、この動画には続きがあって、このインタビューは「小学生向けのメイク動画を紹介するYouTuberが人気」という話題の前に見せるためのインタビューだったことがわかります。

そうすると、賛成の意見を多く使ったことはどう考えれば良いでしょうか?
子どもたちに聞くと、今度は意見が分かれます。「やっぱり賛成と反対は半分ずつ使わないとダメだと思う」という子もいれば、「反対が多いと、YouTuberの動画を紹介する流れが悪くなるので、賛成の意見を多くしてもいい」という子も出てきます。
どちらの意見も間違いではありません。ここで大事なのは、「動画を作った人は、何らかの意図をもって編集した」ということを理解することなのです。
こう書くと、「意図をもって編集するなんてけしからん」と思う人もいるかもしれません。
でも、画像・映像・音声などあらゆるメディアは、「意図をもって構成されなければ、伝えたいことが伝わらず、メディアとして成立しない」(教室の監修も務める、日本大学文理学部・中橋雄教授)のです。
例えば、私たちがスマホで動画を撮るときも、「これを撮りたい」とか、「これを見てほしい」という狙いがあって、カメラを構えますよね。
編集も、「これを伝えたい」という狙いがあって、それがわかりやすく伝わるような流れを作ることで成立します。
だからこそ、受け手は、送り手の意図に敏感になったほうがいいし、送り手は、受け手が誤解しないように注意しないといけないのです。
ちなみに、「送り手」としてのNHKには「放送ガイドライン」という指針があり、それに基づいて情報発信をしています。
う~ん、なんだか難しい話になってきましたね。実際、私にとっても難しいですし、教室を進める中で考えさせられることも多いです。
子どもたちの意見の中に、「テレビ的にはそっちのほうがいいかもしれないけど」という言葉が出てきたときにはドキッとしました。う、子どもたち、鋭い・・・。
それはある意味で、子どもたちが、リテラシーを持っている、とも言えるのかもしれません。でも、私たちも「テレビ的」と呼ばれる、いわば「型」のようなものに、無自覚になっていることはないかとハッとさせられました。
本当にその編集でいいのか。そこに込められた意図は何か。メディア・リテラシーが大切なのは、伝える側の私たちも同じです。この教室を通して、メディアの責任を改めて考えています。
アメリカで感じた「メディアの分断」と学びの大切さ
さて、冒頭にも書いたように、私は子どもとのコミュニケーションが正直苦手でした。うまく伝わらなくて、困った顔をされたらなんて言えばいいんだろう。予想外のことを聞かれたら、ちゃんと答えられるだろうか・・・。とても不安でした。
でも、この教室を「やりたいです」と言ったのは実は自分からでした。それはなぜかというと。
去年の年明け、アメリカに派遣され、2か月ほど滞在する機会がありました。当時、現地ではトランプ前大統領の言動が連日のように報道されていました。
しかし、その伝え方は、大統領に好意的なテレビ局と、そうではないテレビ局がはっきりわかるほどに、メディアによって異なっていたのです。
「アメリカ社会は分断が進んだ」とも言われますが、それは、メディア側にもその責任の一端があったのではないか、というのが率直な感想でした。
一方で私は、滞在先の大学で、メディアの構造や影響力といったものを一から学び直していました。
学校教育の中でそうしたものを学んでこなかった私にとっては、すべてが新鮮だったのですが、それと同時に、そうした体系的な知識を持たずにメディアの仕事をしてきたのは、はたして良かったのだろうか、とも思うようになりました。
メディアはますます多様化し、発信者も増えていきます。社会が成り立つためには、送り手も、受け手も、ひとりひとりのリテラシーが欠かせません。
自分自身の反省もありますが、これからの社会を作る世代には、メディアについてもっと知り、考える機会があるべきだと思いました。
だから、日本に帰ってきて、NHKでもメディア・リテラシー教室を立ち上げるという話を聞いて、「ぜひ担当させてください!」とチームに加わったのです。
意見の違いを乗り越える子どもたち
教室の最後には、子どもたちに今日の感想を聞く時間があります。そこで、ある子どもが言った言葉が強く印象に残っています。
「自分の意見だけでなく、他の人の意見も取り入れて、○○だなと決めつけずに、しっかり考えることが大事だと思います」。
う~ん。もう、うなりました。
「他人の意見を尊重し、先入観なしに考える」。意見がぶつかりあうことも多い今の世の中で、これって誰にとっても大事なことですよね。
そして、私自身も子どもに対しての先入観は無かっただろうかと考えさせられました。「子どもはコミュニケーションが難しい」と構えすぎていたところがあったんじゃないか・・・。
お互いに意見を交わすという体験を通じて、子どもたちがそれぞれに受け止め、いろんな感想を持ってくれたことに、感激しました。
「これからは、自分たちがメディア・リテラシーを知らない人に伝えなければならないと感じました」といった言葉には、頼もしさも覚えました。それと同時に、私の中にあった、子どもへの苦手意識もすぅ~っと消えていったのでした。
大人になってわかった学校の意味
さて、その後も回を重ねているメディア・リテラシー教室。毎回、すんなりいくことはありません。
先日の回で、印象深いことがありました。
教室の最後のまとめの発表で、自分から手をあげて感想を発表してくれた児童がいたのですが、途中で言葉が詰まってしまって、うまく言えなくなってしまったのです。
こういうこと、誰だってよくあることです。
私が意味をくみ取るように話すと、少しの沈黙の後、なんとか最後まで言い切ってくれました。ですが、その子が自分の席に戻るときに、目元をぬぐっていたように見えたのです。私は少し動揺してしまいました。
「あれ、もしかして僕の声かけの仕方が悪くて泣いちゃったのかな・・・」。
教室が終わってもその子のことが気になり、せっかく楽しい体験になるはずが、発表のせいで傷ついていないかな、と申し訳ない気持ちでいました。
ところが翌日、この学校の先生から、こんな話を聞くことができました。
「教室が終わったあと、周りにいた友人たちが、こんなことが言いたかったんだよねとか、がんばったよねと声かけをして、本人もうまく言葉が出なかった部分は、今後の糧として納得できていると思います。成功も失敗もあるのが学びの場なので、大丈夫ですよ」
もう私、感動してしまいました。学校って本当にすごい場所だなと。
こうしたことも含めて、学びなんですね。
私は、学校や教室がなんのためにあるか、大人になってようやくわかった気がしました。いろんな人と意見を交わすこと。そしてさまざまな成功や失敗を体験すること。
そのひとつに、メディア・リテラシー教室が貢献できたら、と心から思っています。
みんなに会えるのが楽しみです
というわけで私、このオンライン教室で、これからどんな出会いがあるか、今ではとってもワクワクしています。
始まる前は不安に思っていた、子どもからの予想外の質問でさえ、ちょっとだけ楽しみにしている自分がいます。
「つながる!NHKメディア・リテラシー教室」、今年度の募集枠はいっぱいになってしまいましたが、来年度の募集は年明けに始まります。情報はホームページに掲載していきます。
クラス単位で応募を受けつけていますので、関心がある全国の先生や保護者のみなさん、ぜひホームページをときどき確認してみてくださいね。
ことしの参加校の子どもたちの感想などもホームページに掲載しています。
(ちなみに、この教室を通じて同時に芽生えたのが、学校の先生への尊敬の念。私は、午前と午後の1日2回の教室を担当しただけでもうクタクタに・・・。毎日、授業をしている先生って本当にすごい。全国の先生、心底リスペクトを抱いています!)
アナウンサー・大橋 拓
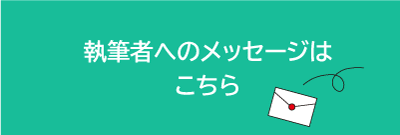
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼メディア・リテラシーについて学べる番組や記事はこちら▼
メディアタイムズ
@media~アッ!とメディア~
#みんなのネット社会 (フェイク・バスターズ)
