
Day9_DX人材育成講座 イノベーションとマネジメント -可変式MS-
0.本日のアイコンプロンプト

うーん、もうちょっと頑張ってほしい
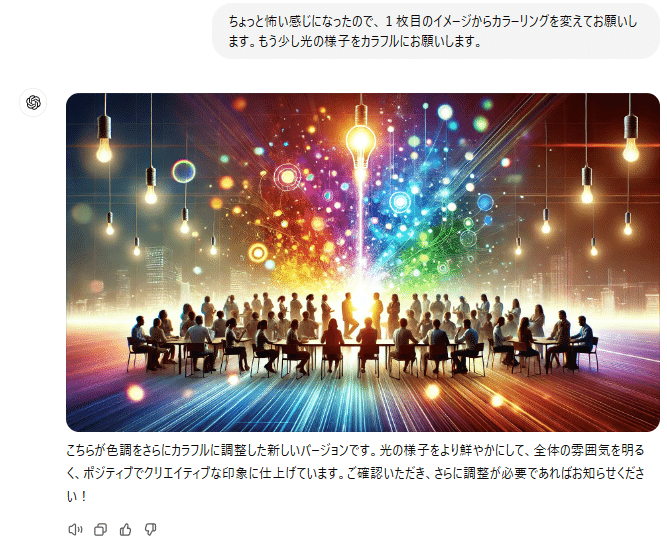
なんか違う……1枚目にするか(何
イノベーションは一人で起こすのは大変なものです。ですので、チームとして変革のために必要な資質が何かという話が今日のテーマでした。
1.未知のものを良いナラティブとして受け取らせる努力

全く新しいことを始める人(イノベーター、天才)は周囲から理解されづらい。時として排斥されていまします。
この図は『天才を殺す凡人』という本からの抜粋ですが、天才は秀才(今までの延長のことしかしない人)には興味がないというのが自分には厳しく感じました。

ただ、やはりイノベーターはここを丁寧にやらねば自分の居場所は変わらないのです。現在のテクノロジーや世論の変化、周囲の受け入れ状況、自分が目指すあるべき姿を上図のように自分の中に描き、どうすればよいかを考え、立場ごとに変化への自然なナラティブを形成し(巻き込み)、実装するというロードマップを作成しなければなりません。最終的に経営陣にもっていくためには財務の知識すら必要。大変過ぎるやろ。
個人的には周囲に合意形成させるための水面下の事前説得が最も大事だと思います。「こうなったらどうかなあ?」とチラっと話に出し、感触を確認し、それに対する反応から次の対応を模索する。そう、アジャイルのためのデータ集積はこんなところから始まるのだと思います。そうしてその人にとって新しいものが良いナラティブになるようにすること。これすなわち根回しです。
ナラティブってのは物語と書きますが、僕はその通り日記やXに「今日は院長からこんな話があった。私はそこまでうまくいくか不安だけど、それでより良いクリニックになったらよいと思う」と前向きになる気持ちが沸き上がるムーブだと思う。
2.マネジメントスタイル(MS)は可変である
可変式MS(モビルスーツ)の宝庫と言えば、Zガンダムですね。自分はやはりアッシマーが初めて変形した瞬間がめちゃくちゃ興奮しました。


話を戻して
組織のメンバーや状態、目的によりとるべきマネジメントの形態は異なる。
それも柔軟に変えなければならない。組織が存亡の危機に面しており、緊急事態であれば独裁者にならねばならないこともあるでしょう。

その中でも、民主主義がもっとも高い業績を残すという意味について掘り下げます。

最も業績に繋がるものは企業文化である。文化としてスタッフが己の力で自走していくことができれば、最も成果が出るであろうということ。ではそういう組織はどうできるか?
オルフェウス室内管弦楽団は指揮者がいないオーケストラです。どのように全体の音楽を作っていくかと言うと、それぞれの楽器を持った人間が頭を使ってどうするべきが最適解なのか考えて動きます。コンマスも曲ごとに毎回変わります。
自分はオーケストラでフルートを吹いていたのでオケの仕組みはよく分かっているつもりです。指揮者はなぜ必要か、のコピペを貼るときがきたようですね。

3.オルフェウス室内管弦楽団に学ぶ民主主義型マネジメントスタイル
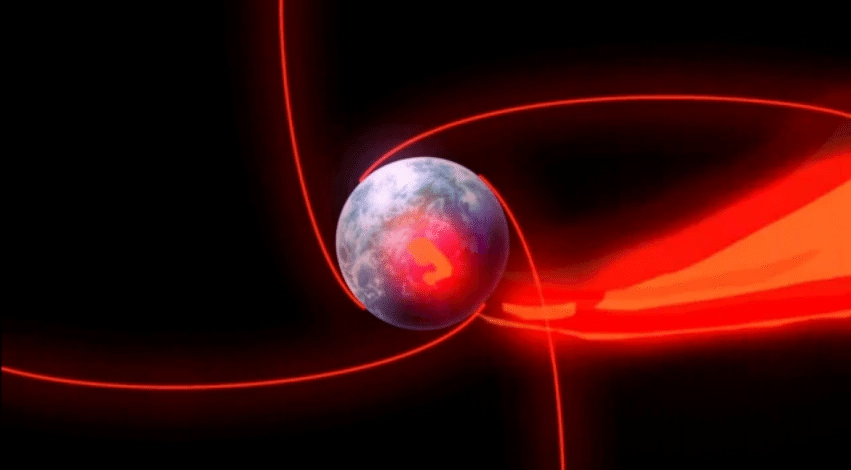
オルフェウスの原則
①その仕事をしている人に権限を持たせる
現場にいて、お客さんのすぐそばにいて生の声を聞いている人が判断するのが一番効率が良い。逐一報告したり、その上でトップダウンにするなどは本当の意味では非効率。
②製品品質に自己責任を負わせる
権限を与えるのであれば、その責任はその人に背負う。
③役割を明確にする
誰が何の権限と責任があるかを明らかにしていく。ジョブディスクリプション(特定の職務や役職に関連する役割、責任、必要なスキル、資格、業務内容を明確に記載した文書)を作成する
④平等なチームワークを育てる
それぞれがそれぞれの役割を果たしているだけであり、社長だから上とかではない。社長の役割が必要ならばそれを使えばよい。それぞれの役割は役割であり、その上で平等である。
⑤リーダーシップを固定させない
誰がリーダーシップを握れば効率が良いのかは、そのときどきで変わる。
④⑤はよくわかります。旅団(クモ)のことですね。

⑥話の聞き方、話し方を学ぶ
普段は上司⇒部下へというスタイルの組織にいるので、平等に接するは難しい。だからこそフィードバックにも、フィードバックを受け取るにも技法が必要です。
(1)フィードバックを与える側は、前向きな気持ちで、相手の行動変化を促すようにを心掛ける。「ダメだよそれじゃ!」では変わらない。
(2)フィードバックを受ける側は、フィードバックを受けたことにまず感謝する。そしてそれを受け入れるかどうかは本人次第である。

■NO RULESで紹介されているNetflixのフィードバックのガイドライン「4A」 | ビジネスゲーム研修なら株式会社HEART QUAK
⑦職務へのひたむきな献身
職員からこれが得られているかどうかは、①~⑥ができているかという試金石になると思われます。

そういった個人が「組織への貢献」に責任を持つ集団こそがプロの集まりであり、それは組織としての強さになります。貢献とは決して純粋な売り上げだけでなく、マーケティング、ブランディング、人材育成など、様々な貢献があります。
「みんな明日からはオルフェウススタイルで行きましょう!」と言う話ではなく、理想論として、このように個々が強い責任感により自発的に動く組織が最も効率的だということです。
4.アップデートのデザインを持つ

変革のためにはチャレンジが必要ですが、チャレンジには失敗がつきものです。ではチャレンジを促すためには、失敗を許容する文化が必要です。しかし文化とはいえ、挑戦したがいいが人事評価が低いでは困ります。そこである程度は人事評価自体を変えてしまおうというのが一つ組織づくりにおける大事なネックになります。
アジャイルなチーム(個々が自分の中で仕事としての小さなチャレンジを繰り返せる)が理想的ではありつつも、そこには不確実性(リスク)が
付きまといます。なので、適切なマネジメントされたチームとは、最終的には不確実性を減らすことが目標となります。
つまり、メンバー各々が物事をよく見て考える(学習する)チームとは、不確実性をマネジメントするということに繋がる。
※おすすめ図書
『カルチャーモデル 最高の組織文化のつくり方』と言う企業文化の大切さを書いた本を紹介したいと思います。利益を上げるビジネスモデルと共に、企業が「いい会社」として成長するためにはカルチャーモデルが両輪で必要だという本です。
「あうんの呼吸」と言われるように、組織には暗黙知として共有され、その都度説明しなくても適切の物事が進んでいくカルチャーが存在します。しかし暗黙知だけあってカルチャーは真意が伝わりにくいこともあります。
カルチャーを構築するための5つのステップ(現状分析、ビジョン設定、方向性決定、言語化、浸透)により、企業は自社の文化を体系的に見直し、改善することが可能になります。
創業者に端を発したカルチャーを、社員が自然と口に出し、顧客にも社員にも良い形で届くように醸成されることで、企業は競争力を身に着け、成長していくとされています。
