
アンラーニング【無】手を放す 空にする 欲しければ捨てる
指導者の端くれとして、交換の時世においては、
情報のつまみ食い
的なコミュニケーションに
いろいろな限界を感じざるを得ません。
指導を受けるための
基本ベースとなる状態
教わる「準備」
についてのお話を
中村天風哲学本その他
からご紹介させて頂きます。

「この日」を限りに人生が一変した!
藁にもすがりたい――。
ギリギリに追い詰められた状況では、
誰もがわずかな命網でも手放せるものではありません。
こんなとき、天風は目を見据えると、
「さあ、その手を放すのだ。後はオレに任せろ」
と、救いの手を差しのべました。
――若き日の岩松三郎(1893~1978)には、
天風が語った寓話がそう告げているように聞こえたのです。
敗戦後の憲法改正に携わり、
最高裁判所の初代判事として活躍した岩松三郎は、
若い頃は悪疾な高血圧と不眠症に悩んでいました。
発作に見舞われると、胸が波打ち、
百メートルも歩くことができません。
治療に努めてみるものの、効果が見られず、
病状は日を追って悪化するばかり⋯⋯。
書かなければならない判決の記録は、
天井に届きそうになっていました。
これを見ると気力が萎え、ますます書けなくなります。
とうてい職務を全うすることなどできません。
岩松は、東京控訴院判事の職を辞するべきかとまで思い詰めます。
相談を受けたのが、大審院長の池田寅二郎(1879〜1939)でした。
池田は中央大学総長を務めた人物で、天風門下生です。
彼は岩松から話を聞くなり、
「いい人を紹介しよう」
と、中村天風のもとに引っ張っていきました。
天風と話した岩松はさっそく、
天風の教えを一ヵ月ばかり受けることにします。
が、内心では半信半疑でした。
しかも、生来の頭のよさが災いして、
天風の話をたちどころに分かったつもりになってしまうのです。
それだけに本気になることができません。
いくら形の上だけで真似てみても、根本の心がふらふらしていては、
その悪疾な病は癒えません。
「結局、効果はなかったのだ」
岩松はそう判断を下すと、
ぷつりと通わなくなってしまいました。
事の次第を知った大審院長の池田は、岩松を呼びつけ、
「紹介者に無断でやめるとはけしからん」
と一喝すると、そのまま天風の前に岩松を突き出しました。
神妙にかしこまっている岩松に、
天風は一つの寓話を語って聞かせました。
岩松は終生、この寓話を忘れることがなかったといいます。
こんな話です。
どうしても悟りが開けないという雲水(修行僧)がいました。
彼は思い余って師の和尚に教えを仰ぎます。
「私には皆目悟りが開けません。どうすればいいのでしょうか」
和尚はその雲水についてくるよう促すと、寺の裏山に登っていきました。
やがて切り立った断崖に出ました。
断崖からは松の大木が横に張り出しています。
その下は、言うまでもなく千尋の谷です。
和尚は松を指差して、
「これへ登るのだ」
と命じました。みるみる雲水の顔色が蒼白になっていきます。
やがて勇気を奮うと、雲水はしがみつくようにして幹に登りました。
すると和尚は、
「その細い枝のところまで行け」
と命じます。ようやく枝のあたりに達した雲水に向かって、
「手だけでぶら下がってごらん」
雲水は命じられるままに、両の腕で枝にぶら下がります。
「それ、片手だけでぶら下がってみよ」
一方の手を放したとき、小枝はしなるように揺れました。
握っているほうの片手には渾身の力が込められ、
まるで鋼鉄のようです。
「さあ、その手も放すのだ」
そう和尚が命じた瞬間、雲水は悟ったのかどうか⋯⋯。
少なくとも岩松は、最後の言葉に心を射られたのです。
「なぜおまえは、最後の片手を放せないでいるのか。
さあ、その手を放すのだ。後はオレに任せろ」
天風が太い命綱を差し出してくれていた、と気づいたのでした。
後年、岩松はこう語っています。
「私は片手を放すところまでの生活しかしていなかったのである。
最後の片手を放せないで、松の小枝にぶらさがっている、
あわれな自分をはっきり見たのであった」
(『哲人哲語』序文より)
この日を境に、岩松の生活は一変しました。
天風の教えに邁進したのです。
たとえば夜、寝際には必ず、
「おまえは元気になれ!」
と、自分に命令暗示をかけました。翌朝、目覚めるとすぐ、
「私は元気になった」
と、断定的な暗示を施しました。
岩松はこうした暗示を、電車の中であろうと、
ところかまわずやりました。気が変になったのではないか、
と周囲に心配されるほどに天風の教えに打ち込んだのです。
すると、どうでしょう。
あれほどまでに彼を悩ませた病はスッパリと癒え、
以後の長い裁判官の職務を見事に果たすことができました。
後年、その功労により勲一等を授けられています。
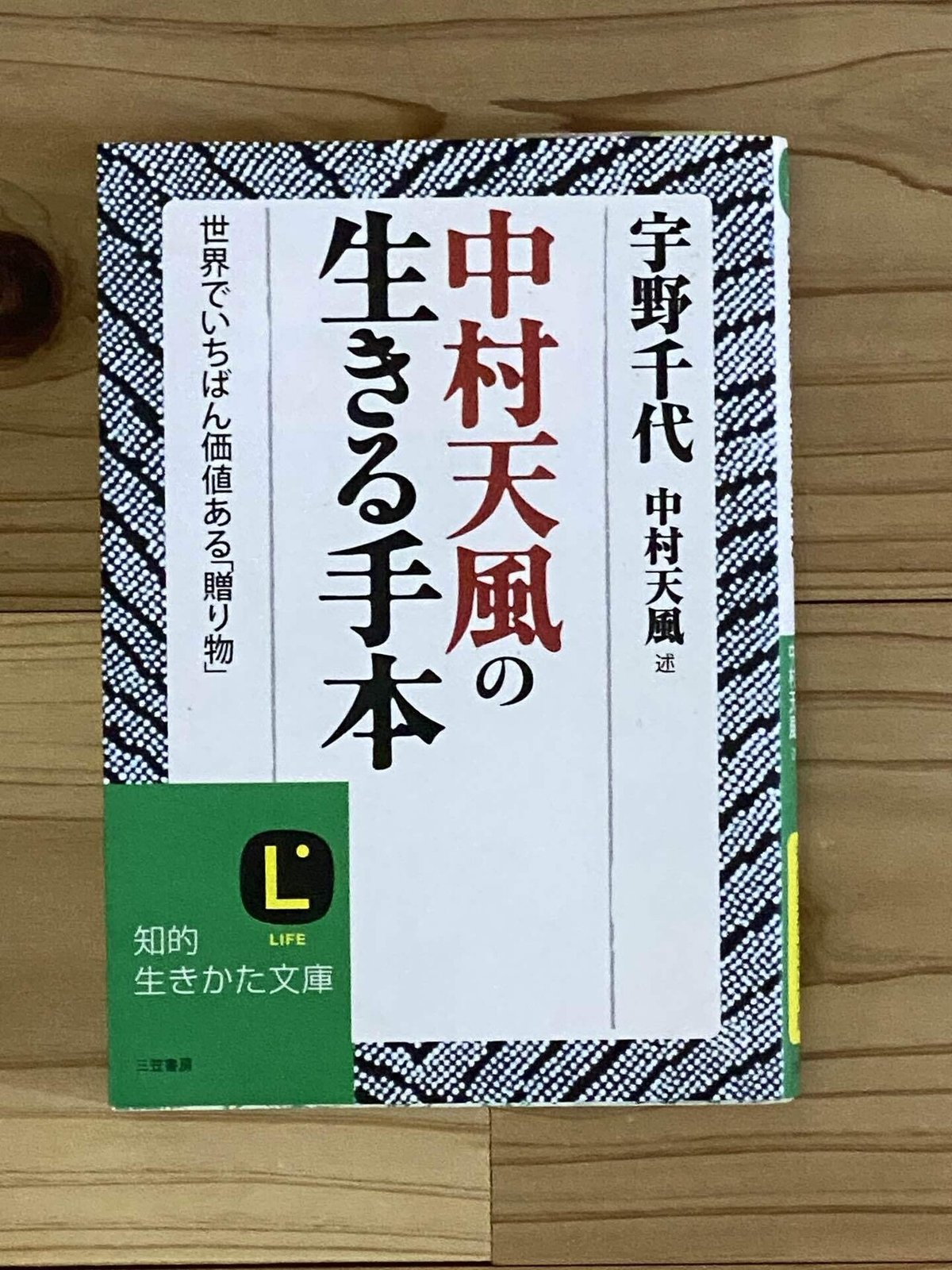
人生の真理を教わる「準備」
こんな筈じゃなかったんだけど、いったいどうなるんだ。
来る日も来る日も、今日教えてくれるか、明日教えてくれるかと、
とうとう二カ月も過ぎようというときに、
あの野郎、こんなくだらないところに連れて来て、何をやる気なんだ。
ぼうっとした毎日で、何にも教えてくれない。
教えてくれないくらいなら、こんなところいる必要はない。
今日はひとつ、追い出される覚悟で直接談判だ、とばかりで躍り出た。
毎朝、必ず廊下を通って、哲学を研究している若い人たちに、
日本でいえば朝のお早ようという挨拶を受けるために、
十人くらいの従者をつれて行く。
われわれは屋根の下にはいる資格はないんですから、
庭から姿を見ているんですが、その朝は胸に一物あるから、
ちょうど私の前に来たときに、ぱあっと立った。
そうしたら、顔を見てにこっと笑うじゃないですか。
しめた、と思って、
「お尋ねしたいことがあるんですが、」
「何だ。」
「カイロでおっしゃったお話は、
いつごろからうかがえるんでしょう。」
「カイロで何と言ったっけな、」
「えっ、お前はまだ救われる人間だ。
だが、自分が助かる大事なことを一つ忘れている。
それを教えてやるから、ついて来い。
そのお言葉で、私はここまでついて来たのです。」
「ああ、あれか。あれなら覚えているよ。」
「いつごろから教えていただけるんでしょう。」
「私の方は、ここへ着いた翌日からでも教えたいと、
その準備が出来ていた。」
「えっ、私はまた、ここへ着いた翌日から、
教わりたい準備が出来てたんですよ。」
「いや、違う。準備が出来たのは、私の方だけだ。
毎日毎日、お前の顔を見て、
顔を見るたびに、まだ準備してないな、
と思うので、いったい、
この男は、いつになったらほんとうに教わる気になるのかな、
と思ってな。私の方から、それを催促したかったんだよ。」
「これはしたり。全然、話が違います。
私は来た日から教わりたくて、教わりたくて、」
「お前はね、気持をそういうふうに偽って言うが、
私の霊感にうつるところは、お前はまだ、
ほんとうに教わる準備が出来ていない、と見るよ」
「いや、その準備は出来ています。」
「ああ、お前は強情だな。お前自身の心の中は、
お前自身より、私の方がよけい知っている。
その証拠は、すぐ見せてやる。
あの水を飲む器に、水をいっぱい注いでおいで。」
頭を「空」にしてみる!
日本にはないのですが、コーヒー茶碗の両方に手のついたような、
大きな、丼くらいの大きさの水飲みがあるのです。
非常に空気が乾燥していますから、夏のどんな暑いときでも、
汗の出ない国であります。アメリカがそうですわな。
夏、汗が出ないというのは、何となく、こう、
日本人は経験しないので、妙な気持になるもんですが、
いたるところに、ちょうどいまの魔法壜みたいに、
素焼きの、二重になった丼が置いてある。
どんな暑いときでも、その丼の中の水だけは、冷っこい水なんです。
言われるままに、その丼のようなコップにいっぱい水を注いで、
それを持って来た。すると、また、こんどは、
「湯をいっぱい持って来い。」
それでまた言われるままに水をそこに置いて、また湯を持って来たら、
「その湯を水の上から注げ。」
あんまり馬鹿馬鹿しいことなんで、私はこう言ったんですよ。
「この国ではどういうふうに考えてるかしりませんが、
文明の民族は、いっぱいはいっている水の上から湯を注ぎますと、
両方ともこぼれる、ということを知っております。」
と言ってやった。癪にさわったからね。これが、私の悪い癖なんだ。
なぜ、悪い癖かというと、俺は文明の国民だと、
しょっちゅう腹の中で思っているんだな。
こんな草深い、どこまで行っても家一軒もないようなところで、
たいていの奴は裸足で、
裸で往来へ寝そべっているような人間ばかりじゃないか。
こいつらめ、ほんとうに犬や猿と同じくらいの人間じゃないか、
と思っている気持があるから、たとえどんな、相手が偉いと思う人にでも、つい、こんな、いま言ったような皮肉なことを言っちまうんです。
そしたらね。
「それを知ってるのか。」
と言やァがる。
「存じておりますよ。」
「それがわかったら、さっき俺がお前に言った言葉はわかる筈だ。」
「さっき私が言ったこととこれとは違うでしょう。」
「違わないね。同じことだ。」
「私は同じことだということを、どうしても了解出来ません。」
「そうかい。それほどまでにお前の頭の中が愚かしいとは思わなかった。」
と言うんです。なんだ。こっちは文明民族なのに、
野蛮人から冷やかされていると思ったから、言いました。
「その理由をうけたまわらせていただきましょう。」
「聞かせよう。私が毎日毎日、
お前をつれて来た翌日からでも教えたいと思って、
お前をじっと見ていると、お前の頭の中はな、
私がどんないいことを言って見ても、
そいつをみんな、こぼしちまう。
さっきの、水のいっぱいはいっているコップと同じような、
そういう状態だと見ているんだ。
いつになったら、この水をあけて来るかな。
水をあけて来さえすれば、そのあとで湯を注ぎ込んでやれば、
湯がいっぱいになるんだがな、と思っているんだが、
いっこう、水をあけて来ない。お前の頭の中には、
いままでの役にも立たない屁理屈がいっぱい詰っている以上、
いくら俺が尊いことを言ってみても、それをお前は無条件に受け取れるか。受け取れないものを与える。そんな愚かなことは、俺はしないよ。
わかったかい?」
ああ、なるほど、こいつは一本参った、と思った。
私という男は、まことにそうなんだ。
二ヵ月前、ここへ始めて来たときに誰かが、
「お前はこれから教わるんだ。頭の中をからっぽにして置けよ。」
と言ってくれればよかったんです。とにかく私は、
心の中から、ああ、そうか、と思った。そしたら、にこっと笑ってね。
「よし、わかったようだな。今夜から俺のところへ来い。
生れ立ての赤ん坊のようになって来いよ。」

一つ欲しければ必ず「一つ捨てる」
――心の原理原則
カリアッバ師に導かれて、インドに向かっての旅が始まった。
インドの東北部、ヒマラヤ連山の東の端に、
標高八六〇〇メートルのカンチェンジュンガがそびえ立つ。
その山麓の寒村に一行は辿り着いた。
ある日、天風は村人に、ここがどこなのかを聞いた。村人は、
「ここはおまえのいるところで、オレのいるところだ」
と答えた。
なるほど、その通りだ。この答えに満足した天風は、
インドの奥地にいることを知らないまま、修行に励むことになる。
天風はカリアッバ師に指導され、
一塁打、二塁打級の小さな悟りを累積していく。
やがて決定打とも言うべき本塁打級の悟りを開いたとき、
天風の物の見方は大きく転換し、ゆるぎない信念の人となるのである。
村ではカリアッパ師は一身に尊敬を集めていた。
階級制度が厳しく、
カリアッパ師は最高地位のバラモン(神、司祭の族)であり、
その下に、クシャトリア(王侯・武士階級)、
バイシャ(庶民)と続く。
天風は最下級のスードラ(奴隷)として村に入れられた。
スードラは羊や馬といった家畜よりも下に位置づけられていた。
聖者カリアッパ師と天風は、村では聖者と奴隷の関係である。
天風は、遠くから聖者の姿を仰ぎ見るだけで、
言葉を交わすこともできない。
いつになったら教えを受けることができるのか。
ひたすら待つが、いっこうにその気配はない。
意を決して天風は、聖者の前にひれ伏して尋ねた。
「おまえは助かるとエジプトで約束されました。
その教えはいついただけるのでしょうか」
聖者は言った。
「ここへ着いたときから、私は教える準備ができている。
しかし、おまえのほうには準備ができていない。
おまえの準備ができてからだ」
「いえ、私のほうにもできています」
と天風は、聖者の次の答えを待った。
それには答えず、聖者は妙なことを命じた。
「では、丼に水をいっぱいついで、ここへ運ぶように」
天風が指示通りに従うと、次に、
「湯を持ってこい」
と命じる。用意が整うと、聖者は、
「丼の中に湯を入れてみよ」
と言った。天風にはばかばかしく感じられ、
「いっぱい入っている水の上から湯を注ぎますと、
両方こほれてしまいます」
と答えた。
次の瞬間、聖者は厳しく諭した。
「丼の水がおまえだ。
おまえの頭の中には、
今までの屁理屈がいっぱい入ったままではないか。
いくら私の教えを湯のように注いでも、
おまえには受け取ることはできない」
ハッと天風は気づいた。それが伝わったのであろう、聖者は、
「よろしい。生まれたての赤ん坊になって、
今夜から私のところに来なさい」
と包むように言った。
この日から聖者のそばで天風は新しい学びを始めていく。
既存の知識を捨てることをアンラーニング(学習棄却)という。
新しいことを学ぶ場合、特にそれが新しい考え方である場合は、
既存の知識をアンラーニングしない限り、
新しい知識を学び取ることはできない。
頭の中の古い知識が、色眼鏡となって、
自分に都合よく解釈させてしまうからだ。
これでは既存の知識の強化でしかない。
このことをカリアッパ師は危惧したのであろう。
ビジネス界でも、アンラーニングの必要性は高まっている。
経営環境の本質的変化に対しては、
アンラーニングが一つの武器になる。
捨てた者こそ、新しい学びを始めることができる。
学習とは、獲得と棄却の両立にあることを気づかせるエビソードである。

茶碗を空にする
若者は神に関して探し得る著書をすべて読破した。
そして、偉大な神師のことを聞いて、教えを乙うために面会を求めた。
二人が座ると、若者は神について
これまでに読んで理解したことのすべてを師に伝え、
神の本質について、得意げにひとしきり蘊畜を傾けた。
しばらくたつと、神師はお茶にしようと言った。
神師が湯を沸かず間、若者は姿勢を正して座り、
茶碗を差し出されると無言で深々と礼をした。
神師は若者の目の前の茶碗に茶を注ぎ始めた。
茶腕が一杯になるまでなみなみと注ぎ、
それでも止めずに注ぎ続けた。
茶は茶碗の緑から溢れ、飯台の上にこばれた。
それでも、手を休めずに生き続けたため、
茶は飯白伝いに役にこぼれ落ちた。
ついに、若者は我慢できなくなって叫んだ。
「先生、お茶を注ぐのをお止め下さい!
茶碗はもう一杯で、これ以上注ぐのは無理です」
そこで神師は手を休めて、若者にこう言ったのだった。
「お前の心は、この茶碗と同じようなもので、
身勝手な意見や先入観で一杯である。
最初に茶碗を空にしないで、何か学べるとでも思っているのか」
多くのゴルファーは、
これまでにゴルフのスウィングに関して
おびただしい数の著書を読んでいる。
そして、自分のスウィングについて
あまりにも多くのことを考えながらレッスンを受けにいくため、
インストラクターが言うことを聞く耳が持てない。
つまり彼らは、
"茶碗が一杯"の状態でレッスンを受けに来るのである。
"茶碗を空にして"からレッスンを受けることは、
知性を捨て去ってインストラクターの言うことに黙って従うこと
を意味するものではない。
大切なのは、教わるものすべてに虚心担懐に耳を傾け、
それをしばらくの間試してみるまで判断を保留することだ。
先生が言わんとすることを全力で理解しようと努め、
先入観を捨ててそれを試す中で、
それが果たして自分にとって有効かどうか判断すべきなのある。
1960年代にアメリカ西海岸で神学の普及に努めた健大な禅師。
鈴木俊隆老師は、次のように語っている。
「初心者の心には、多くの可能性が宿る。
しかし、熟練者の心にはそれはほとんどない」。
初心者の心はオープンで、
意欲的に学ぼうとする“空の茶碗"である。
心が先入観念のないオープンな状態にあれば、
人は探求心に満ち、
周囲の出来事に正しく反応し、全うに対応できる。
取り組む対象が瞑想であろうと、
ゴルフあるいはその他のものであろうと、
われわれが体験することは、初めはすべて新鮮で啓発的である。
何かを始めた当初は、それをすでに達成したという意識は誰も持たない。
そのような状態なら、われわれは多くのことを学ぶことができる。
しかし、しばらくすると新鮮さが失われてしまう場合がある。
すでに何かを悟ったような気になって、やる気が失せることがある。
つまり、心の"茶碗"が満たされ始め、
何か新しいものを受け入れるスペース
が少なくなってしまうのである。
このような事態が発生しつつあることが察知できれば、
仕切り直しをすることによって、改めて初心に戻ることができる。
初心者の心を持ち続けるのは決して楽なことではない場合が多いが、
それは有意義なことだ。初心でいれば、
われわれはすべての人々やあらゆる出来事との出会いから、
多くのことが学べるのである。
ペン・ホーガンは、正確無比のスウィングの持ち主で、
ボールを打つことにかけては、
おそらく史上最高のテクニシャンだったと言ってよかろう。
しかし、そのホーガンは決して練習を厭わなかった。
実は、彼は練習を楽しんだのだった。
なぜならホーガンは、自分には常に、
さらに学ばなければならないものがあると信じていたからだ。
つまり彼は、常に初心を忘れなかったのである。
4種類の生徒がいる
「ゴルフは教わるものではなく、自ら学ぶものだ」
とよく言われる。しかしこれは、
レッスンを受ける必要なぞないという意味ではない。
肝心なことは、インストラクターがどんなに優れていても、
生徒自体の興味の範囲と努力の程度
を上回る効果は期待できないという点だ。
仏の道の学習プロセスを説くに当たって、
仏教では前述の茶碗の陰喩が使われる。
つまり、四つの茶碗がそれぞれ、
異なったタイプの生徒を象徴するのだ。
そして、高僧の教えを象徴するのが、
茶碗に注がれる水である。
最初の茶碗は、伏せてある。
これは、学習するために
インストラクターのところに来ているはずなのに、
注意を払わない生徒のことである。
本を読んでいて、
同じような体験をしたことのある読者がいるかもしれない。
目は最後まで活字を追っているのに、
読み終わった段階でよく考えてみると、
読書中に別のことを考えていたため、
内容がまったく頭に入っていないのだ。
茶碗が伏せてあると、それが起こる。
どれだけ水を注いでも、
茶碗の中はいつまでたっても空っぽなのである。
二つ目の茶碗は、きちんと上を向いて置いてあるが、
底に穴が開いている。
先生の言っていることは聞こえるが、
たちまち全部忘れてしまう。
内容をきちんと咀嚼し、消化し、
深く胸に刻んでおくことができない。
たとえば、ゴルフスクールに出席したあと帰宅して、
友人に何を習って来たか尋ねられると、
「ええと⋯⋯実は、覚えていないんだ」
と言わざるを得ない状態だ。これはつまり、
習ったことが耳を素通りしてしまう典型的な症状だ。
三つ目の茶碗は、きちんと上を向いていて、底穴はない。
だが、内側に汚れがこびりついている。
だから、レッスンの澄んだ水が注がれても、
汚れのせいですぐに濁ってしまう。これはつまり、
インストラクターの言うことをねじ曲げ、
自らの先入観に合うように解釈してしまうことを意味する。
だから、新しいことは何も学べない。
レッスンを受けるとき、
インストラクターの言が本人の見解と合致しているとしたら、
それはレッスンではなく、単なる「再確認」に過ぎない。
つまり第三の茶碗は、自分の考え方と異なる新しいことはすべて、
反発するか、無視するか、
あるいはおろそかにする姿勢を象徴しているのである。
四つ目の茶碗は、生徒としてあるべき姿を象徴する。
きちんと上を向いて置かれ、
教わることをすべて受け止める姿勢である。
この茶碗には穴はなく、教わったことはすべて保持される。
汚れていないから、新しいことを進んで知ろうとする。
だから、できるだけ
この第四の茶碗のようになるように努めてほしいものである。
大半のゴルファーは、
もっとうまくなりたい思っていると打ち明ける。
私がゴルフのメンタルな面をコーチしていることを知ると、
彼らの多くは
「私に欠けているのは、まさにその点なのです」
などと、しおらしいことを言う。
しかし、そういう人々のほとんどは、
実はこの点について何かを限むうとする意思なぞ、
みじんにもないのである⋯⋯まるで「伏せた茶碗」か何かのように。
ゴルフスクールの授業が終わって、
実際にコースあるいは練習場に出る前に、私はときどき、
一つひとつのショットについて特定の注意事項を忘れてはいけない、
と生徒徒たちに注意する。
だが、結果についてあとで聞いてみると、
半数は注意事項などきれいさっぱり忘れている。
つまり、茶碗の穴から水がもれてしまったのだ。
私は、次のレッスンに戻ってくる生徒たちに、
前回宿題として出しておいた
練習の成果について聞いてみることにしているが、
うんざりさせられることが多い。
伝えておいたことにまともに取り組んでくれる生徒は、
ほとんど皆無なのだ。彼らの茶碗の中には
すでに何やらたくさんのものが入り込んでいて、
私が教えたことと渾然と混ざり合っているわけである。
しかし、たまには「第四の茶碗」のような生徒が現れて、
私を喜せてくれる。このような生徒は、
宿題の意味を正しく把握し、その成果を生き生きと語るばかりか、
それを自分のゲームのその他の面にも応用しようとする姿勢
さえ見せるのである。
インストラクターを務めていてもっとも嬉しい体験は、
生徒にこう言われることだ。
「ちょっと待って下さい。先生がおっしゃることは、
ゴルフだけではなくて、
他のことにも通用する人生の真理なのですね」
指導される側が真の成長を遂げるためには、
手に握りしめているものを手放し、
既存の価値観や情報を捨て、
心を空にして指導の機会に臨むことが必要です。
しかし、現代の情報過多の環境では、
自分の考えに固執しやすく、
他の情報に左右されがちです。
このような状況では、
指導を素直に受け入れ、
自己を変化させることが難しくなります。
したがって、真の成長と変化を遂げるためには、
まず自分の考えを捨て、
心を空にして指導を受け入れる姿勢が求める
と思います。
いいなと思ったら応援しよう!

