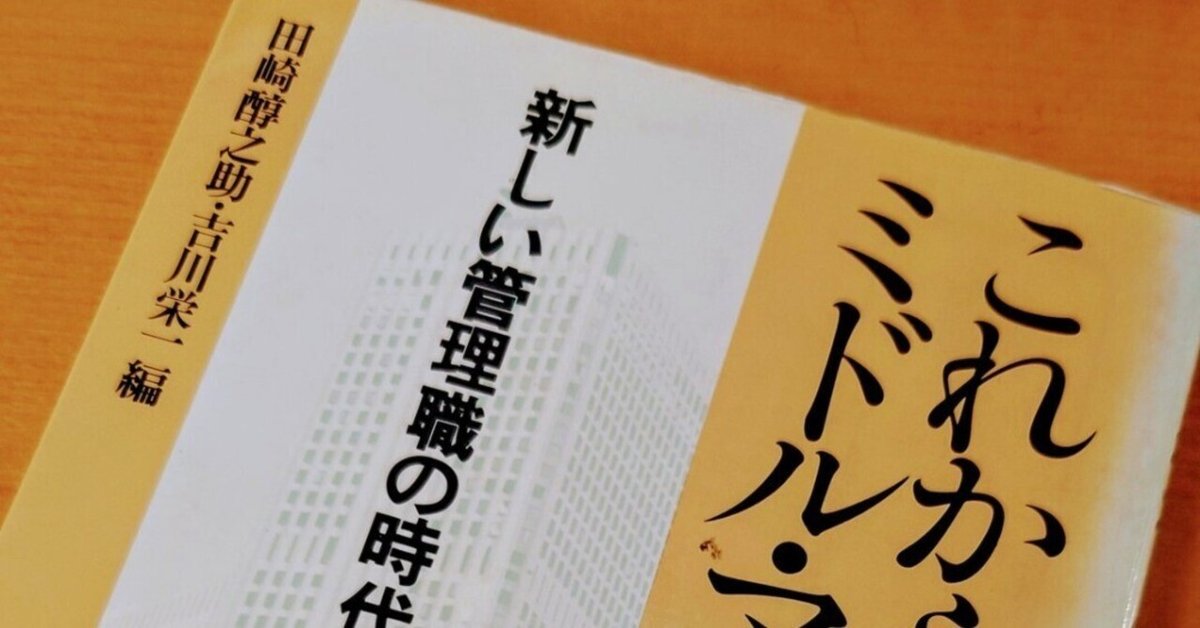
1981年出版「これからのミドル・マネジメント」 読書メモ
このごろ変な話を時々聞くようになりました。「変な」というのは、今までとちがっているという意味です。その話というのは、いろいろな企業で管理者や監督者になることをいやがる人がではじめたというものです。
ちょっと衝撃的な冒頭でした。
2024年現在、「管理職になりたくない問題」というのをニュースで見かけますが、今から40年以上前、1981年の時点ですでにこの問題は始まっていたんですね。
そして、ページをめくると1章が始まります
第1講
低成長時代の管理職 プレイング・マネジャーの時代
ここも!? 今でもHRサイトの記事タイトルにできるテーマです。
高度経済成長が終わり、バブルになる前の80年代前半。社会には停滞感があったんですね。
その影響で、管理職がありかたを再検討されました。たとえば、管理職位の階層の短縮化や管理職の削減などが行われたそうです。驚くべきことに、
「これまでは大企業に就職した大卒者のうちほぼその全員が課長や部長といった管理職に就くことが一般的でした」
という状況でした。たしかに、会社の成長率が下がり、大卒者が増えてくるとそのままでは立ち行かなくなります。
このような管理職に対して、次のようなテーマを取り上げてその現状と対策が書かれています。
・部下の動機づけ
・職場の人間関係
・部下の育成
・女性リーダーの育成
・中高年年齢者の活性化
・小集団と職場開発
・労使関係(組合対応)
・グローバルマネジメント
組合対応は今はない方も多いと思いますが、そのほかは現役のテーマです
ね。かいつまむと次ような内容でした。
〇部下の動機づけ
・働く人の価値観や動機に大きな変化が起きている
・会社中心の動機づけでは難しい
・動機づけに関する管理者の悩み事は、自分のことでなく部下の状態に関するものが多い。(P.38)
〇人間関係
・欧米よりも人間関係の葛藤が多いのが日本の職場
・葛藤を察知して未然に防ぐのが大事
〇部下の育成
・育成の基本はOJT
・部下を育てない管理職は嫌われる
・部下は「大事な預かりもの」として育てる
・ひとりひとりの能力と適性を把握して尊重する
・ジョブ・ローテーションを組みあわせて長期的なキャリアをつくる
・1976年の「部下育成の上手な上司と下手な上司の違い」の調査結果が掲載されていました。やはり、任せる、教えるは大事。

〇女性リーダーの育成
・女性の職場進出は増加
・社内結婚で女性側が配置転換になったり退職勧告されることがある。また、夫の転勤で退職に追い込まれる妻もいる。
・男女平等のタテマエ論でなく真剣に取り組む必要がある
〇中高年年齢者の活性化
・中高年齢者が急激に増加することで問題がいろいろ出てくる
・ひとなみで十分とやる気を失う中高年が増えている
・相手のメンツやプライドを傷つけないように配慮する
・企業は、能力再開発に力をいれるべき
・年上の部下には熱意と誠意をもって期待を明確に伝える
〇小集団と職場開発
・職場レベルでの自主的な改善を進める小集団活動はこれからの職場管理には欠かせない。(ボトムアップの活動)
・職場開発・組織開発といった職場ぐるみの問題解決、目標達成行動のための活動も盛んになっている。(トップダウンの活動)
・日本では役割区分が明確でなく、お互いに補い合っている(役割行動の相補性)ため、この2つの活動は重要。
感想
管理職の悩み、女性リーダーの育成、中高年の活性化、どれもいまのHR界隈でよく聞くテーマで50年の間に根本的な改善されていないように感じました。(もちろん変わってはいるんですが)
経済が伸びずとも大きく減少もしなかったこれまでの50年はなんとか持ちこたえたかもしれませんが、これからの50年はそうもいかないでしょう。
人材活用の知識は各社で個別性が高くまたオープンになっていないため、社会としての知識に変えてこられなかったように思います。人材活用の知識を社会全体で共有して年月と共に改善をはかれるような世の中にしていきたいですね。わたしも研究を進めて、形ある知識を世の中に残していきたいと思います。
