
論文どこに出す? 神経内科・てんかん編
1. Neurology

インパクトファクター: 8.4
特徴: 臨床神経領域のトップジャーナルですね
投稿費用: オープンアクセスは選択制
Neurology Clinical PracticeやNeurology Geneticsなどの姉妹誌もあり、専門分野ごとに深掘りした内容が提供されます。
これまでの経験:
査読に回ることは何度もありましたが、筆頭/責任著者での採択経験はありません。これまで、パーキンソン病関連や脳卒中、てんかんの領域で投稿経験がありますが、感触としては「てんかん」だとハードルが高くなります。脳卒中やPDなど、脳神経内科ど真ん中的なコモンな疾患が好きだと思います。なので、同じようなn数で同じような疫学研究でも、パーキンソン病関連だと査読に回るものの、てんかんだったら査読にすら回らないということがありました。
なお、いざ査読に回っても統計手法含めてmethodへの査読がかなりしっかりしています。よって手法としてベストを尽くしていないと「dataが信用できない」と、あっさりreject
査読にはそんなに時間はかかりません。1-2ヶ月くらいでした。
2. Movement Disorders

インパクトファクター: 8.7
特徴: パーキンソン病など運動異常症のトップジャーナルで、昔はてんかん領域もカバーしたジャーナルでいたが、残念ながら現在はてんかんの取り扱いはほぼありません
これまでの経験:
試しに投稿したことはありますが、通常の単施設の疫学研究ではやはり勝負できません。また、前述のように、臨床のてんかん領域のターゲットジャーナルにはなりそうにありません。過去にBAFMEでのbriefで採択経験はありますが。これも皮質ミオクローヌスという「てんかん領域ではない」側面で評価されたのだろうと思います。
3. Epilepsia

インパクトファクター: 6.04(2019年)
特徴: てんかん領域のトップジャーナルで、基礎から臨床までカバー
投稿費用: オープンアクセスは選択制
姉妹誌にEpilepsia OpenとEpileptic Disordersがあります
EpilepsiaからはEpilepsia Openにtransferされることがありますこれまでの経験:
採択経験はありますが、自分の実力というよりは出向先での研究データに依存した採択結果でした。その後、現在の施設から何度か投稿したことはありますがまだ採択に至ったことはありません。査読に回ることもありましたが、疫学研究でn=300くらいのデータだと査読に回るのも厳しい状況です。テーマ、解析手法、アウトカムの信頼性や新規性など、明確なもアピールポイントが欲しいですね。
4. European Journal of Neurology
インパクトファクター: 6.089(2020年)
特徴: 欧州神経学会の公式ジャーナルで、神経学全般の臨床および基礎研究を対象としています。
投稿費用: 2024年1月からオープンアクセスジャーナルとなり、論文掲載料が適用されているようです!! これはこの記事を書いてて知りました
どこも運営が大変なのでしょうね
$3600 USD / £2750 GBP / €3050 EUR

これまでの経験:
採択経験はありませんが、査読に回ったことは何度かあります。あとちょっとだったかな?ということもありましたので、また挑戦してみたいですね。このジャーナルで査読には回ったもののrejectだった論文は、その後、Journal of the Neurological SciencesやSeizure、Epilepsy and Behaviorなどに採択されました。
基本、てんかんには厳しめのジャーナルかなと思います
一方で、査読者が見つからないという経験もありました
2ヶ月待って「査読者10人以上にアプライしたけど、結局、査読者が見つからずに、申し訳ないけどリジェクトで」という返事がきた時にはかなりショックでしたね
ステータスはずっとunder reviewになっていたので、楽しみに待っていたんですが、残念
5. Journal of Neurology
インパクトファクター: 4.8 (2023)
特徴: 神経学の幅広いトピックを扱う国際的なジャーナル
投稿費用: オープンアクセスは選択制
これまでの経験:
採択経験はありません。そして、個人的にはかなり相性の悪いジャーナルです。前述のEuropean journal of neurologyに査読が回ったような論文でも、このJournal of Neurologyでは査読にすら回りません。
というのも、てんかん関連では毎回、即editor kick
なので、もう投稿することはないかもしれません。ただ、返事は早かったのでその点は良かったのかも
投稿規定が緩めなので、投稿の敷居が低かったというのもあるかも

6. Journal of the Neurological Sciences
インパクトファクター: 3.7 (2023)
特徴: 神経科学の多様な分野をカバーし、基礎から臨床までの研究を掲載
投稿費用: オープンアクセスは選択制
これまでの経験:
複数回の採択経験があります。割と通りやすいジャーナルの一つです。
ジャンルも幅広く扱ってくれていますので、てんかんでもokです。
ただ最近採択された以下の論文を見ると、神経救急系は通りやすいのかもしれません。逆に、てんかんの専門性の高い内容だと査読に回りませんでしたので、てんかん直球なら、やはり専門誌ですね

7. Clinical Neurophysiology

インパクトファクター: 3.7
特徴: 国際臨床神経整理学会の機関誌で、臨床の電気生理のメジャージャーナルで伝統あるジャーナルです。
投稿費用: オープンアクセスは選択制
これまでの経験:
当然ですが、電気生理に厳しいです。また、電気生理の要素や専門性のないものは査読に回りません。例えば「てんかん発作の再発予測モデルの精度を前向き」のようなデザインは脳波の要素がないので例えn数が多くても査読には回らないでしょう。逆にマニアックな脳は解析などはウケが良く、症例数が少なくても勝負ができます。
過去には脳波関連の論文をEpilepsy and Behaviorに投稿して、こちらのClinical Neurophysiologyへの投稿を提案されたことがあります(採択されました)
8. Seizure
インパクトファクター: 3.184(2020年)
特徴: Seizure - European Journal of Epilepsyは、Epilepsy Action(英国最大のてんかん団体)が所有する国際学術誌。IFはそこまで高くないですが、割と敷居の高いジャーナルです。
投稿費用: オープンアクセスは選択制
これまでの経験:
採択経験は一度だけ。割と敷居が高いジャーナルで、査読に回らないこともしばしばあります。Epilepsy and BehaviorとIFはそんなにかわりませんが、Seizureの方が難しいですね。
このジャーナルに通れば、おっやるじゃんと思われるはずです

9. Epilepsy & Behavior
インパクトファクター: 2.5(2023年)
特徴: てんかんと行動学的側面をトピックとしたジャーナルで、2006年からの割と新設のジャーナルです。てんかんに関わる、精神科的な側面や、治療、併存症、社会問題など幅広いジャンルを取り扱っています。IFは高くありませんが、てんかんの専門誌として大事なポジションでしょう。
投稿費用: オープンアクセスは選択制
これまでの経験:
複数回の採択経験があります。逆に、てんかんの論文であれば、少なくともEpilepsy and Behaviorには採択されたところ。なのでこのジャーナルで査読に回らなければ、根本的に論文を見直したほうがいいかもしれません。一方で「てんかん重積状態などの神経救急」や「脳波などの電気生理」のトピックについては、このジャーナルのターゲットになりにくいです。
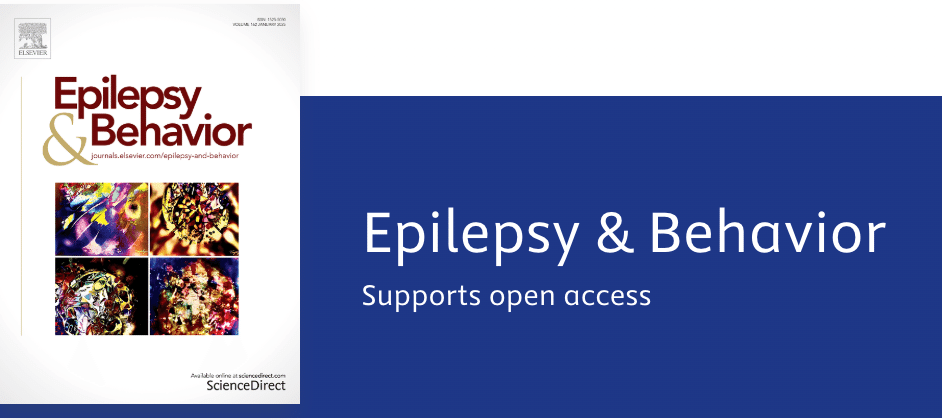
10. Epileptic Disorders
インパクトファクター: 2.3(2021年)
特徴: 国際抗てんかん連盟(ILAE)の機関誌には、EpilepsiaとEpilepsia Open、Epileptic Disordersがあり、前者2つは研究的な立ち位置のジャーナルであるのに対して、このEpileptic Disordersは教育的ジャーナルです。投稿費用: オープンアクセスは選択制

これまでの経験:
Epilepsy and Behaviorでダメだった場合の候補と考えていますが、ここ最近はEpilepsy and Behaviorまででなんとかなっているので、実際はあまり投稿していません。過去に採択経験は一度だけあります。返事が遅かった印象はあります。
その他. Epilepsy Research
Seizure、Epilepsy and Behaviorと同じくらいのランクのジャーナルと思いますが、個人的には投稿経験がほとんどありません

その他. Epilepsy & Seizure
日本てんかん学会の機関誌(英文誌)。
インパクトファクターはついていませんが、専門誌であることやオープンアクセス(会員な無料)というメリットがあります。また毎年、その年に掲載された論文の中から優秀論文が選出され、日本てんかん学会での表彰があります。レベルの高い論文は必然的にIFが高い他のジャーナルに投稿されていますので、若手研究者にとっては狙い目の賞と思います。

その他. Epilepsia Open

Epilepsiaの姉妹誌のオープンアクセスのジャーナル
Epilepsiaに届かなかったものの、専門性のある論文が取り扱われています
今回はオープンアクセスを対象としなかったので、取り上げませんでしたが、てんかん領域としては専門性は高く、主要ジャーナルでしょう
Epilepsiaからtransferされれば、採択率はまあま期待していいと思います
====================================================
ここからは、臨床研究に役立つ医学書を紹介します
主に実際に手にしておすすめできるものをピックアップしていますので、皆さんの研究生活の参考にしていただければと思います
臨床論文の医学書
1. 研究デザイン
臨床研究の道標 第2版〈上巻〉
臨床研究を始める上では研究デザインを学ばなければいけません
その王道の一冊です
筆者は大学院に進む前にこの初版を購入しました
10年以上前の話ですが、著者の福原先生の講演を拝聴する機会があり、ものすごく感銘を受け、すぐに著書を購入したのを覚えています
実例から学ぶ! 臨床研究は「できない」が「できる! 」に変わる本
こちらの片岡先生の本もおすすめです
2. 論文執筆
必ずアクセプトされる医学英語論文 改訂版
とりあえず、この康永先生の本はおすすめ、というか初学者はマスト
大学院生の時はこの初版を購入しましたが、本当に助けられました
そして実際に「必ずアクセプト」されました
実際に持っている人も多いですし、人気書籍ですね↓↓
3. 英語表現
英語論文基礎表現717
古い書籍ですが大学院生の時はこれをよく使っていました。
辞書的に使えて、例文もあって使いやすかったですね。安いしおすすめです。
アクセプト率をグッとアップさせるネイティブ発想の医学英語論文: プロ翻訳家が伝えたい50の基本動詞と読めるのに書けない英語表現
英語は動詞が大事だということを教えてくれた一冊
論文作成では主語に悩むことはあまりないので、動詞のバリエーションをしっかりと掴むことでライティングがだいぶ楽になった気がします
翻訳家の視点で書かれており、それも勉強になった
アカデミック・フレーズバンク そのまま使える!構文200・文例1900 (KS科学一般書)
この1冊もおすすめで、かなり豊富なフレーズが収載されています
ただこの書籍を購入したときには、何も見ずにある程度のライティングが可能になっていたので実際の稼働は少なかったです。
大学院生のときに持っていたら重宝していたでしょうね
自分が使ったことがある医学書を紹介しましたが
とりあえず、おすすめとしては廉永先生の本を1冊読んで、あとは足りないものを「研究デザイン系」や「英語writhing系」でそれぞれ購入すると良いと思います。
一方でAIの活用はもはや欠かせなくなりましたので、AI活用前提の学習も効果的でしょうね。大塚先生、松井先生はXでも発信されており、勉強になります↓↓
医師による医師のためのChatGPT入門2(臨床現場ががらりと変わる生成AI実践術)
医療者のためのChatGPT:面倒な事務作業、自己学習、研究・論文作成にも!
てんかんや脳波の臨床研究に興味があればぜひ
筆者は現在、てんかんや脳波の分野で臨床研究を続けています
主に大学院生の指導に携わり、今年は自分でもいくつか執筆しました
ケースレポートも含めて、2024年の論文は14本でした
もし、一緒に臨床研究をしてみたい、共同研究がしたいなと思った方はぜひコラボしましょう!現在もてんかん重積や救急脳波のテーマで複数の施設と共同研究としてデータを蓄積しています。そういったデータを使っていただいても構いませんし、一緒にやっていく仲間が増えればn数も増え、トップジャーナルにも挑戦できるのではないかと思いますのでwin-winになりますよね。何よりも、一人でやるより楽しいし。
データを共有することでそれぞれが違う角度で解析し、それぞれの論文として生成できるようになるでしょう。経験、所属は問いません、興味がある方がぜひご連絡ください。
てんかん診療をワンランクアップさせたいなら
救急脳波を学びたいなら
脳波の知識ゼロから始められる、非専門医の先生にとって「とりあえず、最低限の脳波の知識を学びたい、意識障害のファーストタッチとしての判定ができるようになりたい」にマッチした実践型書籍
脳波判読を基本から学びたい
脳波判読の基本から応用まで
判読手順の基礎を知りたい
てんかんの診療をブラッシュアップしたい
脳波レポートを作成できるようになりたい
