
22平均律入門-ネーミング編-【042】
こんにちは、こんばんわ、ユートピア!
変拍子兄さんのお時間です!
今年の4月ごろに53平均律の曲を作りまして、そこから早3か月。
その頃とは、季節も大分変わってきたし、新しい平均律に挑戦しつつ
習作として新しく曲を作ろうかと思った今日この頃です。
ということで、変拍子兄さんが次に開拓を試みる平均律は
「22平均律」
興味を持ったきっかけをさらっといいますと…
SevishニキのGleamだったり
Erv Wilson著の微分音の外国書籍を買ってみたら
22音音律について、研究書が見つかったりしました。
半年ほど前にも、オススメの平均律と題して22平均律を紹介していたりします。
こんな感じで22平均律・22音音律の話が本格的に気になり始めたタイミングで、実際に曲としてあつかうなら…?と考え始めたので
考えをまとめていこうかと思います。
◆まずは鍵盤をイメージする
いきなり22平均律を聞いてみよう!
といっても、ただ並べただけじゃよくわかりません。
(音の羅列にしか聞こえない)
22平均律 pic.twitter.com/lnATWhO2n9
— 変拍子兄さん (@OrangeTheKeyqa) June 22, 2020
そこで、
平均律をよりリアルに捉えるのは
ピアノでいうと大体どの音程を弾いてるのか? と理解すること
そのために考えること「鍵盤モデル」ですね
つまり、白鍵・黒鍵をそれぞれ何段にすべきかと。
22=7+5+5+5 ですので
白鍵1段+黒鍵3段 ということになります
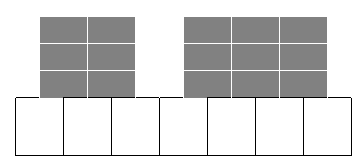
このイメージが22平均律の根幹となります。
実際に人に教える時、黒鍵を手前・中・奥の3カ所を指さして
ステップを数えたりしました。
◆音名を考える(ソルフェージュ用)
さて、次に考えるのは、
各音程をどう呼んでいこうか? というもの
これに関して、正直、正解はないのですが
わたくし変拍子兄さんには、音程を命名する流儀があります。
まずはソルフェージュ用の命名から。
12平均律ならドレミがでてくるところですね。
ですが、アンチドレミ派の僕としては 別の方法を使用します
それが、「ラカナソルフェージュ」という手法
白鍵7音→ La Ka Na Fa Da Ja Pa
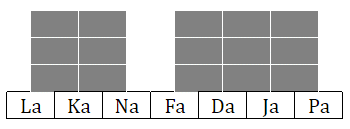
黒鍵5音→ Ra Sa Ba Ga Ta
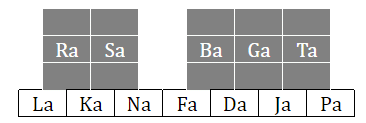
という風に呼びます
ここで注意なのはLとRを区別すること
そのため、カナで書く時は
La→ラ Ra→ら
という風にひらがなを用いて書き分けます
次に
段数が増えると、異なる母音を使って呼び分けます。
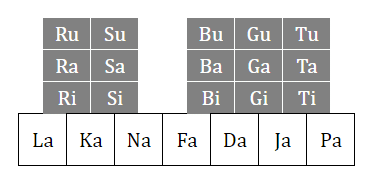
黒鍵の高い方をウ段、低い方をイ段としました
これにて、ソルフェージュは完成です。
音名唱法する場合はこれでやります
ドレミの歌ならぬラカナの歌というものを作るとしたら
ラーはライムのラー、カーはカニのカーとなりますね。
音名唱法で音をとるときに、このように使用します
22平均律シャトルランを作りました。 pic.twitter.com/jn44V1hgM9
— 変拍子兄さん@太鼓受かった (@OrangeTheKeyqa) July 12, 2020
◆音名を考える(コード・スケール表記用)
次に考えるのは、CDEFGAB といった音名
これは発音するよりも、コードやスケールを記載する用途です
ネーミングの由来はすっ飛ばして、結果だけ見たいという人のために
先に見せておきます
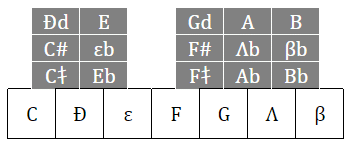
なんだか不思議な雰囲気が漂っていますね
これも人によって違いがでてしまう決め事なのですが、
僕なりの流儀を述べると
①とりあえず、白鍵にはCDEFGABを入れる
②セントを考慮した上で、
12平均律・純正律のCDEFGABから明らかに異なる音が出る場合、
オッドノートを使用する
③黒鍵の数から、臨時記号を考える
という3STEPになります。
順を追って説明しましょう
STEP1 とりあえず、白鍵にはCDEFGABを入れる
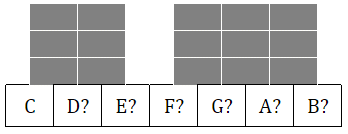
今回、白鍵がちゃんと7個あるタイプの音律ですので
この7音をベースに考えてもOKかと思います
(13平均律とか、25平均律とかはうまくいかない)
STEP2 オッドノートを使用すべきかどうか
セントを考慮するとこれ高すぎ・低すぎじゃね?ってなることがあるので
22平均律では、どうなるのか調べてみましょう。
わかりづらいので白鍵の位置にあたるモノをチェックします
(太字にします)
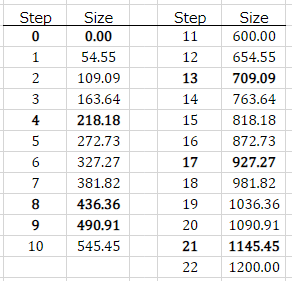
4度=490¢ 5度=709¢ これはやや高いですが
ピタゴラス音律を考えると少し高くなるものですから
まあ、F G そのままで行こうかと思います
次に、
12平均律と比べるとD E A B が高いことがわかります
かといって、1個下の音程もそれはそれで低いという状態
そのためこの4音は Ð ε Λ β という風に表記を変えて
見た目から、なんか違うぞ、って感じにします
これをオッドノートと呼んでいます
実装してみましょう
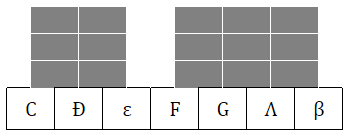
22平均律では特殊な処理として
ε Λ β の1個下の音程は、純正音程に近いことから
1個下の方を E A B という扱いにします
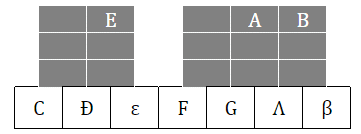
(Ðのひとつ下は163¢と小全音182¢より結構低いのでDにはしない)
STEP3 黒鍵の数から、臨時記号を考える
ナチュラルとナチュラルの間のステップ数が3
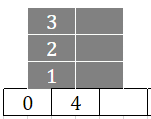
これは24平均律と同様に
1Step キ(ジャンプ)/ d(ドロップ)
2Step # / ♭
とすれば 問題ないですね
実装してみましょう
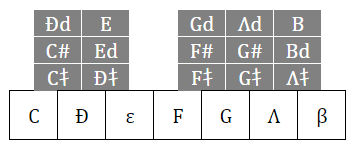
このままでもいいのですが…
キ や d は見た目的に微分音感満載なので、特殊な印象を与えてしまう
ことを考慮して
こういう風にするとEABあたりは♭だけの表記になり
3度あたりの平等感がでてきます
(スケールの比較の際に実感します)
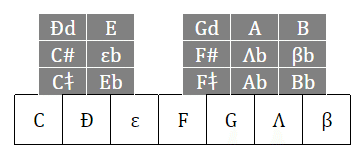
(読み方として、ε→エップ、Λ→ラム β→ベータ と短くして呼ぼうかな
Ðはディーのままでいくとして)
◆インターバル名を考える
M3とかm3といったインターバルまで決めてしまえば
22平均律のネーミングが一通り完了します
まずは5度から
22平均律の5度は709セントとやや高い5度になっています
これを聞いてみると、ちょっと変だな?って感じになります
まあ実際に聴いてみましょう
12平均律の5度(700セント)
— 変拍子兄さん (@OrangeTheKeyqa) June 22, 2020
VS
22平均律の5度(709セント) pic.twitter.com/JuD7XY95dx
微妙に高いだけなので、まあ気にならないっちゃ気にならないレベル
むしろちょっと高いことで、5度の主張が強くなってますので
これはこれでアリだな ともなりますね
とはいえ、音律の要である5度が709セントともなれば
誤差が蓄積していき、DやAが思ったより高い音程になっていきます
そのため、5度はPerfect の称号を失われ Neutral に格下げします
(もちろん転回形となる4度も)
ちなみに、1度、8度はそのままPerfectで問題ないです
そして、22平均律の1Stepは54.5セントと半々音として扱っても問題ない幅ですので、24平均律で用いたインターバルと同様にしていきましょう
つまり Diminish→minor→Neutral/Perfect→Major→Augment
という風に扱います
ということで、このようになります
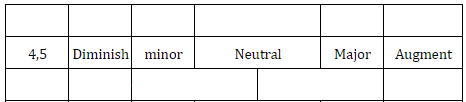
さて、ここからが厄介なポイント
3度に着目してみましょう
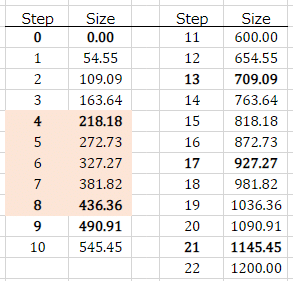
272セント→327セント→381セント→436セント と変化していきますが
どれをメジャーとして、マイナーとすべきでしょうか…?
この辺りのネーミングも人それぞれって感じですし
Xenharmonicウィキをみたところ、
マイナー、メジャーマイナー、マイナーメジャー、メジャー
としているようでしたが、わかりづらいですね
(どっちがどっち?ってなりますから)
そこで
サブマイナー、スーパーマイナー、サブメジャー、スーパーメジャー
と呼ぶことにしました。
これによって、メジャー/マイナーの2極が取り払われて
4つのインターバルが平等な感じになりました。
そしてシンボルも、上線/下線をひっぱるというものにして
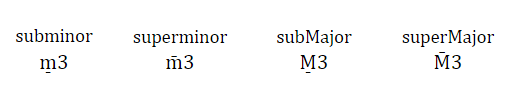
というモノにしました
(面倒なときは M' M. という風に書きます)
2,3,6,7度に適用させて ↓このようになります
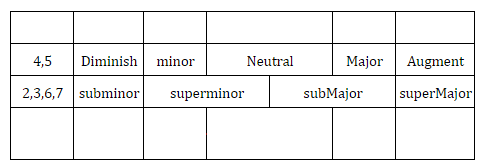
鍵盤モデルと合わせて表記するとこのようになりますね
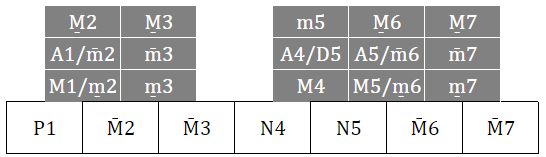
これを活用してスケールやコードの話へ展開していきます。
スケールの話に進みたいところですが、今回はこの辺で一区切りとしましょう。
◆〆
22平均律のネーミングの整備が一通り完了しました。
音名の整備が終わった状態で、実際に音を聞いてみると
22平均律の輪郭がつかめてきます
22平均律 pic.twitter.com/lnATWhO2n9
— 変拍子兄さん@太鼓受かった (@OrangeTheKeyqa) June 22, 2020
黒鍵が3段あることを理解するために
このような音源も作ってみました
22平均律
— 変拍子兄さん@太鼓受かった (@OrangeTheKeyqa) June 22, 2020
・白鍵+黒鍵1段目
↓
・白鍵+黒鍵2段目
↓
・白鍵+黒鍵3段目 pic.twitter.com/yaoilig5Sm
これで、22平均律のメンツが把握できることでしょう。
ということで、22平均律のスケール編や和音編へと進んでいきましょう!
