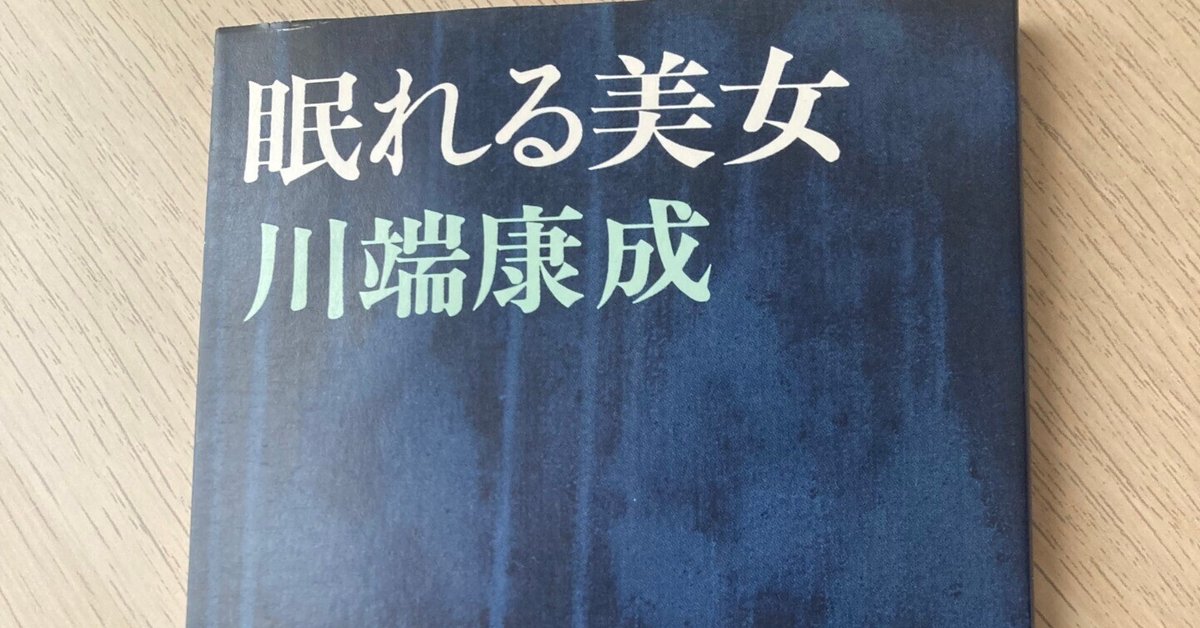
【読書記録】『眠れる美女』川端康成
『眠れる美女』川端康成(新潮文庫)
フランスのマスメディアを連日賑わせている「マザン事件」。約10年間、妻に抗不安薬を盛って昏睡状態にし、50人近くの「客」に暴行させていた男が逮捕され裁判が始まっている。反射的に川端康成の『眠れる美女』のことを思った。
そのココロは、物言わぬ女の体を自由にして楽しむ(金儲けする)というあまりにわかりやすい女の物象化である。
たぶん多くの人が感じていることだろうけれど、川端康成の小説には独特の気持ち悪さがある。今回『眠れる美女』を読み返してみたけれどやはり気持ち悪かった。それはエキセントリックな内容自体のせいだけではない気がする。「気持ち悪さ」とは具体的にどういうことなのか、その正体が何なのか考えてみた。
物語は〈眠れる美女サービス〉を提供する宿で展開する。薬物で昏睡状態に陥らせた若い女性を裸にして布団に寝かせ、客は彼女たちの姿や匂いを愛でながら添い寝できるというシステムである。客は性的に引退済みと「みなされている」老人たちだ。
語りは三人称で、視点は主人公の江口老人に固定されている。彼は醜い老いをさらしているという自虐心と、自分はまだ現役でほかの老人とは違うという自尊心の間で揺れ動く67歳。江口老人が宿ですごした五晩の出来事が、物語の進行すべてである。
登場人物は、江口の頭の中に出てくる二人の老人仲間を除けば、宿での話も江口の回想も全員が女性。彼は、「死んだように」眠る娘を、ただ見つめたり触ったり嗅いだりしながら、これまでに出会ってきた女たちを回想する。
この物語に登場する女たちには名前がない。
彼女たちは、「女」か「娘」とだけ呼ばれる。
名前を持つのは友人の木賀老人と福良老人だけである。
「女」と呼ばれるのは、まず「血の冷えた、そしてものなれた、やりてばばあ」と江口が形容する宿の女将。そして江口の回想に登場する、元恋人、芸者、年上の賢夫人、不倫の相手などかつて関係を持った女たち、そして自身の母と妻だ。
「娘」と呼ばれるのは、宿で老人の「相手」をする眠っている娘たち、そして回想に登場する、江口の3人の娘たち、幼い娼婦、そして初心な接吻の相手。
「女」たちは、みな大人で、頼もしく、しかしあとくされのない、都合のよい存在として描かれる。江口の行動や言動に対して反発や反抗したり、その発言や行動によって彼に何らかの影響を与える他者であり、家庭を最小単位とする社会構造のなかでは江口とほぼ対等な位置にある。「ほぼ」といったのは、この時代の男と女の関係が対等であったわけはないからだ。非対称性は一般に自覚されてもいなかっただろう。
反して、「娘」たちは、年が若いというだけではなく、前提として「きむすめ」(この語が気持ち悪いのはその前近代性のせいだけではない)であり、意思を持たず他者に依存して生きる半人前の個人である。宿の「眠れる美女」たちは薬を盛られて寝ているのだから、人形も同然である。回想に登場する初々しい接吻の相手も、幼過ぎる娼婦もまた、江口の意思通りに動くお人形だった。回想に登場する彼の子どもが3人とも女の子であり、男児がいないという設定は象徴的だ。彼にとって「娘」たちは、嫁がせるまでは自分の支配下にある生き物だ。長女と次女は無事片づくも、三女が婚前に「きむすめ」でなくなったことは江口の心を騒がせたが、身体の問題以上に、男性とオープンに付き合う娘の意思こそ、彼をもっともおののかせたのではないだろうか。
「女」と「娘」という二つの呼称を使い分け、女性たちに名前を与えないのは、江口の無意識の選択であり、この老人が体現している男女の非対称性、男の女に対する憧れ、身勝手さ、物象化を表わしているだけでなく、自分が愛したと思っている相手でさえ一個の人間としては見ていない、究極的にはどうでもよい存在だとみなしていることを暗示している。老人はこの年になっても見事なまでに、自分と自分の属する男社会のことしか考えていない。
繰り返すが、宿の「娘」たちは薬を盛られて、金のために老人の慰み者になっている。老齢=無害という隠れ蓑をまとったこの醜悪な状況は、恋愛や性愛にまつわるクリシェや、分別臭い物言いによって、糊塗され、平凡だけれどうつくしい情景になる。
「あのように清らかな夜を過ごしたことはない」
「僕はそんなに浮気じゃない」
「この家に来て侮蔑や屈辱を受けた老人どもの復讐を、江口は今、この眠らせられている女奴隷の上におこなうのだ」
「もう67歳の老人には、まして一夜きりであろう娘では、その女のかしこさおろかさ、教養の高さ低さなどというものは、なんであろう」
「「見習いか」と江口老人はつぶやいた。あやしいことがあるものだ」(そのあやしい宿のお客さんはだれだと突っ込みを入れるわたし)
「「眠れる美女」は仏のようなものではないか」
偽悪と偽善で混沌とした江口の態度は確信犯的なそれだと思う。わかっているのだ。なんだかんだ言って自分がただのエロ爺さんだって(江口という字面はエロに似ている)。それが物語内の「現実」である。それを引き受けたうえで「抗うお年頃」の哀しみを退廃的な美までに高めようとする作者の筆遣いは、なんと巧妙で残酷なのだろう。審美的な雰囲気の濃度が高まるほどに、江口老人の物言いや思考に見え隠れするかすかな滑稽さがかえって透けて見えるのだ。
デカダンス文学の名作とも評される『眠れる美女』。
眠る娘たちをベタベタ触りながら添い寝し、その感触や匂いに喚起されて回想にふける江口の女性観は、わかりやすい女性蔑視と女体愛の権化だ。でも不平等で不道徳な文学なんてごまんとある。そしてこれは倫理についての小説ではない。
つい感傷的に老化を嘆いてみせながらも、それを半ば開き直って耽美的な性愛の詩に昇華させようとしている主人公の姿はキモイといえばキモいが、この小説の気持ち悪さはそこにあるのではない。
気持ち悪いのは、語りのスタイルや言葉遣いの細工が江口の確信犯的欺瞞にあまりに一致していているから。
娘たちの肉体の美の対極にある老いた身体。現在とは違って、健康寿命と実際の寿命とがほぼ同じであっただろう時代の話である。江口老人は頭がはっきりしているように見えるがほんとうはどうなのか。男の身勝手さの諸事情と女体美の崇高とを回想という形で交互に配置しながらもその境界線を曖昧にして、「僕(たち男)の弱さを許して」という甘えを混乱の中で受け入れさせ、なおかつきちんと嫌悪をかき立てるように設計されている。
作者は精緻な計算のもとに江口老人を書ききって、彼と読者を混乱させ、あとは知らんぷりしている。狡猾で気持ち悪い作者だ(男嫌いなのだろうか)。作者の企みにくらべたら江口老人のキモさなんて、かわいいレベルだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
