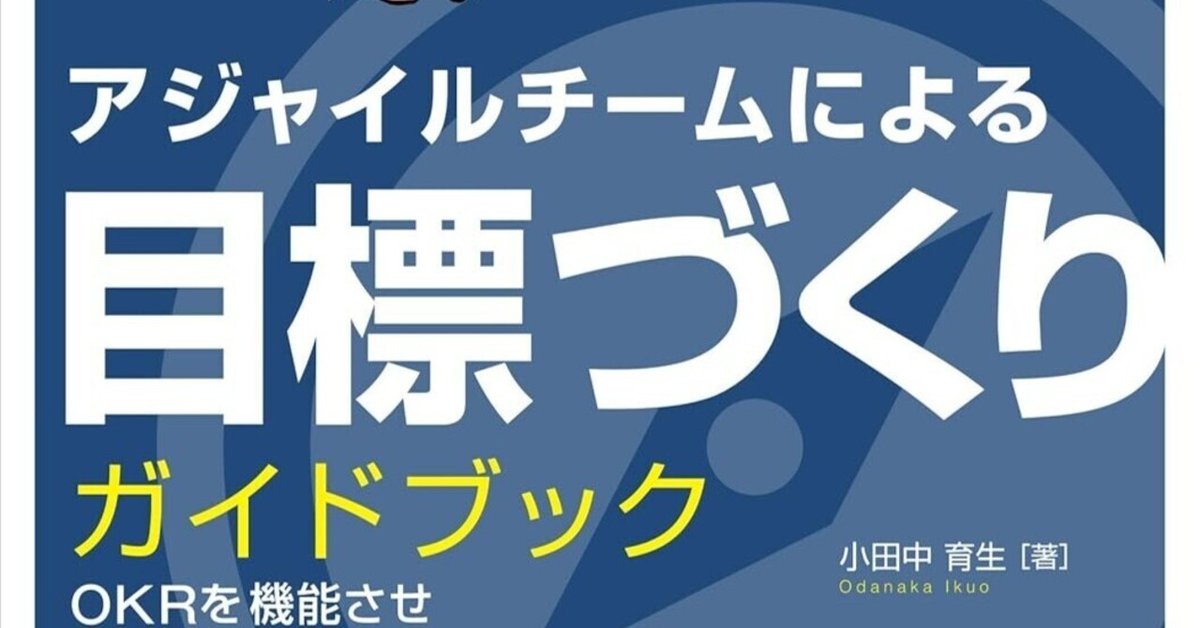
強いチームの作り方を学べる「アジャイルチームによる目標づくりガイドブック」
導入
「アジャイルチームによる目標づくりガイドブック」という書籍が非常に良かったので紹介です。
タイトルには「目標づくり」とありますが、その土台となる強いチームを作るための理論や手法がまとまっています。
ここでいう強いチームは「しなやかで、心理的安全性が確保され(≠ぬるま湯)、相互に成長し合い、目的に向かって本質をとらえながら進められる」といったチームをイメージしてこのような表現にしました。
業界を問わずマネージャーの方、リーダーとしてチームを受け持つ方、フォロワーシップを発揮したいメンバーの方、人事の方などに非常に刺さる本だと思います。
著者は医療テック株式会社カケハシのEngineering Manager、いくおさんです。(X/Twitter、note)
メタル好きの非常にユーモラスな方です。Twitterを見ていると平日はだいたい金曜日で、よく厳しい1on1をしています(※)。
※ ルビはおそらく「同僚と2人で楽しくお酒を飲む」です。


おそらく下記のスライドでいくおさんを認知している方も多いのではないでしょうか。

ほかにも2024年3月で開催された神奈川のスクラムフェスでのスライドもとても良く、現場とコミュニティーの学びのサイクルを循環させ個人と組織に変化をもたらすためのきっかけをくれます。
本書を読もうと思ったモチベーション
こんな感じで元々いくおさんを認知しており、普段からアウトプットを大変参考にしていたので今回書籍を買うに至りました。
また、
・プロダクト開発に限らず汎用性が高そうなアジャイルとスクラムについて、どこかで勉強したいという気持ちがあった
・チームビルディングと人事評価への関心が高まっていた
という私にとってドンピシャな書籍でした
先にも触れましたが目標設定というタイトルでありつつ、もっと広い範囲での学びがあり、目標設定の土台となる強いチームをつくるための理論や手法がわかりやすくまとまっています。
また、参考書籍が29冊とかなり冊数が多く、よくこの1冊にコンパクトにまとめてくれているな~と思いました、ありがたい限りです。アジャイルサムライなどの有名どころも紹介されており、せっかくなのでこれを機に何冊か読んでみようと思います。
各章についての学びと感想
ここからは各章(書籍内ではSTEPと表現されています)についての学びと感想をピックアップします。
STEP1 お互いを知ろう
インセプションデッキやワーキングアグリーメントを通してチームの価値観を共通認識として持つことを紹介しています。
メンバーが入れ替わらない場合でもチームを取り巻く状況や自分たち自身が変化することは十分にありえる。そのため、たとえば四半期に1回、長くても半年に1回くらいはインセプションデッキを更新する機会を設けておくとよいでしょう。
ワーキングアグリーメントは、チームが協力して仕事を進めるうえで守るべきルールや基準、行動洋式を共有するための合意事項であり、チームとしての価値観に基づいて作成されます。
[ ワーキングアグリーメントの例 ]
・毎日の朝会では、ちょっとした気になっていることも共有しよう
・モブプロをやるときは30分に1回ドライバーを交代する
・想定外のことがあったらすぐチームのチャンネルで共有する
・質問歓迎! 手を止めるくらいなら質問しよう
・本番リリースの作業は二人でやる
・チャットツールのメンションは気を使わずにちゃんとつけよう
自分はこれらをチームのミニMVVと呼んでいたり、プロジェクトの四方良し(※)を言語化していたので、チームで共通認識を持つことの有効性については実感していました。ただ、こういったフレームワークがあることを知らずに手探りでやっていたので取り入れていこうと思います。
※ 四方良し:近江商人の「三方良し」に「働く個人」を追加した造語です。
STEP2 ワクワクする目標をつくろう
本質に向き合ったSMARTな目標について語られていました。
Assignable:誰が取り組むのかを明確にする
その目標に取り組む人物を明確にしておけば、目標が宙に浮いてしまい誰もそこにコミットしないという状態を防ぐことができます。
目標にコミットしている人を明らかにするということで、単一の人物に目標を割り当てるということではありません。
目標達成自体の目的化を避け、本当に成し遂げたいことが何かを常に問いかけ続けましょう。
(中略)
組織の慣例として、〇〇%成長を目指すことになっている、など理由が不明瞭な場合は注意が必要です。なぜその成長率を目指すのかが明確でなければ、その目標を追いかけるメンバーが納得感を持つことは難しいでしょう。
すべてを数値で表すことができないため、STEP1でも紹介されているインセプションデッキの「われわれはなぜここにいるのか」などでWhyを言語化するのが大事なのだと思います。
また、「チームの目標であり、個人の目標ではない」というのを共通認識として持つことで、上手く進んでいないときも「原因の追究はするが、責任の追及をしない」といった前向きで健全な議論ができそうです。
STEP3 チームのリズムをつくろう
目標に向かって日々どのように進めていけばよいのかがまとめられていました。
レビューはがんばったことをよしよしする会じゃない
がんばりを認めるのはレビューの場はなくてもできることです。
がんばりはちゃんと認めていることを伝え、その上でレビューはがんばったで賞授与式ではなく生み出した成果から学びを得る場である、ということをチームの共通認識としてもちましょう。
自分はIT業界で働いていることもあり最初はコードレビューを想定しながら読んでいましたが、成果物のレビューすべてに通ずる話だと思っています。
私自身もレビューの目的と心構えを共通認識を持ちたいと思い、以前記事に書き起こしていました。(Qiita記事:コードレビューの思想や心構え)
ほかにも情報の非対称性の防ぎ方や、チャレンジグな目標を達成するために研鑽を積むことを奨励し、場や仕組みを作って継続していくことについて語られていました。
こういったマインドと研鑽の必要性をリーダーが積極的かつしつこいくらい継続的に発信していくのが強いチームをつくる要素のひとつだと思いました。
STEP4 チームのマインドを育てよう
強くてしなやかなマインドセットをつくることについて語られていました。
責務とは行為にある。その結果にあらず。飢えた我が血の最後の一滴まで責務に向かって突き進むのみ。
(中略)
行為には責任を持つが、その行為の結果は執着しないという原則です。
(中略)
ひとつひとつの実行に対しては結果責任を持たない、失敗を許容する。けれども最終的に結果を出すことにこだわり抜く。だからこそ失敗を恐れず何度も実行していくことが大切です。
感謝を伝えるということは「あなたの行いは私にとってポジティブな意味をもたらすものです。」と承認する行為に他なりません。
(中略)
チャットの投稿に対してリアクションすることの副次的効果に、承認したい対象のメンバー以外の目にも承認していることがわかるということがあります。
こういった行動は承認に値するものなんだとわかれば、自分も見習ってみようという気持ちになるかもしれません。
これは評価の不完全さを補える良い取り組みだと思いました。
評価を通じた金銭的な報酬はゼロサムゲームであり、チームとして目標を達成できたとしても全員の評価が必ずしも上がるわけではなく、また目標が未達の際に評価フィードバックのときだけ過程を褒めても納得感に欠ける印象です。
そのため日頃から行いをポジティブに承認する=感情報酬はお互いに与えることで、全員のパフォーマンスが向上する好循環が生まれると考えています。
STEP5 助け合えるチームになろう
チームとして助け合いながら前進していくための振り返り手法やマインドについて語られていました。
勉強や研鑽に割くための「時間がない」の言葉の背景にあるものと解決法
・文字通り時間がない
・朝会の前30分を学習の時間にあてる
・30分ごとに歯抜けの予定が入っているのであれば調整してまとまった時間をとるようにする。
・そもそも予定を減らすというのも有効なアプローチ
・一過性の忙しさならそれが過ぎるのを待ってから取り組むのも一つの手
時間をかけてよいかわからない
・判断を仰ぐべき相手に直接聞く
それに対する意欲がない
・意欲は自信、関心、動機の3つで構成されており、いずれかが欠けている場合は意欲がない状態となる。そのためまずはその技術などを知ってもらい、近い現場の成功事例などを紹介することで自信・関心・動機を満たす。
木こりのジレンマを打破する現実的な方法が書かれていました。
こういった研鑽も先にあったようにポジティブに承認していくことで継続されていくものだと思いました。
STEP6 チームの開発生産性を測ろう
開発生産性の指標と向き合い方について語られていました。
2種類の生産性について
① 物的生産性
同じ労働力でどれだけ多くの生産物を作り出したかに着目する。自分たちの行動でコントール可能
例:機能リリース数、ソースコード行
② 付加価値生産性
同じ労働力でどれだけ多くの付加価値を作り出したかに着目する
例:経常利益、MAU、メディア掲載数
グッドハートの法則:測定が目標になると、その測定は適切な目標でなくなる
チームで対話し、自分たちがありたい姿を徹底的に話し合い、その姿を示す指標ってなんだろうね、ということを形にしていくことが大切
良い例:高速に仮説検証をまわせるチームを目指し、そのチームなら年間100回くらいはデプロイしているよね。と目安として数値を立てるやり方
ほかにも「バランスよく生産性を捉えるためのSPACEフレームワーク」や「開発生産性向上のヒントを得るバリューストリームマッピング」なども紹介されていました。
ここでも目標の背景にあるWhyの必要性、それを実務適用するためのHowが語られており、この書籍の一貫性と誤解を与えない配慮に魅力を感じました。
書籍からもこれだけマインドセットが伝わってくるので、著者のいくおさんが日々本質に向き合いながら強くしなやかなチームを作っている姿が目に浮かびます。
STEP7 チームの外と向き合おう
アウトプット指標とアウトカム指標、目標を追いかけるうえで大切なステークホルダーとの向き合い方について書かれていました。
モチベーションの源泉
・内容理論:人間のモチベーションがどのような要因によって生じるか
・過程理論:モチベーションが生じる過程、そしてどのように行動に結びつくか説明するもの
高すぎず低すぎず、ラーニングゾーンにいられるような目標を設定することで目標達成へと向かう中で成長することができます。しかし、この「高すぎず低すぎず」というのがなかなか難しく、いざ着手してみたら案外簡単だった、全く手のほどこしようがないほど難しかった、ということが起こり得ます。ラーニングゾーンの範囲は意外と狭いのです。
ある程度ラーニングゾーンが見えてくるまで、小さなトライアンドエラーを繰り返しながら目標自体を更新し続けていくとよいでしょう。
モチベーションの源泉についての理論がわかりやすくまとまっていました。マズローの欲求段階説は知っていましたが、それ以外の理論は知らなったです。なんとなく進めがちなチームビルディングというソフトな分野も体系立てて理論で勉強したほうがよいと思えました。
ラーニングゾーンの狭さにも共感です。また、「コンフォートゾーンから出よう!」といって出れる人は最初から出ている説があると思っており、先に挙げた理論をもとにモチベーションを喚起させ、結果的にラーニングゾーンに移動しているということを成立させられると持続的に強いチームになれると思いました。
ステークホルダーとの向き合い方ではブルックスの法則やQCDSについて語られていました。

STEP8 ゴールにたどり着いたその先に
目標達成の結果確認、これまでの過程を学びとしたと次への進め方について書かれていました。
通信簿の例:インセプションデッキ、ワーキングアグリーメント、OKRに対して評点をつけている
インセプションデッキの更新
・OKRの達成状況から学習し、自分たちの次の行動を改善していく
・シングルループ学習:結果から学んで行動を変化させていくこと
・ダブルループ学習:学習、行動の背景にある前提・メンタルモデルまで書き換えていくこと
・個人や組織の行動・判断・思考の基礎を形成するメンタルモデルをも更新対象とすることで、より根本的な改善・変化につなげていくことができる
ゴールは「あくまでその時点でのゴール」として、次に向かおうという前向きなマインドが伝わってきました。
こうしてSTEP1へ戻ってサイクルを回していくことで強いチームが実現するのだと思います。
コラム
各STEPの最後にあるコラムを書かれた方々が豪華でした。会社に留まらず強いチームを作れているのだと思いました。
株式会社SmartHR 代表取締役CEO 芹澤さん
株式会社レッドジャーニー 代表 市谷(いちたに)さん
KDDI アジャイル開発センター株式会社 アジャイルコーチ 小笠原さん
株式会社Layer X 代表取締役CTO 松本さん
株式会社レッドジャーニー 取締役COO 新井(あらい)さん
YesNotBut株式会社 代表取締役 川口さん
株式会社野村総合研究所 チームファシリテーター 森さん
カケハシCTO 湯前(ゆのまえ)さん
さいごに
この書籍は読み進めながらストーリーを追うことで点と点が線になる感覚がとても良かったです。ページ数はマンガやイラストを差し込みながら271ページと標準的なボリュームなのですが、都度考えさせられるため非常に読み応えのある内容でした。
本記事では主観でピックアップしており魅力を伝えきれていないため、興味をもったらぜひ手にとっていただければと思います!
※ 私は回し者ではなく、ただのいくおさんファンです笑
また、2024/9/10(火)19:00~、秋葉原にて本書籍のイベントをするそうです!
追記
著者のいくおさんからポジティブなフィードバックをいただけました!
嬉しい!
メタル好きの非常にユーモラスないくおです。よろしくお願いします。(詳細かつ熱量のこもったレポート、とてまうれしいです!ありがとうございます!)
— 190ODA(いくお) (@dora_e_m) August 13, 2024
強いチームの作り方を学べる「アジャイルチームによる目標づくりガイドブック」|asano @nash_efp #note https://t.co/U1CkM8UAcP
