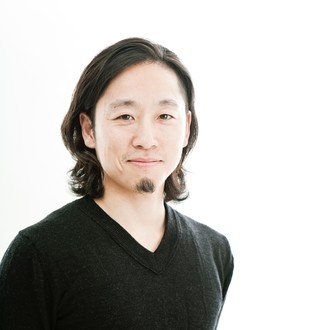【日記】弱った魚は浮いてくる
うちには水槽が二つあって、日淡を飼っています。
ウグイ、タモロコ、オイカワ、アブラハヤ、ドジョウ、シマドジョウなどです。
魚の飼育ではあるあるなのですが、時々魚が水槽の蓋の隙間から上手に飛び出すことがあります。
そのまま気づかずに干からびて仏になることが多いのですが、ピチピチと音がして出たことにこちらが気づいて救えることもあります。
それでも、外に出ている時間が長い場合は一命は取り留めたとしても、徐々に弱ってしまうこともあります。
ちょうど先日もオイカワが1匹飛び出してしまい、、、。
そうやって弱った場合、ある時期から弱った魚は上層を泳ぐようになります。
基本的に、魚は水面の下の方に位置して、浮いてる餌を取るために急激に浮上して食べてはまた下に潜ります。
上層部は鳥の脅威があるので、普通は上層にはいません。
上層は稚魚とかが多いですね。
稚魚は大きな魚が脅威であり、鳥は小さすぎると取りづらいので、稚魚にとってはそこまで脅威ではありません。
弱った魚が上に上がってくるのは、下の魚の競争に勝てずにいじめられる(突かれます)こともありますが、水流の弱いところを探していると上層になるのかも知れません。
そしてそれは結局、鳥に見つかりやすくなります。
これって、大きな食物連鎖としての自然の流れを見ると理にかなっているなと。
弱ったら、上に上がって鳥に捕獲してもらって、命を捧げているようにも思えます。
「食べて下さい鳥さん、、、僕の命はもう僅かなんです。」
そんなふうに見えてしまいます。
元気なら自分の子孫を残すためにしっかりと競って食べ物を取り、自分を生かす(自利)。
弱ったら、競争ではなく自分の命を他の生物に捧げる(利他)、、、。
魚にそういう意思があるとは思いませんが、結果的にそうやって自然は回ってるなと。
人間はどうだろう。
自分が利他になるには自分が弱ることも大切なんじゃないかなと思ってみたり。
元気ということは、自利になりやすい。
そういう意味では病というのは、利他になるための貴重な段階なのかも知れないですね。
年老いていく、不治の病になる、そういうことも利他の精神を得るための過程だと考えられるなと。
最後をどう生きるのか、、、。
最後まで自分にしがみつき、自利を通す生き方と。
弱っていく中で、利他の精神を持った生き方、、、。
後者でありたいなと、上層部を泳ぐ弱った魚に自分を投影して思う今日この頃です。
いいなと思ったら応援しよう!