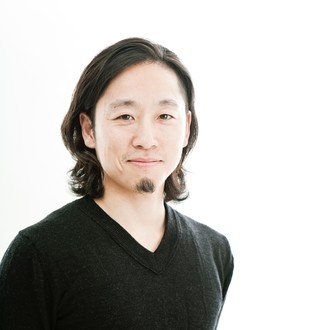【側弯トレーニング日記】なぜ個別性は無視されるのか?
皆身体は違います。
身体が違うということは、個性があるということです。
「育ってきた環境が違うからすれ違いはしょうがない〜♩」
誰かの歌詞ですが、ヒトは遺伝という情報と、神経系の学習とそして環境因子から成り立っています。
それぞれに個性があるので、当然現存する本人と同じヒトは存在しないわけです。
一卵性双生児は遺伝情報は一緒ですが、学習や環境が違えばやはり違う人になるでしょう。
ヒトの個性=遺伝情報+学習要因+環境要因
僕は側弯症の方々の運動療法に10年ほど携わってきました。
その中でよく感じることなのですが、医師は側弯症の方を見ると、ほぼ特発性側弯症と診断します。
それは、多因子遺伝疾患というもので、原因は特定できないけれど、遺伝が関与しているであろう病気という意味です。
しかし、理学的検査をしていくと、スポーツの影響だったり環境の要因が大きかったりと、かなり原因を特定できる方がいます。
そういう遺伝以外の側弯症を機能性側弯症というのですが、本来機能性というのは、骨そのものに変形がない姿勢としての側弯を指します。
ですから、僕は的確な表現が存在していないので、習慣性側弯症と勝手に名づけて分類しています。
さて、理学療法的な視点では、原因が特定できるのに、なぜ医師は十ぱ一絡げに遺伝というのか疑問でした。
もちろん、理学的検査ができる療法士がまず少ないので、診断の補助ができていないというのが大きな理由ですが、それ以上にこれは医師の根本的な概念の話だなと思うようになりました。
つまり、医師が見ているのは個性ではなく、標準なのです。
例えを使います。
血圧に関して、正常血圧というものがあります。
120/80mmHgというやつです。
年代によって少し違いはありますが、概ねこれです。
さてこういう正常値がどうやって決まっているかというと、正規分布を用いて、その中央値を使っています。
つまり、標準的な値を正常と定義しているわけです。
人には個性があるので、血圧も低くて安定してる人もいますし、高くて安定してる人もいます。
でも標準ではないので、それらの方々は異常となります。
症状がなければ本来は問題にならないはずですが、血圧を測れば異常値となり、異常と判定されるわけです。
この考え方は、人を標準化して、個性があるものは異常として捉えるという概念です。
面白いですが、芸人とかは普通じゃないキャラクターに価値がありますが、彼らは標準ではないので、異常な性格となります。
医師も、正直偏差値が高くないとなれない職種でもあるので、異常な人たちです。
でも、健康となると、標準でないとおかしいよとなるわけです。
さて、医療の見ている健康というのは、標準的かどうかということですから、個性があると困るわけです。
個性は見ないという前提があると言ってもいい。
側弯症という変形に関して当てはめると、コブ角という角度は数値なので情報です。
ここに個性はありません。
しかし、その人の性格とか、趣味とか生育歴とか、そういう多種多様な背景には個性がありすぎるので、医療では無視するわけです。
つまり、医師が見たいのは角度なのです。
標準化どうかを見る仕事ですから。
そうなると、スポーツを何していたいとか、生活習慣とかに興味がない。
個性の聴取をしたら標準化できないからです。
医療が見ているものは、数値であり、情報なのです。
そこに個性というノイズを入れてしまうと、医学的な(数値による客観的な)判断ができなくなってしまうというわけです。
医者が話を聞いてくれないと訴える患者さんは多いですが、それはあなたという個性に興味があるわけではなく、数値化された身体に興味があるからです。
話しても意味がないと思っているのです。
話は数値じゃないからです。
これは医師も気づいている人といない人がいるでしょう。
あまりにも当たり前に仕事をこなしているので。
理学療法は、その点個性踏まえないと対応できない仕事です。
なぜなら、その方々の習慣に入り込む必要があるからです。
筋トレをしましょうと言っても、忙しい働き盛りの方と、暇な人、やる気のある人とない人、環境的に難しい人と整っている人、、、。
まるで状況が違うのです。
そこに合わせていかないと実施できないので、生活習慣や環境のことなど様々な個性を聴取します。
これが理学的検査でも応用されるので、既往歴、スポーツ歴、生活環境、偏った習慣など、多様な個性を確認します。
だから、遺伝だけでない原因を見つけることができるのです。
つまり、個性の中から変形の原因を探ることができるのです。
医師は数値化される情報のみから診断をします。
理学療法士は個性も含んだ、環境や習慣も含んで検査します。
これが根本的な違いなのです。
ですから、医師の意見や考え方には、とっても大きなバイアスがかかっているということです。
情報化した身体しか見ていないというバイアスです。
さらにそれに医師気づいていません。
ここが結構問題で、だから患者さんとすれ違います。
これは、医療の教育や診療報酬のシステムに依存した歪みですから、誰が悪いわけでもありません。
ただ、この歪みを明確化して解決するのは理学療法士だと思います。
医師と患者さんの両方の感覚を理解し、その間を埋める役割です。
そのためには、個性を医師が分かるように数値化する必要があります。
また、習慣性の素くぅ暗唱というものが存在するというエビデンスを示すことです。
僕も試行錯誤していますが、医師と患者さんの歪み構造については、概ね把握できたので、ここを解決するために動こうと思います。
まずは研究ですね。
医師は数値、情報は好きですから。
患者の顔は見なくても(顔は個性なので)、レントゲンや血検データは見ます。
そこに習慣やスポーツの影響を数値または、論文に基づいた報告を行えば見てくれます。
日本は強烈なヒエラルキー構造なので、医師の理解なしに医学は存在しないので、医師の説得が全てです。
理学療法士もピンキリなので、的確な理学的検査ができるように底上げをする必要もあります。
やることは沢山ありますが、やりがいがある部分でもあります。
10年間側弯症の方々と接してきて、その理不尽さは痛いほど感じています。
微力ですが、次の10年くらいで今とは違う常識を作っていけたらと思います。
応援してくれたら嬉しいです。
いいなと思ったら応援しよう!