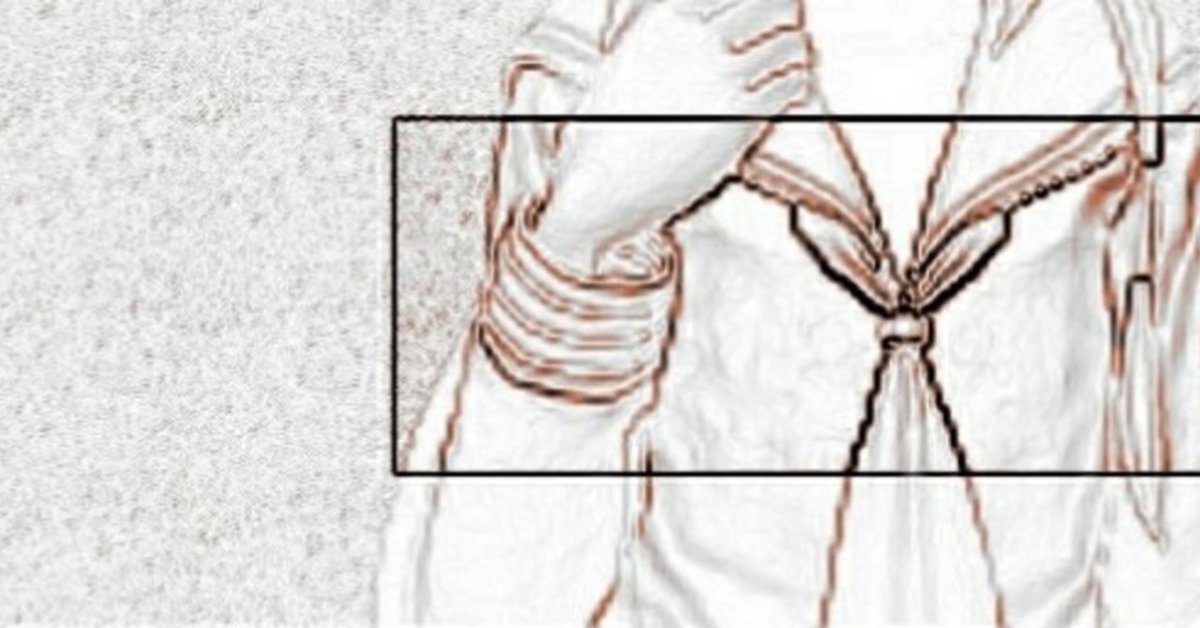
調教しないと出られない部屋
彼女、川嶋津美空《かわしまづ・みく》について知っていることは少ない。
同級生というだけで、接点はほとんどなかった。
あまり目立たない地味目な女子のひとり。
休み時間もクラスの誰とも話さず、自分の席で本を読んでいるタイプ。
磨けば光りそうな整った顔立ちに、頼み込めばやらせてくれそうなおどおどした性格ということで、男子の一部から隠れた人気は集めているようだったが。
私自身はそれほど派手目女子ではないつもりだが、そちら寄りの賑やかな友人の方が多かった。
クラス内ヒエラルキーという言い方をすれば、上層階級の末端くらいか。
何か学校行事の用事で、二言か三言、会話を交わしたことがあっただろうか。
そんな本当にただクラスが同じだけという間柄だったのだ。
閉じ込められて
1
「……さん ……藤沢さん」
誰かに名前を呼ばれているのは分かった。
少し離れたところからみたいな、かぼそい遠慮がちな呼び方で、本当に私のことを呼んでいるのかどうか、少しの間実感が持てなかった。
長い夢を見ていたような気がした。
その夢の中の景色が唐突に薄らいで消えたかと思うと、視野はぼんやりとした薄暗がりにに包まれた。
もうじき目が覚めるのだと分かるのだけれど、自分で目を開くことがなかなかできないというようなもどかしい感じ。
「藤沢さん」
その薄暗がりのどこかで、さっきより少しだけはっきりと呼ばれた。
聞き覚えのある、それでも誰だったかすぐには思い出せない声だと思った。
「ん……」
ようやく目を開くと、自分と同じくらいの女の子が、心配そうにのぞきこんでいるのと目があった。
知っている顔だと思った。
たぶん、毎日のように見ている顔。
だが、誰だったろう。
起き抜けだからというだけではなさそうだ。
どうも頭がはっきりしない。
自分の家の自分のベッドでもないらしいということだけ、だんだん把握できてきた。
高級そうな絨毯の上ではあったけれど、どうやら床に寝転がっていたようだ。
それを意識したとたん、身体の節々が急に痛みだしたような気がした。
「ああ、気がついた、藤沢さん?」
先ほどの娘がほっとしたように言う。
少しだけはっきりした頭でよくよく見てみれば、確か同じクラスの……
「カワシマ?」
「え?」
「あ、ご、ごめん、川嶋津さん」
その少し変わった名前を、仲間内では勝手に省略して呼んでいたのだった。
何しろ影の薄い娘で、私たちが彼女を話題にすること自体、めったになかったけれど。
しかし、分からなかった。
意識はようやくはっきりして来ていたが、目覚めて最初に見えたものがその川嶋津さんの顔だったという状況が、私を混乱させた。
お互いの家を訪れあうような仲ではなかったし、泊まりっこをすることなど考えられない相手だったから。
何かは分からないが、普通ではないことが起こっているらしいと思った。
とりあえず身体を起こそうとして、自分が制服姿なのに気付いた。
そんな格好のまま床に寝転がっていたというのも、また普通なら考えられないことだ。
学校か、登下校の途中で何かがあって意識を失ったとでもいうことか。
そもそも私は最後に何をしていたのだったか。
「つ……!」
記憶をさぐろうとすると、それに抗議するかのように頭が痛んだ。
「大丈夫、藤沢さん?」
川嶋津さんが本当に心配そうに聞いてくるが、それはこっちが聞きたい。
「私、何があったの?」
「え、あの、それは私も分からなくて」
頭痛のせいで顔をしかめてしまったのが、ひどく不機嫌そうに見られてしまったのかもしれない。
普段から気弱そうなしぐさや物言いの川嶋津さんだけれど、それに輪をかけておどおどした様子だった。
もともとそんな彼女にあまり好印象は持っていなかったが、今はその態度がいっそう鼻についた。
何にしても、彼女も今のこの状況を把握は出来ていないらしかった。
ひとまず彼女をあてにするのはやめた。
ともかく自分が今いるここがどこなのかを確かめようと視線を巡らせた。
「な、何よこれ」
最初に目についたものに、私は声をあらげた。
というより、もとから視界のはしにはとらえていたのだけれど。
それくらい私のすぐそばにそれは鎮座していた。
三角屋根に半楕円の出入口、わざとのように雑な着色のなされた、どこからどう見ても犬小屋だった。
ただ、サイズが通常のものよりだいぶ大きい。
私くらいならどうにかもぐりこめそうなほど。
そんなものが自分の寝転がっていたすぐそばにあるというだけで、良い気はしなかった。
さらに唖然とさせられたのは、出入口の上に設置されたプレート、そこに書かれていた文字だ。
ふじさわなお
紛れもなく、それは私の名前だった。
よくよく見てみれば、側にはペット用のエサ皿や水飲み用のボウルもあり、それぞれにひらがなやローマ字でやはり私の名前が入っている。
それらの意味するところは考えるまでもなかった。
「あなたのしわざなの、カワシマさん!」
彼女はそういう陰湿なことをするタイプとは思えなかったし、もっと言えば、ここまで手の込んだいやがらせをされる覚えもない。
そこまで嫌われるような接点もなかった。
それでも一瞬で頭に血ののぼった私は、彼女に食ってかかった。
「ちが、ち、ちが……」
胸ぐらをつかまんばかりに詰め寄る私に恐れをなして、川嶋津さんは両手を振りながら後ずさった。
何もないところで足をとられ、大きくよろけた。
床に尻餅をつかずに済んだのは、倒れこんだその先にたまたまソファがあったから。
そんな彼女の滑稽な様子に、私もいくらか冷静になることができた。
わざわざ人を怒らせるような度胸は彼女にはありそうになかった。
「ごめんなさい」
ため息まじりのような、吐き捨てるような、謝罪の言葉を口にしながら、あらためて自分が今いる場所を確かめようと周囲を見回した。
学校の教室より少し狭いくらいだろうか。
壁紙や照明器具、それに今しがたまで私が寝転がっていた絨毯などは、かなりの高級感だ。
ただ、部屋の広さに比べて家具類、日用品類が極端に少なく、それが全体の雰囲気をわびしく貧相に見せている。
今川嶋津さんの座っているソファと、セットになっているらしいローテーブル。
少し離れて、私たちふたり手足をのばして寝られそうなサイズのベッド。
他には壁に埋め込まれる形で設置されたテレビモニターがあるだけだ。
私の名前を入れられた忌々しい犬小屋やエサ皿などは、これは家具のうちには入るまい。
「なんなの、この部屋?」
川嶋津さんに尋ねるというより、独り言のように言いながらもう一度部屋を見回して、気付いた。
窓がひとつもない。
それなりの広さもあるし、どこかで空調設備が稼働しているのか、閉塞感や息苦しさは感じないものの。
そしてもっと異常なことには。
「どうなってるの、出入口もないじゃないの」
ドアはひとつだけ。
そこにははっきりと「BATHROOM」、つまりお風呂と記されている。
「確かに浴室だった。トイレもついた」
私の視線の先に気付いてか、川嶋津さんが言った。
その言葉を疑う訳ではなかったが、確かめたいことがあって、私はドアまで歩いていって開いてみた。
確かに、浴室だった。
そして、そこにも窓はひとつもない。
もちろん、どこか別の部屋へ通じる出入口も。
換気は行われ、浴室に排水溝もある以上は完全な意味での密閉状態ではないにしても、人や物が出入りできないという意味で、この場は密室なのだった。
こんな部屋に、私たちはどうやって連れ込まれたというのか。
いや、それ以上に。
「私たち、ここから出られるの?」
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
