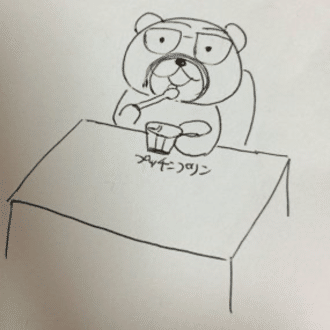精神科の精神保健福祉士のお仕事 ⑪医療保護入院期間の更新の手続き
令和6年に施行された精神保健福祉法で、医療保護入院の手続きがこれまでと大幅に変更になりました。
大きいのは、医療保護入院の更新手続きが必要になったことです。
以下に施行前と施行後どうなったか比較して書いてみますが、特に施行後は手続きや流れが複雑化しているため、もしかしたら間違っている箇所があるかもしれませんので、正確に把握したい亜場合は厚生労働省や各自治体で出している法律のQ&Aをあたってください。
施行前・・・
①家族等の同意を得て、精神保健指定医の診察の結果として医療保護入院になった方が、入院診療計画書で医療保護入院の予定入院期間が示される
②医療保護入院の予定入院期間は最大11か月までだった
③予定入院期間を過ぎる場合は、本人、家族、主治医、精神保健指定医、看護師、精神保健福祉士等で退院支援委員会を行い、さらにどのくらい医療保護入院が必要かを決めていた
退院支援委員会の審議結果のお知らせを本人に渡す
④医療保護入院期間が1年を過ぎると、退院支援委員会を行う必要はなくなり(行ってもいい)、その後は年1回の定期病状報告書と最後に行った退院支援委員会の審議録を、医療保護入院になった月内に都道府県に提出する
施行後・・
①家族等の同意を得て、精神保健指定医の診察の結果として医療保護入院になった方は、医療保護入院に際してのお知らせで、入院予定期間を示されることになった
②医療保護入院の入院予定期間は、最初は3か月以内となった
1月1日に医療保護入院になった方が、3か月後に迎える4月1日を満了日と言う
③予定入院期間を過ぎる場合は・・
Ⅰ 指定医による医療保護入院が継続必要な診察
Ⅱ 退院支援委員会の開催し、審議録を記載する
法改正以前は、退院支援委員会には、主治医が精神保健指定医でない場合は、精神保健指定医の出席が必要であったが、今回の法改正で精神保健指定医の出席は必須ではなくなった
退院支援委員会の審議録は、出席した人全員に渡すことになった(院内職員以外)(例えば、本人、家族はもちろん、訪問看護や保健所、福祉事務所などからの参加者にも渡す)
Ⅲ 同意した家族等について、医療保護入院期間更新についてのお知らせと退院支援委員会審議録を渡す(送る)
A医療保護入院中にその家族と2回以上連絡がとりあっている場合は、更新に当たって、更新のための同意書を提出してもらわなくても、入院継続に反対でなければ同意したものとみなす(みなし同意)
B医療保護入院中にその家族と2回以上連絡をとりあっていなかったり、最初に同意した家族が何らかの理由で(他界した)同意できない場合は、別の家族に医療保護入院の更新のお知らせを渡し、更新の同意書に記載をしてもらう
C市区町村同意での医療保護入院の場合は、市区町村に医療保護入院期間の更新に関する同意依頼書を送り、満了日までに同意書を返送してもらう
Ⅳ Ⅰ~Ⅲがすべてそろったら、満了日の翌日に(ここは各自治体で解釈の違いがあるかもしれません)医療保護入院が必要な本人と同意した家族に、医療保護入院の入院期間の更新に際してのお知らせをそれぞれに渡す
Ⅴ 医療保護入院者の期間更新届を、主治医、精神保健指定医、退院後生活環境相談員それぞれで必要箇所を記載し、更新の同意書と、退院支援委員会の審議録を添えて、都道府県に満了日の翌日を起算日として10日以内に東京都に提出する必要がある
施行後は明らかにやらなくてはいけないことが増えています。
やらなくてはいけない手続きが増えたことで、医療保護入院中の患者さんの意思が尊重され、早期に退院に結びつくことになれば、法律が変わってよかったと思えます。
しかしながら、個人的な印象として、あまりにもやらなくてはいけない手続きが多すぎて、精神科病棟の精神保健福祉士は、手続きを遅滞なく、ミスなくこなすことに忙殺されてしまい、本来入院中の患者さんと時間をかけて関係をつくって、意思決定支援をしていくということが、かえってできなくなってしまうように思えます。
医療保護入院の更新手続きを無事に済ませるということに注力されてしまい、医療保護入院の妥当性を検討することができなくなってしまわないでしょうか?
また、手続きが大変だからという理由で、医療保護入院から任意入院に切り替えるようなケースが増えてくることが考えられます。任意入院になれば、医療保護入院に比べて、単独で外出しやすくなるなど、制限が緩和されるので、患者さんにとってはよいことかもしれません。しかし、任意入院の場合は、医療保護入院の更新手続きのように都道府県で書類をチェックすることがなくなってしまうので、逆に長期入院の温床となってしまうおそれがあります。
任意入院になれば、患者さんが退院したいといいやすくなるかというと、そうとも言えません。任意入院のまま、長期入院をしていることで、退院したいという意欲が減退している、退院することが怖くなっている患者さんも数多くおられます。院長や担当している精神科医が、退院支援に興味がなく、精神保健福祉士が退院を提案しても、難しいという場合もあるでしょう。任意入院の場合も、入院が妥当なのかどうかチェックできる仕組み作りが必要かもしれません。しかし、そうなると、更にやらなくてはいけない手続きが増えて、精神科の精神保健福祉士は、書類処理に忙殺されてしまう可能性がありますが・・
医療保護入院、任に入院ともに、もう少し手続きを簡素化するかわりに、どちらも入院継続の妥当性をチェックできるような法律にして、精神科病院の精神保健福祉士が、常に退院できる可能性はないか地域の支援者とともに模索し続け、患者さんの退院したいという気持ちを汲み取り、退院へのモチベーションを上げられるよう関わり続けていく時間をつくれるようにしていくことが大事かと思います。
いいなと思ったら応援しよう!