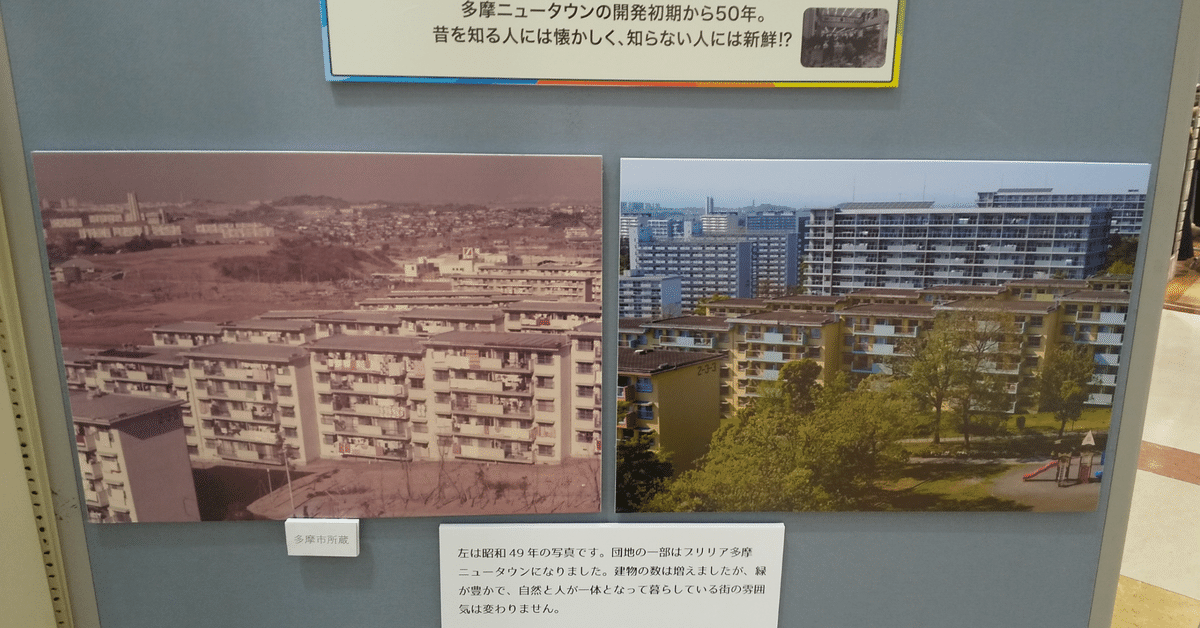
シリーズ 昭和百景 「『絹の道』を取り巻く、ニュータウンの相貌(そうぼう)」
「土地はもう十分買ってある。もう買わなくていい」
西武グループの創業者、堤康次郎は、今際の際で、のちにグループを率いることになる義明にこう告げたと伝わる。
康次郎は1964年に倒れるまで、そこがなお荒野と呼ぶにふさわしいところであろうと、日本全土の目ぼしい土地という土地を買い続けた。
絹 の道は、西武グループが70年代以降、多摩ニュータウン開発に相乗りするかたちで造成開発した八王子北野台に接してはいるものの、幸運にも、小さな痕跡を今にとどめることかなった。それこそ西武グループの創業者である堤康次郎の全盛期に、大塚山公園を含んだ鑓水一帯を包括した都市開発に着手したのであれば、今日そこにはコクド所有の有料道路が引かれ、「プリンスホテル」のひとつが建っていたとしてもおかしくはない。
絹の道は、「強盗慶太」率いる東急グループによる片倉台開発と、「ピストル堤」の西武グループによる北野台開発との、まさに空隙に息を潜めている。
1920年、日本に鉄道省が設置されたその年、康次郎は後の西武グループの礎であり、中核企業となるコクドの前身、箱根土地株式会社を設立した。
第一次世界大戦の戦勝国として、その勢いを買った日本には瞬間的な戦後景気が到来し、石油を初めとする重化学工業を国策として推し進めようとする機運が高まっていた。1918年(大正7年)には、三菱鉱業、古川鉱業が相次いで創設され、炭鉱掘削など資源経済の予兆もあった。対外的には国際連盟の常任理事国として加盟を果たし、世界の列強国としての体裁を整えんとばかりに、産業、経済の国策化が推進されていた。
康次郎がその頃、古くからの温泉郷でもあった箱根や軽井沢に目をつけ、行楽地や避暑地としての開発に乗り出したのは、そんな日本に瞬間的に吹きぬけた発展楽観の機運を肌で感じ取ったためであるかもしれなかった。だが、あくまでもそれは瞬間風速だった。
実際、設立後数年で、箱根土地の経営は急速に悪化し始める。旧華族の保養地であった箱根の優良物件を買収しては分譲開発する手法は、当初は目論み通りの収益を上げた。
当時、「箱根土地の前途」としてダイヤモンド誌がその財務内容を分析し、それを引用した『堤康次郎』でも、その分析を素直に受け入れている。
「すなわち、内部留保はきわめて乏しく、経営を維持するのに二〇〇万円以上を社債などの外部負債に依存していたのである」と。
確かに大正11年上期では744万7千円だった負債が2年後の13年には1583万4千円にまで倍増している。同時期の社債も100万円から300万円に跳ね上がり、その汲々とした資金調達の息苦しさはあからさまになっている。だが、その負債と資産のそれぞれの合計額に目をやると、負債額と資産額の数字が一致していることに気がつく。借入金は多く苦しいのは事実ですが、同額の資産もあるので経営体力としてはトントンですよ、と印象付けているようにも伺える。ときに“芸術品”ともいわれる税務処理で「赤字出さずして黒字出さず、そして税金払わず」で長い歴史を生きてきたコクドの企業経営の原型を見せ付けられているようでもある。
大正13年(1924年)といえば、康次郎が郷里、滋賀で衆議院議員選挙に立候補し、初当選を果たした年でもある。確かにその頃、康次郎は火の車だった。1963年12月5日付けの『週刊現代』は近江の地元有力者の証言を紹介している。
「その後新代議士となってからも、東京宅と云うのを訪問してみると、品川あたりのぼろ屋敷に住み込んでいて、『おお、よくやってきた。まあここへ座れ。ところで我輩はいま、どえらい債鬼どもの包囲攻撃を受けておる最中じゃよ』そういって机の蓋を引っくり返してみせると、ベタ一面に破産申告書や借金取り立ての内容証明ばかり貼り付けてあって、しかもその金高がどれもこれも気が遠くなるようなすごい数字なのには、まったくぎょっとさせられたという話である。でも、新代議士はタメ息まじりの遠来の客を慰めるように、『だが、このワシだって、軽井沢や箱根に、ざっと五百万坪ばかりの土地をもっておるから、これさえ坪一円で売れてくれれば、こんな借金ぐらい屁のかっぱじゃよ』と、呵々大笑したそうである」
大正15年にはついに康次郎は目白の屋敷を撤収し、当時はまだ辺境色の濃い品川・大崎に転居する。
箱根土地の本業はこの有様であるから、当然に「金にはきつい」訳でもある。第一次大戦後の好景気を後ろ盾にした土地ブームは同11年にはすっかり沈静化し、土地の分譲で急成長した箱根土地はいよいよ窮地に追い込まれていった。
そして大正15年3月、ついに箱根土地の社債、およそ200万円が焦げ付き、償還不能事件が発生した。事実上の破産だった。すでに康次郎は国会議員でもある。箱根土地の再建は日本興業銀行に委ねられることになった。通常ならばここで、資産整理が行われ、箱根土地が担保として持つ「500万坪の土地」は二束三文で切り売りされてしまうところである。だが、そこは「ピストル堤」とさえあだ名される康次郎である。一芝居も二芝居も長けていた。
この期に及んでも康次郎は事業の継続を画策していたのであろう。そのため、当時は国策会社だった日本興業銀行にその債権管理業務を当初の神田銀行から引き継がせ、国会議員という立場も全面的に押し出しつつ、債務者でありながらその債権処理の主導権を握ろうとした気配さえ感じられる。
その〝目論見〟は結果として見事に奏功した。興銀は債務者との和議方針を決定し、資産処分を凍結する。ようは、康次郎は債権者をなだめすかしながらこれまでの資産を手放すことなく再建計画に筋道をつけてしまったのである。
6年後の昭和6年5月に開かれた債権者集会では、康次郎は債権者を一人一人座席まで案内するなどし、後でそれが社長の康次郎であることを知った債権者を感激させてもいる。康次郎は折につけ、芸の細かさも見せた。
この前年、箱根土地の資産を継承する事業会社である日本温泉土地株式会社が興銀の主導で設立されている。それを受けて開かれた債権者集会で、康次郎の誠実さに心を打たれた債権者たちはとにもかくにもその場の矛を納めたのである。
だが、康次郎は“プリンス”と呼ばれる興銀マンよりも〝債鬼〟のごとき債権者よりも実にしたたかだった。
社債償還不能事件を引き起こし事実上の倒産に追い込まれる前年、1925年に康次郎は熱海峠と箱根峠を結ぶ自動車専用道路の新設を内務省に申請していた。日本初の有料道路としてその賛否騒動も展開し歴史に名を刻むことになるこの私営道路の建設は、明治政府以来初めての申請でもあり、認可が下りたのは出願から実に五年が経過した昭和五年七月だった。
火の車とも自転車操業とも言われる汲々とした状況のなかでも常に次の種を蒔いているのには恐れ入る。種が芽を葺き、さらに成長し花や実をつけるのには年月を必要とする。康次郎はその事業に通じる自然の摂理を実によく体得していたともいえる。
ようやく認可されたころには興銀を中心にした再建計画にもメドがついていた。そしてこの「十国自動車専用道路」がきっかけとなり、康次郎は鉄道事業に参入していくことになる。
ただ、この十国自動車専用道路を申請したのは破綻直前の箱根土地ではなく、駿豆鉄道だった。康次郎は1925年6月、駿豆鉄道の増資に際して同社株を購入し、役員を送り込み経営に参画していた。後に西武グループが西武鉄道とともに上場させた二社(現在はどちらも上場廃止)のうちの一社、伊豆箱根鉄道の前身が駿豆鉄道だった。
結局、認可から二年を経て工事は完了し、通行料として80銭を徴収する日本最初の有料道路が開通する。この道路を軸に、康次郎は熱海と箱根を結び、バスを通して熱海駅で降りた観光客を箱根まで運ぶことにした。箱根ではすでに芦ノ湖の開発に着手している。グループ会社の箱根遊船会社が芦ノ湖周辺の道路整備も着々と進め、リゾート地としての外観は着実に整えられていった。
驚くべきことに、箱根土地の破綻翌月の1926(大正15年)4月に、芦ノ湖での水上遊覧飛行まで始めている。破綻、破産、倒産という憂き目に遭ってなお、事業計画を推進していく様は今日の企業の経営管理体制ではありえないものである。銀行や役所の顔色や意向をうかがいながら恐る恐る、自らの権益をさりげなく潜り込ませていくといういやらしくも現代的な手法を康次郎は採らない。
あくまでも強引に、派手に、しかし確実に計画を推進していくのである。だが、それは決して夢だけに基づいた甘いものではない。緻密な計算と見通しと将来展望があるからこそ、周囲を説得しながらその強引さを発揮できたのでもあろう。このあたりは康次郎が晩年まで敬愛してやまなかった後藤新平の政策手腕と共通する部分である。
道路を整備し、自社のバスを通し、観光客の誘致を図る。そして到着した先には遊覧船や遊覧飛行がある。大正は15年を最後に昭和初年に入ったその頃、映画はあるが無声映画で、声の付いた「トーキー」が日本に登場するのも昭和に入ってからである。
映画、相撲、歌劇といったインドアの娯楽一辺倒の時代、見晴らしのいい峰々をバスでドライブし、芦ノ湖を見下ろし、湖の上を遊覧飛行機が飛ぶ。その開放感はきっと得も言われえぬ新鮮さを与えたに違いなかった。そして温泉で骨を休める。
康次郎は計画・施工・運営というすべてを一体化したリゾート開発の新しいあり方を模索していた。産業振興と国土開発を御旗とする国策会社の日本興業銀行も、こうした康次郎の展望に経済効果のそろばんをはじき、縷々とした康次郎の説得に耳を傾けたに違いなかった。債権者もまた、具体的な計画に納得したからこそ、その再建計画は順調に進んだのである。見通しのない「引き延ばし」に応じるほど、当時としても投資家の視線はザルではない。
そうした中、幾たびかの苦節を経ながらも、駿豆鉄道は順調に成長した。康次郎が初めて経営に参画してから三年目となる昭和二年には14万5905円だった営業利益が、17年には71万1460円にまで増加することになる。
この間、昭和12年には箱根遊船と合併を果たし、事業拡大に弾みをつけた。この間、康次郎の箱根プロジェクトを支えていたのは、再建計画でその手腕を改めて評価した日本興業銀行(現みずほホールディングス)だった。
当時の興銀の融資は、あくまでも、産業振興と国土開発という設立趣旨に照らした〝国策プロジェクト〟の趣が強い。極端に言えば、政府系金融機関という底尽きない金庫を後ろ盾にもつと同時に、興銀が融資している企業というだけで、事業展開にとっては政府の影さえちらつかせた公共事業のにおいも漂わせていた。もちろん、康次郎が衆院議員であるという信用力も大きな力を持つ。
堤康次郎の事業は、素性の知れない不動産屋から、序々にではあるが、国がバックについた信用力の高いプロジェクト会社であるかのごとき錯覚を与え始めていたはずである。そして、駿豆鉄道の買収で培った「計画・施工・運営」という一体型の開発プロジェクトの成功を弾みに、運輸・輸送という公共インフラを事業として確保することの意味を新たに獲得する。
「500万坪」という箱根・軽井沢の土地も、単なる担保資産ではなく、そこを自らの手で開発することで資産価値はその何倍にも膨らむ。そして定期的な輸送手段を提供して、人が住まえる環境を整えることで、土地だけでなく住宅を建設する需要も生まれてくる。
町を造ることが、開発のもっとも効率的で儲かる事業であるという都市計画の発想に康次郎はある段階で気付いたのである。元台湾民生長官の後藤新平は、後に東京市長時代に現在の東京の主要な幹線道路の原型となる都市計画を自ら発案し、推し進めた。後藤の史料に、康次郎との街づくりに関するやり取りが出てくるものはないが、二人の交流の深さを考えれば、互いのアイディアを交換していたとしても不思議はない。
それは当初、既存の線路に沿って街を造ることから始まった。田舎リゾートの不動産業者が、いきなり鉄道を買収するわけにもいかない。そこで、苦心の末に考え出したのは、線路に沿って駅舎を建て、それを鉄道会社に寄付するという突拍子もない計画だった。
それはかなり早い段階から行っている。衆議院議員に初当選した1924年11月には、大泉学園駅をつくり、武蔵野鉄道に寄付し、同時に駅周辺で土地の分譲を開始した。当初迷惑顔であった鉄道会社も、無料で駅舎を寄付されれば悪い気はしない。多少のトラブルはあったものの、康次郎の宅地開発で利用客も増えれば鉄道経営にとっても決して悪い話ではなかった。ありがた迷惑、しぶしぶ顔で、武蔵野鉄道に新しい駅が誕生し、そしてそこに街が生まれた。
1926年(昭和初年)には国立駅を鉄道省に寄付し、国立大学町として宅地分譲を開始した。汽車が停まり、街ができれば、駅舎の建設費などすぐに回収できてしまう。
そして1931年7月、武蔵野鉄道での経営陣の内紛に乗じて、武蔵野鉄道の大株主となる。次々と腹心を役員に送り込み、東京近郊での開発路線を獲得した。埼玉県飯能市につながる現在の西武池袋線がこれにあたる。
「康次郎の事業活動にとって、大正時代には補助的であった鉄道事業は、この時代になって土地開発事業に次ぐ重要な位置を占めるようになった。ことに昭和十年代になると、武蔵野鉄道が急速に重要性を増大した。武蔵野鉄道の設立の動機は、きわめて地方的な利害に根ざしていた。だが、この地方的な鉄道が、やがら康次郎の経営の傘下に入ってからは、現在の西武鉄道の重要な路線に発展し、ターミナルの池袋は戦後の康次郎の事業展開の拠点のひとつとなった」(『堤康次郎』)
1924年(大正13年)6月14日付の雑誌『東洋経済新報』に掲載された武蔵野鉄道の旅客数推移をみると、関東大震災に見舞われた23年以降に旅客数は目覚しい増加を遂げ、配当率も8・5~9%と高い数字を記録している。
関東大震災で大きな痛手を受けた人々が、新しい居住区を求めて郊外に向かったと推測することもできるが、いずれにしても武蔵野鉄道を買収して間もない康次郎にとっては、この震災が決して災いにはならなかったことは間違いない。
しかし、康次郎が武蔵野鉄道を事実上、買収した1931年以降も一度、経営破綻に直面している。もともと経営不振だった時期に買い取ったことで、引き継いだ負債を抱え込むことになった。加えて電化に伴う設備投資が大きくかさんだ末、社債の償還ができず、1934年9月15日に破産を迎えてしまう。それから38年11月まで武蔵野鉄道は鉄道財団の管理下に置かれ、経営の厳しい監視を受ける。
その厳しさはかなりのものだった。
「強制管理のもとで、一時はいわゆる〝幽霊電車〟の事態が生じた。東京電灯に対する電力料金が不払いとなったため電圧を下げられ、武蔵野鉄道の電車はノロノロ運転を余技なくされた」(『堤康次郎』)という。
ちなみにこの苦境の時期、清二の誕生から7年を経た1934年5月、義明が誕生している。
1939年、再建にめどをつけた康次郎は、新たに多摩湖鉄道と豊島園の買収を敢行する。同時に飯能のハイキングルートを整備し、池袋など都市部からの利用客誘致も進めた。遊戯施設の豊島園を買収したことで、宅地開発とともに肝心な娯楽施設の整備も忘れてはいない。そして翌40年には、池袋駅前に武蔵野デパートを新規開業させる。
05年の堤義明逮捕までの西武グループの原型は、この一九四〇年までに完成していたといえる。
この時期、鉄道インフラを基幹に小売流通、不動産販売、観光開発を進めていたのはもちろん西武グループだけではない。東急、京急、そして関西では阪神、名鉄、南海と日本全土のあらゆる私鉄が同様の事業展開を進めていた。鉄道事業の経営基盤は当然、乗客数の増加である。この鉄道利用者の増加を見込むために、付帯的な拡張事業として駅周辺の開発を進めていくのである。
ただ、西武グループの事業進化の特徴のひとつは、他の私鉄の流れとは逆に展開した点にもあった。鉄道があって街造りに乗り出したのではなく、街造りを行っていた不動産屋が鉄道を吸収したのだった。指摘されることの少ない、コクド・西武においてとりわけ顕著なこの業態進化の〝変性〟は、だが西武グループにとって大きな意味を持つ。
街造りのノウハウにおいて西武グループが一日の長を持つことができたと同時に、昭和期前半から第二次大戦に突入し、そして敗戦の混乱期を経て高度経済成長期に突入していく予測のつかない流れの前で、わがままの利く自社の豊富な事業用地を確保したと同時に、それが資金調達の何物にも代えがたい含み価値として大きく膨張するのだった。
康次郎が、ルソーの格言「土地を見よ、縄を張れ。そこに私有財産が生まれる」を意識していたかは定かではない。しかし、康次郎はまるでそれが自らの本能であるかの如く、土地の獲得に血道をあげた。資金繰りに苦しく、手元に潤沢な事業資金がなくとも土地を手に入れる手法を発見したとき、康次郎はその技術に磨きをかけた。それが、GHQ統治時代の宮家の土地買収で、大きく機能することになる。
今、再び丘陵開発されている磯子駅前の丘に城のごとくそびえる旧東伏見邦英伯爵別邸も辺り一帯の丘陵地とともに1954年に西武グループによって買い取られ、その後横浜プリンスホテルの別館「貴賓館」として利用されてきた。
なお、美空ひばりもまた、若き日の一時期、この貴賓館からすぐそばの場所で両親と暮らしていた。
盧溝橋事件を発端に、1937年に始まった日中戦争は戦況を拡大し、38年には国家総動員法が成立する。製造業は戦時体制が強化され、追いつかない軍事物資の獲得に、政府は軍需工業動員法を強制発動させていた。
私権は国策の名の下に制限され、日本全体は戦後の到来さえ予期しなかった西欧型近代化に突入する前の地均しのような、制度混乱期に突入していた。「揺りかごから墓場まで」を実現する基幹を確保した40年、康次郎は現在に至る確かな路線を確保した。
1941年12月8日、山本五十六率いる日本海軍が真珠湾を攻撃してアメリカ軍との太平洋戦争が勃発する。
この頃、康次郎は国会議員として交通事業調整委員会委員にも名を連ねている。私的事業と公的活動とが康次郎を軸に両輪として見事に一本につながったことになる。そして17年4月の第二十一回総選挙で連続7回目の当選を果たし、国会議員としての立場も揺ぎ無いものとし、東条英機内閣のもとで改めて交通事業調整委員会委員として再任された。
一方、軽井沢や箱根方面の開発を手がけていたコクドの雛形である箱根土地の事業も再び事業を拡大していた。
列島が第一次大戦直後のような軍需景気に再び沸き、景気が上向いていたのが背景にあった。西武グループ公認の正伝『堤康次郎』でも、このあたりの記述にはにわかに勢いを感じさせる。
「日本経済の活況にともない、堤康次郎の箱根土地会社は、昭和八、九年頃から東京の郊外住宅、軽井沢・箱根の別荘とも、ようやく年とともに売れ行きが増加をみるようになった。彼の発想による箱根・軽井沢の自動車道路は建設がすすみ、観光やレクリエーション諸事業は、一九三七、八年頃から軌道にのりはじめた。土地の担保価値の上昇で、この頃から資金の借入が可能となり、長い間、彼を苦しめつづけた極度の金融難は次第に緩和に向かった。興銀・勧銀ばかりでなく、安田信託銀行や三菱信託銀行のような、信託銀行から不動産担保の資金借入も行われるようになった。箱根土地会社は一九三八年からふたたび決算を発表するようになり、一九三九年から収入は急増した」
康次郎の公式の伝記が資金繰りの好転をアピールできるほどに、時代は康次郎にとってようやく追い風となった。そして続けて多少誇張の匂いさえする時代がかった解説が付いているのも象徴的だ。やはり、この1940年前後が西武グループの原型として画期的な時期であったことは間違いない。
「中産階級のための土地開発、文化的な生活環境の創出という康次郎の構想は、この時代になってはじめて、全面的な実現への展望が開けるようになったのである。そのうえ、鉄道業のほうでも成功は確実なものとなった。困難をきわめた武蔵野鉄道の再建も、昭和十二年にはめどがたち、急速な発展が可能となった。それは、東京の西部郊外の宅地開発と結びついて、総合的な開発の経済効果を発揮しはじめるようになった」
そしてその財務状況の好転を裏付けるかのように、かつて「品川あたりのぼろ屋敷」と滋賀の後援者からも酷評された大崎の家を離れ、広尾に3000坪の邸宅を購入する。すでにこの頃の広尾付近は一流財界人がこぞって邸宅を構える高級お屋敷街だった。
そして、大正後期から昭和初期にかけての苦しい黎明期を乗り越えたコクド・西武は一方で、今日に通じる経営の閉鎖傾向を強め始める。
「大正時代においては、康次郎は箱根土地会社を広く資本を調達・集中させるための、開かれた株式会社として設立・運営しようとしたが、昭和初年からは、むしろ閉鎖的な個人企業体として運営するようになった。(中略)株主名簿や決算は非公開となり、綿密な収益性・収支計画は重視されなくなり、配当は彼の関心の外に置かれるようになった」(『堤康次郎』)のだった。
05年、康次郎から事業を継いだ義明が証券取引法違反容疑で東京地検特捜部に逮捕されると、かつての興銀の血を引くみずほホールディングスがその経営を主導することになり、事業の整理・売却が進められ、プリンスホテルも例外とはならなかった。
絹の道の終点であり、始点でもある、磯子にあった横浜プリンスホテルも06年6月、閉館し、売却された。
在りし日の横浜プリンスホテルもまた、山と呼ぶには低いが、穏やかな丘陵地帯の上に建ち、そこからの眺めは偶然だろうか、大塚山公園からの光景とよく似ている。
堤康次郎のかつての事業意欲を垣間見れば、絹の道の両端に西武グループがその土地を押さえていたのがまったくの偶然と信じるほうに無理があろう。
