
神戸市における海中通信への挑戦
今回は、修士2年生の安井さんと学部4年生の高橋さんが、1月末に兵庫県神戸市の海プロジェクトの一環として行った実験について紹介します。
〇実験場所
実験場所は、神戸市の海です。近くには、屋上デッキからも海や景色を楽しめる神戸ポートタワーや、神戸港の歴史や船について学べる神戸海洋博物館、阪神淡路大震災の跡が保存されている神戸港震災メモリアルパークなどがあり、海と共にある街であることを感じさせられる場所です。

〇海中通信が重要なわけ
日本の海洋産業には、いくつかの課題があります。まず、潜水士の不足です。潜水士は水中で設備の点検や修理を行う専門家ですが、日本の広い海で作業するための人手が足りず、作業が遅れたり安全性が低くなったりする問題があります。これを解決するためには、新しい技術を活用して作業の効率を高める必要があります。
次に、水中インフラの老朽化です。海底のパイプラインやケーブルが古くなり、定期的な点検が求められています。そのためには、ROV(遠隔操作型水中ロボット)を使用し、水中通信技術でROVを自動操縦することが効果的です。
しかし、従来の水中通信には課題があります。音を使った通信は遠くまで届きますが、信号が届くのに時間がかかります。一方、光を使った通信は速いですが、方向を合わせるのが難しいです。そこで、低コストで光の向きにあまり依存しない水中光カメラ通信が注目されていますが、通信速度と距離が限られているため、他の通信手段と組み合わせることが必要です。
これらの背景から、水中作業を支援するロボット技術が求められており、光を使ったカメラ通信技術で水中のロボットの位置を正確に把握する方法を検討しています。
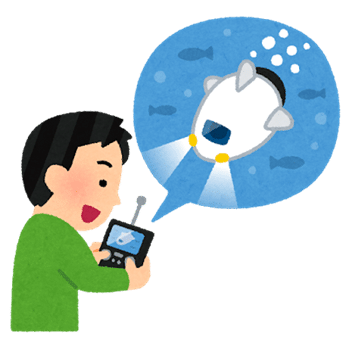
○実験内容
この実験では、水中ドローン、水中用カメラ、そしてLEDユニットを使用します。LEDユニットは、複数のLEDが集まった装置です。



まず、これらを海中に沈め、LEDユニットを操作して光を発します。光は赤、青、緑、白の4色で、さまざまな条件(光の色や強さ、水の深さ、距離など)を変えながら実験を進めます。


その様子を水中ドローンで撮影し、ドローンのセンサーがLEDユニットと水中用カメラの距離や向きを把握します。これにより、LEDユニットが海中のどこにあるかを特定できます。
そして、撮影した画像を使って、LEDの位置を検出するアプリケーションを開発します。このアプリでは、海中の画像データを分析し、LEDユニットと水中用カメラの距離を計測します。
実験の結果、時間や水の深さ、濁り、光の色にかかわらず、LEDの光を検出できることが確認されました。また、動画像を使ってLEDの位置をリアルタイムで特定し、LEDユニットとカメラの間の距離を数センチから十数センチの範囲で正確に推定することができました。これにより、LEDからの光信号を利用して、水中ロボットの位置を推測できるようになりました。

〇実験の感想
今回主体となって実験を行った安井さんにお話を聞いてみました
① 研究のきっかけ
海なし県である埼玉県出身で幼少期から海への憧れがあり、海の可能性を広げられる「水中通信」というテーマに興味をもちました。また、学部生時代に環境問題について学び、海洋マイクロプラスチックなどの海をめぐる環境問題に関心があったため、この研究を選びました。

②水中実験の醍醐味
海によっても、日によっても、時間によっても、LEDの見え方が全く異なり、LEDの強さを変える等の調整が必要になります。そこが実験の難しさであり、面白いところです。また、 海が大好きなので、さまざまな海で実験でき、とても嬉しいです。
③ 今後の展望
現在はLEDとカメラ間の距離を推定するにとどまっていますが、将来的にはカメラに映るLEDの情報を基に、カメラの水中での位置を正確に把握できるようにすることを目指しています。

水中実験に初めて参加した高橋さんにお話を聞いてみました
① 研究のきっかけ
高校時代、吹奏楽部でLEDライトを使ったステージ演出を担当しました。ドラムセットにLEDライトを取り付け、曲調に合わせてライトアップする演出を考える中で、LEDの手軽さや華やかさに触れ、その可能性を実感しました。この経験からLEDライトに興味を持つようになりました。
その後、大学でLEDを用いた光通信の研究などを行っている中山研究室と出会い、さらに水中通信の研究にも取り組んでいることを知りました。以前、海での遭難者の捜索は通信手段がなく困難だという話を聞いたことがあり、水中通信の重要性を感じました。これらの経験から、LEDを使った水中通信の研究に取り組みたいと考えるようになりました。

②水中実験に初めて参加した感想
事前準備から実験に携わることで、これまでイメージできなかった実験全体の流れを理解することができました。実験では防水ケースに入れた照度計を海に沈めるため、事前準備では防水ケースの性能を念入りに確認しました。水槽に何度も水を溜めて条件を変えて実験したり、様々なサイズの防水ケースを試したり、最終的に防水テープを駆使したりして、ようやく満足のいく防水性能を確保することができました。この経験から、水中環境に耐えられる実験設備の準備の重要性や水中実験の特有の難しさを学びました。
実験本番では、準備してきた防水ケースなどの器具が実際に海に沈んでいく様子を見て、達成感と喜びを感じました。

〇神戸市での観光・グルメ
実験場所からは、神戸ポートタワーや港の景色を見ることができ、夜景がとても綺麗で、ライトアップされたモザイク大観覧車も素敵でした。昼間の活気のある雰囲気とは異なり、落ち着いたロマンティックな雰囲気が楽しめます。昼にも夜にも行きたくなりますね。


また、神戸ポートタワーからほど近い南京町には中華街があり、本格的な中華料理と異国情緒を楽しむことができます。
この中華街にある「満園」というお店で中華料理の定番である麻婆豆腐や胡麻団子から大きな魚の煮つけまで様々な料理を楽しむことができました。どれもとても美味しかったので、読者の皆様も神戸に行かれた際には、ぜひ行ってみてください!



帰路に就く前に、神戸阪急でお土産を買い、海鮮丼を食べました。このボリュームで1000円!とてもお得に美味しい海鮮丼を楽しむことができました!

〇最後に
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。海中通信は難しい課題ですが、海をより安全に有効活用するために、私たちは研究を進めています。私たちの挑戦に興味を持っていただけると嬉しいです。神戸にお越しの際には、美しい海の景色をお楽しみください。その際に、海中通信についても思い出していただければ幸いです。

