ジェラニエ
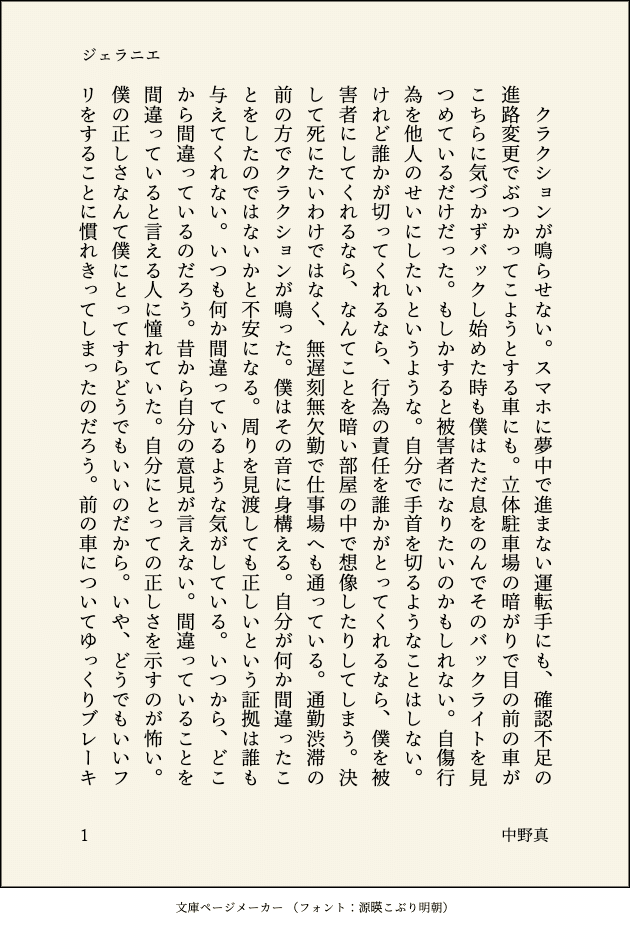




ジェラニエ
クラクションが鳴らせない。スマホに夢中で進まない運転手にも、確認不足の進路変更でぶつかってこようとする車にも。立体駐車場の暗がりで目の前の車がこちらに気づかずバックし始めた時も僕はただ息をのんでそのバックライトを見つめているだけだった。もしかすると被害者になりたいのかもしれない。自傷行為を他人のせいにしたいというような。自分で手首を切るようなことはしない。けれど誰かが切ってくれるなら、行為の責任を誰かがとってくれるなら、僕を被害者にしてくれるなら、なんてことを暗い部屋の中で想像したりしてしまう。決して死にたいわけではなく、無遅刻無欠勤で仕事場へも通っている。通勤渋滞の前の方でクラクションが鳴った。僕はその音に身構える。自分が何か間違ったことをしたのではないかと不安になる。周りを見渡しても正しいという証拠は誰も与えてくれない。いつも何か間違っているような気がしている。いつから、どこから間違っているのだろう。昔から自分の意見が言えない。間違っていることを間違っていると言える人に憧れていた。自分にとっての正しさを示すのが怖い。僕の正しさなんて僕にとってすらどうでもいいのだから。いや、どうでもいいフリをすることに慣れきってしまったのだろう。前の車についてゆっくりブレーキを緩めながら、遠くへ行きたいと思った。けれど遠くとは、いったいどこのことなのだろう。きっと僕は遠くへ行きたいのではなく、ただ目の前の現実から逃げ出したいだけなのだ。何度も繰り返されたありきたりな問答に吐き気を覚えながら、いつか占い好きの友達が言っていた「サターンリターン」という言葉を思い出した。僕はもうすぐ二十九になる。
自分が生まれた時の位置に土星が戻ってくる時期の事をサターンリターンと呼ぶ。占星術で試練や制限、カルマなどを表す土星の公転周期は約二十九年。サターンリターン、つまり二十九歳前後に僕らは人生の壁にぶつかったり転機を迎えたりすることが多いと言われている。僕はそれに希望を抱いているのかもしれない。否応なくこの場所から僕を連れ出してくれる何かを待ち望んでいるのかもしれない。しかしそう考えると、何も起こらないということがむしろ僕にとってのサターンリターンになるのではないか。結局何もできず何もしないまま日々をやり過ごしている僕に何かが起こるなんてことはありえなかった。感染症で街から人が消えいくつもの会社が倒産しても、僕はただ日々が続いていくということを信じそしてそれを恐れていた。なんと恵まれた浅い苦悩なのだろう。ガードレールへ向け思い切りハンドルを切りたい衝動で手が湿るのも、どこか演技のように思え滑稽だった。遠くへ行ったのは僕ではなく僕の周囲の人たちで、取り残された僕はどちらへ向け足を進めればいいのかわからず立ちすくんでいるだけであった。
遠くへ行ってしまった人たち。僕が一番に思い浮かべたのは元地下アイドルの女の子のことだった。僕は彼女たちの正しさを証明したかった。あの瞬間の意味を失いたくなかった。彼女たちから僕が受け取ったものを、ただ消費したくなかったのだ。だから僕は夢を語った。あの日、解散ライブの日の東京では三月末に珍しく雪が降っていた。どうしてこんな日に、とも思ったがこんな日だからこそ雪の舞う都会の空は虚構のように幻想的で、でもその寒さは現実的だった。そんな狭間で混乱した僕の手を握り彼女は涙ぐんだまま力強く笑った。
「前もらった手紙の話、約束だからね」
「うん、授賞式で、君のおかげだっていう」
「小説頑張ってね、君はまっすぐだから、大丈夫だよ」
ラストライブ前の彼女を応援する言葉を用意していた僕は、最後の握手会でも彼女に応援されてしまった。その頃の僕の言葉を読んでくれたのは、それを好きだと言ってくれたのは、ライブの度に手紙を渡していた彼女だけであった。そして彼女はいつも僕が欲しい言葉をくれる天才だった。五分押しで開場したライブは終始涙のフィルター越しに終わりへと向かっていった。やはり彼女たちの笑顔は最強だった。そしてひとりずつ最後の挨拶をし、みんなで泣き崩れて笑った。ライブハウスの明かりが灯り、名残惜しむオタクたちは最後のお見送りをしてくれる出口へ向かうしかなかった。一瞬一瞬が常に消費されていくアイドルという物語が花火の残像のように僕の胸の内に染みついていた。本気を人前で晒し続けた彼女たちの輝きの意味を僕は掬い取りたかった。ここを去れば僕はもう二度とあの子に会えないだろう。けれど小説を書き続ける限り僕たちの約束は過去にはならない。涙で顔をぐちゃぐちゃにした彼女の前で僕はそう思った。手を握り、さよならは言わなかった。しゃくりあげる彼女に対して僕にできることはいつだって何もなかった。だからただ小説を書こうと思った。列が進み隣の子に移った僕に彼女が「絶対小説家になってね」と叫んだ。最後の最後まで彼女は僕を応援してくれたのだった。
そして僕は何をしているのだろう。サターンリターンなどに甘え何を待っているのか。あの瞬間をあの約束をその場限りの虚構にしたくなかったのではないのか。中途半端に生き延びて何になるというのだろう。クラクションに驚いた肩が跳ね上がる。いつの間にか前の車との間隔が離れていた。慌ててアクセルを踏む。灰皿に捨てようとした煙草が指先からこぼれ落ちた。虚構のように、反対車線からトラックがはみ出してきた。タキサイキア現象?映画を見ているように緩やかな接近にそう思ったのはどれほどの時間なのか、そんな思考はすぐさま消し飛び現実の恐怖が体を硬直させる。死にたくない。死にたくない。死にたくない。僕は強くクラクションを鳴らした。
