
よくある勘違いシリーズ④弓は止まる?
指弓といわれるテクニックがあります。
コーレとも混ぜて教わる人も多いと思います。
また、大多数の人はこうやって(運弓と指の動きを観察させながら)弾くと音が切れないんだ、と教わると思います。
言葉というのは大変に気を遣うものですが、どうやったところで誤解は生じてしまいます。見た目の情報に囚われて、イメージだけで理解したつもりになりがちです。
音という物理の話を、最初からイメージでものにしようと考えない方が安全です。
まず、弓には必ず弓先の端と、弓元の端があります。
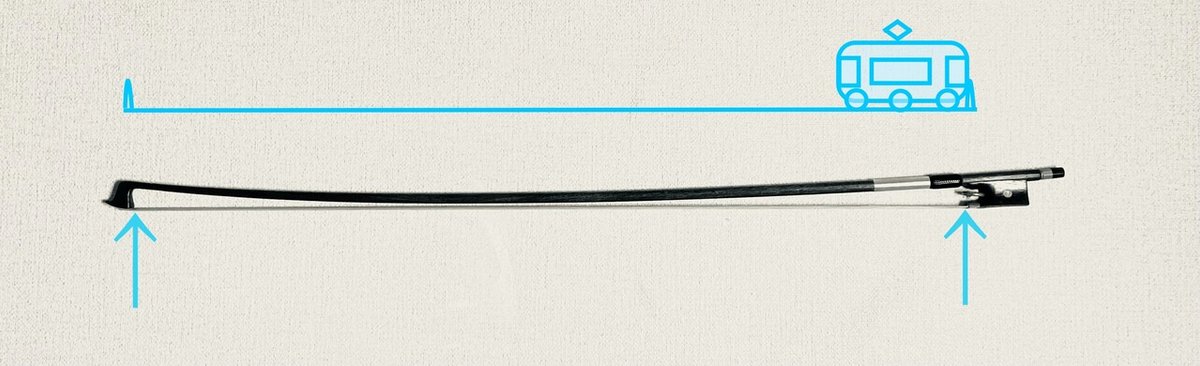
直線の短い線路を往復する電車を想像してください。
つまり、ダウンとアップの間には、必ず折り返しがあります。
よく見かける勘違いはココからです。
指の動きで弓を蛇行させて、弓の返しを(折り返しではなく)急カーブにする発想。これは直線の短い線路ではありませんね。
弓を止めなければ音はつながる。
しかし、これは弓の軌道が乱れるだけでなく、腕の重みの変化や弓の重心の変化を乱し、音のムラを作ります。
これは間違った指弓。
折り返しのときに、弓は必ず一瞬止まります。
レガートや長い音価の中にある折り返しは、無駄な力なくスッと止まり、次の発音までの準備に必要な時間、を刹那にする、ということです。
だからこそ、指弓なしで音を繋げられる奏法もあります。言葉を慎重に選べば、響きを繋げていく、でしょうか。
ヴァイオリンは小柄なので、このあたりを曖昧にできてしまいますが、コントラバスやチェロはまさに、「弓の毛で弦をはじき、響きをつなげる」ことが必須です。よーく観てみましょう。
では、いわゆる指弓って、なんのための動きなのか?
それは次回!
追伸
細かいことは こちらの記事に記載しています。
-------------------------------------------------------------
