
『香りの記憶』─データでは測れない、私たちの物語─
1.プロローグ
『収穫の向こう側』
夜明け前の農園は、思いがけない音に満ちている。
川島さくらは、露が滴る茄子の葉に触れながら、その気づきを噛みしめていた。東京での十年間、彼女の朝は常にスマートフォンのアラームから始まった。けれど今、この神渡町の霧深い明け方には、誰かが設定したわけでもない音が次々と響いてくる。
裏山から吹き降ろす風。竹林のざわめき。古びた納屋の軒先で鳴く雨蛙。用水路を流れる水の音。
「予定は、あってないようなものね」
手帳を開きながら、さくらは小さくため息をつく。びっしりと書き込まれた作業計画の横に、祖母の農業日誌が置かれていた。全ての予定を管理下に置きたいさくらと、天候と自然を受け入れながら生きた祖母。その違いが、日誌の余白に記された「天気次第」という言葉に象徴されているように思えた。
父が倒れてから三ヶ月。かつての企画職での経験を農園経営に活かそうとするたび、さくらは現実の前に立ち尽くす。データと マニュアルでは掬いきれない何かが、この土地にはある。
母屋の窓に灯りが点る。病床の父が目を覚ました合図だ。さくらは露をはらう茄子の葉を、もう一度そっと撫でる。葉の裏には、まだ見ぬ実りが眠っている。
「おはようございます」
祖母の日誌を手に取り、ページを繰る。六月の記録に目が留まった。
『今年も田植えの季節。手伝いの若い衆の笑い声が、土手の向こうまで響く』
さくらは思わず空いた手で耳に触れる。今の農園に、そんな賑やかな声は聞こえない。人手不足は深刻だった。
遠くで、モーニングチャイムが鳴り始める。さくらは祖母の日誌を胸に抱きながら、朝もやの向こうに広がる田園風景を見つめた。今日から、技能実習生を受け入れる。不安と期待が入り混じる中、東の空が少しずつ白んでいく。新しい一日の始まりを告げるように、水田に朝露が光を散らし始めていた。
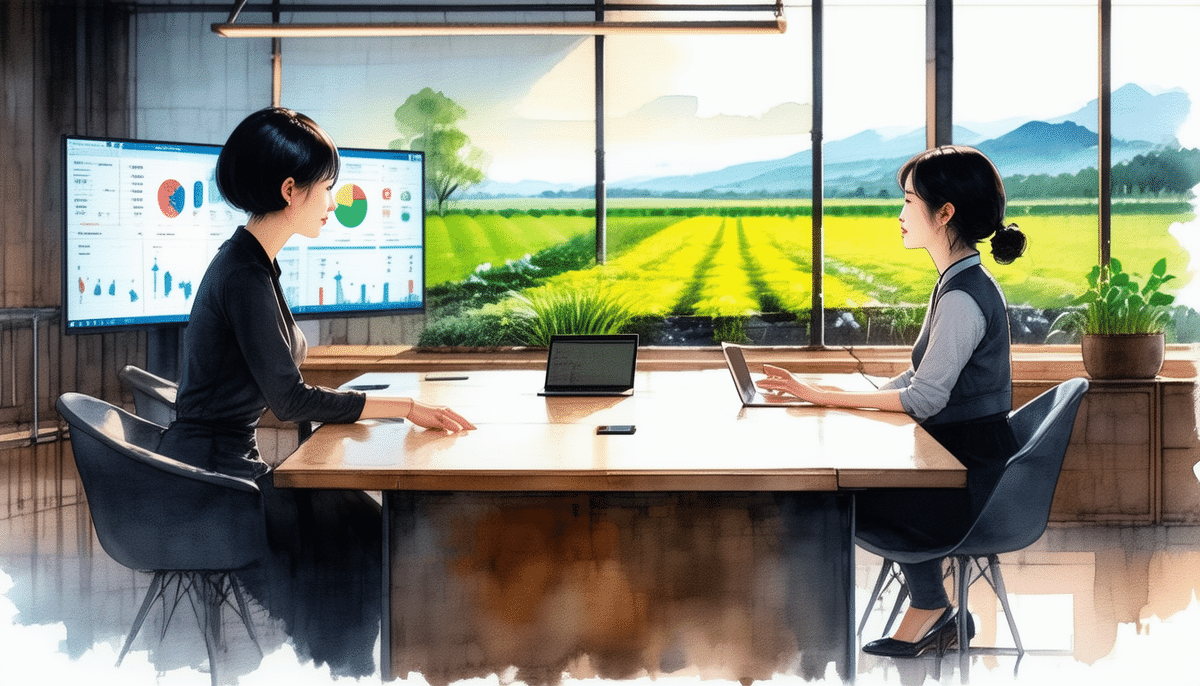
2.ハー到着シーン
光り輝く水田の向こうから、一台の軽トラックが近づいてきた。荷台には大きなキャリーケースが揺られている。運転席には農協の担当者、そして助手席に小柄な女性の姿があった。
さくらは思わず背筋を伸ばした。用意した挨拶の日本語を、もう一度頭の中で確認する。
「おはようございます。グエン・トゥ・ハーさん、ようこそ神渡町へ」
軽トラックが停まり、女性が降り立つ。予想以上に凛とした佇まいに、さくらは一瞬、言葉を詰まらせた。
「はじめまして。川島さくらです」
「はい、よろしくお願いします」
ハーの日本語は、資料で見ていた「日本語レベルN4」という評価からは想像できないほど、明瞭だった。だが次の瞬間、思いがけない質問が投げかけられる。
「スマートアグリの設備は、どこにありますか?」
さくらは言葉に詰まった。確かに申請書類には「IoTセンサーによる環境モニタリング」と書いてあったが、実際に導入できていたのは温度計と湿度計程度。それも古い納屋の隅に放置されたままだった。
「あの、それはまだ...準備中で」
ハーの表情が微かに曇る。彼女の母国の大学では農業IoTを専攻していたはずだ。さくらは慌てて話題を変えた。
「まずは、宿舎をご案内します」
古い倉庫をリノベーションした簡易宿舎へ案内する道すがら、さくらは完璧に準備したはずの計画が、すでに綻びはじめていることを感じていた。
「川島さん、この畑は...」
ハーが立ち止まり、雑草の目立つ一画を指差す。
「ここは今季の計画には...」
「ミントの香りがします。レモングラス、も」
さくらには気付かなかった香りを、ハーは確かな様子で言い当てる。祖母の代に栽培していた香草園の名残りだった。
「実は、これから整地して...」
「もったいないです。立派な薬草、たくさん」
ハーの目が輝きを増す。さくらの完璧な就農計画には、この雑草混じりの一画を活用する案は入っていなかった。
蒸し暑い六月の空気が、二人の間に淀んでいく。軒下では風鈴が、やや騒々しく鳴っていた。
「では、作業の計画について...」
さくらが取り出した完璧なスケジュール表に、ハーは申し訳なさそうな表情を浮かべる。
「すみません。漢字が、まだ、よく...」
二人の間に、言葉以上の距離を感じる午後の陽射しが降り注いでいた。

3.最初の農作業
朝の水やりは、さくらの計画では三十分で終わるはずだった。
「ハーさん、この列はもう十分です」
茄子の苗が整然と並ぶ畝の間で、ハーは丁寧に一株一株の土の湿り気を確かめている。時折、葉の裏まで指先で触れ、何かを観察するような仕草に、さくらは焦りを感じていた。
「あの、次の作業が」
スマートフォンの画面に表示された作業予定表を見せようとする。だが、ハーは土の感触を確かめることに集中していた。
「この子、渇いています」
ハーが指差した茄子の苗は、確かに他より元気がない。だが、土壌水分計の数値は基準値内を示している。
「でも、データでは」
「データより、葉が教えてくれます」
ハーの言葉に、さくらは反論できなかった。確かに、茄子の葉は僅かに萎れ、いつもと違う角度で垂れ下がっている。スマートフォンの画面からは決して読み取れない、その違いに気付けなかった自分に、歯痒さを覚える。
真夏を思わせる日差しが照りつける中、二人は剪定作業に移った。さくらは農業普及所から入手したマニュアルを片手に、規定の長さで茄子の枝を切っていく。
「ここまでです」
ところがハーは、また違う判断を示す。
「この枝、まだ実をつけます」
「でも、標準的な剪定方法では」
「ベトナムでは...」ハーは言葉を探りながら続ける。「植物の気持ち、聞きます」
突如として、祖母の農業日誌に記された言葉が蘇った。
『作物は語りかけてくる。その声を聴ける農家だけが、本当の収穫を得られる』
額の汗を拭いながら、さくらは自分の剪定バサミを見つめる。完璧な計画、正確なデータ、標準的な手順。それらが、必ずしも最善の答えではないのかもしれない。その認識が、どこか不安を掻き立てる。
「川島さん、見てください」
ハーが指差す先には、剪定を免れた枝が、確かに新芽を付けはじめていた。データでは予測できなかった生命力が、そこにはある。
「私、まだまだ、ですね」
自嘲気味に呟くさくらに、ハーは静かに首を横に振った。
「違います。川島さんの畑、とても...なんて言うか...」また言葉を探る仕草。「心、込めています」
その言葉に、さくらは複雑な感情を覚えた。完璧を求めすぎる自分と、植物の声を聴こうとするハー。相反するようで、どこかで通じ合う二つの想い。
遠くで、昼のチャイムが鳴り始めた。茄子畑に立つ二人の影が、真夏の日差しの中で重なり、また離れる。まだ見ぬ実りへの期待と不安が、蒸し暑い空気の中でゆっくりと熟成されていくようだった。

4.夕暮れの振り返り
夕暮れ時の病室は、オレンジ色の光に満ちていた。
「お父さん、今日の様子です」
さくらは農作業の記録をまとめたノートを、父の枕元に置く。几帳面な字で書かれた作業内容と時間、データの羅列。けれど、今日一日を本当に伝えられているのか、という思いが胸をよぎる。
父は黙ってページを繰る。痩せた指先が、さくらの文字の上をなぞっていく。
「ハーさんが言うには」言葉が途切れる。「私の基準は、少し違うみたいで」
窓の外では、夕陽に染まった水田が、鏡のように空を映していた。作業小屋から戻るハーの姿が、その景色の中に小さく見える。
「へえ」
父の声は、意外なほど穏やかだった。
「お父さんの時は、どうだったの?データとか、基準とか」
「ん?」父はゆっくりと目を閉じ、「そうだなあ」と言葉を引き延ばす。「私も最初は、必死に数字を追いかけたよ」
「え?」
「でも、おまえの祖母にいつも言われたんだ。『正人、作物はな、心で育てるもんだよ』ってね」
さくらは思わず、自分のスマートフォンを見つめた。画面には明日の作業予定が、几帳面に並んでいる。
「私、間違ってるのかな」
「間違いも正解もないんだと思うよ」父の声が、少し強くなる。「ただ、土地にも作物にも、それぞれの声があってね」
病室の窓に、夕焼け雲が映り込む。さくらは、今朝のハーの言葉を思い出していた。
『植物の気持ち、聞きます』
「でも、私にはまだ...」
「時間がかかっていいんだよ」
父の言葉に、さくらは何も返せなかった。夕暮れの光の中で、納屋の窓に明かりが灯る。ハーが、今日の発見を日記にでも書いているのだろうか。
さくらは自分のノートを開き、数字の間に、小さな余白を作ってみた。明日は、もう少し違う声が聞こえるかもしれない。そんな期待が、夕暮れの空のように、静かに広がっていった。

5.病害虫発生
蒸し暑い朝もやの中、さくらは茄子畑で立ち尽くしていた。
葉の裏側に、見慣れない斑点。スマートフォンで撮影した画像を、病害虫データベースと照合する。けれど、決定的な回答は得られない。
「困ったことが、起きましたか?」
背後からハーの声がする。昨夜の遅くまで、納屋の明かりが消えなかったことを、さくらは覚えていた。
「この症状、どう思いますか?」
ハーは黙って茄子の葉に触れ、指でなぞるように確かめる。その仕草は、まるで患部を診る医者のようだった。
「これは...」ハーが言葉を探す。「私の村でも、よくありました」
さくらは思わず身を乗り出す。
「害虫、でも農薬だけでは」ハーは首を振る。「自然の味方、必要です」
「自然の、味方?」
ハーは納屋に向かい、昨夜書いていたノートを取りに行く。殴り書きのような図と、日本語とベトナム語が混ざった説明。その中に、見覚えのある植物の絵があった。
「これ、マリーゴールド?」
「はい。虫を寄せつけません。それに...」
ハーが言葉に詰まった時、さくらは祖母の農業日誌を思い出していた。
「待ってください」
母屋に駆け込み、日誌を探し出す。六月の記録に、確かにあった。
『マリーゴールドを植えた茄子は虫が付きにくい。先人の知恵を忘れずに』
「祖母も、同じことを...」
さくらの言葉に、ハーの目が輝く。
「でも、間に合うかしら」
さくらは不安げに茄子の葉を見上げる。病害虫のデータベースは即効性のある農薬の使用を推奨していた。
「私の村では」ハーが静かに言う。「唐辛子の水で、応急処置します」
規定外の対応に、さくらは迷いを覚える。けれど、昨日の父との会話が蘇る。
『土地にも作物にも、それぞれの声があってね』
「やってみましょう」
その言葉は、自分の口から出たとは思えないほど、すんなりと出てきた。
二人で唐辛子の粉を溶いた水を作り、丁寧に葉に散布していく。作業の合間、ハーは時折、茄子の葉に何かを囁きかけるように話しかける。
「なんて言ってるんですか?」
「ベトナムの、おまじないです」ハーが少し照れたように笑う。「強く育って、という願い」
夕方になって、さくらは不思議な光景を目にした。茄子の葉に、小さな天道虫が止まっている。ハーの言う「自然の味方」が、既に動き始めていた。
「川島さん」ハーが空を見上げる。「明日は、マリーゴールド、植えましょう」
その言葉に、さくらは小さく頷いた。データでは測れない何かが、確かにここにはある。それを感じ取れるようになった自分に、小さな誇らしさを覚えていた。
むし暑い空気の中、二人の影が夕陽に伸びる。茄子畑に、新しい希望の芽が吹き始めていた。

6.伝統と革新の狭間
梅雨の晴れ間、神渡町の公民館に、重苦しい空気が漂っていた。
「川島さん、そういうわけにはいかんよ」
区長の山本が、ゆっくりと首を振る。扇風機の風が、資料の端をめくっていく。
さくらが提案したのは、ハーが母国で学んだという新しい水管理システムだった。IoTセンサーで水量を監視し、必要最小限の取水で効率的な農業を実現する——そんな計画に、古老たちの表情が曇る。
「うちらの水路は、江戸時代からの知恵の結晶じゃ」
最年長の中島が、分厚い老眼鏡を上げながら言う。
「でも、このままでは」さくらは必死に言葉を紡ぐ。「水の無駄遣いです。気候変動で、これからはもっと——」
「無駄だと?」中島の声が強まる。「お嬢さん、この土地で七十年農業をしてきた私に、それが言えるかね」
さくらは資料の数値を指さす。
「データで明らかです。現在の水路システムでは、三割以上の水が——」
「データか」今度は山本が口を挟む。「じゃあ聞くが、今年の台風シーズンはいつ頃になると思う?」
「それは、気象庁の予報では」
「違う」山本は天井を見上げる。「この土地の空を読め。雲の流れを見ろ。風の匂いを感じろ」
茶菓子が置かれた机に、誰も手を伸ばさない。
「ベトナムでは」
突然、後ろで聞いていたハーが話し始める。全員の視線が集まる。
「伝統の知恵、とても大切です。でも」少し言葉を探って続ける。「新しい方法と、一緒に使えば、もっといいかも、しれません」
「ハーさん...」さくらは思わず振り返る。
「私の村では、古い水路と新しい技術、両方使います。お互いの、良いところ」
中島が眉をひそめる。
「外国の真似をして、どうなるものか」
その言葉に、さくらの中で何かが反発する。
「でも、このままじゃ」
声が震えているのを感じる。窓の外では、早くも夏を思わせる陽射しが照りつけていた。
「お父様なら」山本が静かに言う。「もう少し地域のことを考えて——」
「父は」さくらは言葉を切る。喉の奥が熱くなる。
その時、ハーが一歩前に出た。
「見に来てください」
「何を?」
「私たちの畑を」ハーがゆっくりと説明を続ける。「マリーゴールドと茄子、一緒に育てています。古い知恵と、新しい考え、両方あります」
中島と山本が顔を見合わせる。先日の病害虫対策の成功は、既に地域の話題になっていた。
「まあ」中島が老眼鏡を外す。「見るだけなら、構わんがの」
さくらは思わず、ハーに視線を送る。小さな、けれど確かな一歩。
帰り道、夕立の気配が空を覆っていた。
「ありがとう」さくらは呟く。「でも、私の言い方は強すぎたかも」
ハーは首を振る。
「川島さんの想い、伝わっています」
「伝わってない気がする」
「時間が必要です」ハーが空を見上げる。「種が芽を出すまで、待つように」
遠くで雷が鳴る。さくらは父の言葉を思い出していた。
『土地にも作物にも、それぞれの声があってね』
そして今、地域の人々の声も、確かに聞こえ始めていた。
「明日から」さくらは決意を込めて言う。「もう少しゆっくり、進んでいこう」
ハーが小さく頷く。二人の影に、パラパラと夕立の雫が落ち始めていた。変わることの難しさと、守ることの大切さ。その狭間で、新しい道を探す季節が始まろうとしていた。

7.意外な発見
梅雨の晴れ間、早朝の光が畑を照らしていた。
「川島さん、見てください」
ハーの声に振り返ると、彼女は香草園の跡地で膝をついていた。雑草と見分けがつかない草花の間で、何かを摘んでいる。
「これ、レモンバーム」
手のひらに乗せられた葉を、そっと摘む。
「あ」
爽やかな香りが、朝もやの中に広がった。
「祖母が育てていた...」
記憶が蘇る。子供の頃、祖母と一緒にハーブティーを飲んだ風景。データや効率に囚われる前の、懐かしい時間。
「他にも」ハーが畑を指差す。「ローズマリー、タイム、もっとあります」
さくらは思わずスマートフォンを取り出しかけて、でも、そっとポケットに戻した。
「教えてください」
ハーが驚いたように顔を上げる。これまでのさくらなら、まずネットで調べていたはずだ。
「嬉しいです」ハーの笑顔が、朝日に輝く。「一緒に探しましょう」
二人で雑草の中を歩く。ハーは時々立ち止まっては、葉を摘み、香りを確かめ、さくらに手渡す。
「これは...パクチー?」
「そうです!」ハーの目が輝く。「ベトナムの料理に、とても大切」
茄子畑の隅で、思わぬ宝物が次々と見つかる。祖母の残した種が、時を越えて芽吹いていたのだ。
「あの、ハーさん」
さくらは少し照れくさそうに言う。
「この香草たち、どう活かせると思いますか?」
「素敵なアイデアがあります」
ハーは立ち上がり、納屋に向かう。昨夜も遅くまで明かりが点いていた理由が、今わかった。
戻ってきたハーが広げたノートには、香草を使ったレシピや加工品のアイデアが、イラスト付きで書き込まれていた。
「これ、全部ハーさんが?」
「はい。私の村の知恵と、日本の...なんて言うか...」
「商品開発?」
「そう!」ハーが嬉しそうに頷く。「二つの国の、良いところ」
さくらは思わず笑みがこぼれた。完璧な計画を立てることに必死で、目の前の可能性に気付かなかった。けれど今、雑草だと思っていた場所から、新しい未来が芽吹こうとしている。
「明日から、一緒に実験しませんか?」
さくらの言葉に、ハーが柔らかく微笑む。
「楽しみです」
朝露に濡れた香草園で、二人の影が重なる。遠くでセミの声が響き始めた。梅雨の晴れ間に、小さな希望が、ハーブの香りと共に広がっていった。

8.祭りの準備
夕暮れ時の公民館に、懐かしい香りが漂っていた。
「これが、お嬢さんとハーさんの...」
中島が差し出されたハーブティーを、おずおずと手に取る。
「あら」
一口飲んで、老人の表情が柔らかくなる。
「祖母の香草園の、再生なんです」
さくらは緊張気味に説明する。
「神渡の夏祭りで、試飲会をさせていただけないでしょうか」
山本区長が、ゆっくりとカップを置く。
「伝統ある祭りだがね...」
その時、ハーが前に出る。
「私の村でも、お祭りがあります」
少し言葉を探りながら、続ける。
「みんなで作ったもの、分け合います。心が、つながります」
中島と山本が顔を見合わせる。先日の香草園見学以来、二人の態度は微妙に変化していた。
「まあ」中島が老眼鏡を外す。「うちの婆さんも、昔はよくハーブティーを飲んでおったな」
「本当ですか?」
「ああ。夏の暑い日には、これを飲むと体が楽になるって」
老人の目が、遠い日を見つめる。
「最近の若い衆は、ペットボトルのお茶ばかりでな」
さくらは思わず、ハーに視線を送る。小さな、けれど確かな変化。
「ところで」山本が空を見上げる。「祭りの天気は大丈夫かな」
「気象データでは」さくらが言いかけて、止まる。
そして、外の空を見る。
「雲の流れを見ると...」
「ほう」中島が身を乗り出す。「どうだね?」
「西風が...」さくらは言葉を探る。「強くなってきてます。でも、湿気は...」
「まだまだじゃな」中島が笑う。「でも、なかなか良い見方をするようになった」
準備の日々は、あっという間に過ぎていった。ハーは母国から取り寄せたハーブの種を、さくらは祖母の農業日誌を。二つの知恵を組み合わせて、新しいブレンドが生まれていく。
「これは」ハーが香りを確かめる。「神渡の、夏の香り」
さくらには、その言葉の意味がよくわかった。畑の土、朝もや、夕立の後の空気。すべてが、この一杯のお茶に溶け込んでいる。
「ねえ、ハーさん」
さくらは空を見上げる。
「これが成功したら、次は...」
「カフェ、ですか?」
ハーが目を輝かせる。
「私も、考えていました」
二人の夢が、少しずつ形を帯びていく。
祭り前日、公民館に集まった村人たちは、試作品のお茶を一口ずつ味わった。
「懐かしい」
「でも、新しい」
「これは、面白いね」
さくらは、村人たちの表情を見つめる。データでは測れない何か。心が通じ合う瞬間。
「明日は」山本が言う。「きっと晴れるよ」
夕暮れの空に、お茶の香りが漂う。伝統と革新が、ゆっくりと溶け合っていくような、そんな予感が、蒸し暑い空気の中に広がっていった。
「明日が」ハーが静かに言う。「楽しみです」
さくらは無言で頷く。胸の中で、不安と期待が、お茶の渦のように混ざり合っていた。

9.予期せぬ成功
夏祭りの朝は、どんよりとした空で始まった。
「川島さん」
テントの設営を手伝いながら、ハーが空を見上げる。
「大丈夫です」
「え?」
「雲の動き、早いです」
確かに西風が強まり、雲の切れ間から青空が覗き始めていた。さくらは思わず、スマートフォンの天気予報を確認しようとして、手を止めた。
「ハーさんの読みを、信じてみます」
予想は的中した。昼過ぎには、夏の日差しが祭り会場を照らしていた。
「あ、これすっごくインスタ映えする!」
若い女性が、ハーブティーのグラデーションを撮影している。
「地元のハーブなんですって。こだわりの農園カフェとかできたら、絶対人気出るよね」
さくらは複雑な思いで、その会話を聞いていた。確かに予想以上の反響だが、これは自分たちの目指していたものなのだろうか。
「川島さん」
ハーが、いつもの穏やかな表情で近づいてくる。
「見てください」
視線の先には、中島さんが孫娘とハーブティーを楽しむ姿があった。
「このお茶ね」老人が孫に語りかける。「おばあちゃんが作ってくれたの、そっくりなんよ」
「へえ、でもなんかおしゃれ!」
スマートフォンを構える孫に、中島さんが優しく微笑む。
「懐かしさと」ハーが言葉を探る。「新しさ。両方、大切です」
その時、山本区長が声をかけてきた。
「お二人、ちょっといいかな」
区長が指差す先には、観光協会の役員たちが集まっていた。
「この企画、面白いね」
役員の一人が言う。
「神渡の新しい名物になるかもしれない」
「でも」さくらが躊躇う。「急な観光化は、地域に影響も...」
「そうそう」
中島さんが、いつの間にか加わっていた。
「でもな、変化を恐れてばかりじゃ、先はない」
「私たちの村も」ハーが静かに話し始める。「少しずつ、変わりました。でも、大切なものは、守れました」
さくらは、祭りの喧騒を見渡す。若者たちの新鮮な反応。年配の方々の懐かしむ様子。そして、その間を優しくつなぐハーブの香り。
「カフェを作るなら」
区長が言う。
「古い蔵を改装してはどうかな」
「蔵を?」
「使ってない蔵が、いくつかあるだろう。伝統的な建物を活かしながら、新しい試みを」
その言葉に、さくらの中で何かが繋がった。データや効率だけでは見えなかった、もう一つの可能性。
「ハーさん」
さくらは思わず声を上げる。
「私たち、できるかもしれません」
ハーが静かに頷く。二人の間には、もう言葉の壁はなかった。
夕暮れ時、祭りの余韻が会場に漂っていた。
「明日から」ハーが言う。「また新しい、始まりですね」
さくらは空を見上げる。夏の雲が、茜色に染まっていく。
「はい。でも今度は」
少し間を置いて、続けた。
「みんなと一緒に、ゆっくりと」
祭りの喧騒が遠ざかっていく中、二人の前には新しい夢が、夕焼け雲のようにゆっくりと広がっていった。

10.平穏の中の予兆
蔵の中は、古い木の香りが漂っていた。
「ここなら」さくらは図面を広げる。「カフェスペースと、ハーブの加工場を...」
ハーが黙って壁に触れる。長年の時を刻んだ木肌が、何かを語りかけるように。
「川島さん」
その声には、いつもと違う響きがあった。
「空、変でしょうか」
縁側に腰を下ろし、二人で空を見上げる。八月の陽射しは強いのに、妙に重たい雲が、低く垂れ込めていた。
「台風の進路予想では」
スマートフォンを取り出しかけて、さくらは息を呑む。画面に映る渦は、予想以上に発達していた。
「私の村で」ハーがぽつりと言う。「大雨の前は、こんな空でした」
さくらは、父の見舞いの帰り道を思い出していた。病室の窓から父が、ずっと空を見つめていたこと。
「お父様」ハーが静かに言う。「心配、してますね」
「え?」
「表情が、違います」
さくらは驚く。確かに父は、天気の話題を口にすることが増えていた。
蔵の軒先で、風鈴が微かに揺れる。例年なら、セミの声で賑わう時期なのに。
「ねえ、ハーさん」
さくらは、言葉を選びながら。
「何か、感じますか?」
以前の自分なら、データや予報だけを信じていただろう。でも今は、空気の変化や、生き物たちの様子にも、目が向くようになっていた。
「懐かしい匂い」
ハーが目を閉じる。
「でも、怖い匂い」
遠くで雷が鳴り、二人は思わず顔を見合わせる。
「資材は」さくらが立ち上がる。「早めに片付けておいたほうが」
「はい。それと...」
ハーが言いかけて、言葉を飲み込む。
「何かあります?」
「茄子畑の、支柱も」
さくらには分かった。台風対策の話を、まだ躊躇っているのだと。
「明日から始めましょう」
さくらが言う。
「地域の方々にも、手伝ってもらえるかも」
ハーが小さく頷く。祭り以来、村人たちの態度は確実に変わっていた。
「あの」
軽トラックに資材を積み込みながら、ハーが言う。
「川島さんのお父様に、会いに行きませんか」
「え?」
「何か、伝えたいこと、ありそうです」
さくらは、また雷鳴を聞いた。父は気象予報士ではないが、長年の経験から、天候の変化を肌で感じ取ってきた。その知恵を、今の自分は少しは理解できるだろうか。
「そうですね」
さくらは空を見上げる。
「行ってみましょう」
蔵を後にする二人の背後で、風鈴が不吉な音を立てた。夏の陽射しは依然として強いのに、どこか肌寒い風が吹き始めていた。
軽トラックが土埃を巻き上げて走り出す。このところの日照りで、土が カラカラに乾ききっている。
「でも」
ハーがつぶやく。
「すぐに、変わります」
その言葉の意味を、さくらは考え込んでいた。平穏な日々の中に、確実に忍び寄る何かを、二人は感じ始めていた。

11.台風接近
病室の窓から見える空は、不穏な色を帯びていた。
「風向きが、変わってきたな」
父の声には、いつもの穏やかさがない。
「気象庁の予報では」さくらが携帯を見せる。「まだ明日の深夜...」
「データじゃ分からんこともある」
父がゆっくりと身を起こす。
「この匂い。台風が加速している」
ハーが黙って頷く。さくらには分かっていた。二人とも、何かを感じ取っているのだと。
「さくら」
父の声が、突然強くなる。
「畑の様子は?」
「茄子の支柱は補強して、香草園にも...」
「水路は?」
その言葉に、さくらは息を呑む。先日の会議で決まった新しい水管理システム。まだ完全には整備が終わっていない。
「私」ハーが一歩前に出る。「ベトナムで、大雨の経験が...」
父は静かに頷く。
「さくら、この子の言うことを」
その時、病室の窓が大きく揺れた。予報より遥かに早い、暴風の始まり。
「行きましょう」
さくらは立ち上がる。父の表情に、かつて見た不安が浮かんでいる。あの時の台風で、集落は大きな被害を...
「気をつけて」
父の声が、風にかき消されそうになる。
帰り道、雨は横殴りになっていた。
「ハーさん、水路の様子を見に行きます」
「私は」ハーが軽トラックから降りる。「茄子畑を」
さくらは迷う。分かれて行動するのは危険だ。でも...
「大丈夫です」
ハーの声が、風を切り裂く。
「信じてください」
さくらは小さく頷く。祭りの成功以来、お互いを信頼する気持ちが、確実に育っていた。
水路に着くと、既に山本区長が待っていた。
「やっぱり来たか」
古い水路と新しいシステムの接続部が、激しい水流で軋んでいる。このまま決壊すれば...
「センサーの数値が」
さくらはスマートフォンを見る。でも、画面は雨で滲んで読めない。
「データなんか」区長が叫ぶ。「見なくていい。目の前を見ろ!」
その時、さくらの中で何かが覚醒する。父から教わった知恵、ハーの直感、そして自分の判断力。すべてが、一つに繋がった瞬間。
「上流の水門を」
さくらが叫ぶ。
「半分だけ開けます!」
「何?」
「古い水路に、少しずつ流れを」
さくらは必死に説明する。
「新しいシステムだけじゃなく、両方を使えば」
区長の目が輝く。
「なるほど。伝統と革新の、いいとこ取りってわけか」
二人で水門を調整する間も、雨足は強まっていく。さくらの胸に、茄子畑が閣過る。
その時、携帯が鳴った。
「川島さん!」
ハーの声が、風雨に混じって届く。
「香草園が...」
さくらは立ち尽くす。水路か、畑か。守るべきものの選択を迫られる瞬間。
「行け」
区長が声を張り上げる。
「ここは俺がなんとかする」
ここから先は
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
