
小児がんと卵巣がんの意外な共通点、研究留学で明らかに
医学の進歩で驚くほど予後が良くなった小児がんがあります。腎臓にでき、日本では年間100人が発症する「ウィルムス腫瘍」です。
「9割が治るがんってなかなかないと思います。」
このがんについて研究する宇野枢さん(医学系研究科 博士課程)は、発見が難しいにも関わらず、見つかってから治療しても予後が良いと話します。

それでも研究するのは、1割の患者さんは治療がうまくいかないから。治療がうまくいくケースといかないケースは何が違うのか、がん細胞を根気強く観察した結果見えてきたのは…?宇野さんに聞きました。
↓インタビューのダイジェストをポッドキャストでお届けしています♪
── 患者さんの体質の違いではなく、がん細胞の違いに着目したのですか?
予後が悪いタイプのウィルムス腫瘍は「アナプラジアタイプ」と呼ばれていて、どんどん増殖して、歪な形になるんです。いくつもの腫瘍サンプルを使ってがん細胞を顕微鏡観察していくと、DNAがかなり傷ついていて、染色体の数も変化していました。通常なら死んでしまうような状況で、さらに増殖していたんです。
── すごい生命力ですね。もともとそういうタイプの細胞なのですか?
実は最近、そのことについて成果を発表したんですよ。
アナプラジアタイプは元からあるわけではなくて、がん細胞が進化したものだと分かりました。

── アナプラジアタイプは、抗がん剤治療で逆に増殖してしまうということですか!?
僕たち臨床医は、化学療法でDNAに傷をつければがん細胞は死ぬと思って治療をしているんですけど、実際に傷をつけてもアナプラジアタイプのがん細胞は死んでなかったんですよね。アナプラジアは、最初からいるわけではなくて、治療によって出現して生き延びていく…進化の考え方が当てはまると考えています。そういう意味で、博士論文のタイトルにも「Cancer Evolution(がんの進化)」というフレーズを使いました。
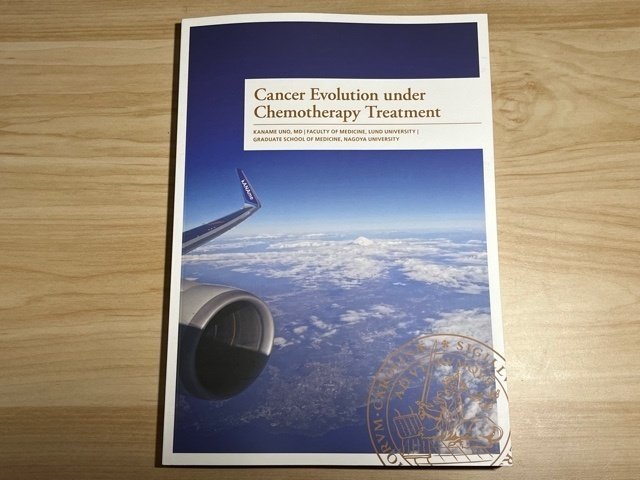
200ページ超の大作!飛行機の翼の「KANAME」ロゴの遊び心が◎
── かっこいい博士論文ですね!書籍化されたんですか!?
僕は1年半ほど、名古屋大学のジョイント・ディグリー・プログラムを利用してスウェーデンのルンド大学に研究留学していたんですが、そこではこんな風に博士論文を本にしてくれるんですよ。
大変だけど、やりがい満点!
名大のジョイント・ディグリー・プログラムとは?
「名大在学中に第二の大学院に入るイメージで、提携する海外のトップレベルの大学に1年間研究留学し、二つの大学からの学位取得を目指せるプログラムです。海外で博士号をとる条件は厳しくて、論文を4本書かなければならなかったので、僕の場合は修了時期が少し延びてしまいました。でも、研究に没頭する時間を持てたのは、キャリアを形成する上でとても貴重でした。日本で臨床医をしながらでは、このような質の高い研究を行うのは難しかったかもしれません。」
── (ちょっと中を拝見すると…)研究の大部分はOvarian cancer(卵巣がん)なんですね…?
実は、僕はもともと産婦人科が専門で、卵巣がんを研究しているんです。卵巣がんは予後が悪いがんで、化学療法があまり効きません。このようながんのメカニズムを研究していたところ、ルンド大学に「がんの進化」が専門の研究者がいると知りました。化学療法が効かないタイプのがんが変異を繰り返して生き延びていく様子を、ダーウィンの生物進化論で考えるんです。その研究者に留学を受け入れてもらい、小児がんをテーマに研究することになりました。ウィルムス腫瘍はアジアよりヨーロッパに多くて、ルンド大学の病院に患者さんが集まるという背景があります。
── 卵巣がんから小児がんですか。なんだか、全然違うようですが…。
僕も最初、産婦人科医が小児がんをやる意味あるのかな、って思いました。でも今思うとラッキーでした。ウィルムス腫瘍のアナプラジアタイプは、卵巣がんとよく似ているんです。遺伝子の変異の仕方や治療法に共通点があって、両方とも予後が悪い。
── そうなんですね。発症する年齢を考えると、卵巣がんの方が進化していそうな感じがしてしまいます。
そうですね。ウィルムス腫瘍はもともと赤ちゃんのようながんなので、成長のスピードが早いんじゃないかと思います。一方、卵巣がんは20年くらいかけてゆっくり発生するんですが、卵巣がんになったときにはかなり悪さを蓄積してきているんじゃないかなと。
── 医療にはどうつながりますか?
今、卵巣がんの治療は、がん細胞を徹底的に取り除くことが基本です。例えば「卵巣がんになぜ抗がん剤が効かないのか」「DNAに傷があるのになぜ生き延びられるのか」を明らかにできれば、別のアプローチを提案できるんじゃないかと思います。攻撃するほどがんが進化していくなら、「がんを飼う(コントロールする)」方向に治療がシフトしていくかもしれません。

── がんと一緒に生きていくという考え方ですね。今後は卵巣がんの研究に専念されるのですか?
大学院修了後はルンド大学に戻って、今度は産婦人科でポスドクとして研究を続けます。これまでの臨床経験で、どんなに手を尽くしてもどうしても救えない患者さんもいらっしゃいました。とても悔しく、この悔しさが大きな原動力になっています。少なくとも数年はルンド大学で研究や臨床の経験を積みたいと考えています。
── 違う世界を経験することで、視野が広がり未来が拓けていく…苦労や喜びがやりがいや自信につながる、実体験を通した前向きなお話をありがとうございました。宇野さんのがん研究の今後に期待しています。
インタビュー・文:丸山恵

◯関連リンク
プレスリリース(2023/1/4)「Wilms 腫瘍の予後不良なタイプ「Anaplasia histology」の発生および化学療法耐性獲得機序を解明 ~Wilms 腫瘍患者のさらなる生存率向上への布石~」
論文(2023/11/10 アメリカ・カナダ病理学会雑誌『Modern Pathology』に掲載)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
